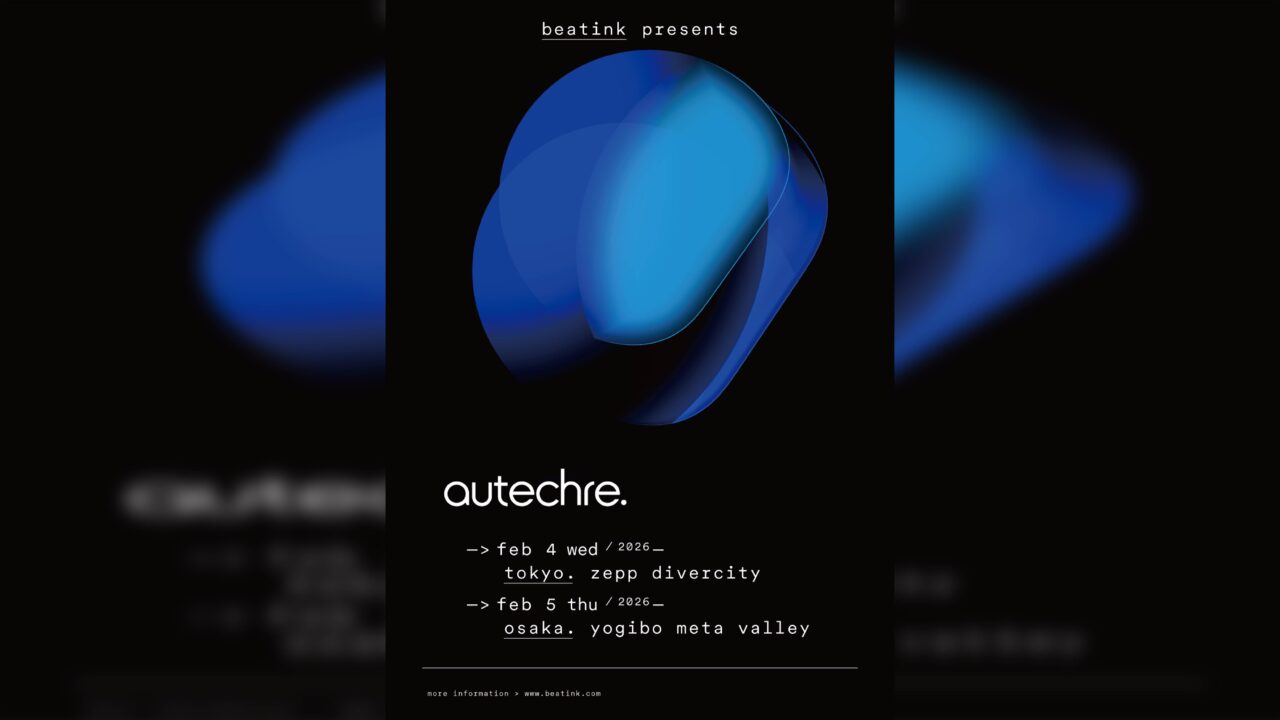クラブやレイヴパーティーに赴くたびに、「実生活からかけ離れた世界で開放感を味わいたい」と渇望している自分の心の欲求に気づく。その欲求を満たすため、さまざまなパーティーに向かうわけだが、開放感を味わえず消化不良に終わってしまったり、理由もなく苦い思いをしたりすることも多々ある。ただ何度も出向くうちに、時折思いがけず素晴らしいパーティーに出逢ってしまう。だからこそ性懲りもなく、新たなパーティーへと足を向けてしまうのだ。
昨年11月、そんな素晴らしいパーティーにまた出逢えた。それが2019年、都内某所の屋上にて始動した『Bonna Pot』だ。開催するごとに、秀逸を極める音響や他のイベントではお目にかかれないラインナップ、そしてインクルーシブな開催ポリシーを評価する声が多く集まり、その注目度は高まり続けている。
昨年はこれまで開催した会場の中でも良い反響が多かったというオートキャンプ銀河にて、2晩にわたり開催。国内外から選りすぐりの出演陣が集結した。今回は本パーティーの仕掛け人である嶋津和(以下、和)と藤田晃司(以下、藤田)の2人の話を交え、その魅力をレポートする。
INDEX
『Bonna Pot』の象徴は、極上の音響と四角形のフロア設計
『Bonna Pot』は、独自性のあるラインナップで来場者から高い評価を得る新たな野外音楽体験の場として注目されている。昨年も、Toshio “BING” Kajiwara、Shhhhh、7eといったディープなダンスミュージック好きにはお馴染みの面々をはじめ、初来日を果たしたO/Y、スコット・ザッカライアス(Scott Zacharias)など、総勢16組のアーティスト・DJが出演。実験的な広義のハウス・テクノを主軸に、ディスコ、ダウンテンポ、トランス、果てはオブスキュアサウンドから民俗音楽まで、さらにはジャンルの枠におさまらないDJプレイやライブが繰り広げられた。
10代の頃からフェスやレイヴをはじめとした野外音楽イベント制作に携わり、自ら主催のイベントも数多く手がけてきた和と、日本屈指の音響・PAエンジニアとしてキャリアを積み重ねてきた藤田の両名が、なぜこのようなアングラかつバラエティに富む音楽性を提示する野外音楽イベントを開催するに至ったのか。その始まりは2000年代初頭に遡る。
藤田:僕らが知り合った2000年代前半は、『Bonna Pot』の前身とも言える『LIVING BALL』というイベントを僕が主催していた時期でした。そのイベントを和とオーガナイズするようになり、2004年には『Bonna Pot』の開催場所と同じオートキャンプ銀河で野外レイヴとしても開催しました。
彼とオーガナイズするようになるまではトランスの流れを汲んだパーティーだったんだけど、タッグを組んでからはテクノやハウス、ジャズも含んだ音楽的に多様性のあるパーティーになったんです。
和:その当時から幅広い音楽が好きだったので、好きなDJやアーティストをブッキングしていたら、自然と独自性のある内容になっていました。テーリ・テムリッツや、Accident RecordsのBrooksなど、普段出会うことのないようなアーティストを呼んでいたので、かなり異質だったと思います。
『Bonna Pot』に欠かせないのが、藤田が手がける音響だ。藤田はVentやOath、またBlue Note Placeといった「音が気持ちいい」と巷で噂される数々のベニューで、空間のサウンド設計から施工に至るまで自ら手を施し、音響を手がけてきた。『Bonna Pot』にも、藤田のつくりあげるサウンドを目当てに訪れるオーディエンスは多い。
藤田:『LIVING BALL』を開催していた当時は、代々木公園にサウンドシステムを出して、ゲリラ的に開催するのがちょうど流行っていた時期で。僕らもそれに混じって、サウンドシステムを持ち込んでパーティーを開催してました。僕ら以外の周りのサウンドシステムはとにかく音を大きく鳴らそうとしていて。そのうちに周辺の住民や公園に遊びにきている人たちから苦情が殺到して、騒音駆除対策を目的に規制が厳しくなったんですね。
その頃の経験で培った僕のPAとしてのモットーは「攻撃的な音を鳴らさない」こと。人を癒す音を出さなきゃいけないと思っています。
また、藤田は『Bonna Pot』の音響や哲学的コンセプトにも大きく影響を与えた伝説的パーティー『LOFT』(※)に参加し、「攻撃的ではない音」とは何なのかを学んだという。
※ニューヨーク出身のDJ、デヴィッド・マンキューソが1970年代から開催していた伝説的なクラブイベント。ラリー・レヴァン、フランキー・ナックルズなど、後世に語り継がれるDJたちにも影響を与えたとされる。
藤田:『LOFT』はメインスピーカーにKLIPSCHORNのスピーカーを使っていて、そのスピーカー5セットでダンスフロアを五角形に取り囲むフロア設計になっていました。すごく音は良いのに、その設計のせいかずっと聴いていても全く耳が痛くならないんです。
当時はすごく感動しましたね。この設計だったら、誰にも迷惑をかけず、しかも能動的に音を楽しめるはずだと。
和:僕もデヴィッド・マンキューソのパーティーには何回も行ったことがあるんですが、行ってまず驚くのがダンスパーティーらしくないほど、音が小さく感じること。自ら意識的に聴くという姿勢で臨まないと楽しめないんです。でも、前のめりになって音を聴くことで、音により集中できるようになる。マインドセットとして「聴く」姿勢を持つことは、オープンマインドな意識の調和にも繋がってくるんだと思いました。
こうした背景もあり、『Bonna Pot』ではTaguchiの平面スピーカーユニットを搭載したスピーカー(※)を使用し、DJブースとダンスフロアを四方から囲むという会場設計を考案・実践している。スピーカーの配置を検討し、決定するまでに、会場下見を含め4日もかけているというから驚きだ。微妙な勾配のあるキャンプ場の地面をレーザーで測量しながら、ミリ単位で配置のズレを修正するなど、そのこだわりは細部にわたっている。
※プロオーディオブランド・Taguchi特有のスピーカー。新木場の工房にて、手作業で製作されている。Taguchiのスピーカーは、国立劇場や日本科学未来館、京都西本願寺など、数々のベニューで採用されている。
この緻密な会場設計と極上のサウンドシステムにより、『Bonna Pot』では耳を刺すような痛さを全く感じさせない有機的な音が実現している。それでいながらイマーシブで立体感のある音になっているため、音に聴き入っているうちに身体が浮く感覚を覚え、不思議とサイケデリックな体験を味わっているような気分になる。一聴するだけで、この音に病みつきになる人は多いはずだ。


またこのスピーカーでつくる四角形のダンスフロアの中に、DJ / ライブブースも位置しているため、ダンスフロア内でDJやライブアクトがパフォーマンスできる設計になっている。それにより、会場にいる誰もが同じ環境で音楽を愉しみ、表現できる仕組みを実現している。
大抵のイベントでは、演者がパフォーマンスするブースとオーディエンスが踊るフロアは分けられており、フロア側に向けられたメインスピーカーと、ブース内で音を確認するためのモニタースピーカーが配置されているケースが多い。
藤田:『Bonna Pot』の第1回目では、モニタースピーカーを使用しませんでした。DJが聴いて体感している音と、ダンスフロアでみんなが体感している音をなるべく同じにしたいから。そう思うと、同じスピーカーで音を聴ける方がいいはずです。
今のDJカルチャーの多くは、モニターとメインスピーカーが分かれています。そのため、聴こえる音がどうしても違う感触になってしまう。この時点で違う世界にいるんですよね。だからその世界を分けないためにも、ダンスフロアの中にDJを入れるように設計しています。同じ音を聴けることにより、DJ / ライブアクトとオーディエンスの心理的繋がりをより深いものにできるはずです。
この設計のおかげもあってか、演者もオーディエンスも会場にいる誰もが音に浸りながら、恍惚とした表情を浮かべる様子を間近で見ることができた。音響の力で、会場全体に一体感を生み出していたように思う。

INDEX
「能動的にイベントに参加する感覚や、価値観の違いに接続する感覚を取り入れるようにしている」(和)
昨年の『Bonna Pot』開催地となった西伊豆・オートキャンプ銀河は、綺麗に整備されたサイトとして、キャンプ利用客からの評判も良いキャンプ場だ。2021年に同会場で開催した際も、訪れたオーディエンスからの評価は高かったという。
昨年ダンスフロアが用意されたのは、オートキャンプ銀河最上段の星見サイトエリア。ここでは芝生が一面に広がり、大きくひらけた空を眺められる。芝生に寝転びながら、美しい朝日も星が瞬く夜空も拝めるという、和の理想を追求するには絶好の空間だ。
和は「このもともと美しい場所の魅力をどうやってさらに引き出すか、ということを念頭にプランしました」と昨年の開催を振り返る。
和:過去の開催時も同様ですが、まずは会場のダンスフロアの位置で、イベント当日の日の入りと日の出のタイミング、そして太陽と月の動きをARアプリで正確に測定します。自然の流れを汲んだシチュエーションを想像しながらタイムテーブルのスロットを作り、それにハマるようなDJの方々にオファーとイメージの共有をしています。
なので、前回はオートキャンプ銀河の星見サイトエリアで、どういう時間帯にどういう音楽を聴きたいのかを意識しながら組んでいきました。nø¡Rに2日目のオープンを頼んだり、BINGさんに2日目の夜明け前から日の出直前の時間帯に出演をお願いしたり、クロージングの専門家であるスコットにロングセットで最終日を締めてもらったり。この3人には最初に特定の時間帯に出演してもらうことを意識していました。
また会場作りとしては、ダンスフロアから見える位置に自然の美しさを阻害するような見栄えの悪いものを置かないことを大切にしています。例えば、運動会テントやイントレなどは徹底的に置かないようにしています。
その上で、照明やデコレーションなどを設置する際はその場にある美しさと共存しながら、元来の魅力をより引き出せるようなものを配置するように意識しています。


開催当日はダンスフロアの周辺や導線にて、参加者たちが持ち寄ったアート作品やアクセサリーを販売する店舗も見受けられた。開催発表時のステートメントでも伝えられている通り、『Bonna Pot』では芸術作品や創作物、装飾やパフォーマンスなど、作品の持ち込みおよび展示も推奨されている。ふと立ち寄る参加者たちと、出展者との交流がいくつも生まれていたのが印象的だった。
加えて、会場内の飲食ブースではベジタリアン向けのオプションやハラル対応の店舗などが出店。こうした来場者の嗜好や国籍、信仰への配慮を感じられる対応にも、多様な価値観を受け入れる運営側の姿勢が見て取れた。

和はこれらの取り組みの背景について、「能動的にイベントに参加する感覚や、文化的な違いに接続する感覚を少しでも取り入れたかった」と語る。
和:一見、アンダーグラウンドで参加しにくいイベントに見えるかもしれませんが、僕らとしては音楽が好きで他者に敬意を持って接せる人たちには誰でも来てほしいと思っています。さまざまなバックグラウンドや考えがある人たちに参加してほしい。そういう意識はデヴィッド・マンキューソの哲学に影響を受けています。デヴィッドの「色んな人がいた方が面白い」というピュアな価値観には共感しています。
他にもチケットを買うお金がない人たちには、ボランティアとして参加してもらうことを推奨しています。参加にあたって、できる限りバリアを作りたくない。誰もが遊びにきやすい環境を作れたらと思っています。
もう一つ心がけていることは、イベントに参加している人たちと演者の関係性をできる限りフラットにすること。演者を祭り上げるような見え方にはしたくないんです。だからダンスフロアの高さと同じになるようにDJ /ライブブースの底上げもしていませんし、照明もなるべくDJだけをフォーカスするような当て方にしないようにしています。


これまで見てきたような音楽だけにとどまらないインスピレーショナルな表現は、両名が音楽にあふれた生活の中で刺激を受けてきた原体験にもとづいている。「特に2000年代初頭の『LIFE FORCE』(※)から受けた影響はすごく大きい」と言う2人。『LIFE FORCE』で経験した共通の原体験についてこう話す。
※東京を中心に1993年から開催されるウェアハウス / オープンエアーパーティー。PAエンジニア・浅田泰がサウンドデザインを手がけることでも知られる。
和:レジデントDJだったニック・ザ・レコード(Nick The Record)のプレイと浅田さんの音響が特に記憶に残っています。普段ニックはディープハウス中心のDJなんですけど、当時の『LIFE FORCE』ではラテンやアフリカンのようなワールドミュージックなどもかけていました。ハウスやテクノと混ぜたら、スカスカに聴こえるリスクもあるようなジャンルでもあると思うんですが、そういった曲でも浅田さんの音響のもとで聴くとちゃんと最高のダンストラックとして機能していたんです。
同じDJのプレイであっても、音響によって聴こえ方が全く変わってくる。それにDJ側も、浅田さんの音響への信頼があるから幅広い音楽がプレイできるわけです。
こういった体験から、『Bonna Pot』でもDJが普段ダンスフロアでかけられないような幅広い曲がプレイしたくなる音響環境を作れるよう意識しています。
藤田:音はもちろんですが、オーガナイザーたちが意識している設計そのものにも影響を受けています。
『LIFE FORCE』はまずフロアが分煙になっていて、しかも運営側が決めたわけじゃなく、参加者たちが勝手に分煙している。そういうことにすごく感激しました。そういう能動的な思考をベースにした自由さを許してくれる空間なんですよね。自由さと秩序が同居し、音楽のあり方や豊かさとあいまった音響の心地よさからくる影響力を発揮している空間でした。そんな空間がもたらす精神性や協調性に大きく影響され育ててもらった記憶があります。
こういう側面は『LOFT』にもあります。子供が鬼ごっこしていたり、おじいちゃんとおばあちゃんがベンチに座ってずっと会話していたり。ある時間になると会場内にビュッフェが並んで、ダンスフロアから人がいなくなっちゃう。そんなフリーフォームなムードに影響を受けていますし、音楽の幅を広げることもその自由さにつながっていると思っています。『LOFT』もさまざまな音楽が優れた音響によって、ダンストラックとして機能していたパーティーです。