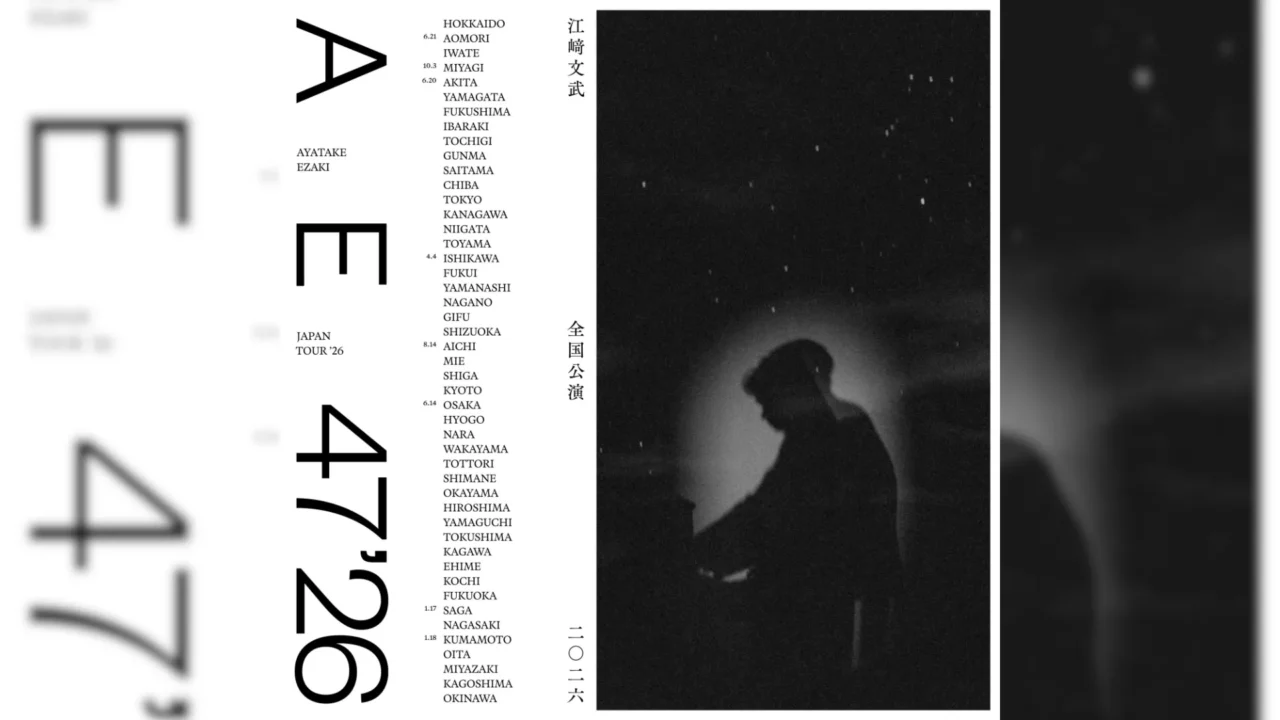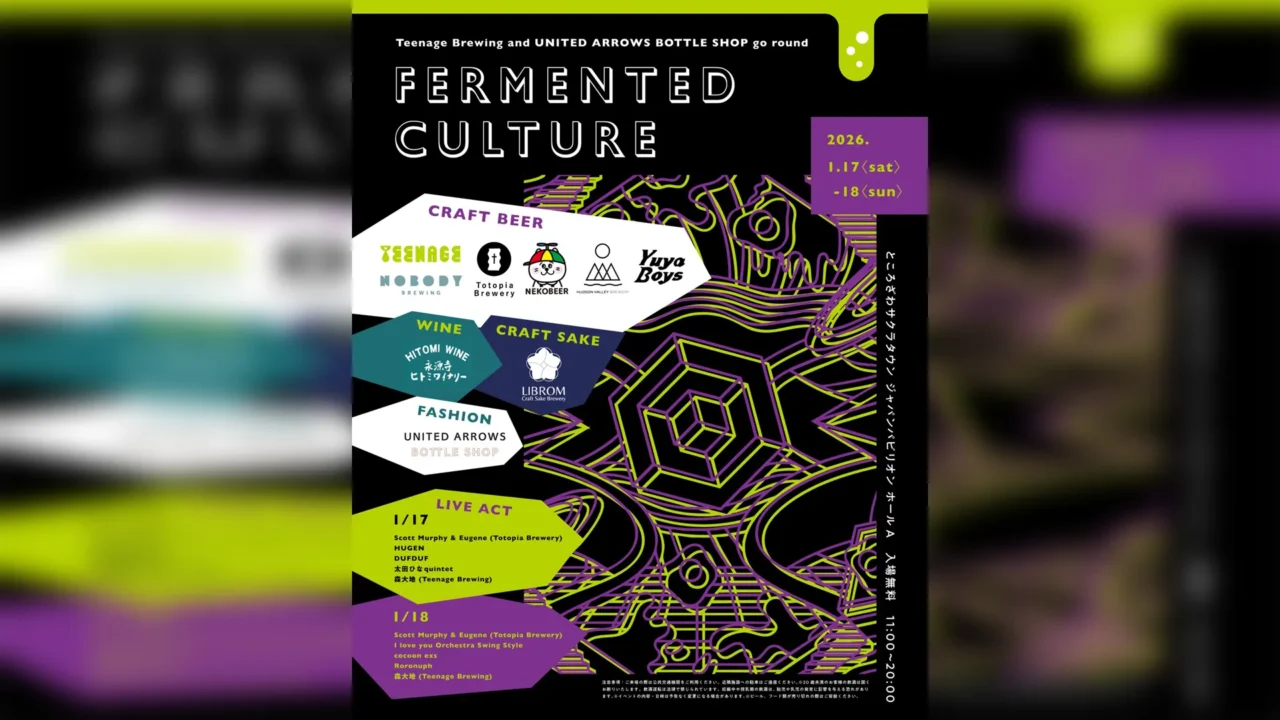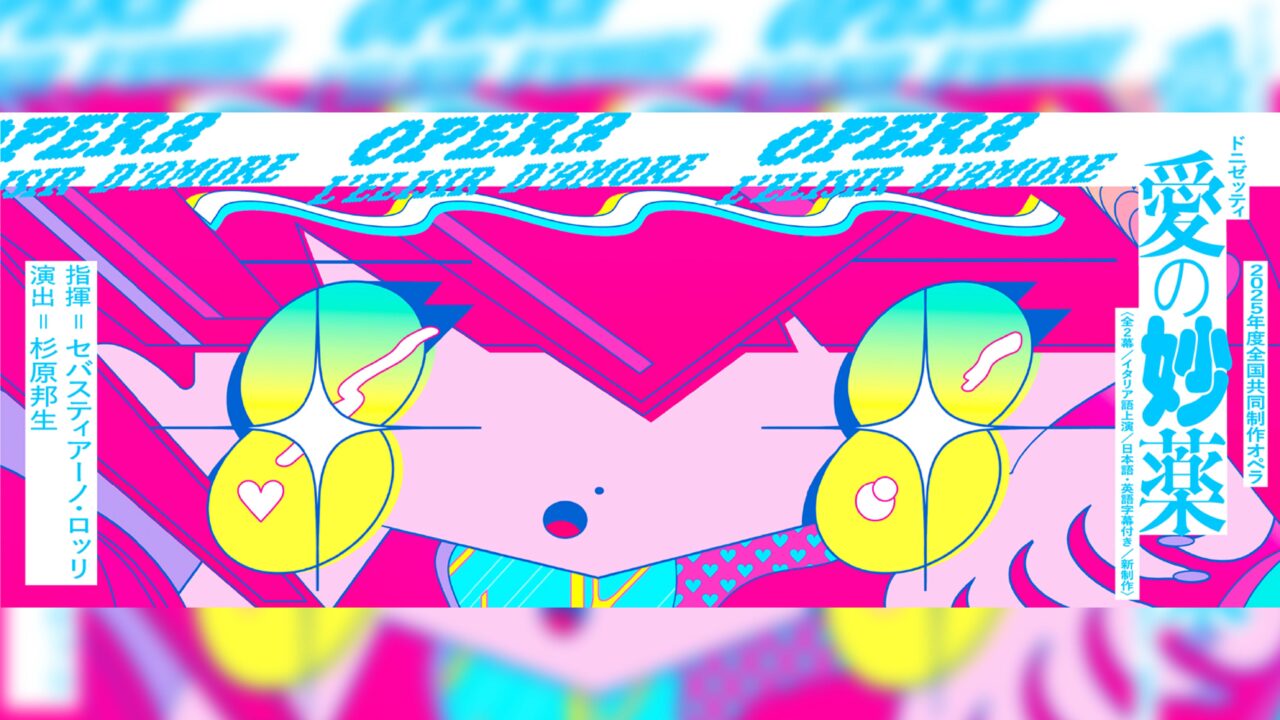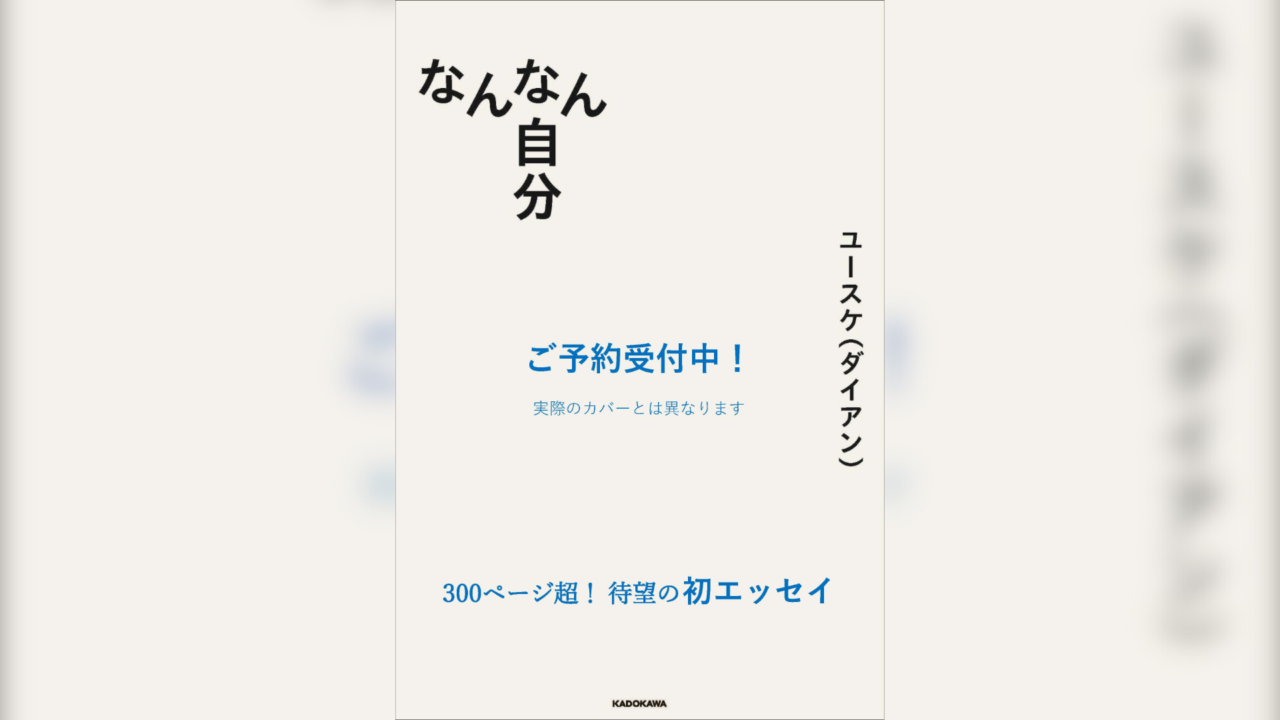ジャンルを問わず、商業的な成功を度外視したような実験性の高い音楽、あるいは独創的な音楽がこの世界には数多く存在している。既存の枠組み、価値観、慣習に囚われないオルタナティブな音楽は日本からも日々生まれ続けているが、そうした音楽に取り組んでいる海外の音楽家はどのようなことを考え、いかにして自身のキャリアを切り拓いているのだろうか。そんな疑問がこの記事の出発地点だった。
たとえば、アメリカには「AACM」という音楽家の非営利団体(NPO)がある。1965年にシカゴで設立された「AACM」のオフィシャルサイトには、ブラックミュージックへの賛美を通じた人間性の高揚、文化理解の促進、そして作曲と即興演奏を通じた音楽の可能性の拡張に加えて、経済的に不利な状況に置かれた青少年に無料のトレーニングプログラムを提供することなどを通じて、「若い音楽家を育成する」という使命が掲げられている。
当初、そうしたアメリカでの事例について話を訊き、日本で活動するミュージシャンや関係者のヒントになるような記事を作れないかと考えていた。国内メディアによる「AACM」の説明のなかには、シカゴ市からの助成を受けて設立されたという趣旨のものがあり、取材前にはアメリカの行政、自治体には音楽や文化に対する理解、そして音楽家をサポートする姿勢があるのだな、という素朴な印象があったからだ。しかし今回の取材を通じて、その認識は現状を必ずしも反映しているわけではないことがわかった。
本稿では「AACM」と関わりのあるトミーカ・リードとそのバンドメンバーであるメアリー・ハルヴォーソンの二人にインタビューを実施。アメリカという国で、コマーシャルではない音楽を生業として生きていくことについて話を訊いた。
INDEX
アメリカのインディペンデントな音楽家の置かれた現状は、日本とも大きく変わらない
―トミーカさんもメアリーさんも、コマーシャルなポピュラーミュージックから外れる領域の音楽をやっていて、自分たちの創造性を保った活動を続けてきていますよね。アメリカでは助成金など、さまざまミュージシャンへのサポートがあって実際に活用されていると思うのですが、お二人はどのように音楽活動を続けてきたのでしょうか。
メアリー:あまりコマーシャルではない音楽でやっていくのは、アメリカでも本当に挑戦的なことだと思います。私の知り合いもみんな、いろんなやり方で何とか生き延びてきていますが、本当に音楽を愛し、創造的な音楽を心から信じているなら道は見つかると思います。

「ニューヨークでもっとも予測のつかないギタリスト」とも評され、多くのプロジェクトでの活動で知られるギタリスト、作曲家。「Nonesuch Records」からリリースされた最新作『Cloudward』には、ローリー・アンダーソンも参加していることでも話題に。2024年6月、トミーカ・リードのカルテットのメンバーとして来日する。
メアリー:たとえば、学校や個人的なレッスンで教えている人も多いし、バンドを複数かけもちする人、音楽と全然関係ない仕事をやらざるを得ない人も数多くいる。私やトミーカのように自分たちで助成金に応募して、それをもらって何とかやっていく人も多いですよね。
でもニューヨークにおいてもそんなにいろいろなサポートがあるわけではないんです。ヨーロッパのほうが芸術に対する助成は多いように私は思います。だから私たちもツアーを回るときはヨーロッパ各地のサポートを得ながらやっています。コマーシャルではない音楽に対して、アメリカでも大学などからのサポートはいくつかありますが、なかなか道は簡単ではないのが現状です。
トミーカ:ノルウェーなどのいくつかのヨーロッパ諸国にはそういう基金みたいなものがいっぱいあって、アーティストを支える構造がありますよね。それに対してアメリカには同じようなものはないんです。

「天才賞」と呼ばれる助成金制度「マッカーサー財団フェローシップ」をはじめ、数々の受賞歴を誇るチェリスト、作曲家。ワシントンD.C.郊外で育ち、シカゴに移った2000年より音楽活動を開始。2009年には「AACM」からの依頼でGreat Black Music Ensembleと呼ばれるラージアンサンブルのための作品を制作し、2015年にバンドリーダーとしてTomeka Reid Quartetでデビュー・レコーディングを行なった。現在はミルズ・カレッジの作曲講座で教鞭をとる。2024年4月、Tomeka Reid Quartetとして新作『3+3』を発表、6月にはカルテットを率いて初来日を果たす。
メアリー:やっぱり北欧の多くの国ではアーティストに対するサポートが多い印象ですね。私自身もミュージシャンになろうと決めた10代のとき、音楽以外の収入を得て自分を支えていかなければ続けられないだろうと考えていました。
INDEX
「金銭的な見返りはない」という覚悟が必要
―オーディエンスや市場の規模、文化的な背景など踏まえると日本の状況とは単純に比較はできないですが、アメリカでもジャズミュージシャンとして生計を立てるのは簡単ではないのですね。
メアリー:それでもいいと決心して音楽家としての道に飛び込んで、21歳でニューヨークに引っ越した最初の5年間はフルタイムの事務職で働いていました。そのときは夜に音楽の仕事をしていて、ある程度音楽でやっていけそうと見えてきたところで会社員を辞めることができました。
私はいま43歳で、26、27歳の頃から音楽だけで食べていけるようになったんですが、自分はとてもラッキーだと思っていますし、これが当たり前だと決して思っていません。特に本当にやりたい音楽を追求するとなると大変なので、クレイジーな人生です(笑)。でも、とても感謝しています。
トミーカ:私も最初の頃は中学、高校の先生とのかけもちで音楽をやっていたからすごく大変だったんですが、「何があってもこの音楽をやりたい」という気持ちがあったので続けることができました。そうやって続ける人ってすごく強い動機があるとか、あるいはクレイジーだから続けられるのかもしれないなって思います。なぜなら見返りがそんなに望めないわけだから。
実際、私がやっているようなアートアンサンブルだと、同じような編成で違うことをやったらすごくお金になるかもしれないんだけれども、それは私がやりたいことではない。基本こういう音楽をやるにあたっては、金銭的な見返りはないって覚悟が必要なんだろうなと思ってます。
たとえばニューヨークの高級アパートに住んだり、テスラに乗りたいと思ったら、コマーシャルな音楽をやらなきゃ無理だと思うし、でも私にとって音楽はそれ以上に重要なものなんです。そういうタイプの見返りはないし、私もずいぶん自力で頑張ってきたけれども、結局のところ自分自身が何を求めているかなんでしょうね。
トミーカ:私は教師として約8年間働いて、ずっと続けようと思えば続けられたんですが、そうしないようにしました。お金になるからとその仕事に縛られてしまうことを、一部では「ゴールデン・ハンドカフ(金の手錠)」って言うんです。だけど、私はミュージシャンになりたかったし、そこで私は満足したくなかったから、仕事を辞めなければならなかったんですよね。
教師を辞めてから最初のころはすごく大変でしたが、長く続けることで物事をパズルのようにつなぎあわせる方法が見つかってくる。そうやって活動していくなかで、ありがたいことにいくつか助成金をもらえて、さまざまなプロジェクトにも参加できたり、機会を得ることができました。そして自分のプロジェクトで作品を出すときには、自分の名前がちょっとずつ知られているような状況がありました。でもそこまで続けるには、よっぽど本気でやってるか、イカれてるかどっちかじゃないと続かないだろうなと思います。