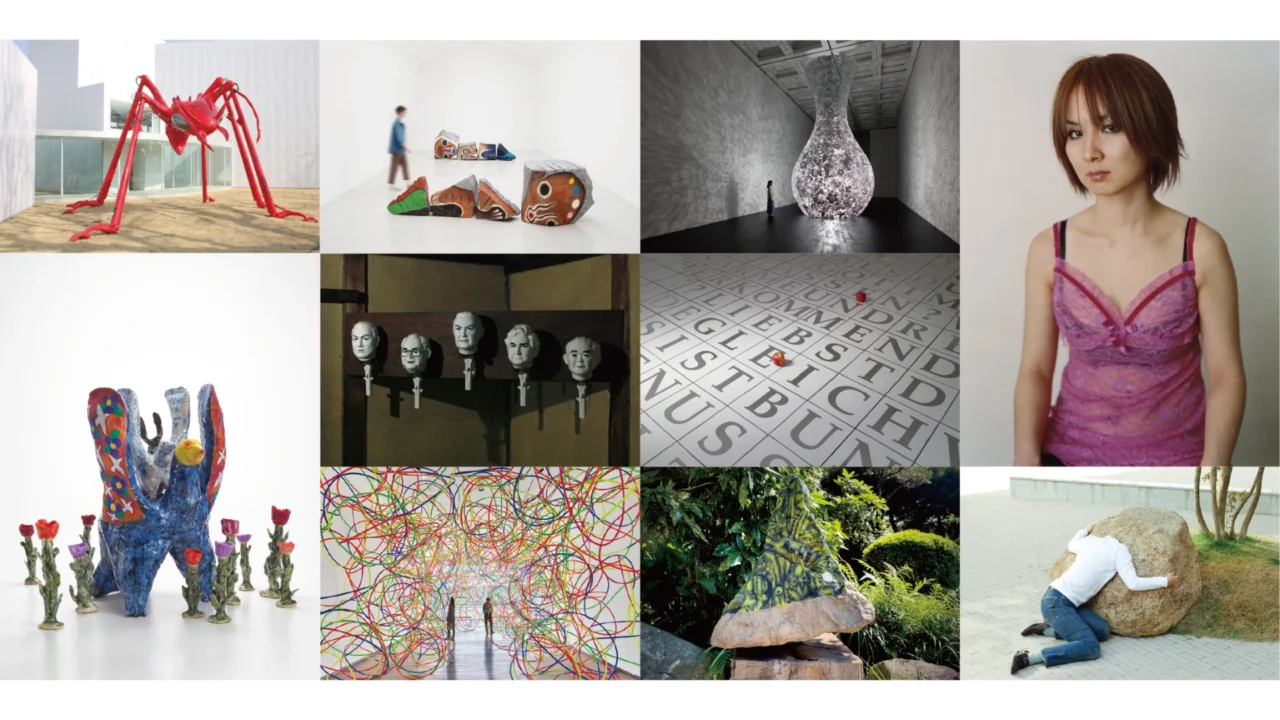『テルマ』や『わたしは最悪。』で、日本でも注目を浴びたヨアキム・トリアー監督。「第78回カンヌ国際映画祭 グランプリ」を受賞し、期待も高まった最新作『センチメンタル・バリュー』は、かつて家族のもとから去った映画監督の父と、気鋭の舞台俳優として活躍する娘を軸に、映画製作と家族のあり方を見つめる重層的なドラマだ。本作をライター・木津毅がレビュー。人間の持つ「多層性」という側面を軸に、作品を深く見つめていく。
※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
ヨアキム・トリアーが描くアイデンティティの複層性
「20年ぶりにこの作品を見ましたが、今でも鮮明に当時を覚えています。撮影していた日々のことや人々のことを。友人と製作したんです。彼らは家族です」
『センチメンタル・バリュー』の劇中、映画祭で自身のレトロスペクティブのトークセッションに登壇した映画監督グスタヴ・ボルグ(ステラン・スカルスガルド)は過去作を振りかえってそのように語る。その発言自体はある種の常套句であり、さして驚くものではないのかもしれない。多くの人間が関わり、しばしば濃密な時間を過ごす映画作りというものは、まるで家族のように緊密な関係を生み出すものである、と。映画を愛する人々が集まる場では好意的に受け止められるものだろう。

しかしグスタヴのこの発言にねじれがあるのは、彼自身が実際の家族のもとを去った人物だからだ。血縁を拠りどころとする従来的な意味合いでの家族関係を維持することに失敗した父親は、監督として映画製作を重ねることで疑似的かつ一時的な「家族」を転々としてきた人物なのだ。そんな彼も15年映画製作から遠ざかっており、二重の意味で「家族」と縁遠い孤独を味わっている。『センチメンタル・バリュー』は、彼がいかにして「家族」を再獲得するかを巡る物語として始まる。
INDEX
大まかに捉えれば、一度家族を捨てた父親が子どものもとに戻り、赦しを求めようとするという幾度となく繰り返されてきた話のように見える本作だが、何よりも重要なのは父親を映画監督、娘を俳優と設定することで、現代の映画文化を巡る1本になっていることだ。そこでの父 / 娘の再会は同時に、映画監督 / 俳優の邂逅でもある――しかも、新作を生み出すための。
振りかえればヨアキム・トリアーは、共同脚本を務めるエスキル・フォクトとともにそうしたアイデンティティの複層性にまつわる人間ドラマを紡いできた。作家志望の若者2人の友情の分岐を見つめた『リプライズ』(2006年)、薬物依存から社会復帰を目指す青年の苦闘を追う『オスロ、8月31日』(2011年)、戦場フォトグラファーであった母の死を巡って遺された家族が集う『母の残像』(2015年)と、社会的立場(あるいは、どのように他者から認識されるか)と個人的な人間関係がどのような関わりにあるのかがそれらの作品では問われていたように思う。たとえば『母の残像』でイザベル・ユペールが演じた人物は、社会的には名の通ったフォトグラファーだが、家族にとっては母親である。だとすると、「彼女自身」は何者なのだろうか? その両方であることは可能なのだろうか? これらは、置かれたコミュニティや状況によって異なる複数のアイデンティティを持つようになった現代人のあり方を再考するものであるだろう。
超能力を備えた少女の覚醒というトリッキーな設定だった『テルマ』(2017年)もまた、いくつかのアイデンティティが重ねられていたはずだ。カトリックの家庭で抑圧されて育った主人公は、みずからの同性に対する欲望を受容するとともに「能力者」としての自己を確立する。あるいはまた、世界中で称賛を受けた『わたしは最悪。』(2021年)の主人公ジュリーは、医学から心理学、さらには写真へと興味の対象を移し、しまいには短編小説まで書いてしまう若い女性だった。様々な才能を持っているからこそ自分が何者か定まらない彼女のあり方は、選択肢が多すぎる現代に生きる若者の迷いを体現するものと言えるが、アイデンティティの流動性を清々しいタッチで映しだしてもいた。
INDEX
脚本と、2本のDVD。2つのアイテムが示す「家族」の複雑さ
『センチメンタル・バリュー』がありがちな父親の贖罪の物語に陥っていないのは、レナーテ・レインスヴェ演じるノーラが「父」から見た「娘」という役割に固定されていないことが大きい。彼女はまず、オスロで活躍する気鋭の舞台俳優である。重度の舞台恐怖症を抱えている彼女が、1人の役者としてどのように精神的な不安定さと対峙するかもまた、本作の重要なストーリーラインの1つだ。

グスタヴはよりわかりやすく、映画作家であることを最大のアイデンティティとする人物だ。いや、そのような生き方が染みついていると言えばいいだろうか、彼の他者とのコミュニケーションの動機はほとんどすべて映画製作に紐づいているようにすら見える。亡くなった元妻の葬儀のために突然現れたかに思われたグスタヴだが、実際はノーラに当て書きした新作の脚本を渡すためにやって来たことがすぐに明らかになる。だが、そのことを依頼する際にも「父親」の役割よりも「映画監督」としての自分を優先する彼は、「お前のやってきた仕事を誇りに思う」といった穏当な言葉をかけるのではなく、ノーラが出演してきた作品の演出を批判する。ある意味、娘に対してもアーティスト同士として率直に接しているとも取れるが、ノーラはそんなグスタヴの態度に我慢ならず、映画監督としてでなく、父親としての彼を拒絶する。グスタヴは詰め寄る――「まず脚本を読め!」。しかし脚本はノーラに受け取られることはなかった。そこで本作のドラマの核心は、ノーラがその脚本を読むことになるのか、読むとしたらなぜ読むことになるのか、になると予告される。
グスタヴとノーラの関係性を示すものとして、象徴的な一幕がある。ノーラの妹で歴史学者のアグネス(インガ・イブスドッテル・リッレオース)の幼い息子への誕生日プレゼントとして、グスタヴはよりによってミヒャエル・ハネケの『ピアニスト』(2001年)やギャスパー・ノエの『アレックス』(2002年)といった、子どもには確実に不適切な映画のDVDを持ってくる。アグネスは子どもの母としてその場にいるので、当然迷惑そうだ。が、ノーラはグスタヴの「ユーモア」に思わず笑ってしまう。結局のところ、2人は似た者同士でもあるのだ。

この場面はまた、観客に対する目配せにもなっている。こと細かな説明がないので、『ピアニスト』や『アレックス』がセンセーショナルな題材を扱った作品であることを知らなければ、グスタヴの映画親父ギャグは理解できないだろう。ただ、これは映画通だけがほくそ笑むことができるスノッブなシーンというより、映画人たちの面倒くささを皮肉交じりにからかうものだ。スカルスガルドがラース・フォン・トリアー作品の常連俳優であったことが効いている。彼の向こう側には、そのように映画監督としては偉大だが、厄介なパーソナリティが少なからず取り沙汰される人物たちの姿が浮かびあがる。