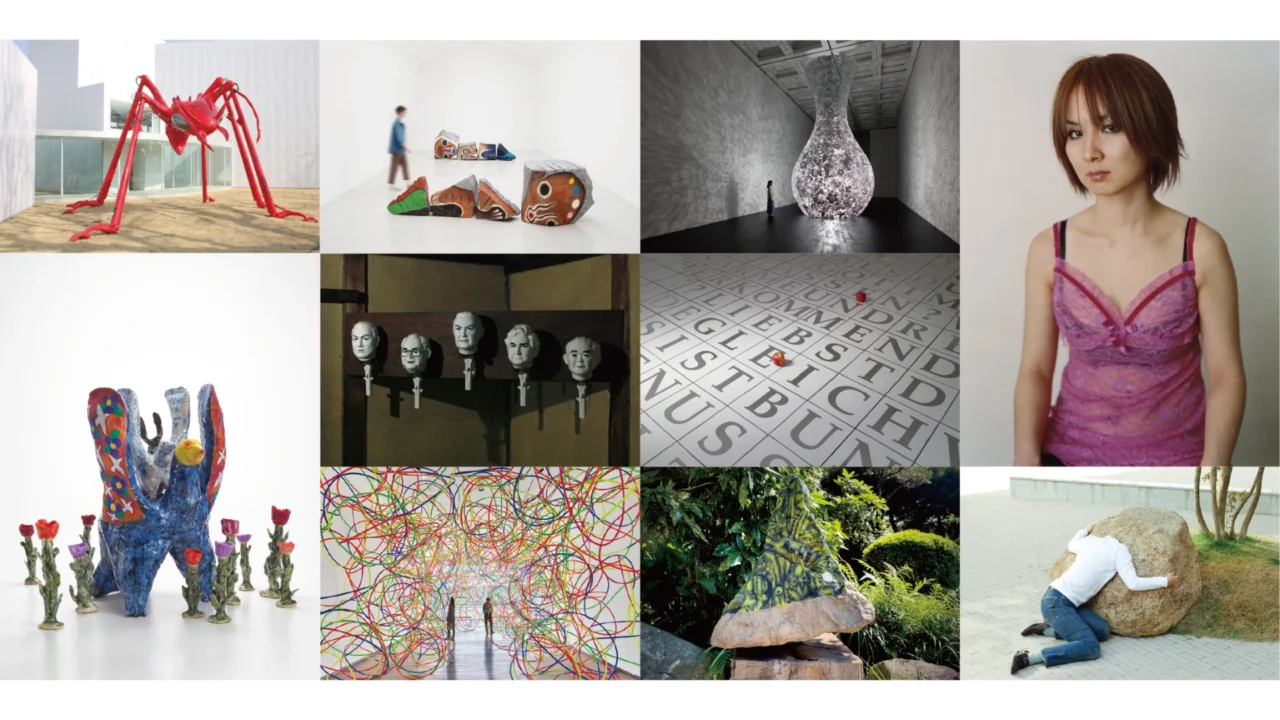『テルマ』や『わたしは最悪。』で、日本でも注目を浴びたヨアキム・トリアー監督。「第78回カンヌ国際映画祭 グランプリ」を受賞し、期待も高まった最新作『センチメンタル・バリュー』は、かつて家族のもとから去った映画監督の父と、気鋭の舞台俳優として活躍する娘を軸に、映画製作と家族のあり方を見つめる重層的なドラマだ。本作をライター・木津毅がレビュー。人間の持つ「多層性」という側面を軸に、作品を深く見つめていく。
※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
ヨアキム・トリアーが描くアイデンティティの複層性
「20年ぶりにこの作品を見ましたが、今でも鮮明に当時を覚えています。撮影していた日々のことや人々のことを。友人と製作したんです。彼らは家族です」
『センチメンタル・バリュー』の劇中、映画祭で自身のレトロスペクティブのトークセッションに登壇した映画監督グスタヴ・ボルグ(ステラン・スカルスガルド)は過去作を振りかえってそのように語る。その発言自体はある種の常套句であり、さして驚くものではないのかもしれない。多くの人間が関わり、しばしば濃密な時間を過ごす映画作りというものは、まるで家族のように緊密な関係を生み出すものである、と。映画を愛する人々が集まる場では好意的に受け止められるものだろう。

しかしグスタヴのこの発言にねじれがあるのは、彼自身が実際の家族のもとを去った人物だからだ。血縁を拠りどころとする従来的な意味合いでの家族関係を維持することに失敗した父親は、監督として映画製作を重ねることで疑似的かつ一時的な「家族」を転々としてきた人物なのだ。そんな彼も15年映画製作から遠ざかっており、二重の意味で「家族」と縁遠い孤独を味わっている。『センチメンタル・バリュー』は、彼がいかにして「家族」を再獲得するかを巡る物語として始まる。
INDEX
大まかに捉えれば、一度家族を捨てた父親が子どものもとに戻り、赦しを求めようとするという幾度となく繰り返されてきた話のように見える本作だが、何よりも重要なのは父親を映画監督、娘を俳優と設定することで、現代の映画文化を巡る1本になっていることだ。そこでの父 / 娘の再会は同時に、映画監督 / 俳優の邂逅でもある――しかも、新作を生み出すための。
振りかえればヨアキム・トリアーは、共同脚本を務めるエスキル・フォクトとともにそうしたアイデンティティの複層性にまつわる人間ドラマを紡いできた。作家志望の若者2人の友情の分岐を見つめた『リプライズ』(2006年)、薬物依存から社会復帰を目指す青年の苦闘を追う『オスロ、8月31日』(2011年)、戦場フォトグラファーであった母の死を巡って遺された家族が集う『母の残像』(2015年)と、社会的立場(あるいは、どのように他者から認識されるか)と個人的な人間関係がどのような関わりにあるのかがそれらの作品では問われていたように思う。たとえば『母の残像』でイザベル・ユペールが演じた人物は、社会的には名の通ったフォトグラファーだが、家族にとっては母親である。だとすると、「彼女自身」は何者なのだろうか? その両方であることは可能なのだろうか? これらは、置かれたコミュニティや状況によって異なる複数のアイデンティティを持つようになった現代人のあり方を再考するものであるだろう。
超能力を備えた少女の覚醒というトリッキーな設定だった『テルマ』(2017年)もまた、いくつかのアイデンティティが重ねられていたはずだ。カトリックの家庭で抑圧されて育った主人公は、みずからの同性に対する欲望を受容するとともに「能力者」としての自己を確立する。あるいはまた、世界中で称賛を受けた『わたしは最悪。』(2021年)の主人公ジュリーは、医学から心理学、さらには写真へと興味の対象を移し、しまいには短編小説まで書いてしまう若い女性だった。様々な才能を持っているからこそ自分が何者か定まらない彼女のあり方は、選択肢が多すぎる現代に生きる若者の迷いを体現するものと言えるが、アイデンティティの流動性を清々しいタッチで映しだしてもいた。