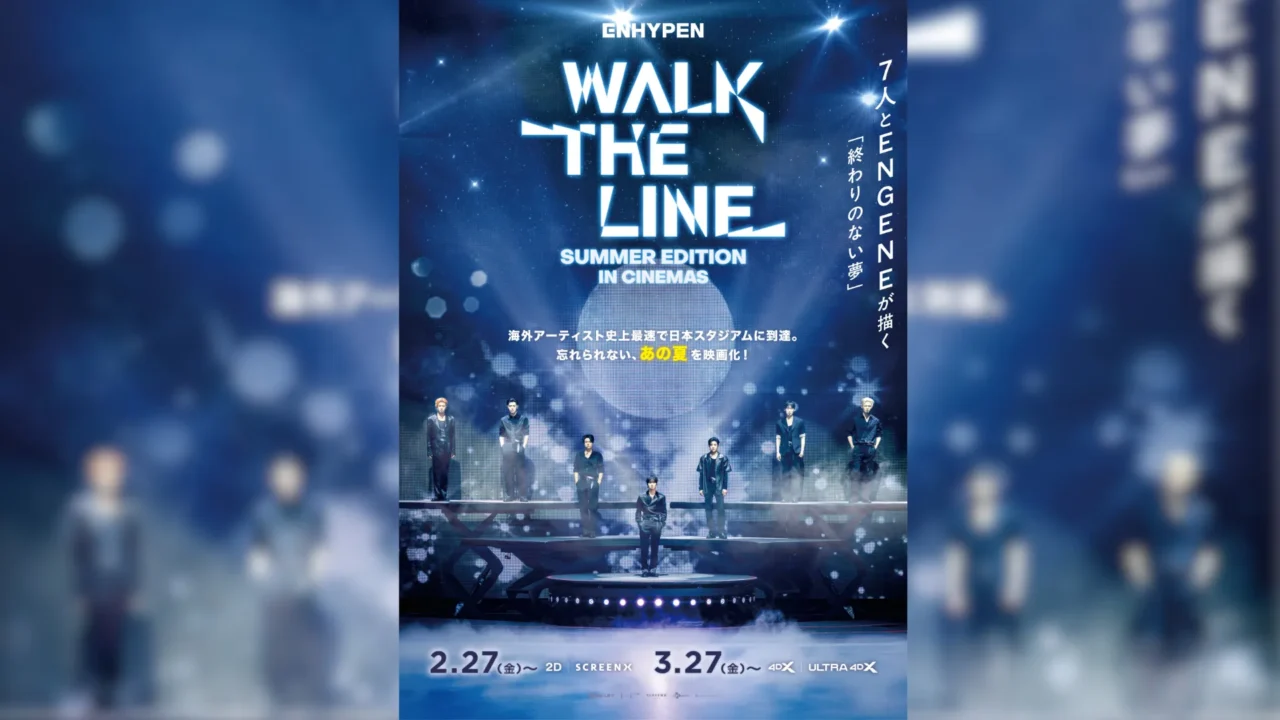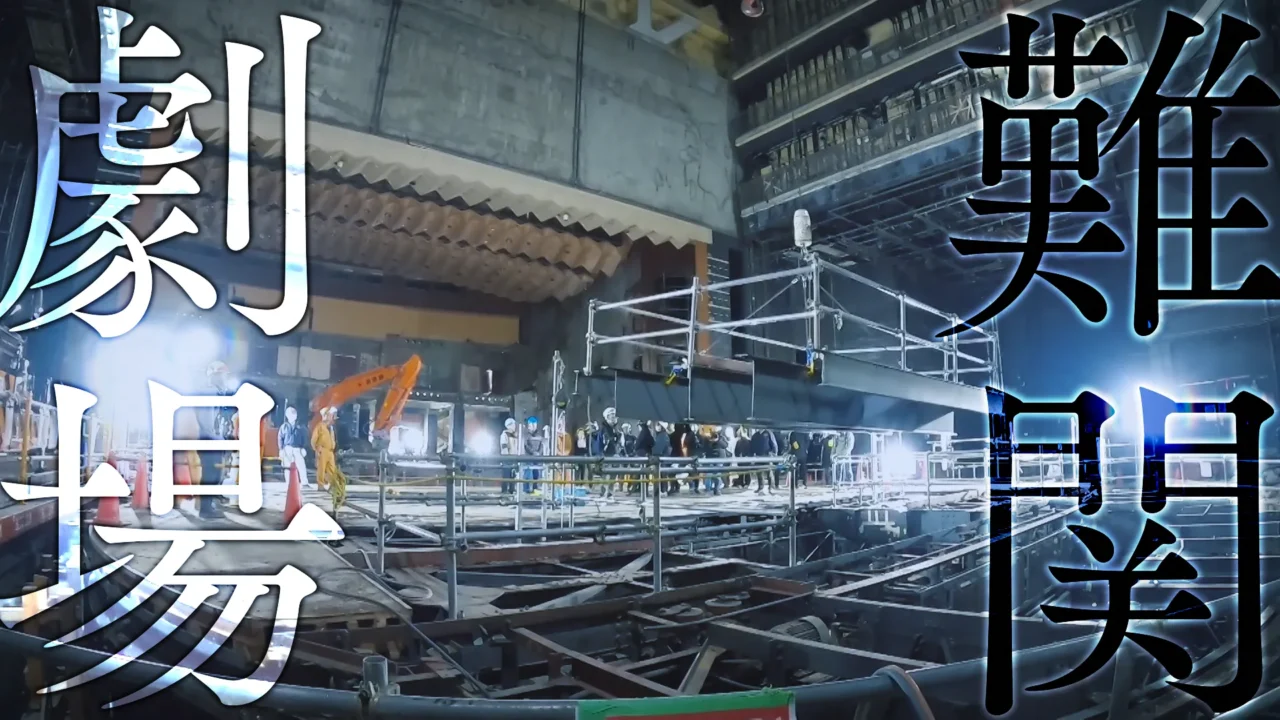物語の住人が、夢の中の「君」に語り掛ける。その場面で僕は、物語の中の人が見る「夢」とはなんだろう? と思う。もしかしたら、それは僕らが生きる現実のことなのかもしれない。そう感じた瞬間にハッとする。<ねぇ 君はどうして 夢の中でも 君の思うように 君をしないの?>――アルバムの最後の曲“後味悪いや|sour”で繰り返されるこのフレーズは、強烈なメッセージになって、現実を生きる僕に目掛けて飛び込んでくる。これは聴き手の力を信じた作品である。
Laura day romanceが、2025年2月にリリースされた前作『合歓る(読み:ねむる) – walls』に続くアルバム『合歓る – bridges』をリリースした。タイトルが示すように、前作の続編として作られた本作。この2枚のアルバムはふたつ合わせて『合歓る – walls or bridges』という、バンドの3rdフルアルバムであり20曲入りのダブルアルバムとして完成した。この時代においてコンセプトを持った長編作品を生み出すこと。そして、その長い物語の中で目まぐるしい音楽的な冒険を果たすこと――それらを成し遂げた偉大なアルバムだ。そしてこのアルバムは、バンドにとってだけでなく、受け取り手にとっても、2025年という時代と切っても切り離せない関係を持った作品になるだろう。そのくらい、このアルバムは今を生きる私たちの現実を浮かび上がらせる。
前編に引き続き、ローラズの3人にインタビューする機会を得た。作品性についてだけでなく、この1年間のバンドの変化についても話を振ったのは、この』『合歓る -walls or bridges』にはバンドのドキュメント的な部分も確かに刻まれていると感じたからだ。井上花月(Vo)が語ってくれた「人として成長しようとするしかなかった」という率直な言葉も、鈴木迅(Gt)の混乱とワクワクを同時に求める冒険心も、礒本雄太(Dr)の役割を背負い過ぎた苦しみからの脱却も、すべて、このアルバムを紐解くヒントになるのではないかと思う。ちょっと長いインタビューだが、アルバムだって長いのだからいいじゃないか。じっくり読んでほしい。時間をかけたっていい。それは、このアルバムやローラズという存在が放つメッセージのひとつだと、私は思う。
INDEX
「迷ったら、やる」と決めたこと。それにより広がったサウンドスケープ
―遂に前作『合歓る – walls』の後編に当たるアルバム『合歓る -bridges』がリリースされますが、本作はバンドにとって「メジャー1stフルアルバム」というポジションの作品でもありますよね。メジャー1stアルバムが続編というのが、とてもローラズらしいなと。
鈴木:確かに(笑)。
―前編も含め、この『合歓る』という長編作品を作り出すに当たって最初に想像していたものと、結果的に後編で辿り着いた場所の間には距離があるものですか? それとも、想定通りの場所に着地しましたか?
鈴木:前編『walls』の時は時間もあったし、「こういうふうに始めよう」という想定も頭の中にあったので、それを忠実に音楽化していく作業でした。でも、後編『bridges』に関しては、より「はみ出していきたい」という気持ちを持って作ったアルバムになったと思います。今回は「迷ったら、やる」って決めていたんです。思い切ったアレンジも、やるかやらないか二択を迫られたら、すべて「やる」方を選ぶ。その結果、想像していた以上にサウンドスケープは大きくなったし、「1曲」という型からはみ出していく曲がたくさんできた。そういう意味では予想外のところに膨らんでいったと思います。自分としても、混乱しながら、同時にワクワクしながら作ることができましたね。
―「迷ったら、やる」と事前に決めたのは何故だったんですか?
鈴木:『walls』を振り返った時に、とても完成度が高いアルバムではあるけど、自分が頭の中に描いた設計図に忠実に描いた結果、想定していたより若干コンパクトな作品になった印象があったんです。それまでのアルバムでやったことの延長線上に存在しているアルバムという感じがして、そこが少し気になったんですよね。「ミュージシャンシップの前進」ということを考えた時、もっと積極的に新しい要素を取り入れたり、攻めた選択をしたりしないと、自分でも予想もつかない瞬間は手に入らないんじゃないか?――そんな実感があったんです。

左から礒本雄太(Dr)、井上花月(Vo)、鈴木迅(Gt)
国内外のミュージックラバーにファンを広げる日本のバンド。鈴木迅が作り出す幅広い音楽性の楽曲と、井上花月の世界観のあるヴォーカル、タイトさと柔軟さを兼ね備えたリズムを刻む礒本雄太のドラミング、そしてそれらを表現するためのベストな形でジョインするサポートメンバー達。ワンマンライブは開催を重ねるごとに規模を広げ、2025年4月には東京国際フォーラム ホールCをソールドアウト。2026年3月からは自身初となるホールツアー『Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”』を開催する。
―井上さんは、この『合歓る』という作品を作り出した当初と、結果的に辿り着いた場所の距離感はどうですか?
井上:前編を作っている段階では後編がどういうものになるか分かっていなかったんですけど、デモの段階から考えても、ここまで広がりのある楽曲たちになるとはまったく思っていなかったですね。歌入れ直前まで迅くんはアレンジを詰めていたんですけど、歌入れしながら「こんなに多彩なアレンジになるんだ」とか「こんな音が入るんだ」と驚くことが多くて。想像の何倍も面白い音がいろいろ入ってきた印象です。『walls』よりも実験的な、「ライブでは無理だろうな」という音も入ってるし(笑)。
鈴木:ははは(笑)。
―礒本さんはどう思いますか?
礒本:『walls』の最後の“渚で会いましょう|on the beach”で、第1シーズンが終わって「一旦の区切り」感があったので、「後編はどういう作りになるんだろう?」と思っていて。『walls』の後日談的なものになるのか、そのまま続きを描いたものになるのか、それとも断片的なサイドストーリーみたいなものになるのか……いろんなパターンを考えながら過ごしていたんですけど、蓋を開けてみると、1個1個、向いているベクトルは違っているというか、いい意味で予想を裏切ってきた感覚はありました。なので、距離感で言うと予想からは離れたなと思います。もの凄くワクワクしながら取り組めたとは思いますね。
―「混乱とワクワクが同時にある」感覚というのは、皆さんがこの『合歓る – bridges』を作るに当たって抱いた感覚であり、きっと、本作のストーリーで描かれているものにも通じる感覚なのかなと思うのですが。
鈴木:うんうんうん、そうですね。
―結果的に、この2025年にローラズはフルアルバム2枚分のボリュームの作品を発表したことになりますけど、『walls』の段階でもどうなるか分かっていなかったというのは、後編は時間的な制約もきっと多分にありましたよね。それがいい方向に作用したアルバムなのかな、という印象も聴いていてあったんですけど、鈴木さん的に「制作時間の短さ」というのは、いかがでしたか?
鈴木:リリーススパンとしては確かに早いですけど、「この曲は次に入るだろう」とか、前編の制作中も後編のことは同時並行で考えていたので、時間が足りないということはなかったです。ただ、自分の手に負えないような大きな作品を作るに当たって、自分自身が作品の全貌を把握できていないくらいの混乱状態にはあったのも確かで。それがいいふうに作用した、ということはあると思います。
―混乱は、やはり自ずと求めた感じですか。
鈴木:いやあ……。
礒本:ははは(笑)。
INDEX
リスナーへの信頼を基盤に生まれた、バンドにとっての「新たな冒険」の始まりの作品
―前後編合わせた作品のタイトルとしては『合歓る – walls or bridges』と発表されていますが、「walls」と「bridges」の間にある接続詞は「or」、というところも印象的でした。もし、『walls and bridges』にした場合、ジョン・レノンの有名な同名アルバム『Walls and Bridges』(1974年)がありますが、この作品の存在は今作の前提にあるものですか?
鈴木:音楽的な面でインスパイアされたわけではないんですけど、あのアルバムの邦題『心の壁、愛の橋』のイメージは、今回の僕らのアルバムのコンセプトとのリンクを感じていました。あと、『心の壁、愛の橋』というアルバムが生まれた経緯や全体的な雰囲気も、参考にした部分があります。
―『心の壁、愛の橋』は、よく語られる歴史的に言えば、ジョン・レノンの「失われた週末」と呼ばれる時期から生まれたアルバムですよね。当時のアメリカ政府から煙たがられ、オノ・ヨーコとも別居して、カリフォルニアで愛人と一緒に暮らしながらお酒に溺れていたような、言わば失意の時期。そんな状況から生まれたアルバムを、鈴木さんはどんなふうに受け止めているんですか?
鈴木:自分としては、ジョン・レノンは「アップダウンの人」というイメージがあるんです。取っつきづらいだろうし(笑)、衝動的なんだけど、そこにある愛は本物……そんなややこしさがある人なんだろうなと思っていて。『心の壁、愛の橋』は、恋愛における躁状態のバックラッシュで生まれた絶望感も混ざっているように感じるんです。愛が大きい人の方が、逆行もデカいだろうし。そこは、自分たちのアルバムを作るうえでのヒントになりました。
―ローラズの場合は「walls」と「bridges」の間を「or」で繋いだわけですけど、それが結果的に、何が起こるか分からない未来を前に立っている感覚を表しているような気もしました。何故、接続詞は「or」にしたんですか?
鈴木:「どうジャッジするか」でしかない、という意味での「or」だと思います。「こっちがどう決めるか?」という話をしている。そういうタイトルにしたかったんです。もしかしたら、「walls」と「bridges」が一緒のものであることもあり得ると思うし。
―物語って、どうしようもなく作り手のドキュメントになっていく部分もあるのではないかと思うんです。この『合歓る – walls or bridges』という作品には、Laura day romanceというバンドのドキュメント的要素はどのくらい入り込んでいると思いますか?
鈴木:僕個人としては、後編を作るに当たって選んだ「攻めたジャッジをアリとする」という選択は、自分たちが積み上げてきたものや、リスナーへの信頼を基盤にした選択でした。バンドがメジャーデビューもして、ここまで着いて来てくれた人たちに対して、変えたくない部分……主に質の部分ですけど、変わらない部分は変わらないままで、「新たな冒険をしに行きます」ということを伝えたかった。その選択によって生まれた今作のサウンドスケープなので、そういう部分は、バンドの歴史を踏まえた、バンドのドキュメントになっているという感じはします……けど、どうでしょうね。

―井上さんはどう思いますか?
井上:ボーカル的な視点から言うと、語り手の視点と、主人公の視点と、私自身の視点があって、それをバランスよく織り交ぜながら歌っていかなきゃいけない、という前提の上で、私自身の視点は『walls』よりも『bridges』の方が大きかったと思います。主人公になり切って歌うとか、客観的にただ語り手に徹するのではなく、「私自身の歌」として録ったテイクが採用されている比率が今回は多かったなと思う。歌い方も『walls』から『bridges』の間に変化しているし、その変遷が見える感じはドキュメンタリー的な部分と言えるのかな、と思います。それで言うと、全部の作品がそうだとは思うんですけどね。
―礒本さんは、今回のアルバムと自分たちのリアリティの繋がりという点はどう思いますか?
礒本:ここ2、3年の自分たちを考えたときに、凄くいろいろあったと思うんです。その中には誰かと折り合いがつかないこともあったし、そういうことに関して、メンバー間で日常的に会話をしていたりする。膝を突き合わせてすることはないけれど、なんとなくフランクに、そういう会話ができている。そういう積み重ねがあったから、作品のテーマを事前に明確に共有されなくても、このアルバムを僕自身も自分事として受け止められていますね。
あと、前編と後編でのサウンドの変化も、「これからバンドとして自分たちがどういう方向を向いて活動していきたいか?」ということが反映されている部分だと思うし、アルバムのテーマにしろ、サウンド感にしろ、バンドのドキュメントは凄く反映されているんじゃないかと僕は思います。
INDEX
メジャーデビューを経た環境の変化への向き合い方。「人として成長しようとする以外には道がない」(井上)
―11月の終わりにライブを観たときに、今のローラズは凄く自然体にバンドのステージが大きくなっていくことに向き合っているように見えました。その姿を見て、皆さんが「ローラズらしくある」ために、この1年の環境の変化にどう向き合ってきたのかということが、きっと今作に入り込んでいると思ったんですよね。この1年間を、ローラズはどんなふうに過ごしてきたと思いますか?
井上:それで言うと、「自然体で大きくなっている」と思ってもらえたのは凄く嬉しくて。私は、どんな状況になっても「なるべく気負わないようにしよう」と思った1年だったんですよね。あとは……単純に、場数がものを言っているような気がします(笑)。
鈴木:ははは(笑)。
井上:凄い数のフェスやライブに出させてもらいながら、『bridges』も作り続けて、ミュージックビデオも撮って……って、とんでもないスケジュールをこなしてきたので、その「やり切ってます」感(笑)。「やるしかないっしょ感」みたいなものが、最近は常に漂っているような気がしていて。
鈴木:体育会系のマインドになった?(笑)
井上:私たちの中に体育会系のマインドが宿った気がする(笑)。しかも、それが結構、効いている気がしていて。かなりキツいスケジュールもこなしてきたおかげで、「どんなステージでも、私たちは今までやってきたことをやるだけだから」って、いい意味での余裕が生まれているような気がします。

―井上さんのボーカルとして、フロントマンとしての佇まいもこの1年を通して変化しているような気がしました。特に井上さんはバンドのスポークスマンとして「Laura day romanceとはこういうバンドである」と説明する場面も多かったと思うんですけど、そうした中での意識の変化もありますか?
井上:思ったより、自分が本当に「やりたい」と思ったことがすべてなんだなとわかりました。周りの人からどれだけ「こういうふうに歌ったら?」と言われたり、「こういうふうな立ち振る舞いをしたら?」と思われたりしても、結局は、私たちが選択したことを突き詰めていくのが一番いいんだなとわかった。さっきも楽屋で言われたのですが、「あなたはカッコつけなさすぎる」とよく言われるんですよね(笑)。そういう部分がステージ上でも出始めているのかなと思います。元々、そんなに気取っているつもりもなかったけど、自分を良く見せようとする瞬間がもっと削ぎ落されていって、いつもの自分のままでステージに行けるようになったのかもしれないです。取り繕ってもしょうがない、というか。ねえ?
鈴木:うん。気合を入れすぎずに自然体でやって、それが今の自分たちが立つステージのサイズ感に合ってきているんだと思う。場数を経た基礎体力があるからこそ、「かかり」みたいなものでカバーしなくてもよくなっているというか。
―「かかり」って、お笑い芸人さんがよく使う言葉ですよね。「かかってんなぁ」みたいな。気合いが入っていて、その結果としてちょっと空回りしちゃう、みたいな。
礒本:「かかり」は最近の僕らのテーマなんです(笑)。
―裏を返すと、かかることの大事さもあったというか、そういう時期を経たからこそ気づいたことがたくさんあったんですね。
鈴木:そうですね。自分を大きく見せるパフォーマンスをすることも大事なときだってあるけど、近道しようとしたり、性に合わないことをし過ぎると、僕らの場合は本来のよさも失いかねないってことに気付きました。そこのブレはお客さんにも伝わってしまうものだと思うし。
井上:今の迅くんの話を聞いていて思ったのは、この1年、フロントマンとしてメディアに出させていただくことも多かったですけど、人として成長しようとする以外には道がないんですよね。音楽を通して、私という人間が見られている感じがめっちゃした。だからこそ、どれだけ取り繕ったり、飾ったりしても、本当に意味がなくて。自分の底力を常に上げていくしかないんだなって、諦めました(笑)。諦めたというか、腹をくくった。
―礒本さんは、この1年を振り返るとどうですか?
礒本:個人的には結構、苦しかったんですよね。正直「ライブが全然楽しくない」みたいな期間がかなり続いていて。その理由を紐解いていったときに思ったのは、僕は『walls』が出たとき、よくインタビューで「自分の仕事は舞台装置だ」みたいな話をしていたんです。そんな自分の役割に囚われ過ぎて、それゆえに凄く悩んでしまった。ライブ中に「あれ? 自分はなんのために演奏しているんだろう?」と思う瞬間もあったし、演奏中に発作を起こしちゃったこともあって。

―そうだったんですね。
礒本:でもいつからか、上手くいかないことや、自分の想定外のことが起こることを「面白いな」と思えるようになってきたんですよね。今までは「きちんと仕事をしよう」と思っていたけど、トラブルもきちんと受け入れてみると、もっと面白い世界が見えてくるんじゃないかなって。なので、最近やっとライブが楽しくなってきたんですよね(笑)。この間やったワンマンも、演奏終わったあとのひと言目が「ああ、楽しかった」だったので、そこはこの1年の間に、自分の中で起こった変化でした。
―今のお話って、まさにこのアルバムの作品性に通じるお話のような気もします。
礒本:確かに(笑)。
INDEX
サウンド面での新機軸。感情の深層に潜ることで辿り着いた、ダンサブルな要素
―サウンド面の話を伺うと、シングルで“ライター”が出たとき、冒頭から聴こえるパーカッシブなビートが、これまでのローラズのイメージと違って凄く驚きました。実際、今回の『bridges』は全編通してバンドサンドだけでなく、よりエレクトロニックな、ダンスミュージックやアンビエントなサウンドも積極的に取り込んでいると思うんですけど、制作スタイル自体に変化があったのでしょうか?
鈴木:後編を作るに当たり、MacBookを買いまして。DAWと言うんですかね、初めてLogicとかを利用した音楽制作に切り替えたんです。『walls』よりも、もっと過激で攻めたサウンドにしたかったし、アイデアもすぐに取り入れることができるようにするために、この選択はかなり効いてくるだろうと思って。
―実際、曲作りの体感は今までかなり違いましたか?
鈴木:DAWを使い始めてからは、これまで以上に「何もかも」が楽曲作りの起点になった感じがします。ちょっとした鍵盤のコードやリズムパターンも、とりあえず録っておいて、それがどんどん膨らんで楽曲になったり。そういう体験を、『bridges』の制作中には結構しましたね。
―個人的には、この『bridges』のサウンドはジャンル的な意味というよりは心持ちの意味でパンキッシュな感じがしたし、凄く肉体的な印象がありました。物語を描くという側面で見たときに、ダンサブルな要素があったりする今作のサウンドを通して、どんなフィーリングを描き出そうとしたのだと思いますか?
鈴木:そもそも、パソコンを導入することによって、自分のベッドルームから立ち上がっていくような音楽になるだろう、という予感があったんですよね。今回、サウンドは肉体的になりつつ、物語としては人の内側により入っていくようなものになっていると思うんですけど。
―まさにそう感じました。
鈴木:内側に入っていったら、より感情にフォーカスが向いて、感情を表現しようとしたら、肉体的なアンサンブルになった……っていう、かなりアンビバレントな感じなんですよね。なので、内側に潜っていったら、よりデカいエモーションがあった。そういうことなんだと思います。
―深く潜ることは、小さくなっていくことじゃなくて、むしろ大きくなっていくことだったんですね。
鈴木:そうなんですよねえ。外の事象を描く方がデカい曲になると思いきや、内側にある怒りや悲しみにズームアップして行った方が、肉体的な曲になったという。不思議な体験ではありましたね。

―今回のサウンドの変化は、井上さんの歌にはどんな影響を与えたと思いますか?
井上:いろんなジャンルが混ざったような曲が多いので、今までよりも自分の軸を意識しないと、いろんな人の物真似をしているみたいになっちゃうなと思ったんです。なので、自分のままでいろんな歌い方をしまくるというのは、今回のレコーディングを通して持てた振り幅だと思います。歌入れのときに、自分が「これ、やりすぎちゃったな」と思ったことに対して、プロデューサーの岩本岳士さんや迅くんが「想像と違う着地点だけど、このテイクがいい」と言ってくれたりすることがあって。そういう面白さが今回は発見としてあったし、本当にシンプルに、自分が成長した作品だと思います(笑)。