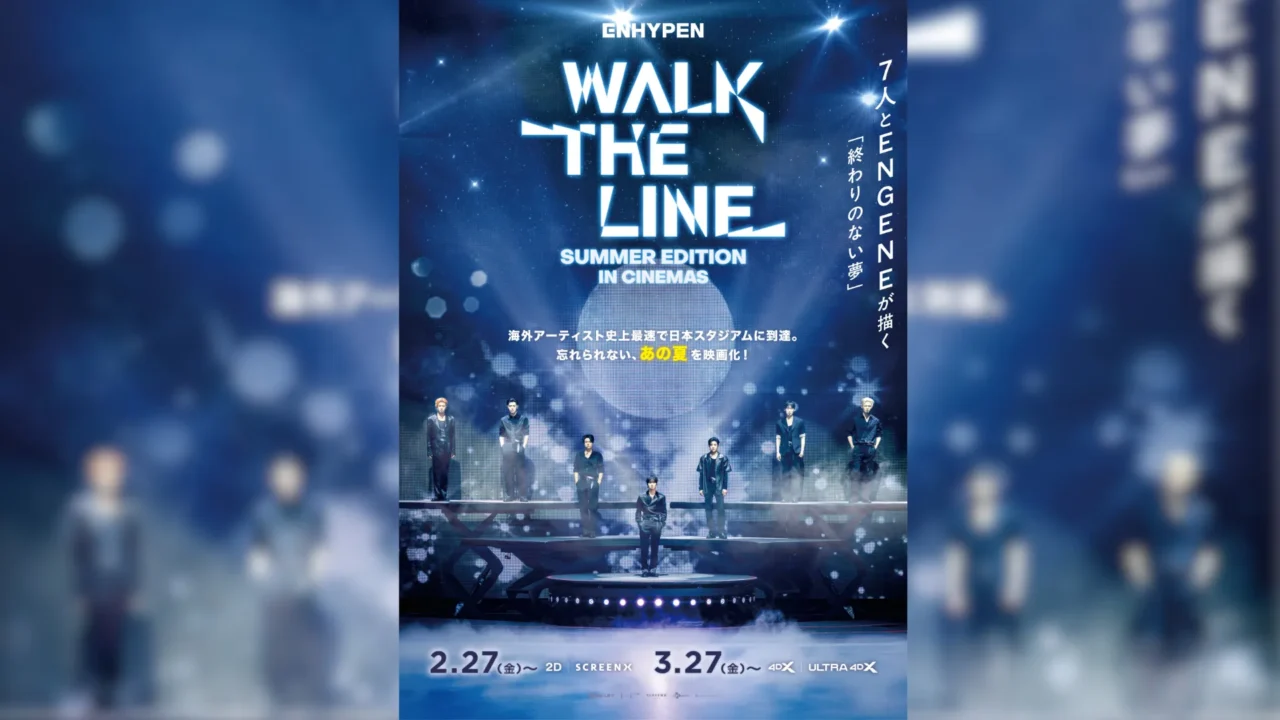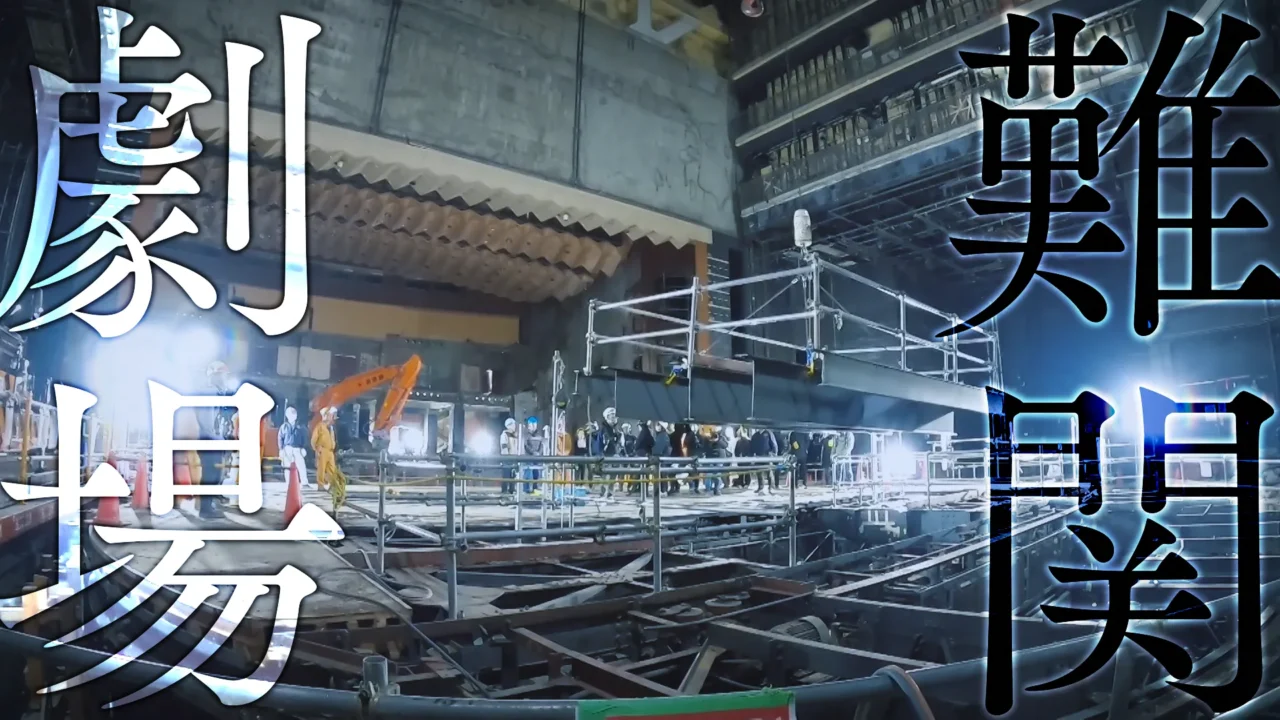INDEX
リスナーへの信頼を基盤に生まれた、バンドにとっての「新たな冒険」の始まりの作品
―前後編合わせた作品のタイトルとしては『合歓る – walls or bridges』と発表されていますが、「walls」と「bridges」の間にある接続詞は「or」、というところも印象的でした。もし、『walls and bridges』にした場合、ジョン・レノンの有名な同名アルバム『Walls and Bridges』(1974年)がありますが、この作品の存在は今作の前提にあるものですか?
鈴木:音楽的な面でインスパイアされたわけではないんですけど、あのアルバムの邦題『心の壁、愛の橋』のイメージは、今回の僕らのアルバムのコンセプトとのリンクを感じていました。あと、『心の壁、愛の橋』というアルバムが生まれた経緯や全体的な雰囲気も、参考にした部分があります。
―『心の壁、愛の橋』は、よく語られる歴史的に言えば、ジョン・レノンの「失われた週末」と呼ばれる時期から生まれたアルバムですよね。当時のアメリカ政府から煙たがられ、オノ・ヨーコとも別居して、カリフォルニアで愛人と一緒に暮らしながらお酒に溺れていたような、言わば失意の時期。そんな状況から生まれたアルバムを、鈴木さんはどんなふうに受け止めているんですか?
鈴木:自分としては、ジョン・レノンは「アップダウンの人」というイメージがあるんです。取っつきづらいだろうし(笑)、衝動的なんだけど、そこにある愛は本物……そんなややこしさがある人なんだろうなと思っていて。『心の壁、愛の橋』は、恋愛における躁状態のバックラッシュで生まれた絶望感も混ざっているように感じるんです。愛が大きい人の方が、逆行もデカいだろうし。そこは、自分たちのアルバムを作るうえでのヒントになりました。
―ローラズの場合は「walls」と「bridges」の間を「or」で繋いだわけですけど、それが結果的に、何が起こるか分からない未来を前に立っている感覚を表しているような気もしました。何故、接続詞は「or」にしたんですか?
鈴木:「どうジャッジするか」でしかない、という意味での「or」だと思います。「こっちがどう決めるか?」という話をしている。そういうタイトルにしたかったんです。もしかしたら、「walls」と「bridges」が一緒のものであることもあり得ると思うし。
―物語って、どうしようもなく作り手のドキュメントになっていく部分もあるのではないかと思うんです。この『合歓る – walls or bridges』という作品には、Laura day romanceというバンドのドキュメント的要素はどのくらい入り込んでいると思いますか?
鈴木:僕個人としては、後編を作るに当たって選んだ「攻めたジャッジをアリとする」という選択は、自分たちが積み上げてきたものや、リスナーへの信頼を基盤にした選択でした。バンドがメジャーデビューもして、ここまで着いて来てくれた人たちに対して、変えたくない部分……主に質の部分ですけど、変わらない部分は変わらないままで、「新たな冒険をしに行きます」ということを伝えたかった。その選択によって生まれた今作のサウンドスケープなので、そういう部分は、バンドの歴史を踏まえた、バンドのドキュメントになっているという感じはします……けど、どうでしょうね。

―井上さんはどう思いますか?
井上:ボーカル的な視点から言うと、語り手の視点と、主人公の視点と、私自身の視点があって、それをバランスよく織り交ぜながら歌っていかなきゃいけない、という前提の上で、私自身の視点は『walls』よりも『bridges』の方が大きかったと思います。主人公になり切って歌うとか、客観的にただ語り手に徹するのではなく、「私自身の歌」として録ったテイクが採用されている比率が今回は多かったなと思う。歌い方も『walls』から『bridges』の間に変化しているし、その変遷が見える感じはドキュメンタリー的な部分と言えるのかな、と思います。それで言うと、全部の作品がそうだとは思うんですけどね。
―礒本さんは、今回のアルバムと自分たちのリアリティの繋がりという点はどう思いますか?
礒本:ここ2、3年の自分たちを考えたときに、凄くいろいろあったと思うんです。その中には誰かと折り合いがつかないこともあったし、そういうことに関して、メンバー間で日常的に会話をしていたりする。膝を突き合わせてすることはないけれど、なんとなくフランクに、そういう会話ができている。そういう積み重ねがあったから、作品のテーマを事前に明確に共有されなくても、このアルバムを僕自身も自分事として受け止められていますね。
あと、前編と後編でのサウンドの変化も、「これからバンドとして自分たちがどういう方向を向いて活動していきたいか?」ということが反映されている部分だと思うし、アルバムのテーマにしろ、サウンド感にしろ、バンドのドキュメントは凄く反映されているんじゃないかと僕は思います。