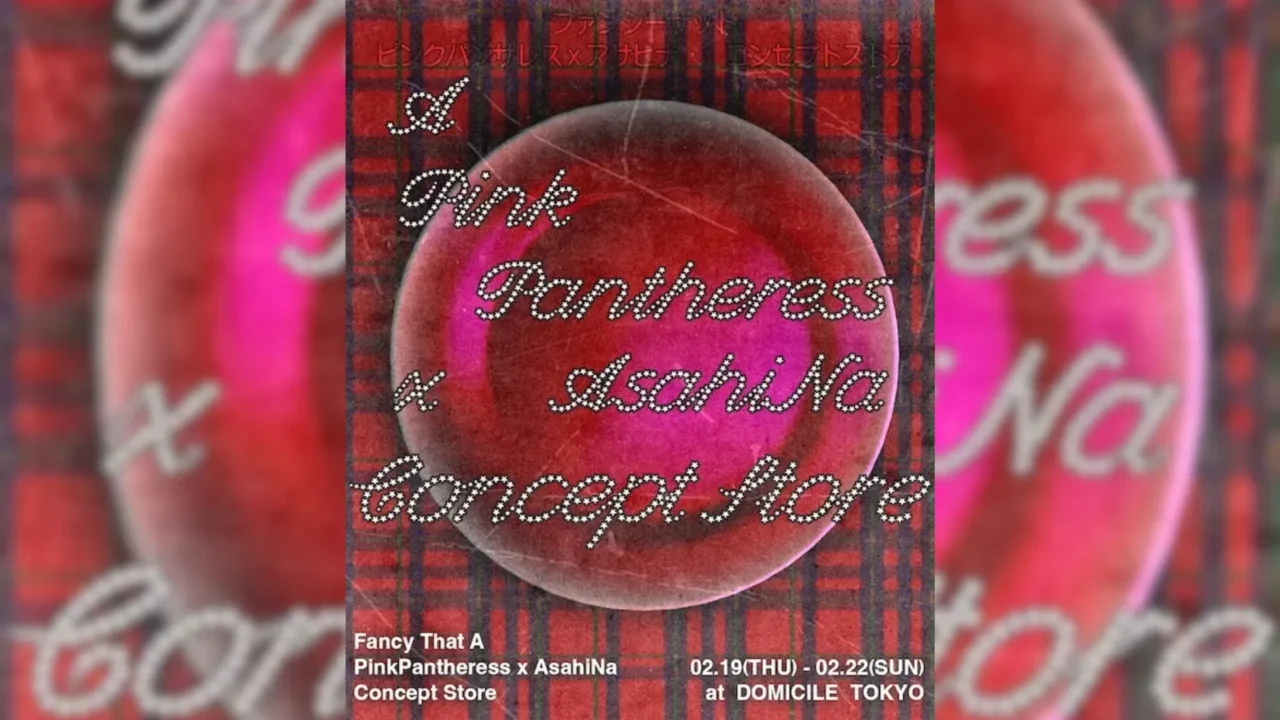INDEX
現在における、アクセシビリティのベスト
―今作のアクセシビリティを説明した文言にある「理解するためのサポート」ではなく「想像することを楽しむための工夫」という表現がワクワクするもので、とてもいいなあ、と感じました。つまり今作で私たち観客は「創造的なアクセシビリティ」を体験できる。「アクセシビリティディレクター」という仕事について、そして今公演のアクセシビリティの取り組みについて、栗栖さんに伺いたいです。
栗栖:障害のある人が出演したり、足を運んだりする作品を手がけた経験がない主催さんだと、配慮をするポイントや予算の組み方など、不明点がいっぱいあると思うんです。私の役割はそういった現場に企画段階から伴走して、アドバイスをしていく仕事ですね。
―公演ごとに、お仕事内容は多岐にわたりますね。
栗栖:オーディション一つとっても、障害のある人をオーディションするのは審査のポイントが通常と違いますから、そうしたこともプランニングします。そして音声ガイドや字幕、鑑賞サポートといった部分の設計まで、初めから最後までいろいろなパートに伴走するイメージでしょうか。今作では、パラリンピックから更に進化した、現在におけるアクセシビリティのベストを出せると考えているので、ぜひご期待いただきたいです。
「誰もが楽しめる舞台」への挑戦
・感覚をひらく、共に創る舞台
創作段階から多様な観客を想定したクリエーションを展開。「視覚と聴覚、両方駆使しなければ舞台は楽しめない」という、従来の常識を超え、「聴覚だけ」「視覚だけ」「視覚と聴覚両方でも」それぞれの方法で楽しめる舞台の創作を目ざして、構成・振付・音楽・テキスト・映像など、多彩なクリエイターとともにアイデアを凝らして創ります。・身体で奏でる、もう一つの「おんがく」
手話をベースに身体で「おんがく」を再構築する「サインミュージック(Signed Music)」を実践するろう詩人・Sasa-Marie をサインミュージックのドラマトゥルクに迎え、森山による振付とともに、〝目で見る世界を通じて「おんがく」を楽しむ”新たな舞台体験を生み出します。・想像力を導く、ひらかれた観劇体験
劇作家・演出家の三浦直之は舞台上の言葉だけではなく、音声ガイドの台本も手がけます。これは本作の大きな魅力。視覚に障害のある方のための情報保障にとどまらず、観客の誰にとっても、想像力で物語の世界を広げるガイドとなるよう制作します。・自由に選べる、観劇のスタイル
「音声ガイド」「字幕」の鑑賞サポートを、個人のスマートフォン等の端末に配信するシステムを採用することで、障害の有無にかかわらず、だれでも自由な座席から手軽に利用できるように試みます。・アクセシビリティ専門家の活躍と実践研修の提供
舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』公式WEBサイトより
上記の試みを実現するために、様々なアクセシビリティの専門家が活躍しています。また、アーツカウンシル東京「芸術文化分野の手話通訳研修プログラム」を修了した手話通訳者に、実践研修の機会を提供します。
―さらには先ほどお話していたような、リサーチを助けて当事者視点の重要さを伝え、ろう者のアーティストと障害のないアーティストの間で通訳的な役割を担ったりと、演劇でいうドラマトゥルク(※)のような役割も果たしているわけですね。
栗栖:こうした公演は、いろいろなコミュニケーションが発生するんです。例えば聴覚障害者のために音楽を可視化したいと考えたときに、蓮沼さんと舞台美術の連携が必要になる場面もあるでしょう。そうした通常だとあまりないクリエイター同士のやり取りがマルチに発生するんですね。なので全体を俯瞰するのも私の仕事です。それぞれが少しずつ表現を補い合いながら、観客が誰一人取り残されることなく、それぞれの立場、それぞれの角度で作品の世界を楽しむことができる。今作はそうした、とっても優しい作品なんです。
※演劇の創作現場において生じるあらゆる知的作業に関わり、そのたびごとにサポート、助言、調整、相談役などの役割を各ポジションに対して対等に果たす役割。