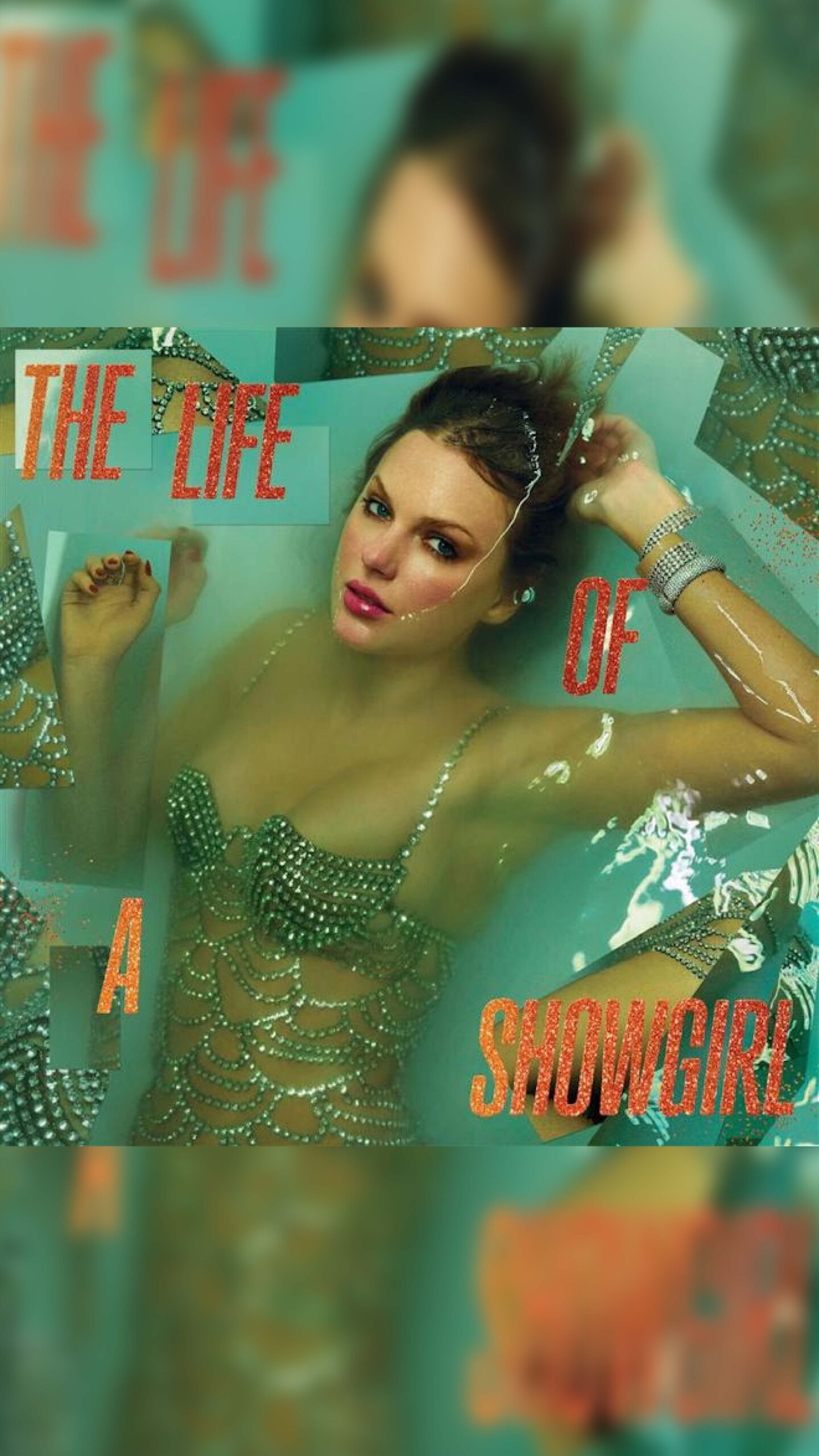INDEX
ポップスターとしてのテイラー・スウィフト像をあえて演じる
もっとも、5年ほど前にはドキュメンタリー映画『ミス・アメリカーナ』やアルバム『folklore』などを通じて、実際の私的な自分が、世間から見られるイメージとは異なることを伝えることに注力していたテイラー。だが本作はむしろ、皆が認識するポップ・スターとしてのテイラー・スウィフト像、つまり(言い方は悪いが)私生活を切り売りしてポップソングを作るアーティスト、というイメージをあえて自ら見せつけているような色合いが強い。それは上記のケルシーとの婚約に加え、この作品が2023年から2024年末にかけて行われた『エラズ・ツアー』からインスパイアされていることも関係しているはずだ。自身のこれまでを総括するワールドメガツアーをやりきったことで、「世界で最も売れている」=世界で最も多くの人からその動向を見られているアーティストとしての自覚そのものをコンセプトとするに至ったのだろう。自作自演のアーティストは大概セルフイメージの独り歩きを警戒するものだが、テイラーがあえてそれを逆手に取ってここまで振り切れるのは、ポップスターとしてトップオブトップに君臨していることへの確信がいよいよ揺るぎないものになったことの証拠だろう。
”Elizabeth Taylor”や”Elderest Daughter”では、心の拠り所としてのプライベートが、人前に見せる自分自身を揺るぎないものとしてくれる様子を提示しているように、本作ではオフィシャルな自分の在り方を決して否定してはおらず、むしろ公と私のセルフイメージの距離やその重なり合い具合を楽しんでいるような印象さえある。マックス・マーティンとシェルバックーーテイラーがトップアーティストへと飛躍した黄金期の作品『Red』、『1989』、『Reputation』を支えたプロデューサーたちとの再タッグによる歯切れのいいサウンドメイクと王道ポップス的なアレンジも、言わばセルフオマージュかのようだ。ただその一方で、彼らの手による本作のバウンスするエレクトロビートは、今時ではあるもののどこか紋切り型的にも感じられる。それこそがまさに本作に空虚なムードを与えている要因の一つでもあるのだが、逆説的に見ればかえってそれが、本作が「スターとしてのテイラー像」を俯瞰したものであることを示唆しているように感じられてくる。
うっすらと空虚な質感を纏いながらも、ハムレットのオフィーリアのような運命を辿らなくて済んだと歌う”The Fate of Ophelia”にはじまり、主体性を失わないことを積極的に歌う曲が多い点も、本作の奇妙さを加速させている。プラスティックなポップソングの中でも主体性を失わない様に説得力を持たせられるのは、自らの手で揺るぎない地位を築いた現在のテイラーにしかあり得ない芸当だ。
彼女が過去作の原盤を自らの手に取り戻した逸話を想起させる、ジョージ・マイケルの同名曲をサンプリングした”Father Figure”の1980年代ポップスのような多幸感もそのハイライトだし、チャーリーXCXヘの応酬ソングと言って差し支えない”Actually Romantic”や、どんな悪口を言われようが炎上しようがへっちゃらだというような境地を歌った”CANCELLED!”ではもう無敵状態。メガポップスターとしての自らの運命や使命、役割を怯むことなく引き受ける胆力を見せつけていて、その迷いのなさは、たった5年前と比較してもすでに全く違う地平にいる彼女の現在地を感じ取らせる。