21世紀に入って四半世紀が経とうとしている。25年という期間は、The Beatlesの『Abbey Road』(1969年)からAphex Twinの『Selected Ambient Works Volume II』(1994年)の時間の隔たりに相当する。では直近の25年、音楽はどのように変化していったのだろうかと振り返ってみたくなる。
2026年に活動20周年を迎える音楽家、蓮沼執太。この記事では、その四半世紀分の音楽遍歴、そして蓮沼執太チーム名義の1stアルバム『TEAM』に至るオリジナルアルバム群を批評家の佐々木敦を迎えて紐解いている。
キーワードとなったのは「2001年をひとつのピークとした音楽のモードの更新と停滞、その後」。蓮沼執太は、どのような足跡をたどり、どこへ向かおうとしているのか。
INDEX

1983年、東京都生まれ。蓮沼執太フィルを組織して、国内外での音楽公演をはじめ、映画、演劇、ダンスなど、多数の音楽制作を行う。また「作曲」という手法を応用し物質的な表現を用いて、彫刻、映像、インスタレーション、パフォーマンス、ワークショップ、プロジェクトなどを制作する。2025年11月、蓮沼執太チーム名義の1stアルバム『TEAM』をリリース。2026年、活動20周年を迎える。
音楽文化の何かがピークを迎えた20世紀末
―蓮沼執太チームの新作『TEAM』のエンジニアをTortoiseのジョン・マッケンタイヤが手がけていて、NiEWでは対談も実施しました。今回、蓮沼さんのキャリアを振り返っていく前に、1990年代末、2000年代前半のおふたりのリスナーとしての感覚についてお聞きしたいです。
蓮沼:Tortoiseの『Standards』(2001年)を聴いたのは高校生のときでしたけど、R&Bとかヒップホップも含めて音楽自体が面白くてリスナーとして楽しんでいました。今のSpotifyのプレイリストみたいな感覚かもですが、毎週レコード屋さんの試聴機が変わって、それを聴いてるだけで勉強になったというか。全体的に新しいものを聴きたい、見つけたいっていうエネルギーがあったんじゃないかなと思います。
佐々木:『Standards』のときに高校生だったんだ! それもすごいけど、そこから20年以上も経ってるってすごくない?
蓮沼:そうですよ、もう42歳です。

佐々木:僕自身の2001年を振り返ると、音楽の仕事をめちゃくちゃ張り切ってやってた末期みたいな時期。「HEADZ」の事務所を渋谷に構えたのが1995年5月で、当時からいわゆるポストロックやエレクトロニカなどに音楽ライターとしてコミットするようになっていました。
蓮沼:『FADER』も読んでました。
佐々木:『FADER』創刊号を出したのが1997年9月ですね。Tortoiseは『Standards』からHEADZのリリースになったんだけど、僕らにとっては圧倒的に大きい存在だった。ポストロックの台風の目としてすごく売れたし、来日もめちゃくちゃお客さんが入った。
あくまで僕の感覚だけど、1990年代の後半から21世紀に入ったぐらいがTortoiseを中心とするポストロック的な何かが超頂点を迎えた時期だったと思うんですよね。Fenneszの『Endless Summer』が2001年で、それ以降はいわば「エレクトロニカ以後」の世界になっていく。
佐々木:僕的には2001年ぐらいが音楽のピークで、大きな流れとしてはそれ以降、退潮していった認識です。もちろん散発的には才能のある人はいっぱいいるし、細かく見ればいろんなことがあるんだけど、その先はいわば応用編。いろんなモードやいろんなスタイル、例えばハウス、ヒップホップ、ハウス、テクノ、ドラムンベース、エレクトロニカ、クリック、ドローン、グリッチとか、1990年代はもう凄まじい勢いで出てきて面白かった。
1990年代の終わりぐらいまでは、何か決定的に新しいモードとかスタイルを生み出すことが可能だったし有効だったと思います。その「音楽のモードの更新」が2001年あたりで停止した感覚がどうしてもあるんですね。そしてそれは別に悪いことでもない。そのときに蓮沼君が高校生だったというのは衝撃的だな。でも蓮沼君は、それ以前から音楽好きだったわけでしょう? 高校生で突然目覚めた、みたいなことじゃないですよね。
蓮沼:そうですね。いろいろ聴いてないとたぶん、高校生でTortoiseにたどり着けなかったと思います。

INDEX
音楽のモードの更新と停滞、その後——蓮沼執太が「時代の申し子」たる所以
佐々木:1980年代から2000年代の頭の辺ぐらいまでは、音楽の時代だったと思います。1990年代まではユースカルチャーの中で音楽という趣味の位置が上位にあった。
そのピークが2001年ぐらいだったという感じが、レーベルをやったりライブを企画してた僕の肌感覚としてあって。いつの時代もマニアックな人はずっといるけど、「たしなみ」として、今ならマニアックと思われるような音楽を聴く人の母数はそのあたりから減っていったとは感じてますね。

批評家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。ミニシアター勤務を経て、映画・音楽関連媒体への寄稿を開始。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、早稲田大学文学学術院客員教授やゲンロン「批評再生塾」主任講師などを歴任。マルチスペース「SCOOL」共同オーナー。現在、映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師、早稲田大学非常勤講師、立教大学兼任講師。著書多数。最新刊は『メイド・イン・ジャパン 日本文化を海外で売る方法』(集英社新書)。
蓮沼:今とまったく違うなと思うのは、インターネットがなかったり、リスナーのコメントがたくさん入ってくる状況ではなかったことで。自分で足を使ってマニアックなものからメジャーなものまで知っていきました。その中でレコード屋さんのバイヤーさんの紹介、批評家が書くレビューなど、とても価値が大きかったです。レコード屋さんが出している冊子、『bounce』とか、WAVEが出してたフリーペーパーをスクラップして保存してましたから。そういう文化の中で新しいものが生まれている感覚は感じてました。
佐々木:でも、その5年後にはデビューしているわけですね。
蓮沼:まあデビューというか、一応1枚目のリリースは2006年でした。
佐々木:割とすぐに作り手に回っていった?
蓮沼:そうでもないですね。当時は渋谷にあったDMRというレコード屋さんで働いたり、音楽をひたすらずっと聴いてましたね。そういう中で面白いものもその都度発見があるし、聴き方がだんだん変わってくる感じだったかな。
あとは「新しいものがすべてというわけではない」とも感じていました。それこそ大学生のころは時間があったので、昔の音楽を聴けるチャンスだったし、音楽のより深いところを知っていく行為の真っ只中で。例えばFenneszで言うと、『Endless Summer』の次の『Venice』(2004年)はさらに深い感じになっていて、発展というより、成熟していく感覚もありました。

蓮沼:僕にとってはそういうことって音楽シーンどうこうではなく「面白ければいい」って感じで、自分の耳で良さを見つけていくみたいな感じで楽しんでいました。そういえば佐々木さんがHEADZでFenneszのライブ盤(2003年『Live in Japan』)を出したじゃないですか。あれはちぎれるぐらい聴いてましたよ。
佐々木:あれは売れたね。セールス的には2000年代前半ぐらいまでは1990年代の盛り上がりの残響がまだある感じだったと思う。今は売れないものと売れるものの差が極端に激しくなっているけど、昔は話題になれば平均してまあまあ売れてた。蓮沼君がデビューしてからの20年って音楽業界は激動だった。東京の人だし、音楽が趣味の王様だった時代に10代を過ごしたわけで、ある種「時代の申し子」だなと改めて思いますよ。
要するに2000年代以降は「もう新しいものはない」というポストモダン的な状況で、様式はほぼ全部出揃っていて、しかもちょっと勉強すれば使用可能で、だからこそみんな横並びになってしまうんですね。その上で、ただ使うってだけではもう誰も新しいモードを認めてくれないし、面白いと思ってもらえない。
そんな状況の中で、さまざまな要素をどう足したり、掛け合わせたりかっていうセンスの時代に突入したと思っていて。使えるものをどうプロセシングしてアウトプットするかが一番重要なことだと考えると、蓮沼執太の20年を振り返ることで音楽のモードの更新、停止以後の20年を考えることにもなるんだと思う。

INDEX
蓮沼執太の多彩、多岐にわたる活動のスタート地点
―蓮沼さんはデビュー作品を制作するにあたって、どんなことを考えていたのでしょうか。
蓮沼:当時はフィールドレコーディングをして、パソコンで音を出すことに熱中していました。デビュー作では楽器を演奏した音をあまり入れたくないと思っていましたが、結果的に楽器の存在に頼っている部分もあります。何らかの音楽的な思考とか意図があったというより、形にすることをすごく考えていましたね。
蓮沼:でも今考えると、空気が通ってる音としてフィールドレコーディング、空気を通さない音としてパソコンで作る音があって、そこにメロディーや旋律っていう自分の中から浮かび上がってくるものを混ぜるというか。そういうミックスされたものを作りたかったんだなと思います。で、時代はエレクトロニカなのでアウトプットは、エレクトロニカになったって感じです。
―佐々木さんは、どのタイミングで蓮沼さんの活動を認識されたんでしょうか。
佐々木:2007年ぐらいでしたかね。蓮沼君は当時NTTインターコミュニケーションセンター(ICC)でアルバイトをしてて、僕の親友の畠中実とのつながりで「音楽やってるんですよ」って聴かせてもらったのが最初かな。
僕自身はソフトウェアを使い倒して作られた音楽に飽き始めていた時期で、音源をもらって、レーベルやってる人として話をしたような記憶があります。
直感的に、「もっとメロディアスな方向性で、電子音楽だけど歌心があるものが蓮沼君はできる気がする」みたいなことを言って、『POP OOGA』(2008年)をHEADZで出すことになって。こんなに長い付き合いになるとは思わなかったですね。
蓮沼:僕もそう思います。
INDEX
ポップミュージックを視界に入れた『POP OOGA』という最初の分岐点
―蓮沼さんのキャリアにおいて、2008年に歌を入れた作品を作ったのは大きな分岐点のように思います。
蓮沼:この作品はもう1年ぐらい毎日向き合って作っていたんで、今思うとそんなアルバムないですよね。佐々木さんに「今までやってきたことを全部出せ」みたいに言われたのを覚えてます。当時はCD-Rに音源を焼いてたんですけど、たまにHEADZのイベントに遊び行ったときに「デモなんですけど」って渡して、「返事来るかなー」みたいな(笑)。
佐々木:蓮沼君が最初に事務所に来たときも、HEADZで出したいから来たわけじゃなかったよね。
蓮沼:そうです、そうです。
佐々木:でも思い出してみると、僕には「これはレーベルの戦力になるんじゃないか」って意識がやっぱりあった。
―2008年の9月に『POP OOGA』が出て、2008年の11月に蓮沼執太チームが結成されます。
蓮沼:その前にレコ発で「チーム ポップ オーガ」っていう編成でやったんです。リリースが近かったから、ASUNAの嵐(直之)君とかキノピー(木下美紗都)にも出てもらって。バーチー(蓮沼執太フィルのメンバーの千葉広樹)もいたし、植野さん(テニスコーツの植野隆司)とかもいた気がします。
―バンド編成を提案されたのは佐々木さんだったそうですね。
佐々木:詳しくは覚えてないけど、レコ発をやるならラップトップでやるよりやっぱりライブっぽいことがあったほうがいいよね、って話でした。まあ言ってしまえば、こっちは無理難題を言ってるだけというか。バンド編成とか、フィルのような大編成でやってみたら、って言ってみると、本当にそれを実現してしまう。蓮沼君にはそういう才能と馬力があるなと思いますね。そもそもフィルより先にチームがあるんだもんね。
蓮沼:そうです。チームを母体にして、その拡張としてフィルに発展させていったので。
INDEX
日本のカルチャーの新たな拡張、雑誌文化の低迷、震災

―ソロ名義の『POP OOGA』、蓮沼執太フィルの『時が奏でる』には約5年のインターバルがあります。その間、『wannapunch!』(2010年)や『CC OO』(2012年)といったコンセプトアルバム、EPを複数リリースし、2011年にはのちにフィルバージョンも発表されたシングル『Earphone & Headphone in my Head』をリリースしています。蓮沼さんのキャリアにおいてどのような時期でしたか?
蓮沼:どんどん外と接続していく感覚ですね。「イベントも作品だ!」ぐらいの感じでやっていました。どこかで音楽を音盤とかライブに落とし込むのに飽きてるというか、もっとエクスパンデッドしたいという思いはあった。時代的には本当にジャンルがわけわかんない状態で接続されている感じもありましたよね。あの感じって何だったんですかね。
佐々木:確かにね。2000年代後半は僕が演劇にハマって、蓮沼君が快快(ファイファイ)とやるとか、三浦康嗣(□□□)が劇団ままごとの『わが星』の音楽を作る流れもありましたよね。
音楽と他のジャンルとの関係性、ネットワークが生まれていく感じがすごく面白かったし、盛り上がった。その中で、やっぱり蓮沼君も本当にいろんな人とつながっていって、今に至ったところはあるよね。
蓮沼:間違いなくそうです。
佐々木:2001年に音楽のピークがあったって勝手に僕は言ってるけど、その10年後にカルチャーのピークがあったと思うんです。すごくローカルで、マイナーなカルチャーのミックスのピークが2010年ぐらいにあった。
その少し前からCDが売れなくなり、イベントも人が入らなくなり、『Snoozer』(2011年6月号で廃刊)や『STUDIO VOICE』(2009年9月号で休刊)がなくなり、雑誌文化も2000年代の後半ぐらいにひとつの限界を迎えて、いろんなことが起きましたね。
蓮沼:僕は結構鍛えられてるというか、全然潤ってないところでずっとやってるんで、かなりタフにはなってる自覚があるんです。
佐々木:なかなか重いね、その発言(笑)。重いし、頼もしい。
蓮沼:意外と大切なことだと思います。
佐々木:タフにならないと生きていけないよね。
蓮沼:そうですね。それって自分のやりたいことを実現していく純度を高めていくには大切なことで。体力的にもそうだし、メンタル的にも折れないことは僕の活動においては大きいです。
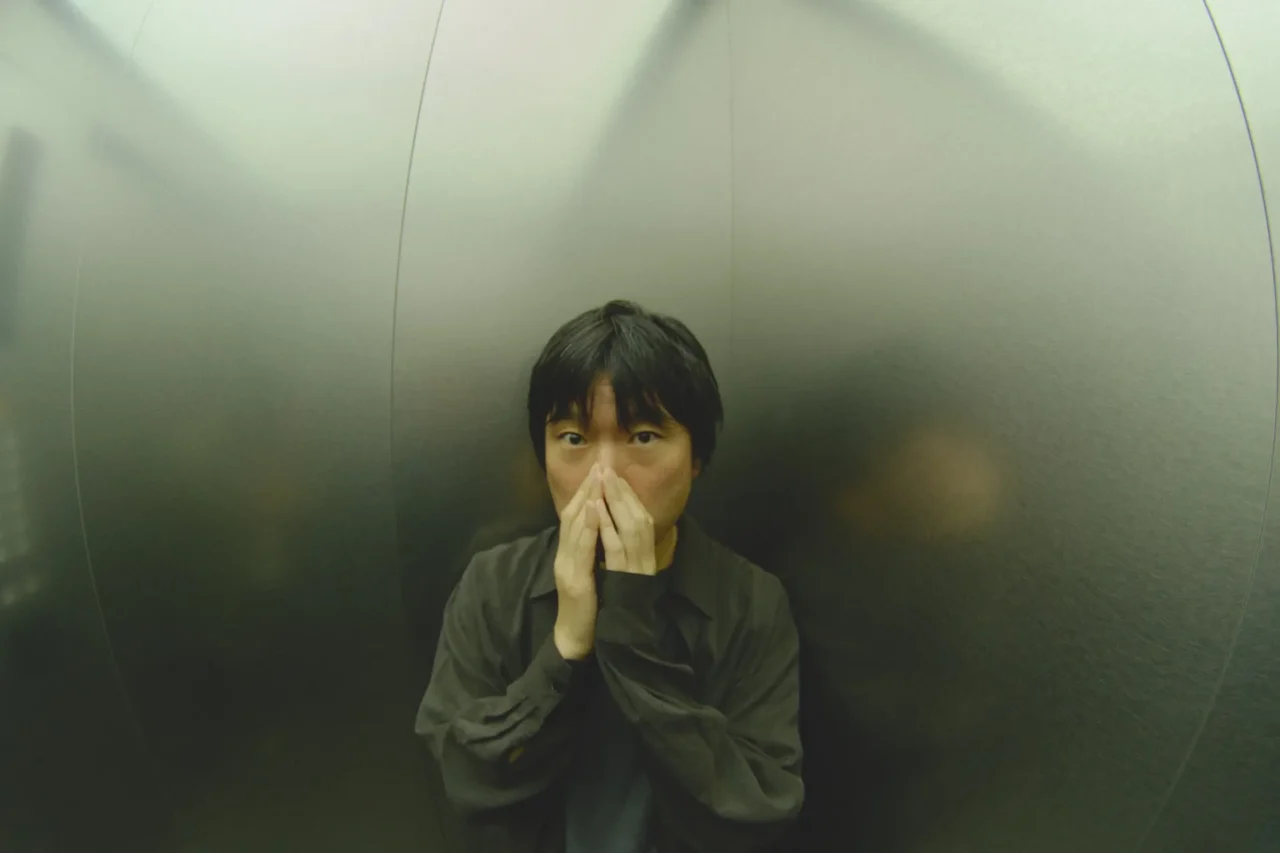
佐々木:そういう音楽や雑誌文化の状況の変化の中で、2011年3月の東日本大震災で断絶が起きたという。3.11は原発をはじめ、テクノロジーに対する不信を生むきっかけでもあったわけですし。
―震災は日本特有の転換点でもありながら、やや俯瞰してみると、ストリーミングが世界的に浸透する直前の時期で、これまでのテクノロジーの発展を背景にしてきた音楽文化がどこへ向かうのか、可能性を模索していたような感覚もあります。
佐々木:2000年代以降に激増したコンピュータで音楽を作る人たちの一部に、ラップトップを閉じて耳を澄まそう、みたいな感覚も生まれたような気がしますね。
蓮沼君は震災以前からフィールドレコーディングをやっていましたけど、主にエレクトロニックなミュージシャンが、アコースティックや生音的なもの、環境音に目を向ける動きが無意識レベルも含め、あったと思う。
蓮沼:自分の活動自体としては、この時期は表現をどう拡張していくかってことに意識的になっていましたね。もちろん、震災は怖かったし、何もできなかった思いがずっとありますが。
当時は快快をはじめ劇団やダンスと一緒にやるとか、その少しあとには古川日出男さんとのコラボレーションを経験しましたけど、それはジャンルをミックスしていたってこと以上の意味とか価値があったと思います。音楽以外のジャンルの世界に体系的に参加させてもらったことに意味があるなって。
―今の多彩な活動につながる土壌が形成された期間だったと。
蓮沼:そうですね。音楽の活動と並行して、例えば展示を作ったりっていう活動も同時にありましたし。
INDEX
蓮沼執太フィルがそのキャリアにもたらしたもの
―2013年の『時が奏でる』やフィルで蓮沼さんの活動に出会った人も多いんじゃないでしょうか。
蓮沼:そう思います。『時が奏でる』は僕が主導して作ったというより、エンジニアでフィルのメンバーの葛西敏彦さんが「そろそろまとめたほうがいいんじゃない?」って言ってくれたんですよ。僕自身、そんなに自分の意志で突き進んできたというより、周りが言ってくれるんだったらっていうことが性格としても大きくて。だからフィルも自然とライブで育んでいった感じです。
佐々木:フィルを続けていくつもりは最初はなかったんじゃない?
蓮沼:そうですね。新しいチャレンジだなってくらい。やっぱり佐々木さんみたいに外から「面白いんじゃない?」って提案してくれる人がいるっていうのは、すごく大きいんです。そうやってチャレンジをしていくなかで出会った仲間から学ぶことも多いし、その連鎖が活動になっていく。だからフィルは完全に佐々木さんだからなせるチャンスオペレーションです。
佐々木:フィルって、もともとラップトップを使って1人で音楽を作っていた蓮沼君が、ある種の共同体的なものに身を置いて創作するという挑戦でもあったわけじゃない?
蓮沼:そうですね。僕自身、自分が思う通りにしたいというタイプじゃないし、ゴールとか目的があって生きてるわけじゃない感覚が強いので。
佐々木:力強いリーダー感は出したくないってことだよね。でもこれだけの人数の音楽家たちと一緒にやる、しかも自分より年上の人もいれば、もともとの活動領域が全然違う人もいたり、アンサンブル全体の中では個別の人間関係もあるだろうし、これは大変だろうなって思う。それを長く維持してきているのは、やっぱり並大抵のことではないですよね。
―蓮沼さんのキャリアを見ていくときに、「個」と「集団」という創作手法の違いは重要な要素ですよね。あるいは「家」で自ら録音するというのと、バンドやフィルでスタジオなど「外」で録音するということも各々の作品性に大きく関わっているように思います。そう捉えたときに、『時が奏でる』であり、フィルは活動の大きな転換点だったんじゃないでしょうか?
蓮沼:フィルはおっしゃるとおり、人とやるっていう集合と離散を繰り返すもので。フィルは集合知で曲を作るとか、集団性をもとにした挑戦のきっかけになったし、自分と他者というものをクリエーション面で考えていく発想も生まれました。
間違いなく新しいアウトプットになっていきましたね。フィルでの経験を別の美術の作品に転換するであったり、音を通して関係性を築くという視点が生まれたのは大きかったです。

INDEX
「歌」にフォーカスした『メロディーズ』
―2016年にはソロ名義の『メロディーズ』を発表されます。
蓮沼:『時が奏でる』のリリースツアーもあって、この時期はものすごく過密にずっと何かやってたので、インプットしようと思って2014年にニューヨークに行きました。
あとはこの少し前の時期に、坂本美雨さんとアルバム(2014年『Waving Flags』)を作るとか、赤い公園のサウンドプロデュース(2014年『猛烈リトミック』)とか、Negiccoの編曲(2015年“自由に”)とか、ポップミュージックに関わる機会があったのも大きいんじゃないかなと思います。
―『メロディーズ』はフィルでさらに加速した歌心が生かされている印象を受けます。
蓮沼:僕は曲の作り方をいつも変えたいと思っていて、『メロディーズ』は自分の声から旋律を作っていったんです。曲は鍵盤を触ってるといくらでも作れるわけで、でもそういうものとは違った、自分の中から出てくるものを試したいと思って。「歌」で自分なりのものを作ってみようということで、「声」にフォーカスして曲を作っていったのが『メロディーズ』です。
これは今でも思っていますけど、僕はミュージシャンではないんですよ。「僕はこれです」って楽器があるわけでもないし、でもそういうわけにはいかない。自分にあるのは「音を作ること」なんじゃないかと思って、『メロディーズ』を作ってる途中ぐらいにEMSのSynthi Aっていう極めてシンプルなアナログのシンサイザーを買ったんですよね。
―音楽の領域においても活動範囲が広がりつつ、サウンドのポテンシャルを深めていった期間のように感じますが、バランスを意識することはあったんでしょうか?
蓮沼:バランスではないですね。バランスを取ろうと思ってやってるわけじゃなくて、両方が同時に走ってる感じかな。

INDEX
多岐にわたる活動は個別バラバラではなく、すべてが有機的につながっている
―2017年にはU-zhaanさんとの『2 Tone』を発表しています。このあたりで生楽器と電子楽器の違いに本質的な差異はない、つまり響きがあり、記録されるという点で同じなのではないかという認識を持たれるようになったそうですね。それは、音楽家として新たな地平を見たというような感覚なのでしょうか。
蓮沼:いや、もう1stアルバムの時点で生楽器や環境音、電子音を組み合わせているので、自分の中にはそもそもあったあった認識だと思います。『2 Tone』に関しては、他者が鳴らした生の音を対等に扱うことができるようになったという感覚でした。それもフィルと似たような話なんですけど、自分と他者の関係性によって作品が変わっていくってことにより自覚的になった、ということだと思います。
―2018年のフィル名義の2枚目『アントロポセン』、2020年の蓮沼執太フルフィル名義の『フルフォニー』を経て、新型コロナウイルスのパンデミック以降の『unpeople』(2023年)でまたキャリアの転換期を迎えたようにも見えます。サウンド的には、それまでの経験で培ってきたもの携えて初期にやっていたエレクトロニックなものに回帰した側面がありますね。
蓮沼:そう見えますよね。でも単純な話、ずっとやっているんです。つまり『POP OOGA』のような路線をやめて、フィルをやっていたわけじゃない。技術力は上がっているし、U-zhaanはタブラで、灰野さんは歌で、というようにコラボレーションの蓄積があって、その都度、進化をしてこれたんじゃないかなという感覚なんです。
―実際に『unpeople』ではCornelius、ジェフ・パーカー(Tortoise)、灰野敬二さんをはじめ、個と個によるコラボレーションの密度や深度も上がっているように感じます。
蓮沼:『unpeople』は、コンセプトがないってコンセプトで、パツンとモードを切り替えて曲を作ったんで、またちょっと違うんですけど。やっぱり『unpeople』はいろんなことが積み重なってきた中、パンデミックで時間ができて曲を作ったのが形になっていったところがありました。
―2023年にはフィル名義の3枚目『シンフィル』もありますし、いろんな活動が同時に走っている感じがやはりありますね。
佐々木:蓮沼君のキャリアを見ると、前の作品を踏襲したり、単に変えたりというだけじゃなくて、どんどん横に広がっていく感覚がある。いろんなアイデアを実現していく馬力はやっぱりすごいと思う。それらが全部つながって、今までやってきたことがパノラミックに見えてくるという類い稀なタイプのミュージシャンだと思います。
蓮沼:そんなように言っていただき、ありがたいです。




























