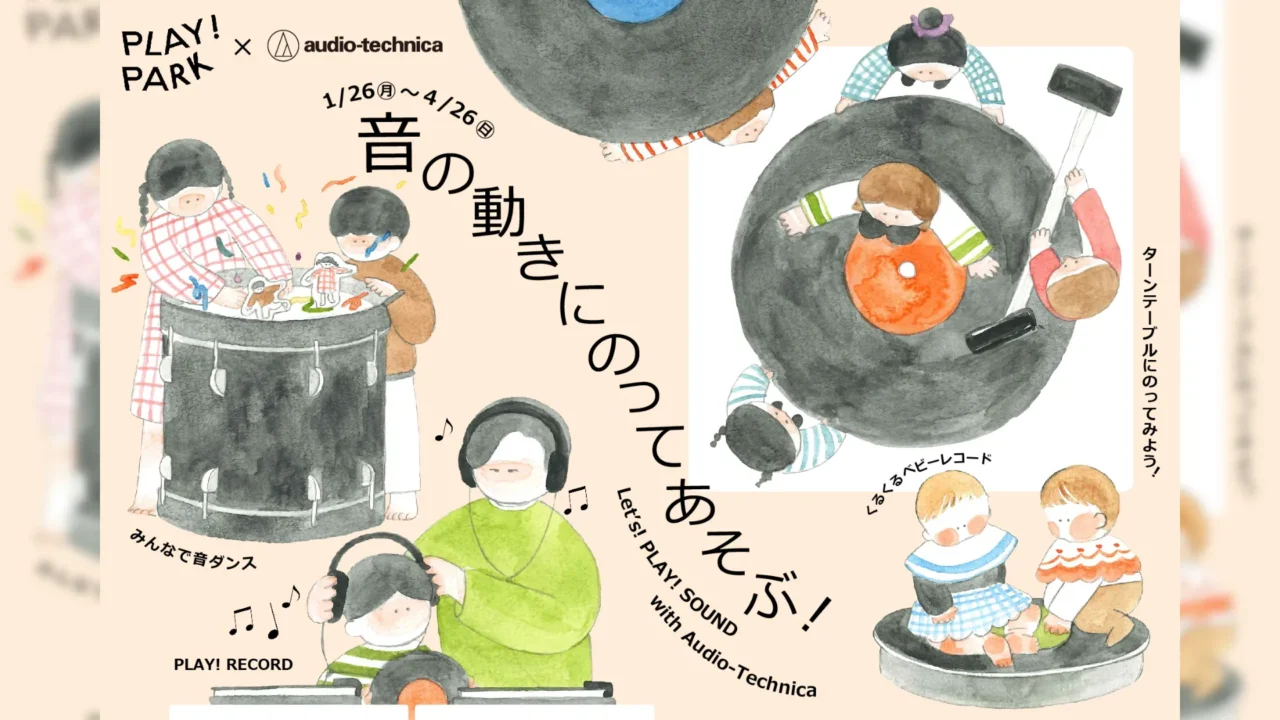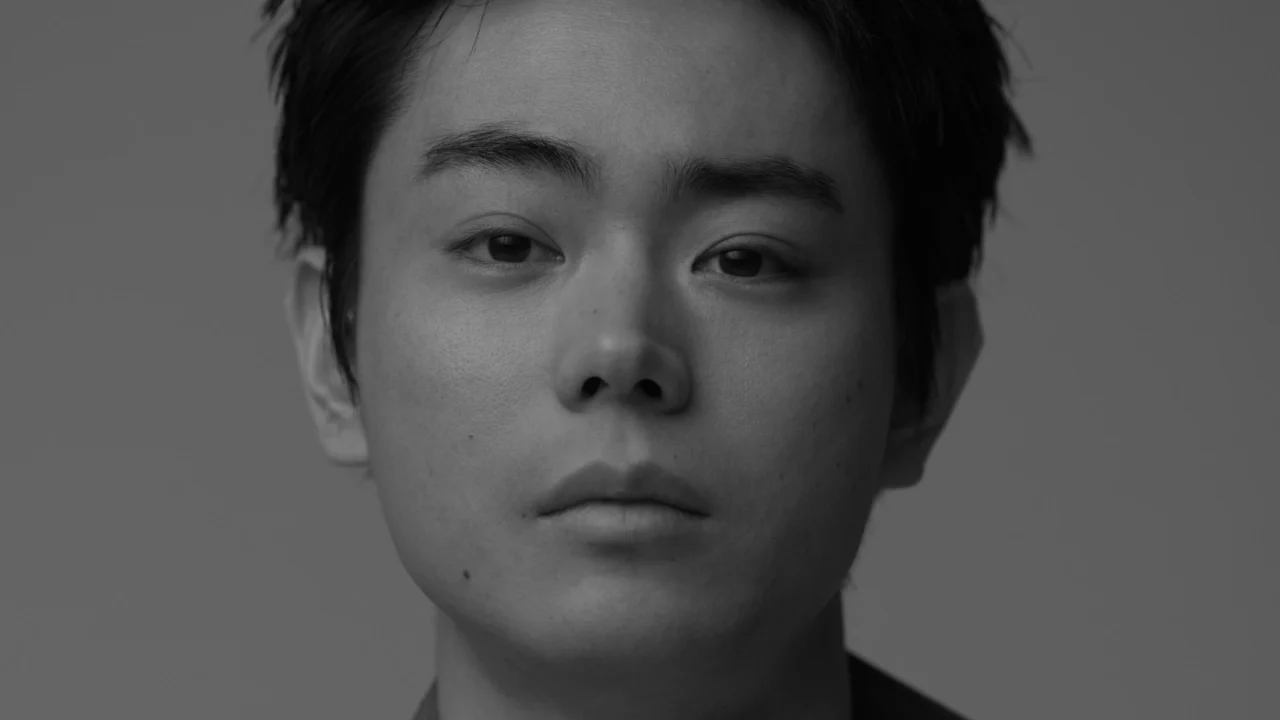堀込泰行のソロプロジェクト・馬の骨がファーストアルバム『馬の骨』から20周年を記念したベストアルバム『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』を発表した。キリンジとしての活動の一方で、自身のやりたい音楽性をよりダイレクトに反映し、遊び心を持って取り組んだ馬の骨は泰行にとって非常に重要なプロジェクトであり、この名義でリリースしたのはアルバム2枚ではあるものの、そこから厳選したベストを作ることは、20年越しの念願だったという。また、16年ぶりの新曲となる“Let’s get crazy”や、名曲“燃え殻”における作為性のなさ、必要最低限の音数でただただいい曲を作ろうとする泰行の姿勢からは、時代に左右されることのない普遍性の種が確かに感じられる。2000年代のキリンジの活動の中で抱えていたジレンマも振り返りながら、馬の骨の意義について語ってもらった。
INDEX

97年兄弟バンド「キリンジ」のVo/Gtとしてデビュー。2005年キリンジの在籍時にソロプロジェクト「馬の骨」を始動。2013年4月12日同バンドを脱退し、以後ソロアーティストとして活動を開始。ソロ名義の最新作は2025年8月にリリースした配信シングル「夏の罪人」。2025年、馬の骨デビュー20周年を迎え、16年振りの新曲を含むベストアルバム「BEST OF UMA NO HONE 2005-2025」をリリース。希代のメロディメーカーとして業界内外からの信頼も厚くポップなロックンロールから深みのあるバラードまで、その甘い歌声は聴くものを魅了し続けている。
ソロ活動ができないならもう辞めようかな。強い決意の産物だった「馬の骨」
ー2005年に馬の骨のファーストアルバムをリリースするに至った経緯を振り返っていただけますか?
堀込:キリンジは2003年に東芝EMIでアルバムを1枚、翌年2004年にシングルを何枚か作った後にコロムビアに移籍したんですけど、僕的には自分のソロプロジェクトをやってみたくて、移籍後の第一弾が馬の骨で、ほぼ同じ時期に第二弾として、兄(堀込高樹)の『Home Ground』(2005年)が出て。その後にキリンジで出したのが『DODECAGON』(2006年)で、ソロはそれに至る前の音楽的な遊びの場所というか、いろんなことを試してみる場所だったんです。
当時のキリンジはレコーディングは曲ごとにスタジオミュージシャンを、適材適所な感じでお願いしていたんですね。でもソロではレコーディングでもある程度メンバーを揃えて、よりバンド感のあるサウンドを作りたいなと思っていました。
ー「ソロをやりたい」と思ったのはどんな理由だったのでしょうか? 2000年に“エイリアンズ”が出て、その後はキリンジにとってどんな時期でしたか?
堀込:“エイリアンズ”もそうだし、僕の曲だったら“スウィートソウル”、兄の曲だったら“Drifter”とか、いわゆる「いい曲」みたいなものが求められる感じはあったというか、流れ的にそうなってるのは感じていました。ただ自分たちとしては、キリンジの持ち味はいわゆる「いい曲」と言われるものだけじゃない、面白みのある曲も大事だと思っていたので、この先ずっとキリンジとして、いわゆる「いい曲」みたいなものを作らなきゃいけないのかな? みたいな気分はあったかもしれないですね。
ーそこはちょっとしたジレンマがあったわけですね。
堀込:“エイリアンズ”も“スウィートソウル”も“Drifter”も、正直な気持ちから作られた音楽であるのは確かで、だけどそれらの楽曲の後に作為的にその路線を保ちながら活動していくのはちょっときついかもなって。兄はどう思っていたかわからないけど、僕はそういうふうに思っていて。
あとキリンジって、明確な目的地を定めて、そこに向かうというやり方ではなかったんです。例えば、キリンジという馬車があって、僕と兄が2頭の馬だったとして、でも馬を操る人はいない。その2頭の馬はそれぞれの方向を目指していて、必ずしも同じ方向を向いてはいないんだけど、でもそうやってキリンジという馬車が移動していくという形なんです。

ー結果的に行き着いた場所が、その時々のアルバムになっている。
堀込:そういうことです。なので、そこが結構難しいグループだなと感じていて、もうちょっと自分で方向性をコントロールしたい意思があって、ソロをやってみたいということを兄やスタッフに相談して。その当時は「ここでやらないと、もう嫌だな」っていう感じではありましたね。このタイミングでソロができないんだったら、もうちょっと辞めようかな、ぐらいの。
ーあの時点でキリンジを辞めていた可能性もあった?
堀込:それくらいの気持ちではありましたね。要するに「1人で自由に作ってみたかった」ということで、できあがったサウンド自体は全然緩いんですけど、「このタイミングでソロをやりたい」という気持ちはすごく強いものがあったと思います。
INDEX
心残りがあった2枚のアルバムと、救いになったベスト盤
ー馬の骨という名前は、キリンジ(=麒麟児)の「天才児」という意味と対になるものをイメージしてつけたそうですね。
堀込:そうですね。そこはやっぱりキリンジと関連付けて考えてました。結果的にはやって良かったと思っていて、とにかく自力で1枚作ってみることが自分にとって大きかった。サウンドの部分でも、キリンジではやってないことをやりたい気持ちが強かったので、例えば、“PING&PONG”は打ち込みのドラムを矢野(博康)くんと一緒に作って、アレンジのベーシックになる楽器としてアコギを選んでみたら、すごく面白いものができて。
堀込:その後にキリンジで『DODECAGON』を作るときに、兄から「“PING&PONG”みたいな方向性のアルバムを作りたいね」と提案されて。僕としては、“PING&PONG”で見つけた打ち込みプラスアコースティックなサウンドは今後も馬の骨でやっていこうと思っていて、キリンジはやっぱり王道のものをやっていくんだろう、みたいな感じでいたんです。でも兄は兄でちょっと変化が欲しかったようで、結局“PING&PONG”のアイデアがキリンジの方に生かされていって。
ーキリンジは打ち込みの要素が強くなって、逆に馬の骨の2枚目は全編が生演奏になりましたよね。
堀込:そうなんですよ。馬の骨で「打ち込みとアコースティックを混ぜたものをやるぞ!」と思っていたのに、『DODECAON』を作ったことで、馬の骨でやるネタがなくなっちゃった。僕は馬の骨を継続してやっていくつもりだったから、そこはちょっと困ったなと思ったんです。
もしかしたら、コロムビア的にはソロを1枚ずつ作って、その後はまたキリンジに集中することを望んでいたのかもしれないけど、僕は「両方やっていきます」って、結構態度を硬化させていたところがあって、それで2枚目はちょっとアメリカーナな感じを目指して作ってみたりして。馬の骨のファーストは、一人で1枚作り上げたことはよかったと思いつつ、時間が足りなくて、自分としては不本意な出来の曲も収録されてしまっていて。なので、2枚目はそういうことがないようにしっかり準備をして、粒ぞろいのデモ曲が揃ったんですけど……ただ兄はもうソロをやりたいという気持ちはなかったみたいなんですよね。

ー高樹さんはファースト以降はソロは出してないですもんね。
堀込:僕は馬の骨の2枚目のことを考えて、「今度こそ後悔しないものを作るんだ」と意気込んでたけど、キリンジの活動も止まっちゃいけないので、キリンジでも定期的にリリースをして、どちらかというと、兄がそれを頑張ってくれていて。なので、スタッフとしては馬の骨だけそんなに長くレコーディングをやられちゃ困る、という状況ではあったんです。
それで当初思い描いていたよりも短い制作期間しか取れなくて、その中で寝る間を削ってやったはやったんですけど、結果的には前作と同じように、満足いくものとそうじゃないものが混在しているアルバムができちゃって。だから「またこういうのを作っちゃったな」っていうすごく悔しい気持ちが残ったのを覚えてますね。

ーそこはずっと心残りだった。
堀込:なので、馬の骨の曲は単体では気に入ってるんだけど、アルバムとしては自信を持っておすすめできない感じがずっとあって。でも今回20周年でベスト盤を作るにあたって、2枚の中から自分が満足しているものを集めて、新曲も1曲追加して、個人的には馬の骨の新譜みたいな気持ちがあって。このベスト盤ができたことで、さっき言った消化不良の感じが……解消できたとまでは言わないけど、ひとつ救いになったというか、自分の中で納得することができたっていうのはありますね。
INDEX
堀込泰行の「バラード論」と、地味だけど美しくて強い音楽の探求
ー“燃え殻”は馬の骨の代表曲の一つと言えますが、もともとどんな着想から生まれた曲だったのでしょうか?
堀込:曲自体はもともとキリンジのためのデモのひとつとして存在していて、何かのレコーディングの際に、候補曲として提出したりもしてたけど、この曲のどこが気に入っていたかというと、「地味なところ」が気に入ってたんです。もしキリンジでやるとなると、当時だと結構ゴージャスな、リッチな感じのアレンジになると思ったので、それだとこの曲の素朴なよさが消えちゃうなと思って。なので、途中でキリンジの候補曲の中から外して、これはいつか自分がソロをやるときに、シンプルなアレンジでやろうと思っていました。
ー資料にナチュラルファウンデーション(当時の所属事務所)の代表の柴田やすしさんのコメントで、「1990年代から2000年代にかけて、日本の音楽シーンにおけるバラッドは、しばしば過剰な情熱と、ドラマ性を伴うスタイルが主流であった。そんな時代において、堀込泰行の音楽は一線を画していた」とあって、たしかにと頷きました。泰行さんがバラードを作る際のこだわり、「バラード論」みたいなものがあればお伺いしたいです。
堀込:「バラードを書こうと思って書いてるわけではない」っていうのはあるかもしれない。普通の曲を書き始めたつもりが、たまたまテンポが遅い曲になったっていうものが多いんです。当時のバラードのヒット曲を書いた人たちが、どういうプロセスや気持ちでそれを作ってたのかはわからないけど、僕は活動初期から「バラードって普通の曲のテンポの遅いやつでしょ?」ぐらいの発想だったんですよね。
ー先ほどのキリンジの活動を馬車に例えた話もそうでしたけど、その作為性のなさが普遍性の種になっているように感じます。
堀込:そうかもしれないですね。僕がこれまで作ってきた曲の中には、バラードみたいなものがまあまあの数あるとは思うんだけど、特別な意識があったわけではなく、他の曲を書いているときと同じ感覚で、「いい曲を書こう」とか「いいメロディーを紡ごう」っていうところでやっていて……だから、やっぱりテンポが遅くなったものがたまたまバラードになったっていうことだと思うんですよね。

ーそうやって生まれたものがたくさんの人に響いて、“燃え殻”に関してはこの名前を冠した作家が現れ、その人の書いたウェブ小説(『ボクたちはみんな大人になれなかった』)がNetflixで映画化され、エンディングテーマとして“燃え殻”が使われた。そのことについてはどう感じていますか?
堀込:最初に燃え殻さんという作家さんが出てきたのを知ったときは、自分の曲とは特に関係ないと思ってたんです。でも燃え殻さんの方からウェブ記事の対談に声をかけてくださって、初めてお会いして、自分の音楽も聴いてくれてたということで、もし自分の作った曲が燃え殻というペンネームの起因になったとしたら、それはやっぱりすごく嬉しいなと思ったし、エンディングテーマとして使ってもらえたのも嬉しかったです。
ー作った当時からすれば、「まさかそんなことが起こるとは」という感じですよね。
堀込:あんなに地味な曲なんだけど、そういう連鎖が生まれたのはすごくありがたい。さっきも言ったように、この曲は地味なところが気に入ってたので、売れっ子のプロデューサーの人に仕上げてもらって、「当ててやろう!」というような下心は全くなかった曲なんですよね。オルガンとかを入れて、もっと派手にもできたとは思うんですけど、当時も今も変わらないのが、少ない楽器編成で、それぞれの楽器が本当に大事なフレーズしか弾いてないような曲を目指してるんです。音数こそ少ないけれども、それらが有機的に反応して、1つの美しくて強い音楽になるのが自分の理想なので、そこはすごく投影されてる曲だなと思いますね。

INDEX
「狭い社会の中で、みんな息苦しさや生きづらさを感じてる」
ー馬の骨名義でアルバム2枚を作って、2013年のキリンジ脱退以降は「堀込泰行」名義での活動に変わるわけですが、それは自然な流れだった?
堀込:そうですね。やっぱり「キリンジがあっての馬の骨」という考え方だったので、名前も対になってるし、自分1人でってなったら、本名のほうがいいと思ってました。
ー今回、馬の骨名義の新曲を作ることによって、「馬の骨とは?」というのを改めて考えるきっかけにもなったかと思うのですが、“Let’s get crazy”はどのように作られたのでしょうか?
堀込:ベスト盤の1曲目を新曲にしようということで、ストックがいくつかあった中から、これがいいと思いました。やっぱり馬の骨らしい音にしたかったので、基本的にキーボードとベースとドラムと歌で成り立っていて、合間合間でギターが入ってくる、すごくシンプルな編成で、どの楽器も必要最低限のことしかやってない。それでもドラマティックになるっていう部分に関しては、僕としては馬の骨のファーストのイメージでした。ファーストの1曲目が洋楽のカバー(ロバート・レスター・フォルサムの“My Stove’s On Fire”)で、あれに代わるような曲というので、リラックスしたムードがあって、アレンジはできるだけシンプルさを心がけて、今の自分が馬の骨サウンドを作ってみたっていう感じです。
ーソロアルバムの1曲目が1970年代の隠れた名曲のカバーだったというのは、馬の骨らしい遊び心の表れだったと思いますが、その感覚をもう一度やってみたと。
堀込:そうですね。だから新曲“Let’s get crazy”も、収録したものは曲の最後がウィンドチャイムの音になってますけど、デモの段階ではふざけてドラの音にしてたんです(笑)。「こういうのは馬の骨でしかできなかったよね」と思ってたんですけど、でも曲を作っているうちに、もうちょっとロマンチックな方がいいなと思って、結局ウィンドチャイムにしました。
ートークボックスも印象的ですよね。
堀込:ソウルっぽい曲だから合うだろうと思ったし、キリンジの“YOU AND ME”とかでも使ってたので、ここでもう一回自分が昔よく使ってた、馴染みある楽器を持ってくると、ファンの人も喜ぶかなと思ったりして。シンプルさの中にも一個ユニークなサウンドが入ってた方が、曲のフックにもなるだろうし。
ー<小さな窓の小さな声に心が萎んでしまう>といった歌詞は、2005年には書けなかった、スマホやSNSが一般的になった2025年だからこそのものですよね。
堀込:そこは自然と、今を生きている人間として、みんな普通にやってるSNSで、ちょっとした言葉で気持ちが沈んだり、そういうことがよくあるのを想像して。でも最初からそういう歌を書こうと思ったわけじゃなくて、歌詞ができあがっていく中で、<Let’s get crazy 涙を忘れたいミッドナイト>がバチッとはまったので、そこから連想したり、いろんな要因があるんですよね。Aメロのメロディーを書いて、<The sun and the stars>が出てきたから、「まあ、宇宙か」みたいなところから……。
ー<膨らむ宇宙>と<小さな窓>が対比になっている。
堀込:そうですね。宇宙は膨らんでるけど、僕らはちっちゃい窓を眺めて、そこで一喜一憂している。顔を上げれば、外にもっと広い世界が広がってたりもするんだけど、狭い社会の中で、ちっちゃい窓のちっちゃい世界の中で、みんな息苦しさや生きづらさを感じてるよね、みたいなことを織り込みたいなと思ったんです。やっぱり2025年に出すので、今を生きている僕らの気分みたいなものを反映したい気持ちはありましたね。