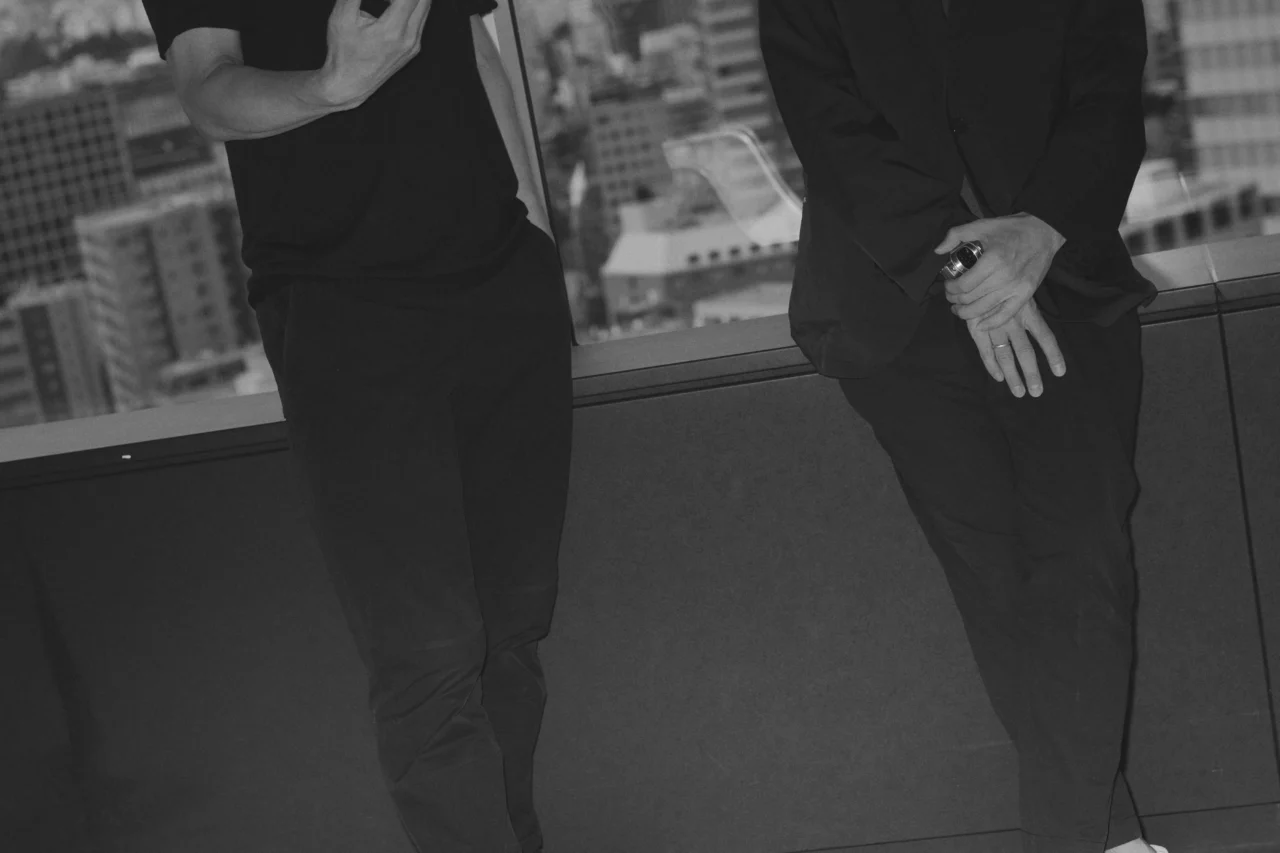INDEX
「正解」を求めがちな現代、「正解」が曖昧な中で遊んでいた1990年代

─TESTSETはライブに力を入れていますが、作曲の時点で、ライブを意識しているのでしょうか?
砂原:「ライブではこうなるだろう」というのは、少しは考えます。TESTSETにおいてリリース音源は、その曲のもっとも「プレーンな状態」という認識で、ライブでどんどん変わっていきます。
白根:ライブで実際に演奏して、映像や照明もあって、お客さんのリアクションを受けて、その中で楽曲が熟成していく……というような感覚はあります。
─ライブの雰囲気やお客さんの年齢層、反応はどうですか?
砂原:国内だと40代や同世代が多いのかな。どちらかといえば大人しい感じかと思います。先日出演した中国のフェスも、まあ、まだ我々のことも知らないし「何だろう?」というように見てる感じでしたね。もちろん同世代だけでなく、20代の子たちも観てくれるなら嬉しいですけどね。

─先日、パソコン音楽クラブがLIQUIDROOMでオールナイトのイベントを企画していて、非常に盛況だったんです。コロナ以降、ヒップホップだけでなく、若い人たちの間で四つ打ちやテクノの需要も増えているのかなと。一方で、大舞台もこなせる若手の電子音系のアーティストが足りていないようにも感じます。才能あるアンダーグラウンドなDJはいると思いますが。
砂原:前提として、今の子たちにとって面白いシーンはあるし、アーティストもいると思います。
でも1990年代は、全体的な盛り上がりがすごかった。それは社会からの抑圧が今ほど強くなかったことも関係しているだろうし、バブルの余韻で社会全体に経済的な余裕、あるいは浮かれた気分も少しはあったし。今はもっと、窮屈な感じはありますよね。その影響はあるのかもしれない。
砂原:あと単純に今、日本は全体的に高齢化が進んでいるし、国全体の雰囲気として年を取ってる感じもありますしね。1990年代って、遊び方もエネルギッシュというか、乱暴だった気がします。
白根:若い人が、マジメにならざるを得ない時代なのもわかりますね。「正解」が求められがちな時代ならでは不安とか、抑圧もすごくあると思います。
1990年代って「正解」がもっと漠然としていたから、もうちょっと自由だった。ジャンル的にも、いろんなことがシームレスに繋がっていた気がしますね。いろんなことが漠然としていて、でもそれが許された時代だったかなと思います。