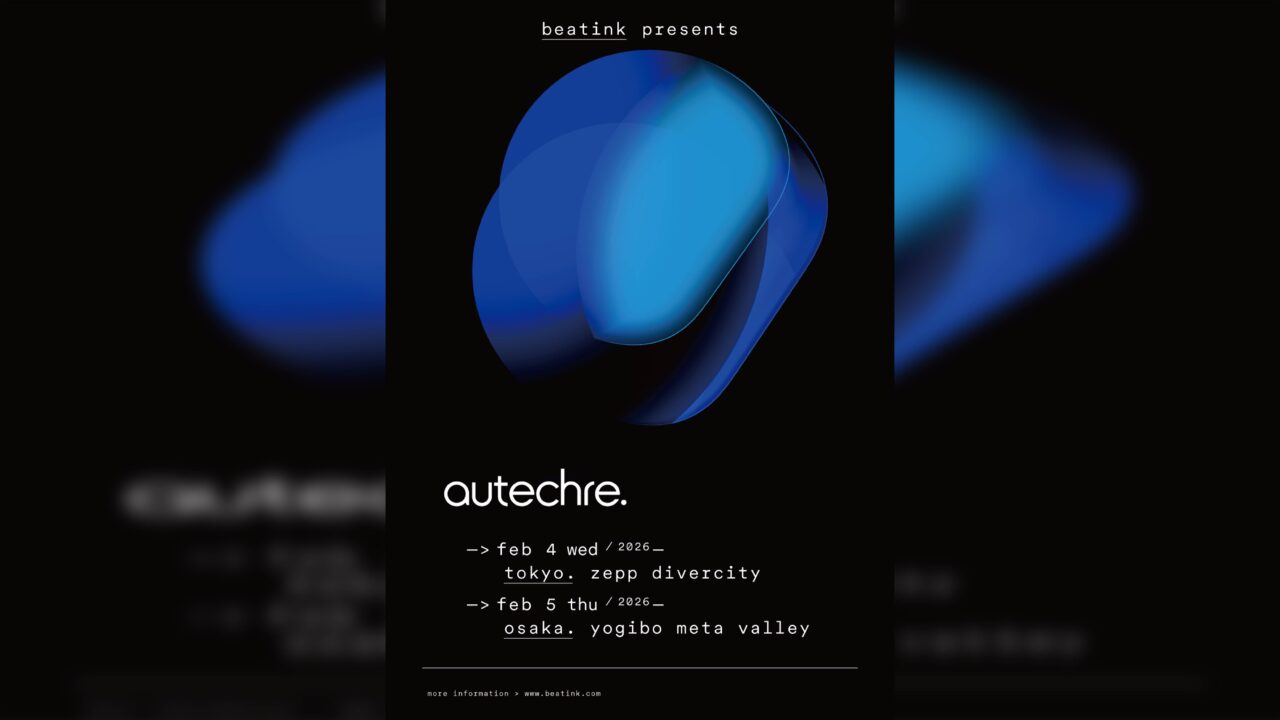世界には大きくわけて2種類の優れた映画がある。観客をストーリーやキャラクターに感情移入させる作品と、観客に全く新しい世界の見え方を提示し、驚きを与えるような作品だ。
ポーランドの巨匠イエジー・スコリモフスキの新作『EO イーオー』は後者で、世界とわたしたち観客を新しい形で結びつけてくれるだろう。本記事では『EO イーオー』が提示した世界の見え方を、ライターの木津毅氏が論じる。
INDEX
還暦を越えてもますますエッジーなポーランドの巨匠。イエジー・スコリモフスキの「瞬間の美学」
この世界は驚異に満ちている。ポーランドの異才イエジー・スコリモフスキの映画を観ていると、そのように感じられる瞬間がしばしば訪れる。わたしの錯覚なのかもしれない。しかしながら、視覚と聴覚を激しく揺さぶるようなスコリモフスキの映像表現には毎度圧倒されるばかりだ。

若い頃にはジャズドラマーやボクサーを経験し、アンジェイ・ワイダやロマン・ポランスキーといったポーランド監督作品の脚本を務めたのち、ヌーヴェルヴァークの影響のもと制作された『出発』(1967年)や『早春』(1970年)で高く評価されたスコリモフスキ。『30 Door Key』(1991年)以降はおもに俳優としてデヴィッド・クローネンバーグの『イースタン・プロミス』(2007年)などに出演し、その間は画家としても活動するなどきわめてユニークな経歴の持ち主だが、『アンナと過ごした4日間』(2008年)で17年ぶりに監督復帰すると絶賛とともに迎えられた。しかも、以降の監督作品ではますます表現のエッジを増しているようにすら感じられる。
孤独な中年男の不遇な恋の様子をいじらしく映していると思えば、そこに突然爆音のヘリコプターが飛来する『アンナと過ごした4日間』。逃亡するテロリストを描きながら、背景にある政治性が不明なばかりか主人公に一言もしゃべらせず剥き出しのアクションのみが展開される『エッセンシャル・キリング』(2010年)。11分間の間に起こる出来事を複数の視点から描き、決定的な一瞬の内側をあまりにもダイナミックな映像で見せる『11ミニッツ』(2015年)。
スコリモフスキの映画にはしばしば登場人物たちの人生を一変させるような「瞬間」が脈絡なく訪れ、それを目撃するわたしたちは文脈も背景も掴めぬままに呆気に取られるしかない。予想を凌駕する光景の迫力を、どれだけ生々しく描けるか――台詞や物語よりも画面の中の動きや音でこそ、スコリモフスキは観る者を驚嘆させる。80歳を過ぎて発表された新作『EO イーオー』はそして、わたしたちの世界の見方を一新してしまうような驚くべき瞬間の連続でできている。
INDEX
ロバの放浪を描いた映画『EO イーオー』。論理を超えた不条理な世界と対峙する
『EO イーオー』はロベール・ブレッソン監督作『バルタザールどこへ行く』(1966年)にインスパイアされて制作された、1匹のロバを主人公とした作品だ。サーカス団に飼われてパフォーマーの若い女性と親密な関係にあったロバのEOだが、あるとき動物愛護団体のデモにより彼女と引き離されてしまう。その後、目的地もないまま放浪することになったEOの旅を映画はただ追い続けることとなる。
本作は何よりも、EOの視点で世界を旅することを徹底している。サーカス団から連れ出されたEOは、農村や町をさまよう中で多くの人間たちに出会うことになるが、そこに善悪の判断はない。『バルタザールどこへ行く』には存在した大きなストーリーラインもなく、EOは純粋な目で行く先々で起こることを断片的に目撃していく。ゆえにその過程を見守るわたしたちも、映されるものをありのままで受け止めることが求められる。

だからと言って、必ずしもリアリティーのみを追求しているわけではないことが『EO イーオー』の重要なポイントだ。オープニング、赤い光が明滅する中でパヴェウ・ミキェティンによる荘厳なオーケストラ音楽がゆっくり立ち上がるさまは非常に陶酔的であるし、道々の大自然を捉えるミハウ・ディメクの映像はにわかに信じがたい美しさを湛えている。またEOが耳にする音の数々は、ときに極端に立体的な音響で表現される。どこまでも感覚が研ぎ澄まされるような映画だ。
つまり、『EO イーオー』という映画を観る行為自体が論理を超えたひとつの体験として提示されているのである。木がメリメリと音を立てて倒れ、馬たちは大地を颯爽と駆け、戸棚が突然ガシャンと崩れ、ハンターたちに追われたオオカミは重傷を負っている。まったく説明もなく4本足のロボットが何やら象徴的に映されもする。だがそれらはすべて明確な意味を持たず、ただそこで起こる出来事としてのみ立ち現れる。
INDEX
ロバの視線が表すもの。先入観や思想を手放した感覚で世界と出会い直す
それは、EOの目を通して描かれる人間たちの行為ですら同様だ。動物愛護団体による主張も、心優しい女性による親切な振る舞いも、サッカーチームの対立も、唐突な殺人も、獣医が損得関係なしにEOを救うのも――それらは物語を構成する要素として配置されているわけではない。時折EOが人間から受ける暴力に観る者は怒りを覚えるだろうが、だからと言って、それらは「人間は残虐なものだ」という作家による「主張」のために導入されたものでもない。それらはただ、そこで起きるのだ。

スコリモフスキはインタビューで、現在ヨーロッパで戦争が激化していることに心を痛めていると話している。おそらく多くの人がいま、世界で起きている悲惨な出来事にさまざまな意味や文脈を求めようとしているだろう。そしてときには、それらに対して「主張」や「メッセージ」を放つこともあるだろう。
『EO イーオー』はしかし、それとはまったく異なるやり方で世界に対峙する。先入観や凝り固まった思想を完全に手放して、ただその瞬間に起きていることに目を凝らし、耳を澄ませる。どこまでも感覚的に、ロバのように曇りのない瞳で……。そこには意味を超えた喜びや悲しみ、驚きや快楽があり、スコリモフスキはそれこそが映画的な営みであると提示するかのようだ。映画は――芸術は、「理解する」ためにのみあるのではない、と。
いま、人間によって世界中で引き起こされている悲惨な事態を思うとき、ロバのように純粋に世界を捉えようとすることはあまりに無邪気なことだと感じる者もいることだろう。だが、『EO イーオー』は詩的な映画表現としての力強さでそうした冷笑的な考え方をも乗り越えていく。そしてこの映画を観るわたしたちもまた、理解したつもりになっていた世界と新たな感覚で向き合うことができるのだ。