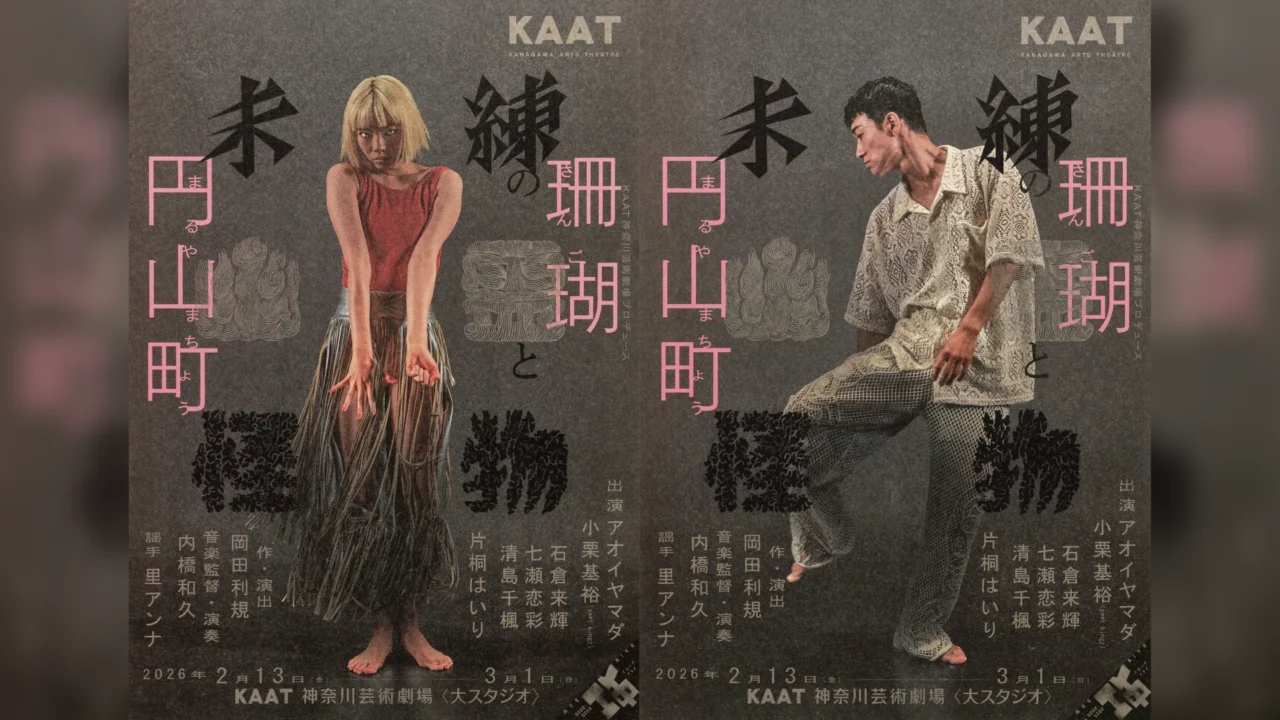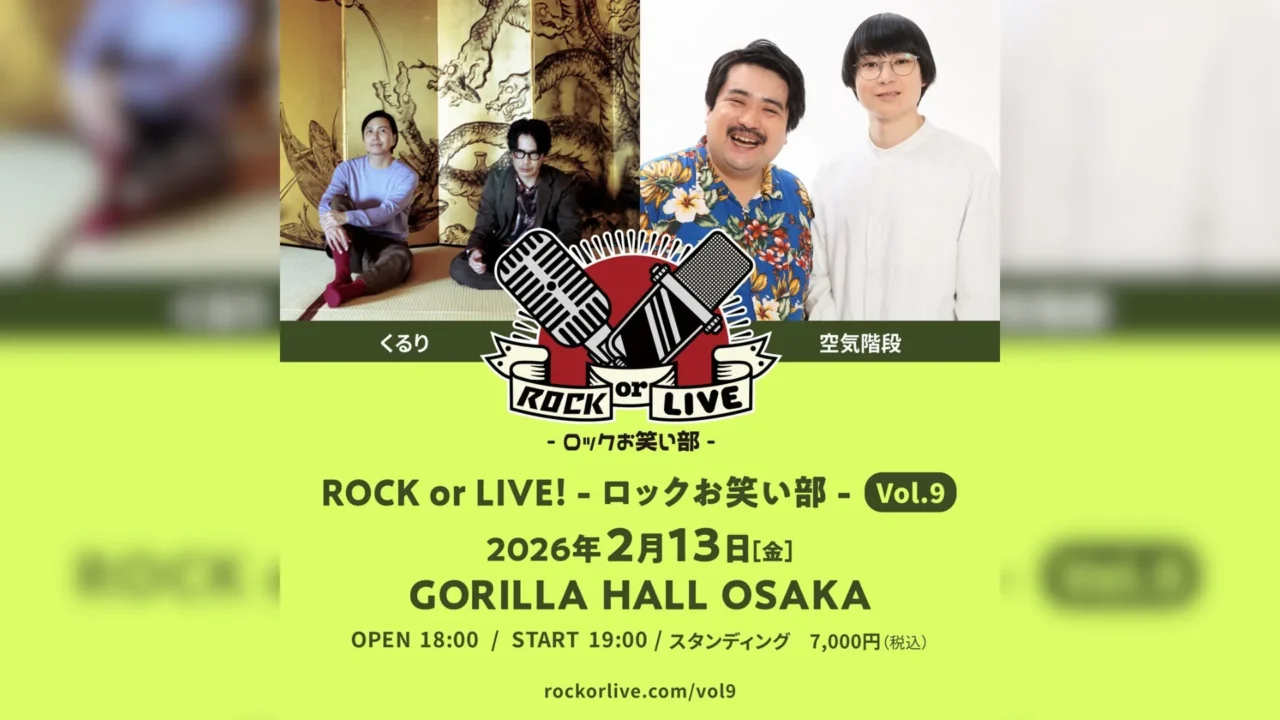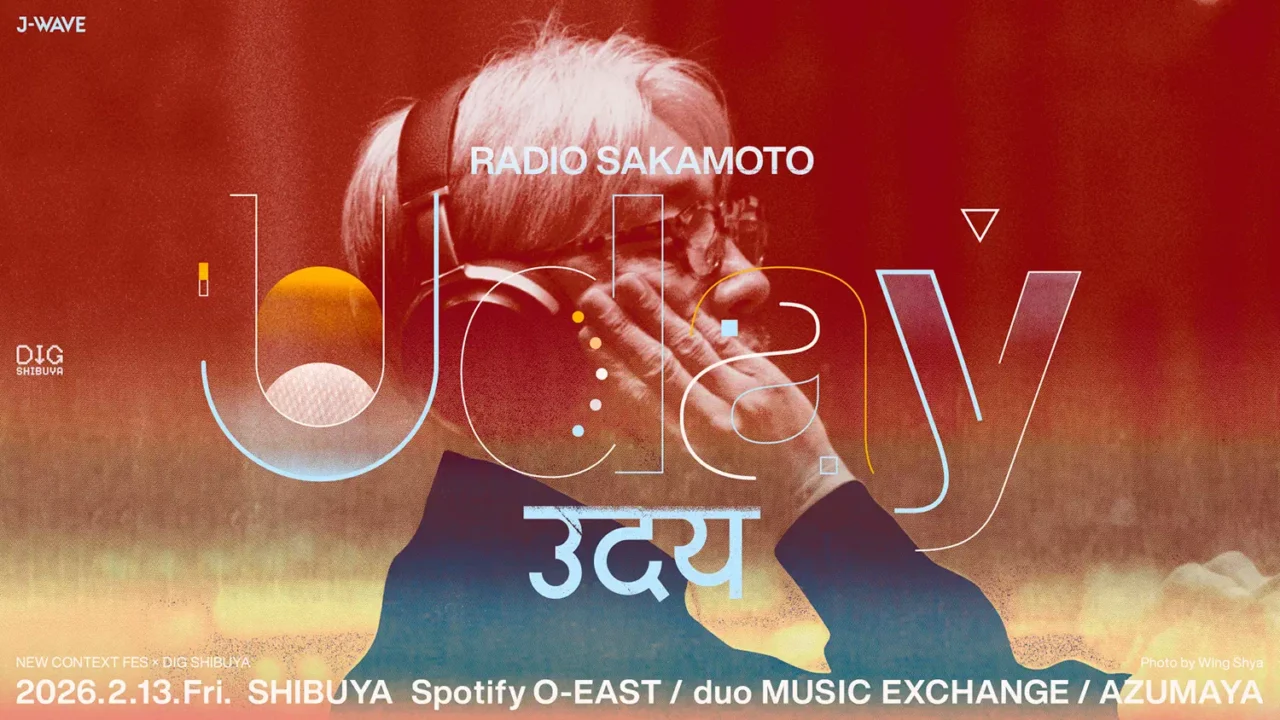INDEX
作品は、いつ、なぜ「完成」するのか。「あ、できた」という実感と「穴」
郡司:アートという営みも、この場合と同じ意味での外部からやってくるものがあってこそ成立するものだと思うんです。「これこれこうだから結果的にこういう表現になっています」ということではなくて、外部を感じる体験へと誘導する装置こそがアートなのではないかな、と。
つまり、一人称的な表現が単にたくさん並列されているだけではなく、それを「脱色」して、そこからヒョロッと外部へ抜け出ていく穴があるということが非常に重要ではないかと思うんです。ええと、だいぶ遠回りしてしまいましたが……(笑)、今回の鼎談にあたってOGRE YOU ASSHOLEの音楽を聴かせてもらって、まさにそういった意味での「アート」性を感じました。
出戸:それは嬉しいですね。自分が音楽を作っているときに、ふと「あ、できたな」と思う瞬間があるんですけど、今お話されたこととも関係しているような気がします。それは何か完成図を想定したうえで能動的に取り組んでいった末に訪れるんではなくて、例えば、ひたすらシンセサイザーを鳴らしたり試しに音を抜き差ししていく中で突然やってくる感覚で、言葉で説明できない類のものなんです。
自分でも、なぜそれをもって「できた」と判断しているのかわからないんですが……でもそこには確実な満足感があるんです。郡司さんの書かれた『創造性はどこからやってくるか ――天然表現の世界』(2023年、筑摩書房)という本に、何かを創造するにあたって、徹底して受動的になることによって能動的に構える、という話が出てくると思うんですが、もしかするとそういう状態にも近いのかなと思いました。

郡司:私たちは、自己意識をもって生きている限り完全に受動的になるのは難しくて、なにがしかの能動的態度を持たざるをえないわけですが、そういう矛盾した状況の中でこそ創造的行為が初めて可能になるんじゃないかと考えています。
そしてそれは、何か特別な鍛錬の末に到達できる「悟り」のような大きな話でもなく、案外日常のいろいろな場面にありうることだと思っているんです。そういう意味でも、「待つ」という受動的な状態を歌っている“家の外”という曲は、その感覚をうまく捉えていると感じました。
出戸:なるほど、そう言われると確かにそうかもしれないですね……。これもうまく言語化できないんですが、ライブで演奏していても、あらかじめ設計図を組み立てておくんじゃなくて、なにがしかのトラブルや想定外のことが起きる場合のほうが純粋にいい演奏だったなと思えることが多いんです。
だから、何度も練習してきた曲の中にわざと曖昧なパートを設けたりしています。あたかも知らない曲のように演奏するわけですけど、そうすると、さっき郡司さんがおっしゃった「脱色」に近い状態になるというか。いわゆる「完成度の高い上手な演奏」みたいな概念では推し量り難い何かが生まれてくる感覚があって……。
勝浦:それはわかるな。そもそも、僕は前提として「上手な音楽」が昔から嫌いで(笑)。自分たちが巧いプレイヤーであることの自覚が前面化している音楽を聴いたところで、「ここには何も起こっていないな」と感じてしまうんです。
かつては思い通りにドラムを叩きたいという気持ちもあったんですが、結局、自分の身体を介在させる時点で完璧に叩くなんて絶対に無理なので。最近はむしろ思った通りに叩けないからこそ面白いんだと思うようになりました。昔は演奏中にバンド全体のリズムが混濁したりするのをノイズだと思って排除しようとしていたんですけど、ここ数年は、無理に辻褄を合わせようとしないほうがいいと思っていて。
郡司:私も自分で造形物の創作をやっていますが、それはもう「あえて技術にこだわらないほうがいい」みたいなレベルの全く手前にあるものなのでおこがましいのを前提にお話しますね(笑)。
私は、「あ、これはできたな」という瞬間をちゃんと捕まえられるのが本当のアーティストなんじゃないかと思うんです。昨今の芸術というと、ポストモダン理論の影響もあって、ともすれば「できた」という実感を先延ばしにして生成変化していく状態がずっと続く状態こそが創作である、みたいに語られたりもするんですが、実際にものを創る人たちの中には、やっぱり「あ、できた」という実感があるはずなんですよね。
それは第三者からみたら全然完成してないじゃんっていう状態かもしれないけれど、当事者においては間違いなく「これで完成だ」というポイントがやってくる。それこそが、作品の中に外部に通じる「穴」を穿つことができたということなんじゃないかなと思うんです。そのリアリティーが客観的にどういうことなのかというのは、人工知能的な考え方の元ではそもそも記述不可能なものなんですよね。