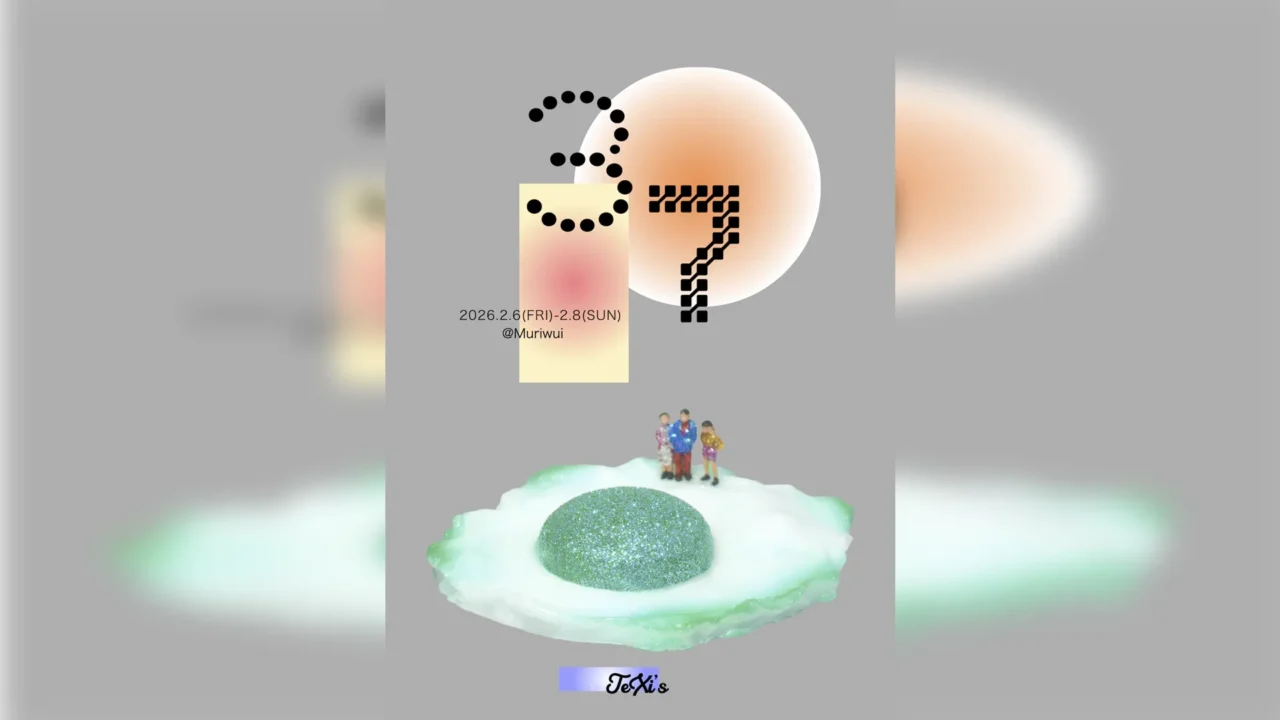INDEX
フェスを音楽ジャンルと世代から考える
―現在のロックフェスでは、「ロック」という特定のジャンルに拘泥しないジャンルレスなものが増加傾向にあるように感じているのですが、フェスとジャンルの結びつきに関してはどのようにお考えですか。
永井:そもそも『フジロック』が、割とジャンルレスだったんです。「ロックフェス」と言っているものの、テクノもHIP HOPも出るしというので、後続フェスも同様の雰囲気でした。しかし、時間経過とともに、いわゆる「邦ロック」のようなシーンが登場して、それ一色になっていく時代があったのではないかと思います。
―四つ打ちが流行した2010年頃でしょうか。
永井:その周辺ですかね。2010年頃までに増加した地方のフェスは、各地のプロモーターが開催するものでした。背景には、Zeppなどの大規模なスタンディングのハコの成立があって。Zepp規模でイベントを作っている人がフェスを開催すると、ロック系のバンドが自然と多くなって、一気に「ロックフェス」という形式で普及していったのだと思います。
そういったDJカルチャー的なものが排除されロックが残留した一時代を終えて、今はHIP HOPフェスが増えていますが、これは世代間の問題でもあると思うんです。確かに、若年層もロック系のフェスに行ってはいますが、年齢層は上がっていっている。一方でHIP HOPフェスは、若い世代が中心です。世代間の問題としてフェスを捉えると、ジャンルを混ぜた方が今後は広がりがあるのかなと思っています。
ー例えばロックを主で聴くミレニアム世代の人と、HIP HOPを主に聴くZ世代の両方を集合させる、ということでしょうか。
永井:そういうのも面白いかなと感じます。同じメンツで、同じお客さんばかりライブに行っているのは、どこかで限界があると思うので、代謝が上手くいっていない気はします。

ーフェス文化の成熟に伴って多世代化が進行しているように感じる一方で、フェス黎明期からのお客さんが中心になっているフェスと、新しい世代が中心になっているフェスで分断してもいますね。
永井:そうですね。そして「ロック」というジャンルの中でも、新しいロックバンドは出てきているけれど、「若者に人気のバンド」という形で差別化されて、分断している気がします。
ーひとえに「ロック好き」と言っても、「若者を中心にするフェス」や「中高年を中心にするフェス」「国内独自の変化を遂げ続けている邦楽中心フェス」「グローバルなロックの歴史を汲んだ洋楽中心フェス」のように分かれているということですね。
永井:そんな感じが今はしています。ここ何年かは代謝が悪かったのかな。ただ、面白いバンドはたくさん出てきていますし、インディー系のバンドとHIP HOPが接近したり、クラブっぽい雰囲気のバンドが出て来たりと、近接するシーンもあるので注目です。
ー海外のフェスに関してはいかがでしょう。
永井:ドラマや映画など音楽以外のカルチャーの場で、音楽が効果的に使用されカルチャー同士が融合し、他ジャンルの音楽同士の接点が生まれる。それをフェスに反映させることはあるのかなと思うんです。
最近だと『THE IDOL』というドラマがあって。The WeekndとBLACKPINKのジェニーが出演しているんですが、この世界観はまさしく『コーチェラ(Coachella Valley Music and Arts Festival)』です。こういったことが日本の骨格の中で考えるのであれば、アニメで起こりうるのではないかなと。
ーアニメカルチャーにおける音楽使用によって、他ジャンルの音楽同士が接触し、フェスもその影響を受けるということですね。
永井:ええ。他ジャンルの音楽が混ざって一つの価値観を作るということが、フェス以外ではまだ少ないのかもしれないです。ヒットチャートと連動した大規模フェスが、より一層そういった役割を担うことに期待です。