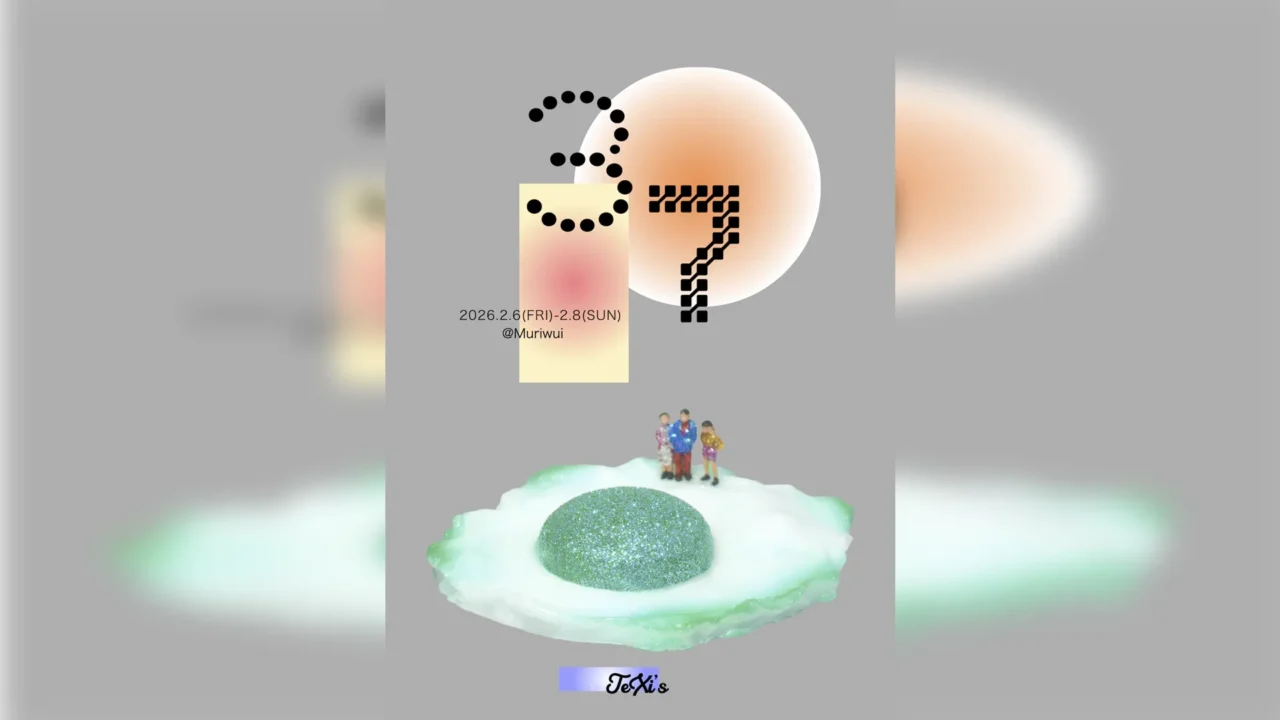INDEX
コロナ後のフェスシーン。ビジネスの場としても注目が集まる
ー永井さんは2021年に『コロナ禍のライブをめぐる調査レポート』(2021年、日本ポピュラー音楽学会)を執筆されています。コロナ禍が収束してきた現在、コロナ前後でフェスにどのような違いがあるとお考えでしょうか。
永井: 実は、フェスに対する世間一般の認識と内実がずれている気がしていて。というのも、2022年の夏以降は制限はありながらも、市場的にもフェスの内容的にもほぼ元の状態に戻っていたと思っています。
2020年に『コロナ禍のライブをめぐる調査レポート』の調査をした頃は絶望的な気分で日々を過ごしていて。2021年も風当たりが強くて、『フジロック(FUJI ROCK FESTIVAL)』も人はたくさんいるのに、お通夜みたいな感じで不気味だったんです。
―その状態からの転機が2022年だったと。
永井: そうですね。2022年の夏頃からマスクはあるけれどお酒もOKになって、友達と飲食もできて、普通にフェスを過ごせるようにぬるっと再開した印象はあります。
だから2023年に「今年から全て元通りです」となった時に、変化としてはマスク着用の任意化と声出しの解禁くらいで、前年とそんなに変わるのかな? と思っていたんです。でも、実際はやはり違いました。
―どこが変わったのでしょう。
永井:一番大きく違うのは、社会の規範的なものです。2022年までは参加に後ろめたい気持ちがあったけれど、堂々とフェスに参加できるようになった点で大きく変わりました。

ーフェスの現場では、社会規範を反映して参加者の意識の変化が生じたということですが、コロナ禍で配信でのフェス参加も普及したと感じています。フェスの配信に関してはどのようにお考えですか。
永井:2020~2021年は配信が盛んだったのですが、国内フェスに関して強く定着はしなかったと思っています。単独アーティストの公演配信の方が売れ行きはよかったということも聞いていて、期待していたのとは違う現在になっているかなと。
ただ、海外の大規模フェスのいくつかは、配信でブランド力を高めていたし、2023年はありませんでしたが、『フジロック』も多くの人が配信を利用していたと思います。
―配信以上に現場が重要視されているということですね。フェスの現状として、注目されていることはありますか。
永井:新興のフェスが増加していると感じます。おそらく2020~2022年に準備していたものが2023年に開催されたのだと思うのですが、小規模でローカルフェスのテイストはありながら、ビジネスライクな感覚も持ち合わせているフェスが増えています。
背景としては、5~6年前よりもフェスがビジネスの場として注目されるようになり、企業などが協賛や主催として参入するようになったのだと思います。
ーなぜフェスが従来よりもビジネスシーンで注目されるようになったのでしょう。
永井:ローカルビジネスとフェスが連動してきているのだと思います。例えば、クラフトビールの会社が主催するフェスがあるというのが分かりやすいかな(CRAFTROCK BREWING主催『CRAFTROCK FESTIVAL』や協同商事コエドブルワリー主催『麦ノ秋音楽祭』など)。