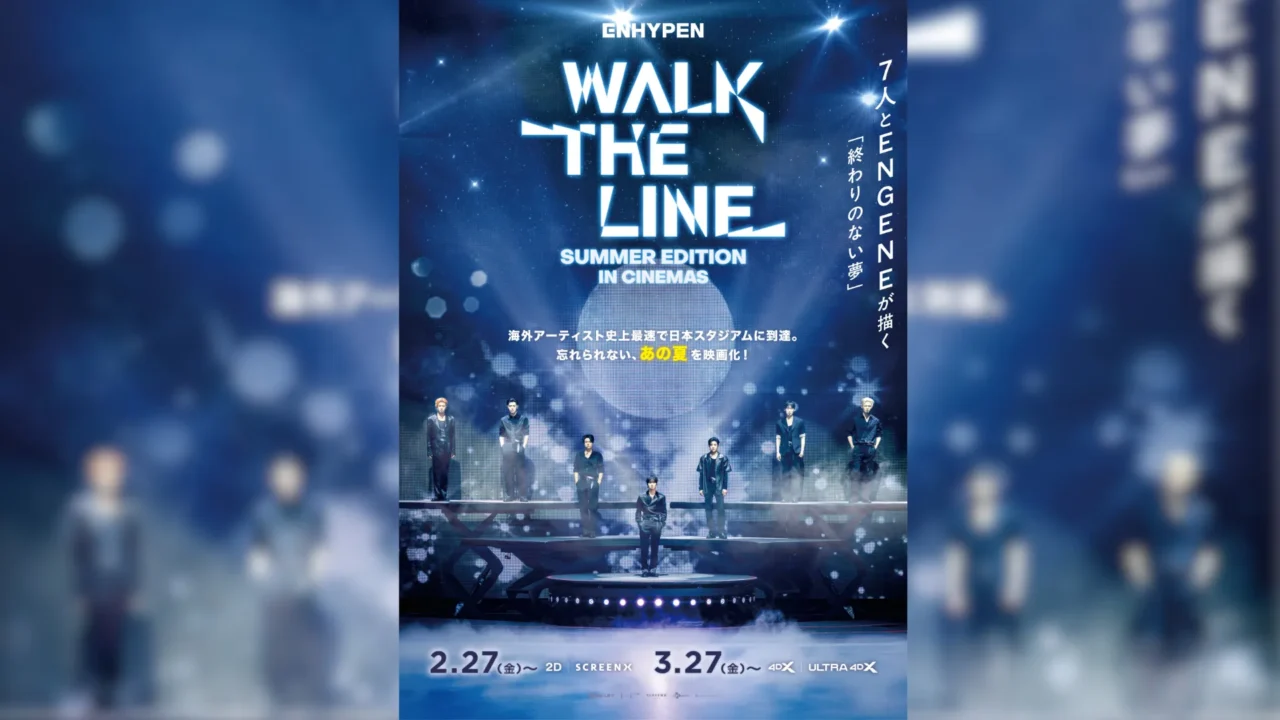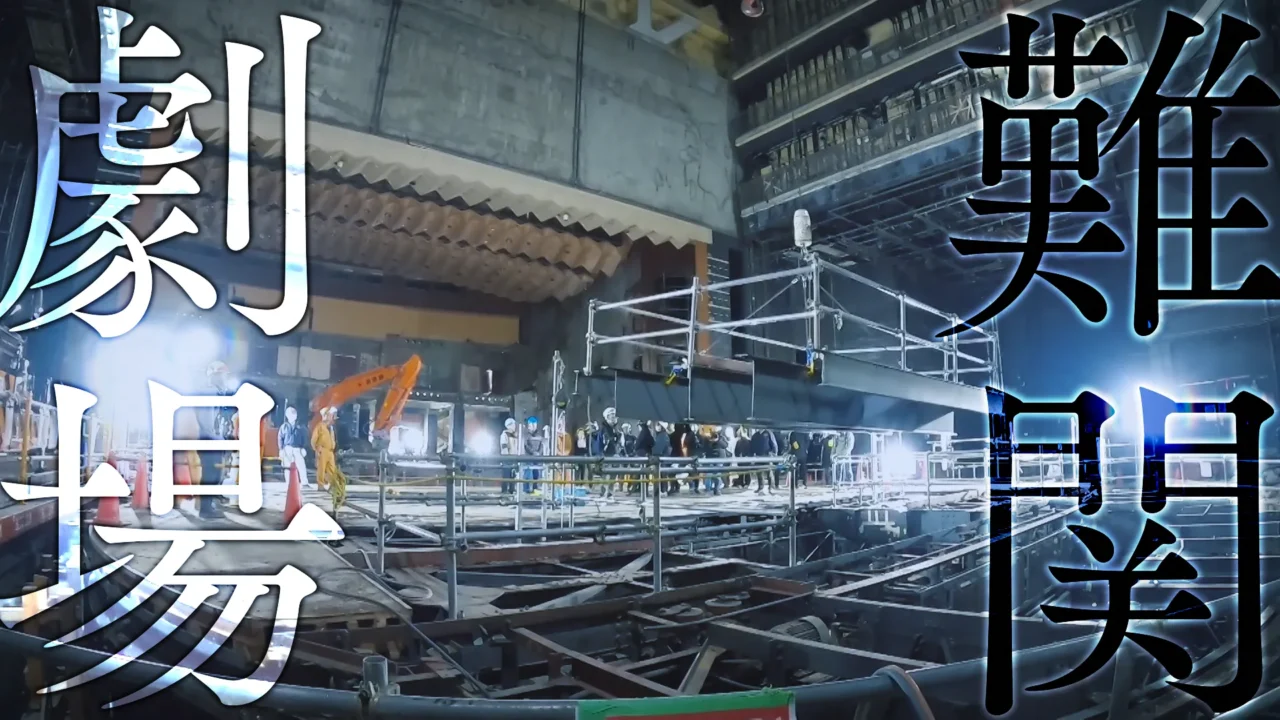NOT WONK / SADFRANKの加藤修平が「自分自身」を探る本連載、今回のゲストは音楽家の香田悠真。SADFRANKのコアメンバーとしても活動を共にする二人のトークセッションは、なんと「ベンチ」の話題から始まった。
INDEX
香田悠真のベンチマーク活動とは?
加藤:悠真くんって、こういう対談とかインタビューって結構やってます?
香田:こないだ、建築家と生態系研究者の方の3人で「散歩って何なんだろう?」っていうお話とかしたよ。
加藤:ベンチマークの話もした?
香田:ああ、したした(笑)。
―ベンチマークって何ですか?
香田:よく散歩する友人と、Googleマップ上にお気に入りのベンチが登録できたらいいな、っていう話をしていて。好きなベンチをピン付けしてアーカイブしていくってだけなんだけれど(笑)。いつかこれをアプリ化できないかなって思っていて、そのアプリ名がベンチマーク(笑)。

1991年生まれの音楽家。映画音楽やファッションショーの音楽監督を務める傍、舞台芸術やインスタレーションへの楽曲提供も多く手掛ける。2019年にAnshul Chauhan監督の長編映画『コントラ』において、第23回タリン・ブラックナイト国際映画祭の最優秀音楽賞を受賞。 近年には音楽を担当した清水 康彦監督作『スクロール』、Anshul監督作『赦し』、下津優太監督作『みなに幸あれ』等が公開。
―ベンチマークって名前はすげえセンスいいですね。
香田:レビュー機能もつけたくて。ある人は初恋の相手と座ったけど、別の日にある人はひどい二日酔いで寝てたとか、いろんな記憶が重なっちゃうと思うんですよ。それがいずれ良いリストになっていくだろうなって。
加藤:評価1から5が満遍なくあるのがいいベンチ(笑)。
香田:ベンチの良し悪しってすごく考えようがあるなって。都市計画から考えられているであろうベンチは、日照時間とか導線がちゃんと計算されてる。逆に皇居周りにあるベンチとか、とにかく量を置こうとしてるものは間隔がとても狭かったり。プライバシーがあんまりないっていうか。
加藤:ベンチって告白とかしちゃうぐらいだから、ある種プライベートな場でもありますよね。

NOT WONK/SADFRANK。1994年苫小牧市生まれ、苫小牧市在住の音楽家。2010年、高校在学中にロックバンドNOT WONKを結成。2015年より計4枚のアルバムをKiliKiliVilla、エイベックス・エンターテインメントからリリース。またソロプロジェクトSADFRANKとしても2022年にアルバムをリリース。多くの作品で自らアートディレクションを担当している。
香田:あとグレーなベンチも面白いなと。暖かい地域に多い気がするんだけど、地元の住民が家から椅子を持ってきて、座りたい場所に置いてる。沖縄だとバス停とかにも勝手に置かれてるのをよく見たりして、行政に全部任せきってない意識があるな、と。なかったら自分たちで作ればいいじゃんっていう、公共と個人の感覚がちょっと曖昧というか。
―東京は地価が高いから、座る場所自体が圧倒的に少ないですもんね。
香田:排除アート(※)とかも、いろんな工夫をして置きますしね。
加藤:絶対に寝転べないようになってますもんね。僕、歌詞書くとき、ケータイだけを持ってウロチョロしてんすよ。で、徐々にスタジオに近づきながら歌詞を書くんですけど、オペラシティの辺りにベンチがあったんで、持ってたカバンを枕にして、横になって歌詞書いてたんですね。そしたら警備員が近づいてきて、「ここは寝そべれないことになってるんです」って言われて。「体調悪いんだったら救急車呼びますし、そうじゃないんだったら起き上がってもらって良いですか?」って。ああ、そうですか……じゃあ立ち去ります、みたいな(笑)。
※パブリックスペースが損壊されたり、想定された用途以外で使われたりしないよう建造物に手を加える造形物。ベンチで寝られないよう間仕切りが設置されることもある。
INDEX
「音楽の単位としての『曲』と自分の思想とか歌詞の相性があんまりよくない(笑)」(加藤)
香田:詞を書くときは結構散歩するの?
加藤:移動しながらじゃないとちょっと嫌なんです。ずっと歩きながらケータイで打って書きますね。ペンと紙だと消すのめんどくさいんで。
―普段、思いついたフレーズとかメモしたりしますか?
加藤:しないです。制作するってなったときにガッて書く。基本的に嫌いなんですよ、歌詞書くの(笑)。

香田:メロディ先行?
加藤:メロディ先行です、圧倒的に。いい詞が書けたら良かったなとは思うんですけど、書くこと自体は嫌いです。メロディの方が僕の中で圧倒的に優位なんで、それを崩すのがすごく嫌なんです。すごくいい詞がテトリスみたいにメロディにフィットしたときは快感があるんですけど、その範囲がめちゃくちゃ狭いんですよ。
香田:なるほど。僕が曲を書く時は楽譜とかピアノ先行型だから、歌から作れることがあまりなくて。フォーキーな人がよくやるけどさ、先にメロディがあって、そこに無理やり収めたなっていうワード感があるでしょ。あの音符に対する憧れがすごくある。
加藤:それは僕もあります。やっぱ一個一個の玉が長くなっちゃうっていうか。
香田:歌いながら作るんだっけ?
加藤:そうです。ラララ、って感じで。ここはこの速さで歌いたいとか、この音で伸ばしたいとか。
香田:そういえば、こないだ合唱団に向けて曲を書かせてもらったんだけど、それがラテン語のテキストを引用してて。長い発音のメロディが多い楽譜を書いたんだけど、合唱の先生から意味の伝わり方をご指摘いただいて、とても為になった。その時にふと気づいたんだけれど、僕は複数の声部で違う歌詞が歌われたりするモテット風なスタイルとか、歌詞の意味が失われること自体にはあまり抵抗ないんだろうなと。その曲はテキストが記号的なのもあったんだろうけど、そもそもポップスであっても昔から歌詞に意味をあまり求めていなかったのに気づいて。だから言葉が変に伸びたり縮んでも気にならないのかも。

加藤:じつは昨日、人とその話めっちゃしてて。米津玄師の“Lemon”って曲あるじゃないですか。
(米津玄師の“Lemon”を流す)
加藤:ここの<きっともうこれ以上>って、すげえ間違ってるみたいに聴こえるんですよ(笑)。他人の曲なのに。いぃじょう、ってなんか違くないコレ? みたいな(笑)。
―日本語って割と無理しても成立しちゃうんですかね。広東語は伸ばすところとか発声の力み具合で意味が全然変わっちゃうから、広東語ポップスなんかは作詞がすげえ大変って聞いたことあります。
香田:なるほど。そのあたりの感覚が僕は薄いのかも。いま作ってるアルバムで、安部勇磨くんにボイスパーカッション的なことをやってもらってる曲があるんだけど、「ヨイショ、ヨイショ」とか「うふふ」とか色々すてきな日本語を入れてくれてるのね。それが聴いているうちにだんだんと意味が消えていって、パーカッションの一部として機能してくる。すると僕が抱えてる日本語に対する気恥ずかしさから逃げられたりするんだよね。加藤くんは英語も日本語もどっちもやるよね。
加藤:NOT WONKとしては2月に出すアルバムで初めて、日本語がちゃんと飛び出してくる瞬間をいくつか作ってるんですよ。前回のアルバムではワンワードだけ<あなたの名前>って言ってるんですけど。

―“Your Name”ですね。あれ以外で日本語って出てきてないんですね。
加藤:そうなんですよ。“Your Name”では通り過ぎるように、認識すらできないぐらいの感じで使ってるんですが、今回も急にインサートされるみたいな。それが一番効果的な気もする。音楽の単位としての「曲」ってあるじゃないですか。それと自分の思想とか歌詞の相性があんまりよくない(笑)。
香田:NOT WONKの新作の話ちょっとする? 僕、ざっと聴かせてもらったんだけど……ソロとバンドの違いについて一回ちょっと聞いときたいなと(笑)。
加藤:うんうんうん(笑)。
香田:まずシンセサイザーの扱いが面白いなって感じたんだよね、今回。ソロで色んなスタイルをやってしまったからこそミニマルなトリオをやることの難しさに向き合ってたと思うんだけど、どういう考え方でやったんだろうって気になってて。
加藤:今回のアルバムはトリオの作品として作り始めたけど、実際ベースがずっと不在な状態だったんで、ドラムのアキムとスタジオ入って、ベースがいないままダーッと作ったんですよ。アンサンブルが未完成の状態でレコーディングに突入するっていう。デモを作りたくないっていう欲があって。
香田:なるほどね。

加藤:デモがあるとそれ以上にならないっていうか、なぞっちゃうんで、やっぱり。ソロだったら「こうしたいんすよ!」っていうのを汲み取ってもらうためにも、デモの重要性が高かったんですよ。自分の中の100パーセントに近い状態で聴いてもらって、「でもこうじゃない?」ってサラッと変えちゃってもらえることが快感っていうか。けどバンドはそれやっちゃうと、過去の自分をなぞる感じになるんです。前作(『dimen』)は、ガッチリデモ作ってからやったんですけど、今回はそうしたくないなっていう。足そうと思ったらいくらでも足せるじゃないですか。
香田:僕がさっきシンセサイザーの話をしたのはそこが聞きたくて。足そうと思ったら足せる環境の中で、控えめに置かれてるシンセサイザーが何個かあるなって思ってて、これはどういう基準があるんだろうなって。
加藤:効果的ではないんだけど間違いなく作用している、みたいなシンセの使い方が音響的に好きで。「そういえばこの曲シンセ入ってんな」みたいなの結構あるじゃないですか、そういう仕事をシンセサイザーにしてもらいたいなって。“Changed”って曲も実はシンセ使ってて、サブベースの一番下のオクターブで、キックにピッチをつけるつもりで入れてるんです。ずっとトニック(主音)が鳴ってる状態って、場面転換がしない感じがして。パッて聴いてもわかんないんだけど、間違いなく作用している。

香田:ふ~ん。
加藤:SADFRANKでもそれやりましたね。無調の世界の、めちゃくちゃ下に低音をドローンみたいに忍ばせて、途中から急にそれが曲を進行させてゆくっていう。調性(キー)を作るものが、曲の中で移行していくみたいな考えが好きなんですよね、僕(笑)。
香田:どの曲だっけ?
加藤:“最後”って曲ですね。
(SADFRANKの“最後”を流す)
香田:こういうコンクレート的に作った曲って、聴き直すたびにいろいろ蘇るよね。
加藤:そうなんすよ。最初ツーコードで進行させてるんですけど、けっきょく実は裏の進行が“丸の内サディスティック”っていう大オチをつけたのを思い出しました(笑)。嘘みたいに“Just the Two of Us”進行になるっていう(笑)。まさにこの部屋で僕がほとんどミックスして、最後に微調整してもらったっていう感じでした。

―このミックス、めちゃくちゃ時間かかりそうですね。
加藤:ヤバかったっす(笑)。こういうのは大体みんなMIDIでやったりとか、テンポ決めたりしてやるんですけど、これはそういうの何もやらなかったんで。聴いて、オーディオをひたすら動かし続けるっていう。
―超アナログな。
加藤:超アナログ。ほんとにテープ切って貼ってるみたいな感覚でコラージュして。しかも一発録りなんすよ、これ。
香田:ここで4人すし詰めになってやったよね。ポップスの上で調性を揺らすってどうやるんだろうなって、いま僕も制作しながら考えてるんだけど。
加藤:それは、揺らしたい?
香田:揺らしたい。感情がすごく固定される気がして。せっかちだから耳が飽きるだけかもだけど。わかりやすく複調や多旋(※)を用いてみたり。でもこれはあんまりうまくいかないね。
そう言えば先々月かな、『ドナウエッシンゲン音楽祭』っていう、ドイツで毎年やってる有名な現代音楽祭があって、今はストリーミングでも見れて。僕にとってはある潮流を見られるのでとても興味深いのだけれど、そこの初演が結構、調性が保たれたものが増えてきてて驚いた。
※様々な旋法を並列して用いること

加藤:あ、そうなんすね。
香田:前衛の方が、調性に戻ってきているような。ライヒっぽく受け取りやすいな、って思うような曲が多い。ブツ切りの、和声を現代にした、どんどん流れるような曲が多く感じて。
加藤:それはチョップされてるんじゃなくて、最初からそういう構造になっている?
香田:そう、それをあえてオケでスコアに落とし込むっていうか。そういう潮流を感じた。
加藤:いま、いろんな音楽がそうですよね。J-POPも和声進行がすごく複雑になっているじゃないですか。そういう構造をアナライズする番組も増えてきてるし。
香田:それは、スポーツ化しやすいからってことなのかな?
加藤:だとも思いますし、芸大至上主義的な考えがまた戻ってきているのかな。そういうアカデミックなものに対する一般的な興味って増してるような気がする。批評したいんですもんね、今、みんな。
-SNSとかは年々批評的になっていますよね。
加藤:完全にその流れだなって僕は感じていますね。転調とか変拍子とか複雑な和声の権威性が高いっていうことじゃないですか、現代の日本は。複雑さイコール高尚、みたいな考えがいまのポップスにはあると思うんですけど、ひょっとしたらまたTHE BLUE HEARTSみたいなのが出てきて、また更地に戻すようなことが起きるのかなー、とか。

香田:複雑さっていうのは好まれやすいんだろうね。ブライアン・ファーニホウとかが国内でとても人気があるのは、楽器ひとつとっても動きがとても複雑で、わかりやすい凄みがあるというか。
加藤:受け止め切れる複雑性の限度ってどこなんだろう、って思いますね。聴き取れるハーモニーってどこまでなんだろうとか。ピアノとか、バンドの中で弾いてても聴き取れないっすもんね。
香田:バンドにおけるピアノって難しいよね……。J-POPって呼ばれるものの中では、和声を担保するというよりパーカッシブなアプローチが多いんだろうなと思うけど。実は下声部のほうでこんなことやってます、っていうのも競技的な趣があるよね。そういうものは星がつけやすいというか。
加藤:そう考えるとベンチと同じで、星が1から5まで満遍なくついてる音楽が、一番優れてるのかな(笑)。
INDEX
ボサノヴァから寅さん、映画音楽、そしてスーパーのBGMまで
香田:普段思ってることがどこまで曲に染み渡るかって、当たり前だけど大事だよね。加藤くんはそれが現れやすいような。キャラクターと曲が解離してる人って多いから。「普段ここを恥ずかしがれるのに、これをやっちゃうんだろう?」みたいな。加藤くんはそういう解離が少なくて、キャラクターと曲がとても近く感じる。
加藤:詞だけじゃなくて、ビートとかハーモニーもそうじゃないですか。僕、悠真くんのソロで一曲歌ってるんですけど、「そうっすよね!」ってなる。「ここがただのセブンスになるの、わかるぜ!」っていう(笑)。

―その楽曲をけさ聴かせてもらったんですが、何というか無国籍感がすごかったですね。どこの国の音楽かわからない感じがしました。
香田:あれはボサノヴァっていうか、最初は特にミナスサウンドを思いながら作ってたんだけど。SADFRANKで難しいボッサの曲弾かせてもらったから、僕もそのあと彼に作った(笑)。
―局地的なボッサムーブメントがあったんですね(笑)。
香田:僕がミナスの音楽に最初に出会ったのって、ブレッソンの『白夜』という映画のワンシーンで。橋の袂に楽団が乗ったボートが流れてきて、それがだんだんだんだん下っていく、香り高くて色気のある情景で、それこそ「どこの国の音楽なんだ?」って。調べてみたらマルク・リバスの“N’Biri, N’Biri”って曲だったんだけれど。そのミステリアスな感情をそのまま曲にしたくて、歌ってもらったんですよ。加藤くんの新作のボッサに関しては何の影響が大きい?
加藤:Pinstripe Sunnyの『Bossa Loser』ってアルバムがあるんですけど、これが凄く良くて。
(Pinstripe Sunnyの“Toilet Boy”を流す)
加藤:このベッドルームの感じというか、一人の音楽になってる感じのボッサは好きですね。
―そういえばブラジル音楽って全体的に音が良い気がするんですけど、何でなんでしょうね。
加藤:うーん……優しく弾くから?
香田:最近思ったのはストリングスの音がひじょうに優れてるものが多いような……。とくに1970年代あたりのは節度が凄く守られてる。あとマイクの本数が少ないのかな。ふと思い出したけど『男はつらいよ』のテーマとかもそう感じるんだよね。
―寅さんですか。
香田:これもねえ、結構音いいんだよね。
(渥美清の“男はつらいよ”を流す)
香田:never young beachが衣装を寅さんの格好でやってた時期があって、SEもずっとこの曲だったから、僕が参加してる時は全国いろんな会場の音響でこれ聴いたんですよ。で、どの会場の音響にも耐えうるな、再現性あるな……ってステージ脇で思ってた。
―再生環境を選ばないっていうのも音の良さのひとつですね。曲自体に地力があるというか。
加藤:スーパーマーケットの店内BGMとかの、打ち込みのJ-POPカバーあるじゃないですか。アレもいい曲はやっぱいいですよね。蕎麦屋で流れてるお琴アレンジのスピッツとか最高じゃないですか(笑)。
香田:バッハ的な考え方だね(笑)。そう言えば武満さんが、自分の音楽とバッハとの対比をどこかで書いていたね。バッハには再現性があるけど、自分の音楽は音響込みでしか完成しえないと。

―ジョン・ケージも音楽はライブでしか聴かなかったとか言いますが、ライブと音源の解離っていうのは音楽家にとってやっぱ命題なんですかね。
香田:いま映画音楽に集中してたから、その話になっちゃうんですが、映画館って一回性のライブに近いところがあるので、劇中で流れる音楽は、そうした映画館での体験を意識して作ります。一方でサントラはもう少し踏み込んで音楽だけで成立するように構成を変えたり、劇中の環境音を取り入れて映画の世界観を補完したりもする。リモデルとかの流れはむしろ解離を良しとしてますよね。
―映画音楽家の仕事って、どこからどこまでなんですか?
香田:昔は作曲して、録音して音楽を完成させたらお終いだったと思うんですが、いまだと音楽と映像を合わせるダビングまで立ち会うことが多いんじゃないですかね。僕は音楽なのかSEなのか解らないような劇伴も多いから、ダビングまで付き合わないと印象が変わっちゃう。たとえば環境音からキーを決めたりしてた場合、劇中で鳴ってた掃除機とか電話の音のチューニングが、ダビング段階で変わってたりすると厄介というか。映画を観ててなにか音痴に感じるときって、実はそういうとこにエラーがあるのかなとか。
INDEX
選曲しながら音楽におけるノスタルジーを探求
―しかし、『男はつらいよ』はなぜこんなにノスタルジーを誘うのでしょうか。坂本龍一さんも晩年、最初のタイトルバックが出て、このテーマが流れた瞬間に涙が止まらなくなるって言っていましたが。
香田:『男はつらいよ』に関して言えば、僕らの世代にとってはどこか架空のノスタルジーなのかなと思うけれど。
加藤:日本人のDNAに訴えかける、とか言いますけど、ノスタルジーって実は刷り込まれたものな気がするんですよ。けっきょく一番懐かしいのって、親の車でかかってたDA PUMPとかじゃないですか?
香田:本当の意味での故郷だ(笑)。この話は小林秀雄さんとかが故郷喪失ってテーマで触れてるよね。僕らは喪失を埋めるために、いろんなタイプのノスタルジーをいろんな国から吸収して作り上げてきたというか。

加藤:僕が一番ノスタルジーを感じるのはIVかVm6(マイナーシックス)ですね。僕がノスタルジーを感じる曲には大体入ってる(笑)。これ“Shenandoah”って言うアメリカの民謡なんですけど。
(“Shenandoah”の合唱版を流す)
―すばらしい。これはどういう歌詞なんですかね。
加藤:あー、なんか七夕のことを歌ってるように僕は感じるかも。
―七夕系ですか(笑)。教会で歌ってるのかな? なんかホーリーな感じが……
香田:アメリカの讃美歌って、こういうコード感よね。これも移民たちが異国に安心感を作るためなのかな。そして似てる曲がとてつもなく多い。
加藤:何でなんですかね。
香田:だれもが歌えるってこと重視でキーが少なくなったとか、構成も限られていったからかな……。
加藤:一番下の音がないって感じがするんですよね。難しい表現になりますけど、戻ってくる場所じゃないんですよね。あと、僕のノスタルジーっていうとコレとか……
(矢代秋雄の“夢の舟”を流す)
加藤:この人は、奇譚クラブっていう有名なSM雑誌によく寄稿してたらしいんですけど(笑)。
香田:フェデリコ・モンポウ好きでしょ?
加藤:あ、好きですね。初めて聴いたとき「これみんな好きなやつでしょ?」って思った。この“Impresiones intimas: No. 5, Pájaro triste”って曲が凄く好きで。
(フェデリコ・モンポウの“Impresiones intimas: No. 5, Pájaro triste”を流す)
香田:エマホイ・ツェゲ=マリアム・ゴブルーとか好き? エチオピアの作曲家なんだけど……
(エマホイ・ツェゲ=マリアム・ゴブルーの“Mother’s Love”を流す)
香田:モンポウとエマホイの郷愁性ってそれぞれ別物だけど、どちらも僕らには架空のノスタルジーを感じさせる。加藤くんは、意識して自分の曲に取り入れることはある?
加藤:自分の中でのリアルなノスタルジーは結構あるかもしれない。
香田:なんだか瞬間とっても苦い記憶がよぎった……みたいな感覚は大事だよね。
加藤:そういうのって大体違う色で表出してきますよね、それをキャッチすんのも面白いですね。詩とかも自分でキャッチできるようになったら面白いんでしょうけど。

INDEX
「僕は自分の感情が塗り替えられてしまうことに疑惑の目を向けてる」(香田)
―加藤くんは好きな作詞家とか詩人とかっているんですか?
加藤:それこないだ取材でも聞かれたんですけど、いないんですよ。自分の中にお守りみたいにしてる言葉とかないんですよね。
香田:それは日本だけじゃなくて?
加藤:そうですね……詞とか言葉を心に留めといたりすることがないんですよね。人の曲歌ったときに、これいい詞だなとか思ったりはするんですけど。
香田:僕はわかりやすく良い言葉にも惹かれるのだけれど、リルケとか、言葉が強いというか、奮起させるような詩は、それがそのまま音楽になったらちょっとくどいというか。あいまいに留めておきたくて。ヴェルレーヌの『詩法』っていう、詩の書き方について散文で書いた作品があるんだけど、その一節で、「定かなる 定かならぬと打ち交わる灰色の歌 この灰色の歌は何者にも勝らん」っていうのがあって、作曲するときにたまに思い出したりする。古いお守りみたいなものかもね。
加藤:僕は、会った人とか、見かけたシチュエーションとかから着想を得たりしますね。その人の表情の前後をすごく想像する。さっき公園で撮影してるとき、小学生ぐらいの子供が「何してんの?」とか言って絡んできたんですよ。で、「ローラーブレード滑れる?」とか聞いてきたから「滑れるよ」って言ったら、「俺もできるよ、東京ドームシティで毎日滑ってる」って。

―自慢げに?
加藤:自慢げに(笑)。無料で入れるチケットを親がいっぱい持ってるから、毎日そこで滑ってるとか言ってて。その瞬間の感じとか一生忘れないですよね。彼は都会の子供で、僕は田舎の大人だから、全然取るマウントが違うなって。おれのマウントって、親がクワガタいっぱい取ってきたとか、車の名前めっちゃ知ってるとか、そういうマウントだったよなって。しかも都庁の真下の公園で遊んでるんですよ。都庁がピカーっと赤く光ってて、その真下にホームレスの人がいっぱいいて。
香田:両親も近くにいなくてね。
加藤:帰らなくていいの? って聞いたら22時まで遊ぶっつって。嘘だろ、みたいな。
―そういうロケーションが残っていくんですね。
加藤:凄く下品な言い方をすると、そういう画として残る感じが好きなのかもしれない。社会問題的な目線ももちろんあるんですけど。

香田:こういう子はどんなノスタルジー持つんだろうねとかね。都庁の赤い光が安心感になるのかとか。
―そういう瞬間が歌詞になっていったりするんですか。
加藤:なりますね。こないだPROVOの龍太さんとTHA BLUE HERBの話をしてたんですけど、ヒップホップは自分じゃ思っていても言えないようなことをパーンと言い切ってくれるからすげえ楽になるよなって言ってて。
―代弁というか、思考を言語化してくれたみたいな。
加藤:でも本当は思ってないとも思うんですよね、それって。受けた瞬間に発生してるだけで、自分が思ってたことではない。
香田:僕は神経質だからか、そういう自分の感情が塗り替えられてしまうときにとても慎重。書いた曲をある程度プレイヤーに委ねて演奏してもらうって瞬間にもよく起きるけど。とてもすばらしいものになった反面、僕の感情ではないっていうとき、それを良しとするか、ダメとするか。楽器であったり人であったり、力強すぎる代弁者が現れた時に細部は塗り替えられちゃうことがあるよね。

加藤:均質になるんですよね。すばらしく感じるものってだいたい一緒だから。デカい海とか美味い魚みたいなのって均質なんですよね。そこに凄く抗いたい感はある。「すばらしい」ってある種デジャヴだと思うんですよ。だからみんなLSDとかやるんでしょうね。僕はやんないですけど(笑)。
香田:それもある種均質化なんじゃないの?
加藤:リバーブ踏んでディレイかけるだけみたいなのは、本当の美しさに接近してないと思うんですよ。
―踊ってばかりの国の下津君が、昔インタビューで「2万円あればサイケは出来る」って言ってました。
加藤:リバーブとかディレイは誰でも買えますしね(笑)。近しいものが提示されても、それじゃないって言える強度が自分のビジョンにあればいいんですけどね。
―均質化を追求するというか、ずっと同じものを作り続けるクリエイトとかもありますよね。JBとか、ラモーンズとか……そういうスタンスはどう思いますか?
加藤:自分にはできないですね。キーにしてもテンポにしてもギターの音にしても、想起させるものが自分の中にあると自己模倣してるような気になって、避けちゃう。でも同じものが並ぶ気持ち良さって、やってみたくはあるんですよね。
香田:だけれど僕らはどうしても西洋化されてるから、よこしまなアーカイブ欲がある。どこか博物館的なことをやりたいというか。

加藤:あとから作品をズラッて並べた時に、時代を経て点で繋がるところがあるんです。自分の中ではこことここは繋がってるって説明できると思う。でも誰にも語らずにほくそ笑むっていう(笑)。
香田:まぁ人生の中で10ぐらいのスタイルの曲が作れたら十分じゃないのかな? 脚本とか比較神話学の本読んでたら、物語が10ぐらいに限られるというか。僕らが根幹に持ってるスタイルって本当はそれぐらいで、それをどこから受け取ってどこに繋いでるのかって話にかんじてる。
加藤:曲作ってても、結局ここを変えるか変えないかの二択しかない。その二択をずっと選び続けてるだけなんですよね。
香田:まぁそう言えば、確かにね(笑)。
―さて、そろそろ締めくくりたいと思いますが、今回話してみていかがでしたか?
加藤:悠真くんとはいっつもこういう話してますね。悠真くんと話してると「そうなんすよ!」って言うこと多いですね(笑)。
香田:恥ずかしく思うポイントとか欲しがるポイントがちょっと似てるんですよ、きっと。
加藤:言い当ててくれることが多いです(笑)。

NOT WONK 5th Album『Bout Foreverness』

アーティスト:NOT WONK
タイトル:『Bout Foreverness』
リリース日:2025年2月5日(水)
レーベル:Bigfish Sounds
フォーマット:配信 / CD
販売価格:CD ¥3,300(税込)
トラックリスト
1. About Foreverness
2. George Ruth
3. Embrace Me
4. Same Corner
5. Changed
6. Some of You
7. Asshole
NOT WONK ONEMAN TOUR “Bout Foreverness”
チケットリンク:https://w.pia.jp/t/notwonk-2025/
料金:学割 3,000円 (+1D) / 一般 4,000円 (+1D)
■2025年2月27日 (木)東京・渋谷 CLUB QUATTRO
時間:OPEN 18:15 / START 19:00
■2024年3月14日 (金)大阪・心斎橋 Live House ANIMA
時間:OPEN 18:15 / START 19:00
■2025年3月15日 (土)愛知・名古屋 CLUB UPSET
時間:OPEN 18:00 / START 18:30
■2025年4月20日 (日)北海道・札幌 BESSIE HALL
時間:OPEN 18:00 / START 18:30
主催/制作:Bigfish inc.INFO:エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/