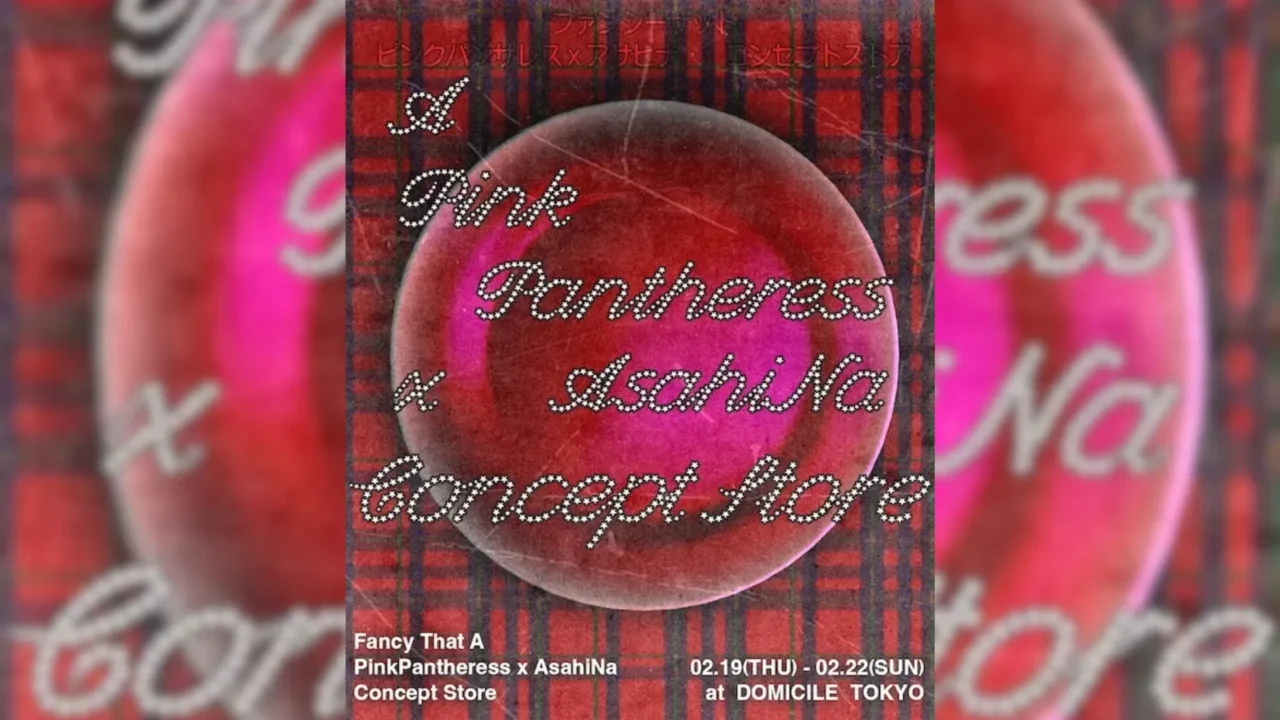2025年12月19日(金)より劇場公開となる、コリン・ファレル、マーゴット・ロビー主演映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』。久石譲が劇伴音楽を務めたことでも話題の同作を、評論家 / 音楽ディレクターの柴崎祐二が論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第33回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
久石譲、初のハリウッド映画劇伴
何年か前のこと。とあるアメリカ人の知人と映画や音楽について世間話をしているときに、君は久石譲の作品についてどう思うのか、と訊かれたことがある。私はちょうどその頃、映画音楽作家として巨大な成功を収める以前の久石の初期作品に強い関心を抱いていたこともあって、ミニマルミュージックの歴史に根ざしながら電子楽器等のテクノロジーを積極的に取り入れたそのジャンルレスな作品に大いに感銘を受けている、と答えた。するとその知人は、私の感想に同調しつつ、スタジオジブリ作品の有名なスコアや、クラシック〜現代音楽作曲家としての久石作品を例に出しながら、自分にとっては、それらの中に彼特有の深い情動があるように感じられるのだ、と力説してくれたのだった。続けて彼は、その情動は、何よりもファンタジックな想像力に通じているものであり、時に「非西洋的」な美意識を想起させるのだ、とも言った。私自身、久石の音楽に漠然とながら似た印象を抱いていたものの、改めてそのように指摘する知人の意見によって、なるほど彼の作品が海外にも膨大なファンを持つ背景を、はっきりと認識できたのだった。
久石譲は、そのような世界的な認知度を持つ作曲家でありながらも、やや意外なことに、これまでにハリウッドの映画作家とコラボレーションを行った経験は全くなかった。この度公開された映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は、そんな彼が初めて劇中音楽を担当したハリウッド製映画である。監督を務めるのは、『コロンバス』や『アフター・ヤン』等の作品で高い評価を得る韓国系アメリカ人監督=コゴナダで、自身がスタジオジブリ作品とその劇中音楽の大ファンであることから、熱烈なオファーを経た上でコラボレーションが実現したという。

INDEX
ファンタジックな物語、やや空回りの感も……
映画のあらすじを紹介しよう。
ある雨の日。デヴィッド(コリン・ファレル)は、不思議なレンタカー店で車を借り、友人の結婚式へと駆けつける。そこで彼は、同じく独りきりで式に参加しているサラ(マーゴット・ロビー)と出会う。
その場限りの会話を交わし、翌朝には各々帰路に着こうとする二人だが、なにやら様子のおかしいレンタカーのカーナビに誘われて、一生に一度の「美しい旅」へと繰り出すことになる。デヴィッドとサラは、現実を離れ、かつて自分たちが体験した人生の場面に再び立ち会いながら、過去の過ちや後悔と向き合い、現在の自分の姿を見つめ直す旅を続ける。
こう書き出してみただけでわかる通り、本作『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』は、現実と幻想が入り混じるマジックリアリズム的想像力に貫かれた作品だ。ドアを開けると、そこには別世界が広がり、時空を超えた超現実的な体験が主人公の二人を導いていく。こうした舞台設定、物語の構造は、まさに監督が敬愛するスタジオジブリ作品――特に宮崎駿監督作品の世界を彷彿させるものだ。
加えて、その視覚的イメージの面でも、現実と夢想の表象が溶け合いながら、見るものに対して没入感と浮遊感を同時に投げかける。このような両義性もまた、我々が親しんできたジブリ作品の特質に通じているわけだが、本作は、さらにそこへ自己言及的な構造――スタジオの中にひっそりと佇むレンタカー店を始めとした演劇的な舞台設定や、劇中劇の上演などを通じて、もう一捻りを加えようとする。
一般に、こうしたメタ的な構造は、熱心な観客に「考察」の楽しみを与える一方で、よほど上手に取り扱わなければ、ファンタジーの存在を無条件の前提とする構造が引き起こす一種の矛盾を自らがわざわざ指差し確認すること、さらに言えば、ただ「現実離れ」した白々しさを観るものに植え付けることにも成りかねない。もっと言えば、リアリティレベルの一貫性からの逸脱が、それが本来狙っているはずの劇的な効果に結びつかず、どうかすると単なる空想の遊戯に耽っている印象を強める危険性すら秘めている。

正直に述べると、本作『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』の画面からは、まさにそうした遊戯性への傾きを感じる瞬間も少なくない。スクリーン上のルックとしては、美術も、構図も、照明もごく練り込まれたものであることは理解できるのだが、その一方で、一枚絵的な美しさを大胆に超え出てみせる映画的なダイナミズムを(テーマの壮大さや、役者陣の芸達者ぶりに比して)はっきりと感じることは難しい。
プレスリリースによれば、ファンタジックな「絵」が必要になる場面でも、ポストプロダクション段階におけるVFXの使用をなるべく排し、撮影現場に設置したLEDパネルで仮想的な環境を作り出す先端技術=インカメラVFXが使用されているとのことだが、それらの存在にもかかわらず(それらの存在ゆえに、と言うべきかもしれないが)、個別的な画面のいかにも分かり易い「美しさ」は確かに担保されているように感じるものの、シーン内 / シーン間のシーケンシャルな一貫性という観点からみれば、やはりそれほど劇的な効果を上げているとは感じられない。つまり、画面を追うだけでは、大事な「何か」が動いてないように思えるのだ。
INDEX
ミニマル的なスコアが逆説的に生み出す情感
けれどもその一方で、映画全体として鑑賞してみた時、なにやら心地の良い情動(としかいいようのない何か)の流れ=運動が存在すること、さらには、その流れ=運動に身を委ねる快さがあることもまた、否定できないところなのである。私が考えるところでは、そうした役目を(本来期待される以上の責任をもって)担っているのが、他でもない久石譲のスコアなのではないかと思う。

本作における久石のスコアは、スタジオジブリ作品や様々な邦画における、いかにも情緒豊かな彼の作風に慣れ親しんでいる我々の感覚からすると、やや静的で、冷温的なものに感じられるかもしれない。本作の音楽からは、しばしば「東洋的」と評されがちなスケール〜メロディーの個性はそれほどまで目立っては聴かれないし、オスティナート(編注:あるフレーズを繰り返し反復させること)を多用した構成もまた、一見したところでは、なにがしかの強い感情を想起させることを避けるように立ち回っているようにも感じられる。つまり、ここで聴かれる音楽は、スタジオジブリ作品に顕著に現れていたような「キャッチー」さからやや距離を置いたもの―――むしろ、久石のキャリアにおける重要な軸の一つ=ミニマルミュージックと、それらに続くポストミニマリズムの諸実践に直接的に連なるものだろう。仮に久石の膨大なディスコグラフィーの中に位置づけるとすれば、初期のオリジナル作品や、一部の北野武監督作における反復的なスコア、そして、2009年以来展開されている現代曲集『Minima_Rhythm』シリーズの流れを継ぐものだといえるのではないだろうか。
だとすれば、実際にこれらの音楽を画面が得た際にも、同じように、静的で、微温的な印象のみが立ち現れるのであろうか。決してそうなっていないし、それどころか、画面の裏側に隠されていた感情が、音楽が流れ出るのにあわせてにわかに動き出すのを感じないわけにはいかない。悲しいとも、嬉しいとも、暗いとも、明るいとも言い切れない感情の機微が、画面の彼方に畳み込まれた微細な表情とともに、静かに、だが忽然と立ち現れる。小編成のアンサンブルから紡ぎ出されるシンプルでいて儚げなメロディー、素朴ながらも美麗なハーモニーが、微妙な変化を交えながら反復することで、主人公二人の、および彼らを見つめる私たち観客の情動を、巧みに導いていくのだ。
ここには、細やかなフレーズの反復と変化の連続が音のモアレを描き出し、果てはそれ特有の肌理を作り出していくというミニマルミュージックの根源的機能との深い連関も垣間見える。久石の音楽は、そのモアレの模様の鮮やかさ、肌触りによって、私たちの感情の奥深くに触れようとするのだ。そして映画は、このような力を秘めた久石の音楽と出会った時、ようやく本格的な(感情の)運動を開始するのである。