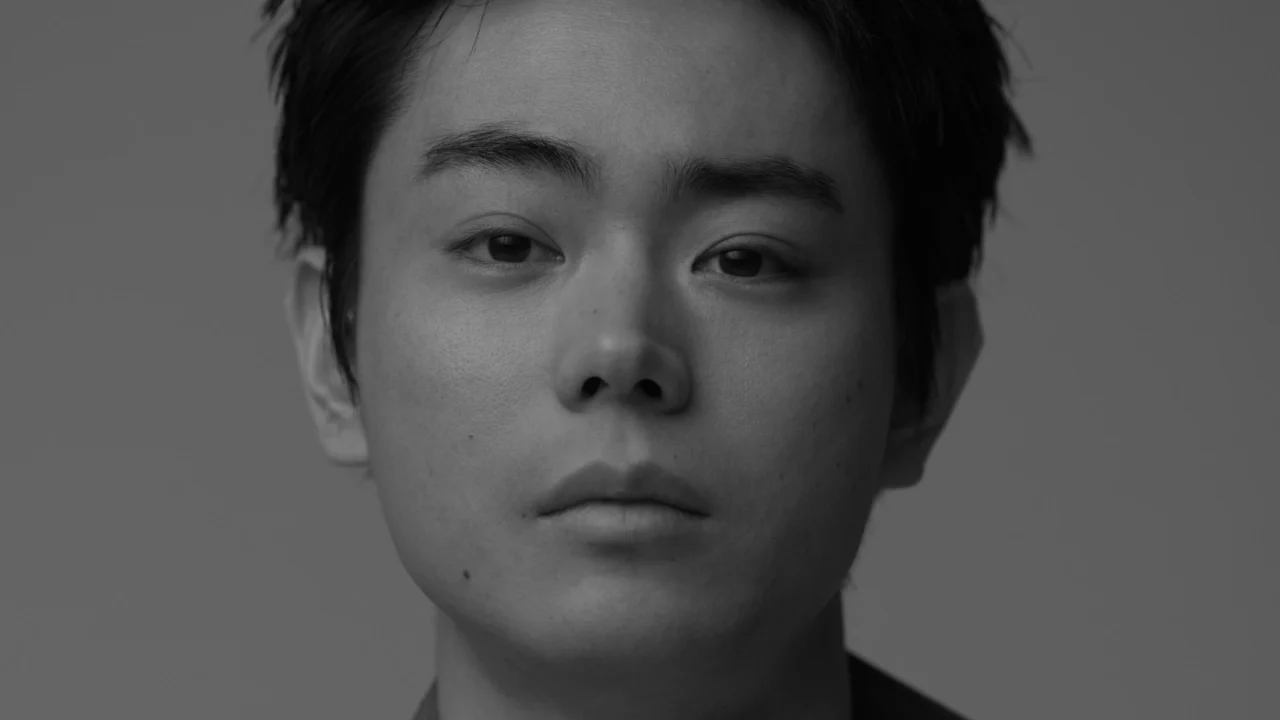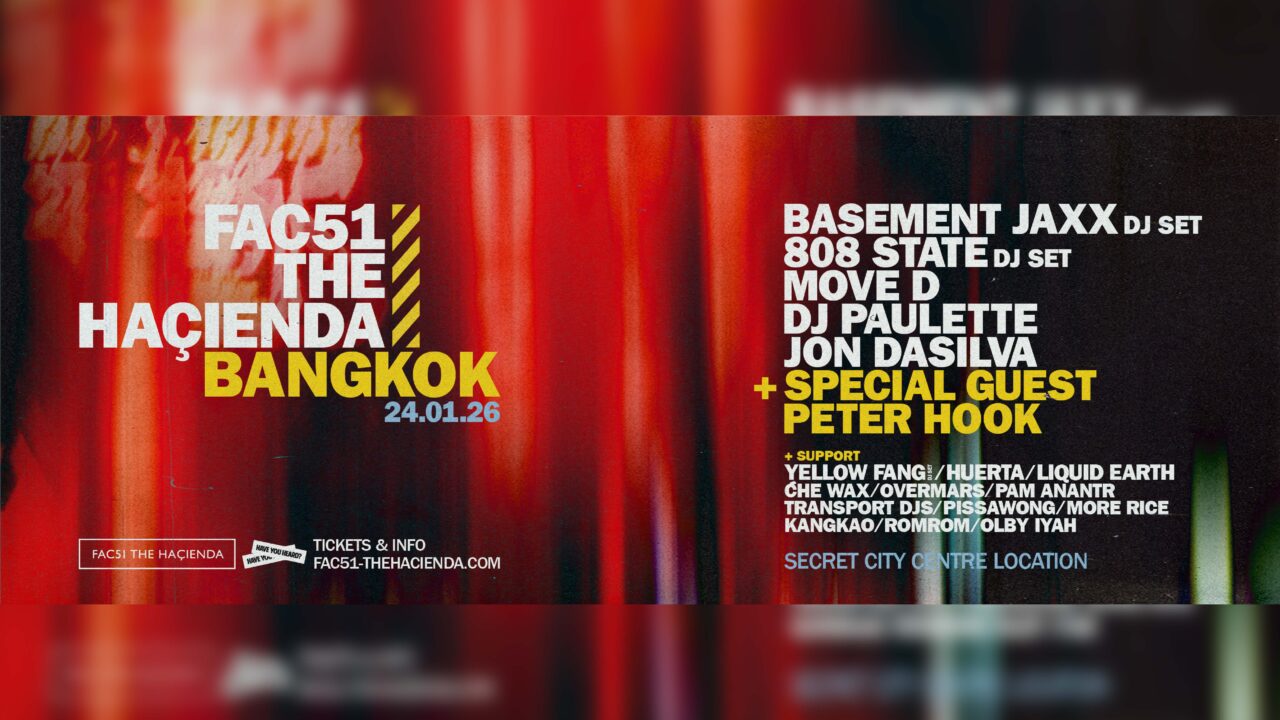連載「その選曲が、映画をつくる」第12回は、ドキュメンタリー映画『美と殺戮のすべて』を取り上げる。
写真家ナン・ゴールディンの半生を辿るとともに、彼女が追求してきた薬害問題に迫った本作は、第79回『ヴェネツィア国際映画祭』でドキュメンタリーとしては珍しい金獅子賞(最高賞)を受賞するなど、大きな話題となっている。
華々しくも刹那的で危なっかしい1970年代〜1980年代ニューヨークのアンダーグラウンドカルチャーを映し出す音楽、そこから一転して音楽使用が排されることの効果、一見長閑なホームビデオのような映像とともに流れるスタンダード曲から読み取れる恐ろしさなど、評論家・柴崎祐二が音楽の観点から本作に迫る。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
アメリカで大きな社会問題となった「オピオイド危機」
大手製薬会社パーデュー・ファーマ社が開発し、1995年にFDA(米国食品医薬品局)に承認されたオピオイド系処方鎮痛薬「オキシコンチン」は、既存の鎮痛薬よりも効果が強く依存性の低い安全な薬品として、大々的に売り出された。結果、その後10数年にわたっておびただしい数の市民に処方されることになったが、当初謳われていた安全性とは裏腹に、多くの深刻な依存者を生み出していった。過剰摂取等による中毒死も相次ぎ、これまで全米で50万人以上が死亡するなど、社会全体を揺るがす大問題を引き起こしてきた。
2007年、連邦政府は、オキシコンチンの危険性を虚偽表示したとしてパーデュー・ファーマ社に対して訴訟を起こし、その結果同社は過失を認め、約6.3億ドルの支払いが命じられた。しかし、その後もオピオイド系鎮痛薬の処方はとどまることはなく、処方件数は更に増加、合成オピオイドの密輸入も本格化するなど、より一層多くの依存者を生み出してきた。
非公開企業として背後の資本関係が長らく一般に知られることのなかったパーデュー・ファーマ社であったが、2017年に『エスクァイア』誌に掲載された記事によって、美術館への寄付などの慈善事業で知られるサックラー家が同社を所有していることが明らかにされた。写真家のナン・ゴールディンは、オピオイド危機の事態改善を訴える市民組織P.A.I.N.(Prescription Addiction Intervention Now)の設立を宣言。翌年には、サックラー家が製薬事業から得た利益を様々な美術館や大学へ寄付していた事実を詳述した記事を『アートフォーラム』誌へ寄稿した。以来P.A.I.N.は、サックラー家の悪事を糾弾し、アート界への偽善的な関与を糾弾するため、各地の有名美術館で抗議活動を展開していく。時に奇異の眼差しを受けることもあった彼らの活動だったが、絶えることなく発信を行い、社会的な関心の高まりとともに着実な成果を挙げていくのだった。
本作『美と殺戮のすべて』は、そのP.A.I.N.の活動と、ゴールディン自身の半生に迫る長編ノンフィクション映画である。
監督を務めたのは、2014年公開の監督作品『シチズンフォー スノーデンの暴露』が第87回『アカデミー賞』長編ドキュメンタリー映画賞をはじめ多くの賞を獲得したドキュメンタリー映画作家 / ジャーナリスト、ローラ・ポイトラスだ。巨大権力による不正に対し勇気を持って戦う個人の姿を追うそのスタイルは常に重厚な説得力を伴っており、本作においても、ナン・ゴールディンという一人のアーティスト / 活動家の揺るぎない信念をごく丁寧に映し出している。

INDEX
ナン・ゴールディンを取り巻くカルチャーと音楽
本作は、アクティヴィストとしてのナン・ゴールディンの現在の姿を活写する一方で、少女期に体験した姉バーバラ・ホリー・ゴールディンの自殺という忘れがたいトラウマを起点に、波乱に満ちた彼女の歩みも追っていく。類稀なフォトグラファーであるゴールディンが、いかにしてその活動を開始し、どういった交友関係の中で芸術的なアイデンティーを獲得していったのかが、1970年代〜1980年代当時のアーカイヴ映像や彼女自身によるスライドショーを交えながら映し出されていく。ボストンからニューヨークへと拠点を移していく中で、ドラァグクイーン、ゲイカルチャー、ドラッグカルチャー、パンク〜ノーウェイヴシーンなど、彼女を取り囲む「拡大家族」とともに過ごした同時代のコミュニティとその活況が貴重な証言 / 映像とともに綴られており、当時のアメリカ東海岸のアンダーグラウンド文化に少しでも興味のある観客なら心を奪われるのは必至だろう。盟友たる写真家デヴィッド・アームストロングとの出会いにはじまり、ジョン・ウォーターズ映画への出演でも知られる女優 / 作家のクッキー・ミューラー、更には、ノーウェイヴ映画作家のヴィヴィアン・ディックやベット・ゴードンなど、次々に紹介されるゴールディンの友人たちおよびその作品は、1970年代から1980年代にかけての新たなアンダーグラウンドカルチャーの担い手として、特に重要な存在ばかりである。

映画におけるポップミュージックの印象的使用にフォーカスしてきた本連載の視点からは、そうした新鋭アートシーンに渦巻くエネルギーへ迫った一連の流れにまずは興味をそそられる。
映画中盤までに流される主な楽曲は、以下の通りだ。クラウス・ノミ“The Cold Song”、The Velvet Underground & Nico“All Tomorrow’s Parties”、“Sunday Morning”、Suicide“Cheree”、シャルル・アズナブール“What Makes A Man”、ディヴァイン“Female Trouble”、The Marvelettes“The Hunter Gets Captured By the Game”、Bush Tetras“You Can’t be Funky”、リジー・メルシエ・デクルー“Fire”、ジャニス・マリー・ジョンソン“Boogie Oogie Oogie”、スクリーミン・ジェイ・ホーキンス“I Put a Spell On You”、The Sugarhill Gang“8th Wonder”他。
当時のニューヨーク地下シーンに生まれたパンク〜ノーウェイヴ系から、現地のディスコを賑わせていた曲、さらには時代を遡った往年の曲まで、なかなか幅広い選曲となっている。これらは、ゴールディンがキャリアを本格始動した時代を取り巻く一つのサウンドトラックとして優れているのはもちろんだが、フィメールパンクバンドの Bush Tetras やリジー・メルシエ・デクルーを筆頭として、クラウス・ノミ、ディヴァインまで、明確にフェミニズムやゲイ、クィアカルチャーを体現する曲が織り交ぜられているという点において、ゴールディン自身の写真とも見事な共鳴を示している。彼女自身が本作の音楽コンサルタントを務めているという事実を知れば、その強い関連性にも得心のいくところだ。加えて、本編でも触れられている通り、当初彼女の写真のスライドショーは、自身が選曲した音楽とともに上映されることが多かったのだという。ベルトルト・ブレヒトの『三文オペラ』に刺激を受けて制作されたという彼女の作品集『The Ballad of Sexual Dependency(性的依存のバラード)』が、当初、The Velvet Undergroundやシャルル・アズナブール、スクリーミン・ジェイ・ホーキンス、ジェームス・ブラウン、ニーナ・シモンらの楽曲とともに上映されたという事実に鑑みれば、まさしく、ここでの選曲もそうした使用例を踏襲したものだといえそうだ。
INDEX
抑制的な音楽使用と、サウンドトラックの効果
その後映画は、ゴールディンの当時の恋人ブライアンによる凄惨な暴力事件の回想を起点に、P.A.I.N.メンバーへの尾行疑惑や、1980年代末のエイズ禍と仲間の死去、ゲイコミュニティに対する差別と薬物中毒患者への偏見、そしてそれらに通底する政治的抑圧の問題、更にはパーデュー・ファーマ社の破産申請の審理(*)の様子など、現在と過去の出来事双方を行き来しながら、にわかにシリアスな方向へと進んでいく。次いで、姉の自死に隠されていた衝撃の事実が語られるまで、その間約60分弱。前半までと打って変わって既存楽曲の使用が一切排されるのだ。
ドキュメンタリー作品において、こうした明示的な音楽の不在による劇的な効果というのはことさらに大きい。狭義の「演出」を排し「現実そのもの」へと観客の意識を向けさせる手法が、本作でも目覚ましい効果をあげており、私達観客は否応なくその緊張の只中に投げ入れられることになる。
*2019年、パーデュー・ファーマ社は破産法の適用を行い、オピオイド訴訟による多額の賠償を回避しようとした。

そして、こうした一連の沈黙を挟んだ上で回帰してくる音楽もまた、同じく劇的な効果を発揮する。姉の死を巡る隠された真実が語られる上述のシーンでは、本編全体のスコアを担当しているサウンドアート集団Soundwalk Collectiveによる音楽が、特に効果的に働いている。サウンドトラック上は“Sisters II”と名付けられているミニマルかつ幻想的な曲に導かれて再度語られる家族の物語は、この映画が、一人の芸術家による勇敢なアクティヴィズムを映し出していると同時に、何よりも、彼女自身のトラウマと、両親よって隠蔽された過ち、秘密の重さ、そして、そこに刻印された偏見(スティグマ)との戦い / 解消こそを主題としていることに気づかせてくれる。同時に、ゴールディンにとってその主題が、かつて自身が陥ったオピオイド中毒と同じように、根源的な恐れと怒りをもってしぶとく回帰する、全身全霊を賭けて立ち向かわなくてはならない傷であることが示唆される。
だからこそ彼女は今、隠匿と秘密、偏見(スティグマ)と戦うのだ。彼女にとって悪とは、社会的な存在でもあり、個人的な存在でもある。この映画は、あまりに直截な意味において、「美と殺戮のすべて」が、彼女の半生に絡み合っていることを明らかにするとともに、私達観客自身へも、自らの生の中でその絡み合いの文様を勇気を持ってなぞってみることを強く促している。