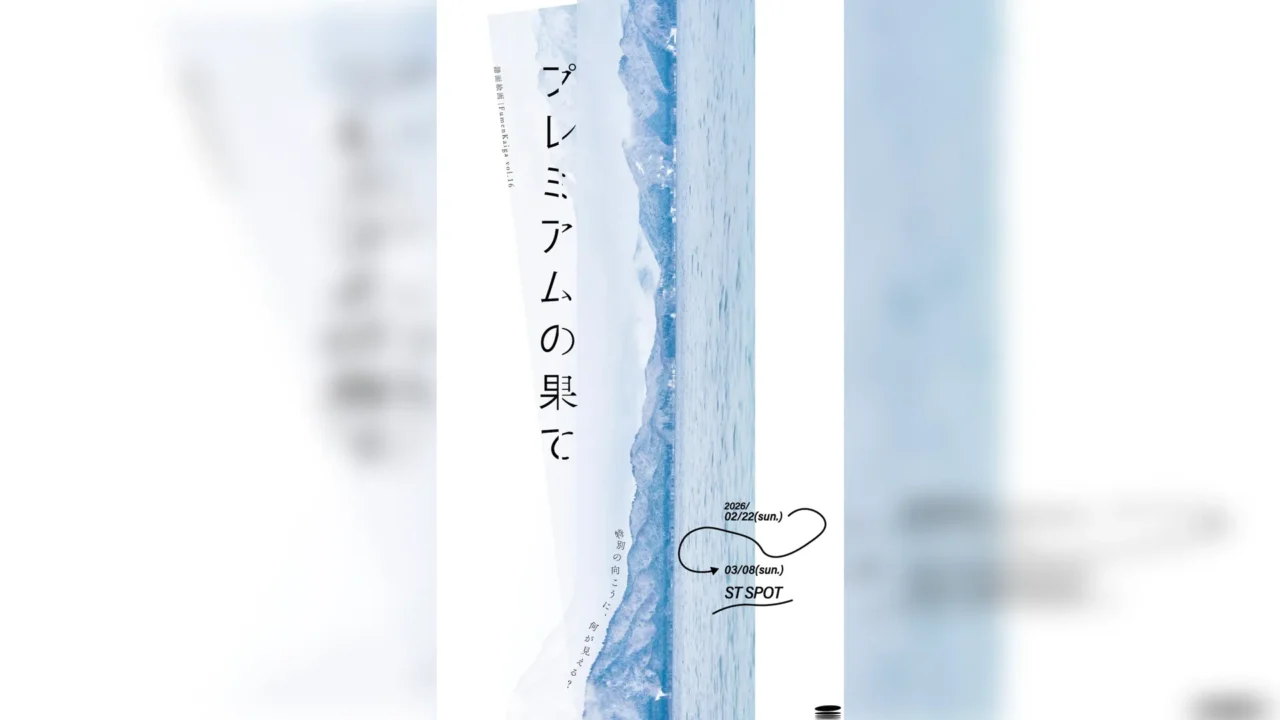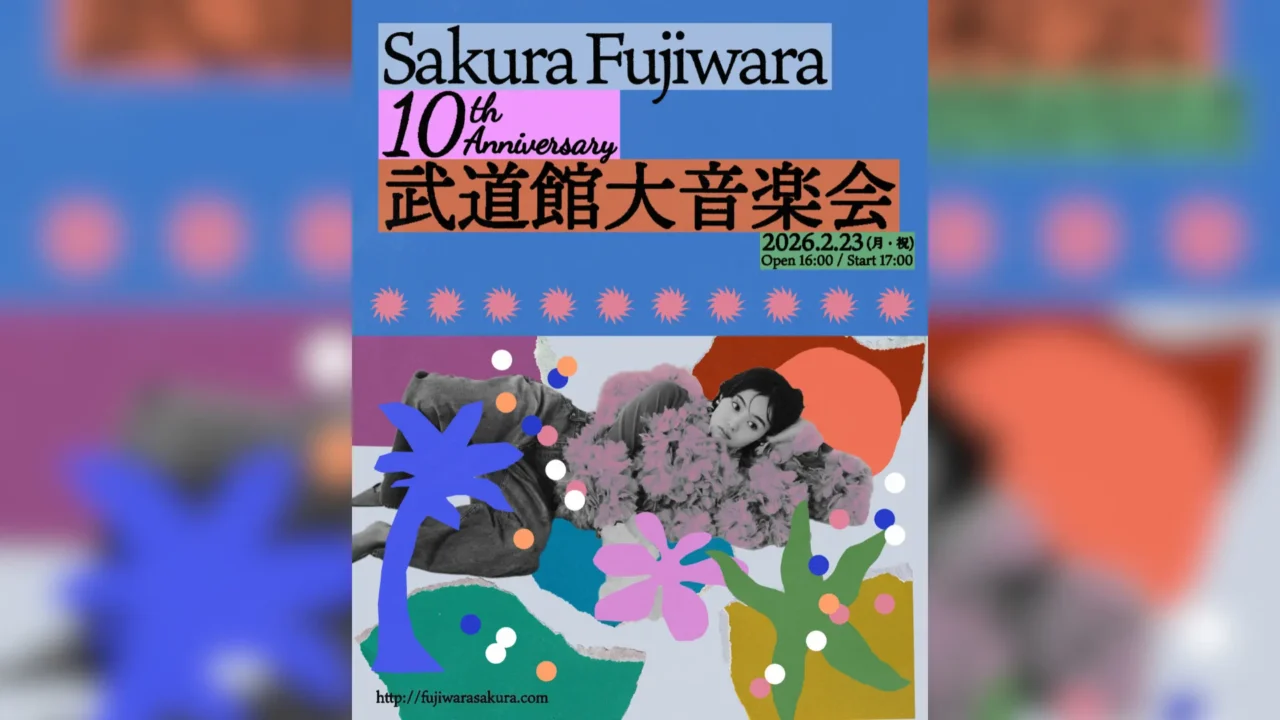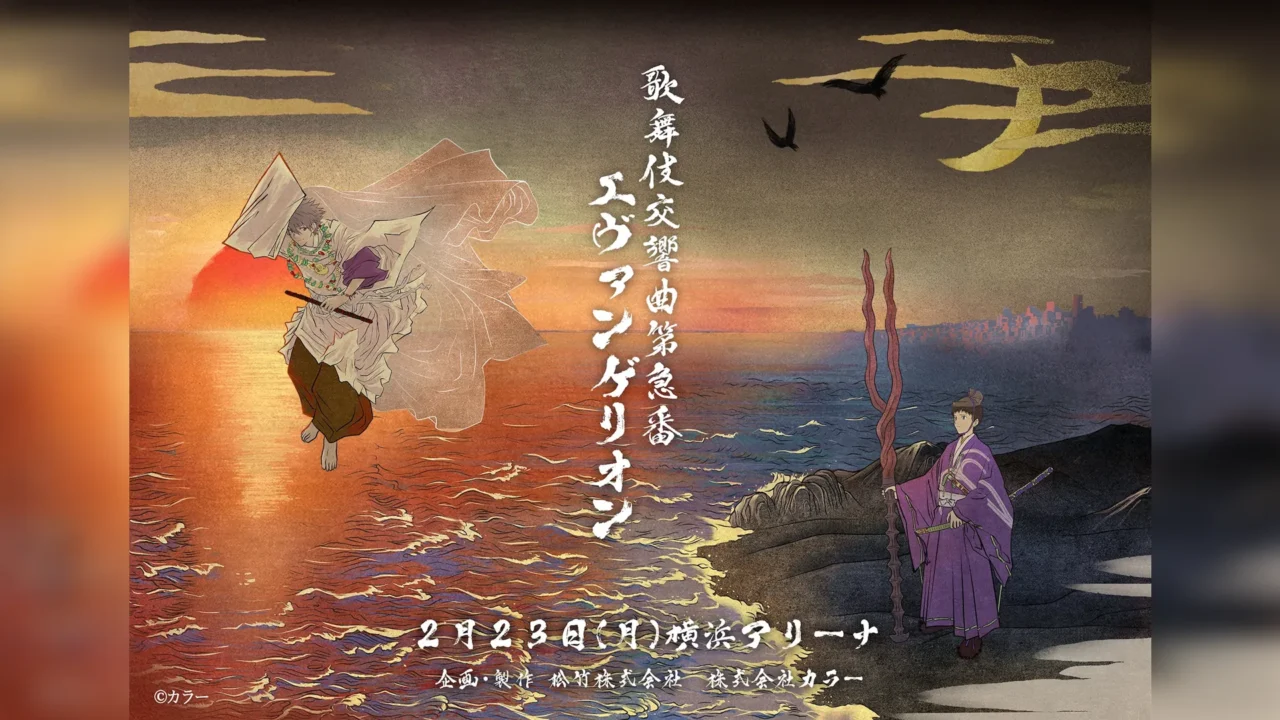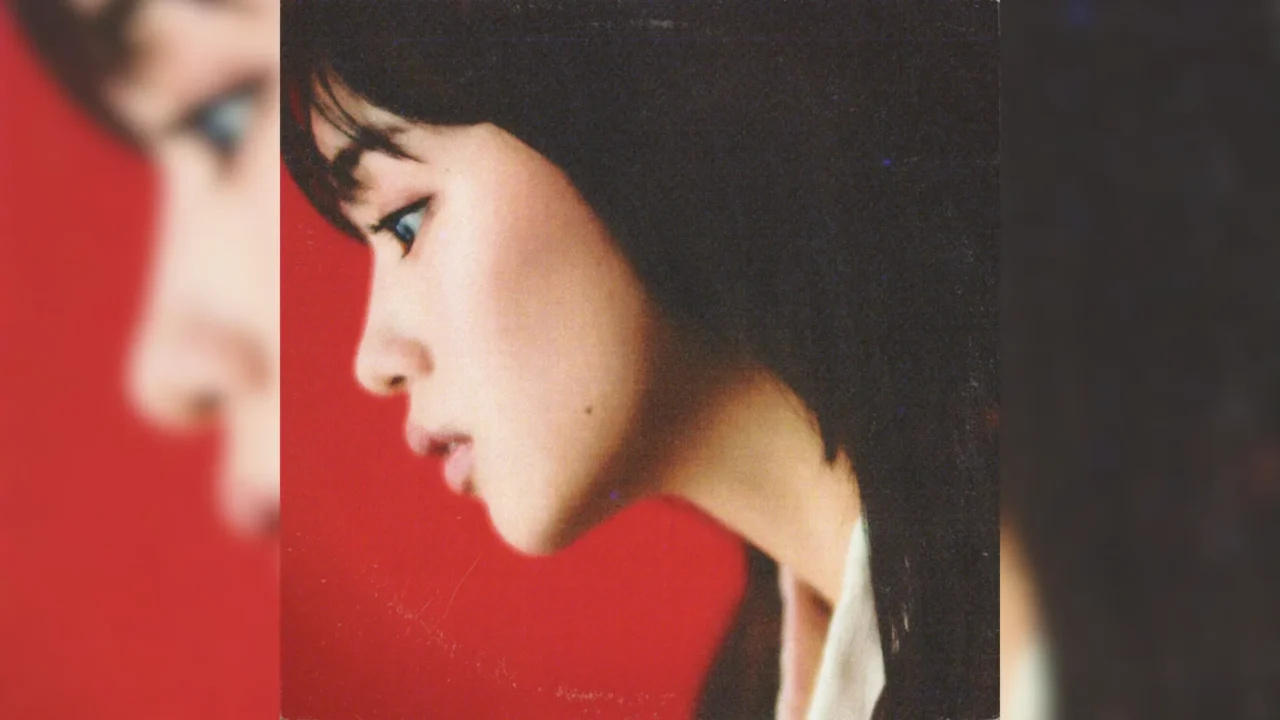INDEX
音楽が想起させる『アトミック・カフェ』と『マーズ・アタック!』
突然だが、『アトミック・カフェ』という映画をご存知だろうか? 核兵器開発競争に邁進する戦後のアメリカで大量に流通したニュース映画やプロパガンダ映像などをコラージュして作り上げられたドキュメンタリー映画で、1982年の公開以来、カルト的な人気を集めてきた傑作だ。
この映画は、音楽の使い方にも皮肉(以上のもの?)が効いている。様々な有名無名歌手がプロパガンダに乗じて原子爆弾を褒めそやす、戦後期に実際にリリースされた楽曲が大量に使われていたのだ。そして、このサントラの中で、ポピュラーボーカルものやゴスペル等に混じって特に目立っているのが、ヒルビリー系の楽曲だった。
『アステロイド・シティ』を観て私が最初に感じたのが、この『アトミック・カフェ』に使用された「愛国的」なヒルビリーソングを聴いたときに覚えた空恐ろしさ……つまり、先に述べたような「一見すると明るく健全だが、その裏に荒涼とした不安感が巣食っている」という感覚だった。
もちろん、アンダーソンおよびポスターは、あからさまに上述のような「原爆ソング」を使用しているわけではないが、わざわざ幕開け曲“Last Train to San Fernando”に被せる形で核ミサイルを登場させたり、本編中にも核実験によるキノコ雲の描写を複数回登場させているところからすると、少なからず『アトミック・カフェ』におけるカントリーソングの強烈な異化作用を意識していたのではないか、と推察してみたくなる。
やや牽強付会が過ぎたかもしれない。しかし、こうしたカントリーミュージックの異化作用というのは、優れた映画作家が少なからず実践してきた手法でもあるのだ。
最も著名な「異様な使い方をされているカントリーソング」といば、ティム・バートン監督作『マーズ・アタック!』(1996年)におけるスリム・ホイットマン“Indian Love Call”(1952年)だろう。甘いヨーデルボイスをトレードマークとする伊達男ホイットマンの代表的レパートリーである同曲をかけると、火星からの侵略者である宇宙人がその曲の特有の周波数のせいで頭を破裂させて息絶えてしまうという、強烈(かつ超重要)な使われ方をしているのだ(余談だが、曲名通り同曲が先住民の伝説をモチーフとしていると捉えると、ここで頭を破裂させる「侵略者」は、かつてのアメリカ大陸への侵略者=ヨーロッパ人たちを差しているとも考えられる!)。
そして、このスリム・ホイットマン版の「インディアン・ラブ・コール」は、本作『アステロイド・シティ』でも、ラジオから流れる曲として使用されているのだった。『マーズ・アタック!』を観たことのある観客なら、この曲の流れるシーンで反射的にあのビザールでおどろおどろしい火星人の姿を思い出してしまうはずだ(アンダーソンが『マーズ・アタック!』を観たことがないとは考えづらいから、これはどうみても確信犯だろう)。

「スキッフル」がもたらす「フェイク感」の巧みさ
加えて気になったのが、いくつかのスキッフル曲の使用だ。先に述べた通り、劇中劇「アステロイド・シティ」の幕開けとして、“Last Train to San Fernando”が流れるのだが、この曲を歌っているジョニー・ダンカンは、(アメリカ生まれではあるが)生粋のブルーグラス系アーティストというより、英国のトラッドジャズシーンに移ってからスキッフルブームの中で成功を収めたミュージシャンだった。
ロックの歴史書めいてしまうので深入りはしないが、「スキッフル」というのは、元をたどるとアメリカにおける特定のアコースティックバンドスタイルを指す用語であったわけだが、1950年代後半のイギリスでロニー・ドネガンが「スキッフルシンガー」としてにわかに人気者になったのを境に、トラッドジャズやフォーク、ジャグバンドミュージック、ブルース、ロックンロール、ヒルビリーなどを複合したアコースティック編成の音楽を総称する用語として定着していった。それゆえに、音楽的な定義にもゆらぎ(ゆるさ?)を伴った、(純粋主義的なアメリカンルーツミュージック愛好家からすると)やや「ニセモノめいた」ものと理解されがちな音楽だったりするのだ(今となっては、そこまで厳密な種別を意識するリスナーは少数だろうが)。
同様のことは、エンドロール(の前半)に流れる、The Chas McDevitt Skiffle Groupとスコットランドのフォーク歌手ナンシー・ウィスキーによる“Freight Train”の、威勢のいいいかにも英国スキッフル的なカバーにもいえるかもしれない(同曲のオリジナルは、黒人フォーク歌手、エリザベス・コットンによる)。

何が言いたいかというと、それなりにヒルビリーやカントリーミュージックを好んで聴いてきた私の耳には、これらの英国産スキッフルソングの使用が、1955年の米南西部という舞台設定と比較した場合、どうしても「フェイク」っぽく聴こえてしまうということだ。誤解してほしくないが、「だからこの映画の音楽の使い方はダメだ」などと狭量な小言を言いたいのではない。むしろ逆で、この「ニセモノ」っぽさこそが、この映画のプロダクションの傾向にうまく合致し、それどころか、冒頭のインタビューでアンダーソンの言っている「化学反応」を生じさせ、結果的にその演出効果を加速させているように思うのだ。
いかにも「本物」らしいけれど、すんでのところでフェイク性が顔をのぞき、いつの間にか我々観客もその蠱惑に騙され、豊かな人工美の世界へと招かれる……。アンダーソンの映画にあるそういう磨き上げられたフェイクのおかしみ、入り組んだリズム、ありえない画面移動、過剰に緻密な画面構成の美しさが、本作におけるどこかいかがわしげな音楽の使い方の魅力にも通じているように感じるのだ(長くなるので詳述はしないが、そういう意味で、「架空のパラダイス」を描くレス・バクスターのエキゾ曲が使われているのにも、合点がいく)。