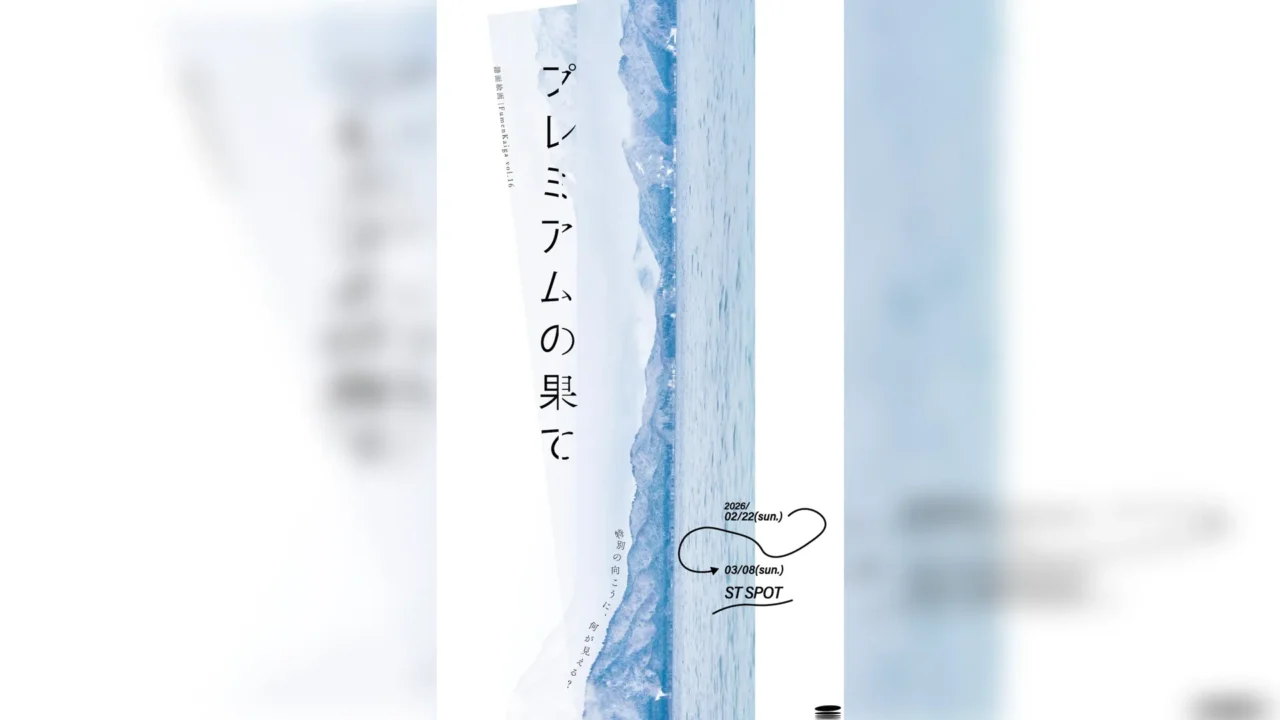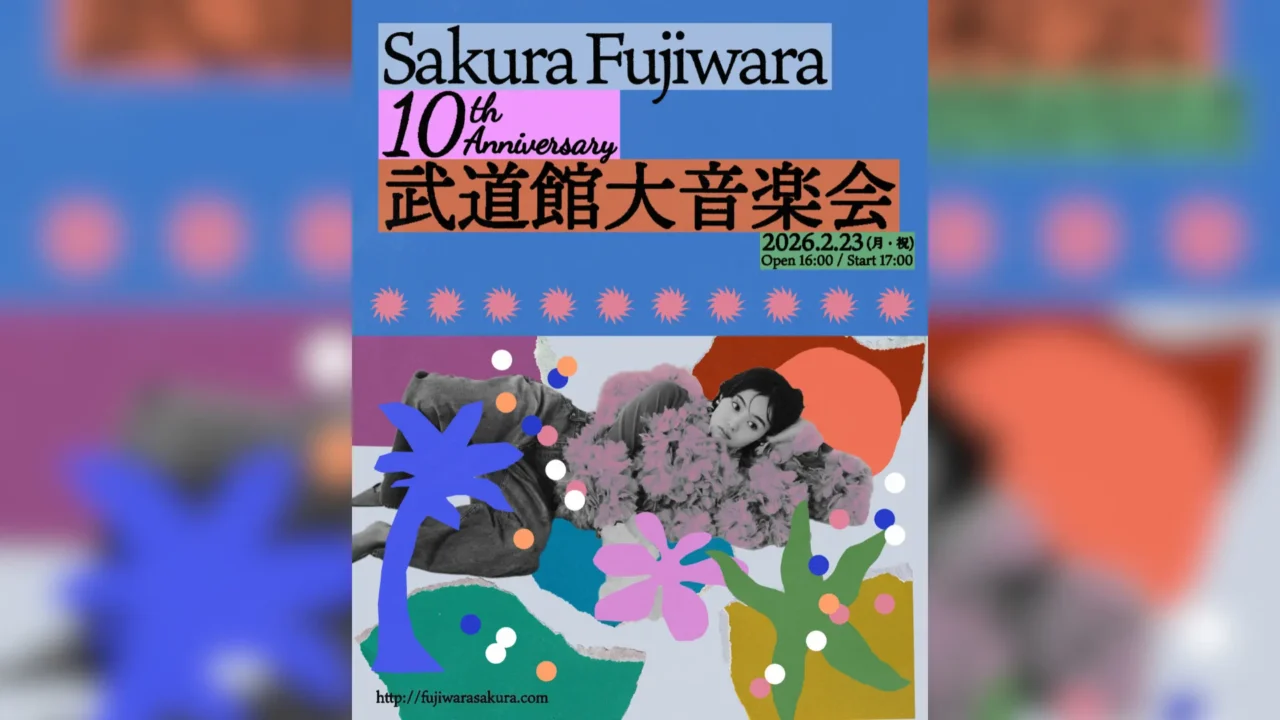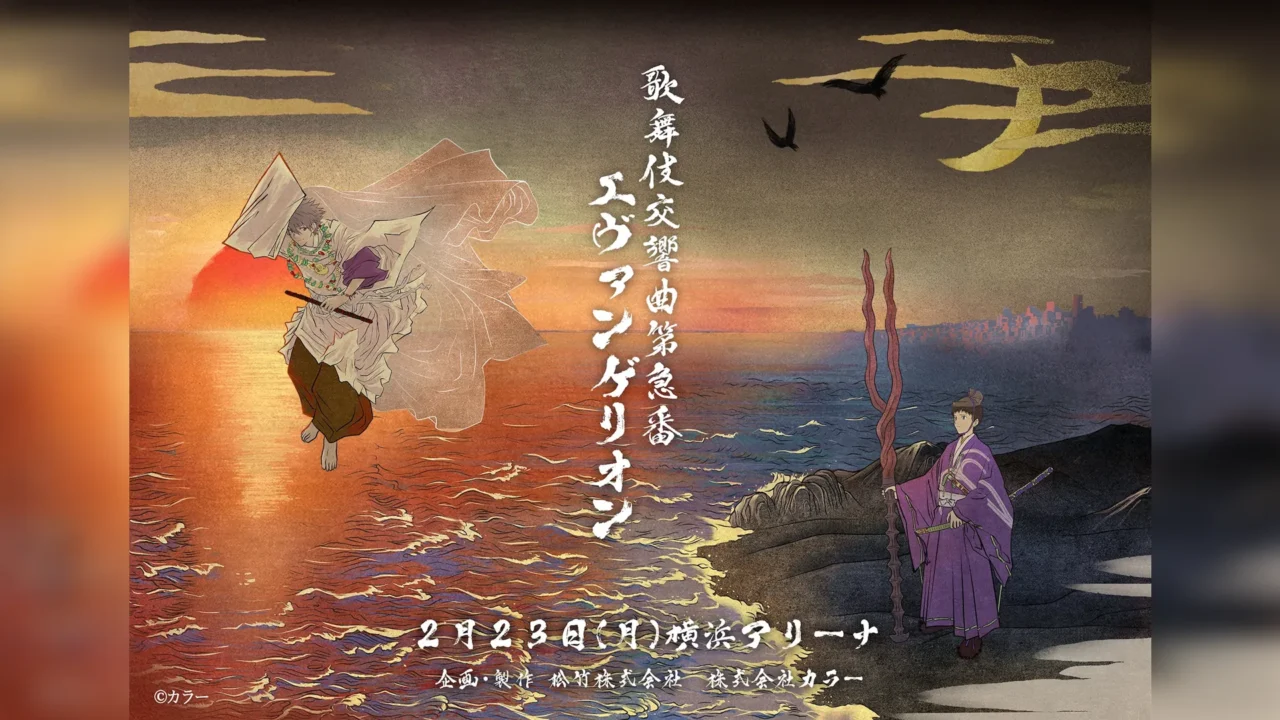先週は『フジロック(FUJI ROCK FESTIVAL)』の土曜日に行き、ROMYのDJとTSHAのライブセットで久しぶりにダンス。ROMYはセットの全体を通して前回のFloor Essenceで紹介した1990年代のトランスをプレイし、エンディングではなんとFerry Corstenの”Out Of The Blue”に彼女の新曲”LoveHer”のボーカルをミックスしたスペシャルバージョンを披露。その瞬間オーディエンスの大歓声があがり、深夜のRED MARQUEEが最高にハッピーなパーティーになった。今回はROMY世代のシーンの状況を俯瞰してみよう。そこから今のダンスビートの背景やクラブシーンの雰囲気を感じてもらえたらと思う。
INDEX
EDM全盛期に新しいビートを模索した先駆者たち
ROMYがThe xxでデビューしたのが2009年、ちょうどEDMが世界的なブームとなり始めたタイミングで、フェス映えする派手なトラックの全盛期だった。多くのDJもクラブからフェスをターゲットにした活動に軸足を移しはじめた。特にアメリカでの反応が良かったことで派手なフェス仕様のトラックが世界的な潮流となり、オーディエンスの動きやステップにも少なからず影響を与えたんだと思う。ダンスというよりは上半身だけで反応する、パーティーというよりもステージを観るフェス仕様のノリが当たり前になっていく。
その一方イギリスではグライムやダブステップを中心にアンダーグラウンドでさまざまなビートの実験が繰り広げられていた。それはクラブのフロアとベッドルームを行き来しながらシリアスで新しいスタイルを産み出そうと多くのDJやアーティストが活発に活動をはじめる、その先駆者がBurialだろう。そして彼に続くようにFour TetやJon Hopkinsが頭角を表し、そんな状況の中からThe xxが登場する。必ずしもフロアにフォーカスしていなくても彼らは確実にダンスシーンのDNAを受け継いでおり、その世代が今のUKダンスシーンをフロントラインで牽引している。また例えばダウンテンポ、レフトフィールドから出てきたBonoboがフロアでも熱狂的に受け入れられているのは今のシーンがビートやテンポの縛りからも自由になってきている証でもあるだろう。
INDEX
Bicep(バイセップ)はここ数年のダンスシーンにとって最大のゲームチェンジャー
中でも注目なのが、北アイルランド・ベルファスト出身のBicepだ。まずこの映像をみてほしい。
これは彼らが出演した去年の『グラントンベリー(Glastonbury Festival)』の映像だが、数千人のオーディエンスがこのハウスというには遅いビートに熱狂しているのがわかるだろうか? Bicepの音楽は1990年代後半から2000年代前半に世界中を席巻したシリアスでエモーショナルなトランスの雰囲気をそのままにベースラインを抜いて、テンポを落としたサウンドなのだ。一体誰がこんなスタイルのダンスミュージックを想像しただろう。彼らの心に切り込むようなエモーショナルなシンセのリフはシンプルだが、パーティーの大音量で聴かされたら狂わずにはいられない。あるレビューで彼らの音楽はここ数年のダンスシーンにとって最大のゲームチェンジャーだと書かれていたが、本当にそうだと思う。1990年代のフロアに熱狂生み出したトランスとまったく同じメッセージをまるで別の形で伝えてくる、彼らもこの10年のUKダンスシーンの層の厚さと絶え間ない実験が生み出した成果と言っていいだろう。Bicepは去年からアリーナでのツアーを続けていて、世界中を熱狂させている。今年の4月にはゲストにROMYが出演した日もあった。DJセットでいいので来日してくれないだろうか。
INDEX
今一番の注目はFred Again..(フレッド・アゲイン)
そして今一番注目なのは、9月にリリースされるROMYのアルバムのプロデューサー・Fred Again..だ。既発のシングル”Lifetime”や”Strong”で彼のプロデュースワークをもう聴くこともできる。
Fred Again..はBrian Enoのアシスタントとしてキャリアをスタート、George Ezra(ジョージ・エズラ)やRita Ora(リタ・オラ)のプロデュースで大きな成功を収めたことで注目された。僕自身もROMYとHAAiをフューチャーしたシングル”LightS Out”で彼の名前を知って、すぐに彼のアルバム『Actual Life 2』をチェックした。
このアルバムはパンデミックの間に彼が日常の出来事や聴いた音楽などを日記的に曲にするというコンセプトで作られている。その中にElectribe 101のシンガーだったBillie Ray Martinのヒット曲である”Your Loving Arms”が”Billie”というタイトルで収録されていた。このアルバムはダンスビートを基軸にした彼独特のポップミュージックだが、深い作りになっている。そして”Billie”のように随所に1990年代のフレイバーが散りばめられている。彼はポップなフィールドからダンスにアプローチしていて、その背景にはBrian Enoが注目したのも頷ける音楽的な素養が見える。この映像を見てもらえれば納得できるだろう。
2月にはFred Again..とFour TetとSkrillexが3人でニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンをソールドアウトさせている。このパーティーが今のシーンの健全さと面白さを象徴しているだろう。
アンダーグラウンドとポップとトップが混ざりあってのBack To Back、会場のとんでもない熱狂がいくつもYoutubeに上がっているので気になった方はぜひチェックしてほしい。Fred Again..は1万人を収容するロンドンのアレキサンドラ・パレスを4公演完売して現在もワールドツアーを続けている。
INDEX
シーン注目の若手、Ninja Tuneの3組を紹介。TSHA、Jayda G、Barry Can’t Swim
そして最後にシーン注目の若手をいくつか紹介しよう。昨年秋にリリースされたTSHAのデビューアルバム『Capricorn Sun』は極上のハウスアルバムだった。
基本ハウスだが、時折入ってくるレイヴなビートや1990年代の名曲のリフが印象的。『フジロック』でのライブではドラマーとギタリストと共に彼女はベースを演奏し、アルバムでも何曲か歌っているレクシーというシンガーが数曲でボーカルをとった。TSHAはまさに新世代のアーティストだが、やはり1990年代以降のダンスシーンのエッセンスを強く感じさせる。
そしてTSHAと同じNinja Tune(ニンジャ・チューン)から先日アルバムをリリースしたJayda G、彼女もハウスとポップを自由に行き来するアーティストだ。アルバムからのシングル”Scars”がまさに今ヒットしている。
もうひとりNinja Tuneから紹介しよう。Barry Can’t Swimはスコットランド出身のDJで、ジャズやソウルを感じさせるハウスで頭角を表してきた。彼もカテゴリーにとらわれない自由な作風が特徴で新世代のハウスDJと言っていいだろう。
10月にはデビューアルバムのリリースも控え、現在積極的にツアーを行なっている。せっかく同じレーベル、同じフィールドで注目の若手が3組そろっているのだから日本でショーケースをやってくれないだろうか。
次回はイギリスを離れてユーモアで繋がるドイツ、フランス、アメリカのダンスアクトを紹介したいと思います。それではみなさん夏を楽しんでください!