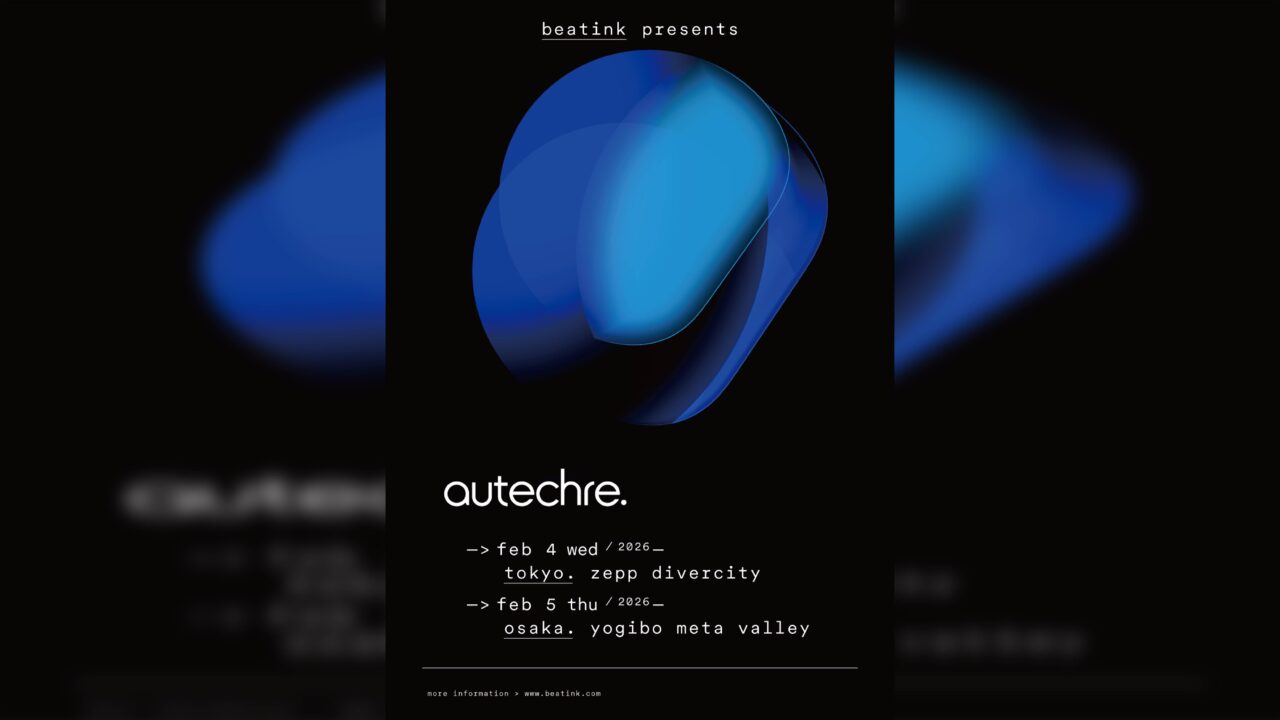昨年大きな反響を呼んだ、FRISKが新たなチャレンジを始める社会人や学生たちを応援するプロジェクト「#あの頃のジブンに届けたいコトバ」の一環として、今年もJ-WAVEの番組『GRAND MARQUEE』とのコラボレーションコーナー「FRISK DEAR ME」が実現。
初日に登場したのは、MONO NO AWAREのギターボーカル・玉置周啓。周囲から助けてもらうことに居心地の悪さを感じていた20歳の自分に向けた手紙をもとにしながら、バンドを続ける上でわかってきた人を頼ることの重要性や、スースーした人間関係の心地良さなどについて話を聞いた。
INDEX
人付き合いへの恐怖心を早い段階で無くした方が、人生は楽しい
タカノ(MC):今回は玉置さんに、あの頃のジブンへ向けた手紙を書いていただきました。手紙の宛先は?
玉置:くすぶっていた20歳の私です。
タカノ:手紙は「愛されたい。でも、必要以上に愛されると返すのが面倒くさい」と歌詞のような書き出しで始まります。MONO NO AWAREの結成は玉置さんが20歳の頃とのことですが、当時はどのような状況だったんですか。
愛されたい。でも必要以上に愛されると返すのが面倒くさい。ベタつきたくない。自立したい。
嫉妬を隠したい、影響を受けすぎたくない、反発をモチベーションに生きたくない。
だったら、人間関係スースーさせよう。
手紙の序文。玉置周啓(MONO NO AWARE)直筆の手紙全文は4月10日(木)から下北沢BONUS TRACKで開催されるFRISK『あの頃のジブンに届けたいコトバ展』で展示される(詳細はこちら)
玉置:人に話しかけるのが怖くて、バンドメンバーを集めたいのに誘うのもままならない状態でしたね。大学にも行ったり行けなかったりするような、そんな生活の中で、成順(加藤成順・Gt)が見るに見かねて「メンバーが見つからないんだったら、俺とバンドをやろう」と誘ってくれたんです。
この頃は自意識も強かったし、お世話されるというか、返さなきゃいけない恩をいただいている状態に対して、居心地の悪さを感じていて。でも、誰かがお世話するような形で僕らと関わってくれたおかげで、ここまでバンドが続いてきた。30歳を超えて、そうやってバンドと関わってくれる人がいることのありがたさを実感していますね。

東京都八丈島出身の玉置周啓と加藤成順は、大学で竹田綾子、柳澤豊に出会った。その結果、ポップの土俵にいながらも、多彩なバックグラウンド匂わすサウンド、期待を裏切るメロディライン、言葉遊びに長けた歌詞で、ジャンルや国内外の枠に囚われない自由な音を奏でるのだった。FUJI ROCK FESTIVAL’16 “ROOKIEA GO-GO”から、翌年の投票でメインステージに出演。数々の国内フェスに出演するなど次世代バンドとして注目を集める。2024年6月にはニューアルバム『ザ・ビュッフェ』を引っ提げて、約3年ぶりの全国ツアー「アラカルトツアー」を開催した。
タカノ:当時の心情を綴った書き出しだと。その後「べたつきたくない」というフレーズがあったり、「人間関係スースーさせよう」とも書かれていて、これ名コピーですよね。
玉置:そこを最初に思いついて(笑)。そういう話しかけられ方をしないと、多分当時の自分は心が動かなかっただろうなと思って。
タカノ:「人間関係スースーさせよう」っていうのは、どういうニュアンスなんですか?
玉置:「必要以上に愛されたくない」とか、「誰かに話しかけたり何かに誘ったりすることへのためらい」みたいな、人付き合いへの恐怖心や照れくささを早い段階で無くした方が、人生は楽しいと思うんです。
タカノ:もう少しカラっとした人付き合いをしていく。
玉置:そう。もちろん、傷つけたり、傷つけられたりする危険性は高まるけれど、ウジウジしているよりもスピード感があって良いよなって。20歳の頃はこんなことを思えなかったからこそ、タイムマシンがあるなら早い時期にこの言葉を届けたい。「ウジウジしている時間は楽しくなくない?」みたいな。歴史上、誰もが言ってきたことではあるんですけどね。
タカノ:まさしく「スースーしようぜ」と。
玉置:僕は自分に対する自信の無さよりも、人とどう関わるかが大きかったから。なので、それを伝えたいなって。
INDEX
「人に頼る」こと、「人に感謝する」ことの大切さ
Celeina(MC):そこから「自分は自分で良い」と確信を持てるようになったのはいつだったのでしょう。
玉置:このお仕事を貰ったタイミングですかね。
Celeina:え⁉ このコーナーでですか? 嬉しいです(笑)。
玉置:これ、本当の話で(笑)。こういうことがないと、20歳の自分のことなんてなかなか考えないので、良い機会になりました。「人間関係スースーさせよう」とかは、友達と「なんて言葉をかけるよ?」「適当なことは言えないぞ」と相談しながら考えたりもしていて、その過程も楽しかったんですよね。
タカノ:まさにご友人を「頼った」ことで生まれた文でもある。
玉置:確かに! 僕は人を頼ることができなかったんですよ。事実上では頼っているのに。
Celeina:人を頼ってるのを認めたくない、これは頼ってるわけじゃない、みたいな。
玉置:そうなんですよ。だから人に相談しないまま物事を進めて、崩壊寸前で誰かが助けてくれることも何度もあった。それって結局、人を頼っていることと同じじゃないですか。でも、最近になって、ようやく自発的に人を頼ることができるようになった気がします。

タカノ:玉置さんが人を頼ってみようと思えたきっかけは何だったんですか。
玉置:大きなきっかけがあったわけではなく、バンドメンバーやマネージャーさん、事務所の方とコミュニケーションを取るうちに、周囲の人たちが動いてくれていることで自分たちの音楽が聴いてもらえることに気づいたんです。その気づきを得たことで自然と、頼る意味や頼られる意味がわかってきた。その過程は茨の道でしたけど。
タカノ:そう考えると、バンドって良いですよね。皆やっておくべき、みたいな部分があるかも。
Celeina:なるほどね。人間関係の学びを得ることができるから。
玉置:確かに。バンドにはその側面があると思います。メンバー間の、仕事なのか友達なのかも曖昧な状態の危うさを抱えた上で、やりたいことをやりながらお金をいただくのがバンドなので。必然的に人に感謝できる人じゃないと、生き残れない気もするし。そういった考えもないまぜになって、今回こういった手紙を書けましたね。
Celeina:バンドに限らず、会社の中のチームとか、仲良かった学校の仲間たちだって当てはまりますよね、「人を頼ろう」っていう意味では。まさにサードプレイス。欲しいよね。
玉置:大人になってもそういう場所があるといいし、サードプレイスは必ずあるけど、用意されているものではなく、頼る行為から始まるのかもしれない。