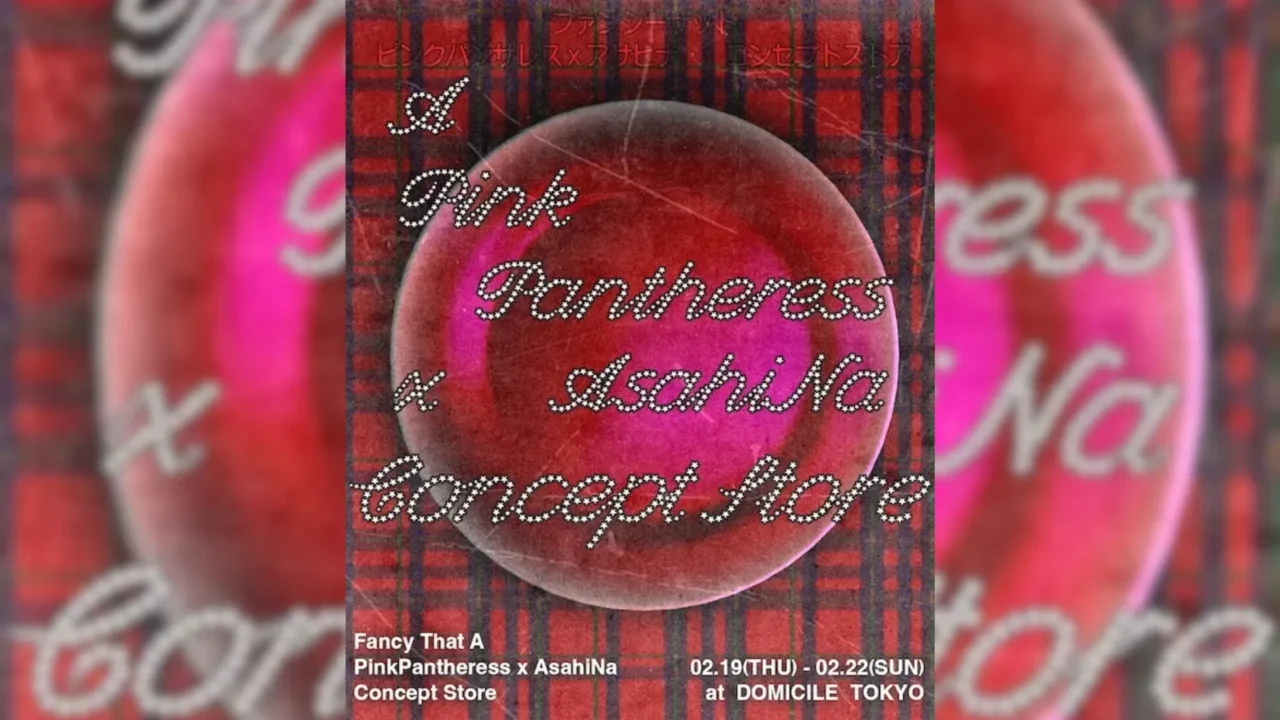INDEX
「当事者が演じるべきでは?」という批判の声
何故、これが懸念されるような事態になるというのか。それは、俳優がマイノリティを演じる場合、近年「当事者が演じること」が、複数の観点から重要なことだとされるようになってきているからだ。
もちろん、そもそも俳優という存在は、自分とは特徴の異なる、あらゆる役柄を演じる職業であることは確かなことだ。日本においても、歌舞伎の「女形」や、宝塚歌劇の「男役」など、俳優の自認する性別とは異なる役柄を演じるという枠組みが伝統的に存在し、映画やドラマでも、役柄の特徴を持たない俳優が、さまざまな役を務めてきたのも事実である。しかし性的マイノリティなど、さまざまな社会的少数者の役柄が、映像作品や舞台作品に導入されることが、以前と比較して増えてきた流れのなかで、この当事者問題が近年とくに持ち上がってきている。

当事者でない俳優が、その役を演じることで発生するのが、第一に雇用問題だと考えられている。例えばハリウッドでは、これまで長年、性的マイノリティや人種、障害などを持つマイノリティの役を、マジョリティが演じることが多かった。通常、マイノリティ当事者が活躍できる分野は、マジョリティの俳優のアドバイザーなどに限られてきたのである。もちろん、裏方の仕事も重要ではある。しかし、表舞台にマイノリティが出る機会が少ないという事実は、職業の機会を社会や業界が奪っていると見なされる場合がある。
逆にマイノリティーーとくにカミングアウトを経た性的マイノリティがマジョリティを演じるケースの少なさを考えれば、その不公平さは浮き彫りになるのではないか。役者はあらゆるものを演じる仕事ではあるが、そういった「芸術性」を言い訳にして、マイノリティが排除されてきた状況があることも、また事実だ。
それ以外にも、当事者が演じることで、マジョリティには想像できない領域のリアリティある表現が達成されたり、当事者が活躍することが、同じ特徴を持つ人たちに希望を与え、社会にはびこる偏見を改善する機会になることもある。これらの理由から、現在の不平等な社会状況のなかでは、できる限り「当事者が演じる」ことが望まれているという考えが浸透してきているのである。
例えば、イギリスの俳優ベネディクト・カンバーバッチは、『イミテーション・ゲーム/エニグマと数学者の秘密』(2014年)においてゲイ男性の役柄を演じたことをきっかけに、ゲイの権利のための社会運動に参加することとなった。しかし、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021年)で再びゲイ男性を演じた際には、彼は当事者性の問題から一部で批判にさらされ、インタビューで釈明することにもなったのだ。これは、およそ7年の間に、マイノリティについての考えが業界内や社会で一歩進んだことを意味しているだろう。

このような経緯を知れば、『イカゲーム』シーズン2において、パク・ソンフンがトランスジェンダーの役柄を演じたことに批判が集まっている状況を理解することもできる。パク・ソンフン自身がトランスジェンダーでない場合、製作者、および俳優の社会的な意識が足りてないとする指摘は、的を射ていると考えられる。
また、性的マイノリティの表象を用いて娯楽化することで、人間の属性、特徴を搾取しているのではないかという、懸念や指摘がなされることもある。例えば、作中でゲイではない男性同士による恋愛関係のように見える描写が、俳優のファンに好まれる場合があるが、これは「クィアベイティング」だと指摘され、批判を受ける場合がある。同性愛の仄めかしを利用することで、同性愛を期待する受け手の興味を惹きながら、同時にそれを確定させないことで、同性愛を嫌悪する受け手の心象を悪化させないという手法である。このような試みは、性的指向を都合よく利用する「道具化」と見なされかねない。
登場人物が性的マイノリティであることを明示している作品は、基本的にはその限りではない。しかし、当事者でない俳優が性的マイノリティを演じるという場合、その構図もまた、一種の「クィアベイティング」にあたる可能性が出てくる。美形俳優、人気俳優に性的マイノリティを演じさせることで、ファンの興味を煽り、当事者とは関係のないところで、性的指向を搾取してしまうという考え方だ。