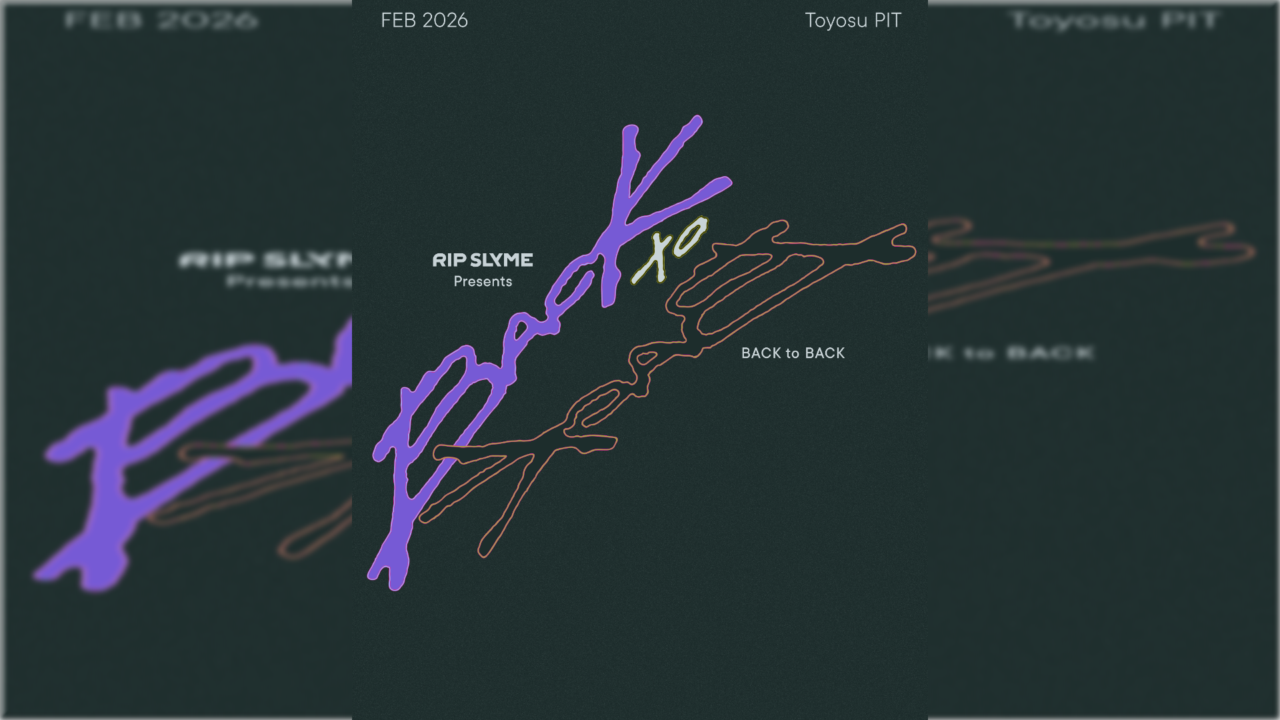近年、アメコミ原作映画が席巻してきたハリウッドで、それに迫らんとする勢いでゲーム原作映画が台頭してきている。日本に先駆けて世界的大ヒットとなっている『マインクラフト/ザ・ムービー』は、言語や世代、文化を超えて広がるゲーム原作映画の力を証明しつつある。日本でも『8番出口』など、次々に控えるゲーム原作映画だが、その潮流は今後どこへ向かうのか。映画評論家の小野寺系が解説する。
INDEX
アメコミからゲームへ。転換期を迎えるエンタメの潮流
エンターテインメントをグローバルに牽引してきた、アメリカの大作映画。ここ10数年間でその主流となってきたのは、アメリカンコミック・ヒーローのユニバース化シリーズだといえる。そんな潮流が近年、変化のときを迎えようとしている。日本でも公開が始まった、世界的な人気ゲームを原作とした映画『マインクラフト/ザ・ムービー』の大ヒットは、そんな転換の潮流に拍車をかける1作となりそうだ。
プレイヤーが世界の姿を変えていけるサンドボックス型オープンワールドゲーム『マインクラフト』は、世界売上3億本を突破し、「世界で最も売れたゲーム作品」としてギネス世界記録に認定されたメガヒットゲームだ。その初の映画版となった『マインクラフト/ザ・ムービー』は、若年層やファミリー層を中心に、強い訴求力を発揮。ジャック・ブラック、ジェイソン・モモア、エマ・マイヤーズなどの人気俳優の出演や、若者を中心としたSNSなどでのバイラル効果もあって、わずか2週間で約7億ドルの興行収入を獲得。先に大ヒットを果たした『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023年)とともに、大きな記録を積み上げている。
INDEX
言語や世代を超えて広がるゲーム原作映画の可能性
『マインクラフト/ザ・ムービー』の驚異的なスタートダッシュには、さまざまな理由がある。その一つが、CGなど技術革新によって、ゲームの世界を魅力的に映像化できるようになったこと。そして、新たな世代へのアピールだ。Netflixをはじめとする配信事業やYouTubeなどの動画配信によって、従来の映画産業や映画館が厳しい状況にあるなか、『マインクラフト』のような大ヒットゲームを題材にしたことが、これまで映画館に足を運んでこなかった層の流入を実現したのだ。

それを象徴するのが、若者たちの劇場内での盛り上がりだ。劇中の「あるシーン」において、ゲームのユーザー同士に理解できる存在が登場したことで、そのシーン自体が、『天空の城ラピュタ』(1986年)のTV放映で「バルス」シーンがSNSでミーム(ネタ)化したように、イベントとしての意味を持ったのである。アメリカの一部劇場では、該当シーンで大きな歓声をあげたり、ポップコーンを投げるなどのマナー違反も横行し、出演者のジャック・ブラックが注意喚起するなどの事態に発展している。もちろん問題含みではあるが、それは新しい層を「掘り当てた」証拠でもある。日本でも、HIKAKIN、ドズル社のような、ゲーム実況をおこなうYouTuberを、日本語吹き替え版の声優に起用することで、若年層獲得を強化している。

さらにゲーム作品は、「ノンバーバル(言語不要)」で楽しめる面があったり、地域性や固有の文化を限定しない特徴が挙げられ、国際市場での強みを持っている。中国をはじめとしたアジアで映画の消費が高まっている現状を考えると、ゲームを題材とした映画は、より大きなヒットを見込める宝の山だという見方もある。新しい年齢層だけでなく、地域性、文化を乗り越える面で、優秀なジャンルだといえるのだ。