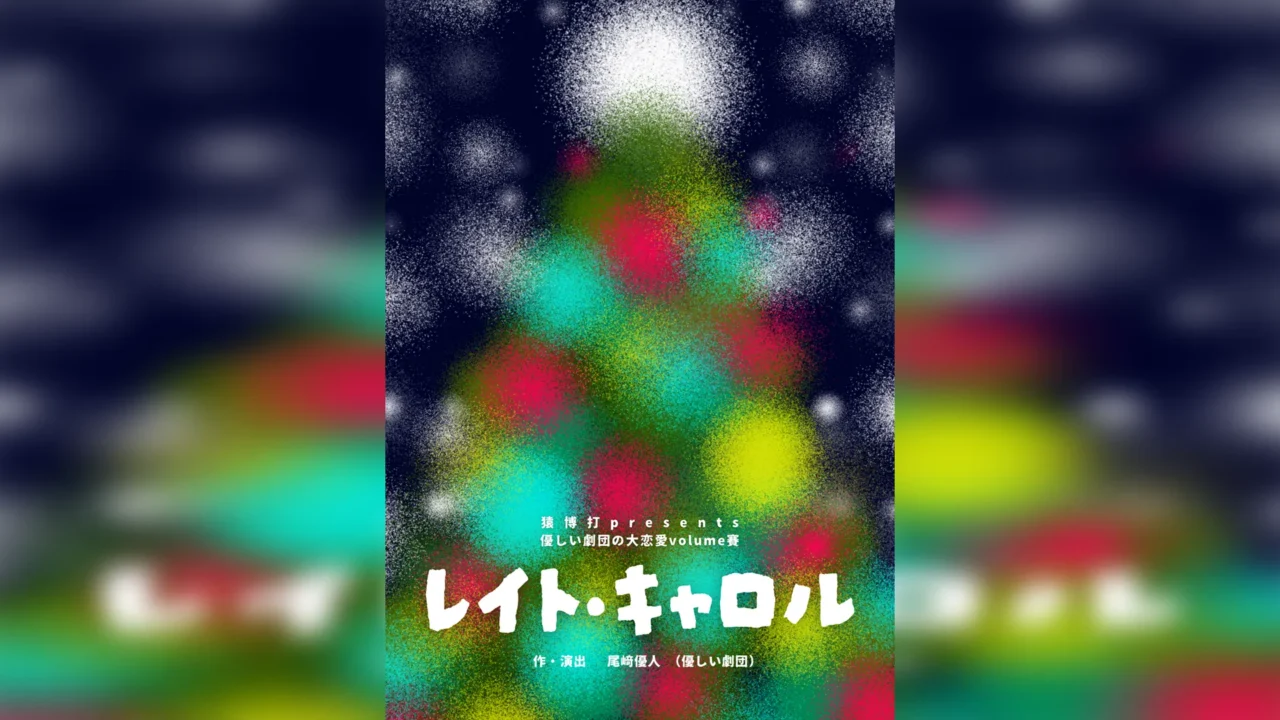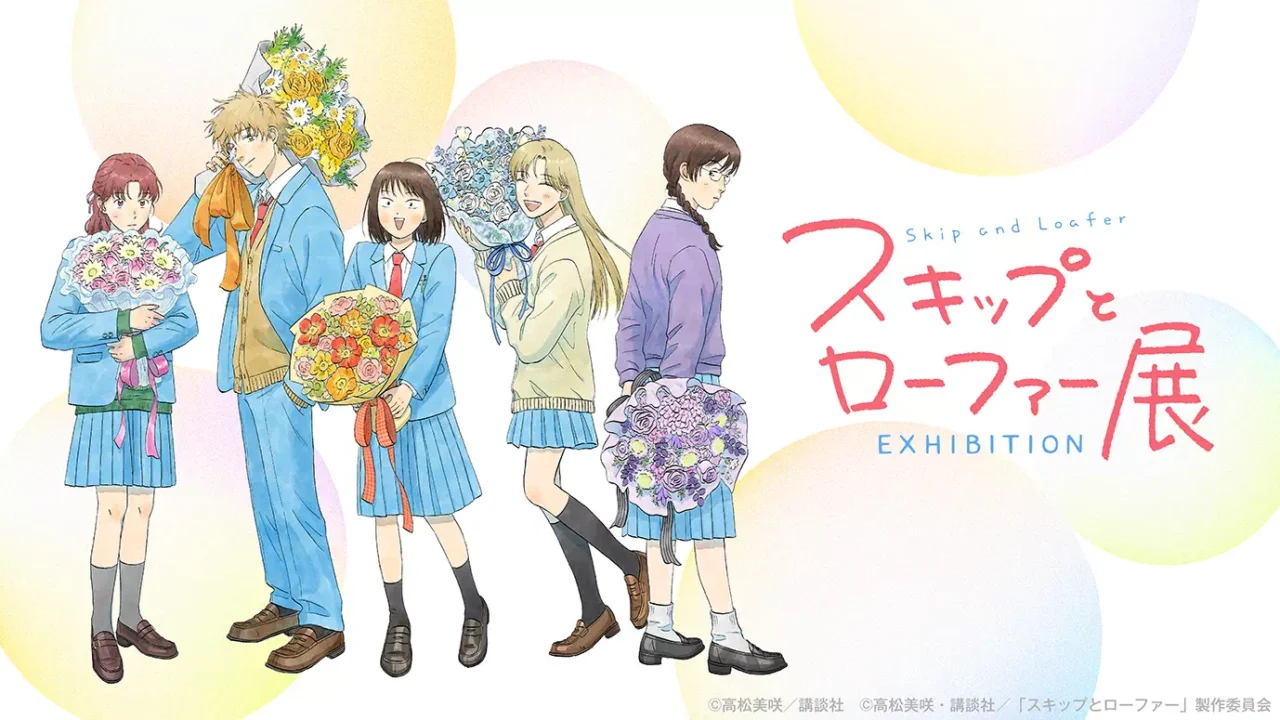2005年公開の映画『リンダ リンダ リンダ』。ペ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、関根史織(Base Ball Bear)ら俳優陣の演技と存在感、ジェイムス・イハによる劇伴音楽、また、湯川潮音による劇中歌の歌声も話題となり、今なお「青春映画の金字塔」と呼ばれる同作は、山下敦弘監督の名前を映画ファン以外にも知らしめ、その評価を揺るぎないものにした。
20年の時を経て、『リンダ リンダ リンダ 4K』が2025年8月22日(金)より劇場公開される。本作に強い思い入れを持つという映画批評家 / ライターの相田冬二に、その魅力をあらためて語ってもらった。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
INDEX
『リンダ リンダ リンダ』の「普通」という美徳
昨年『カラオケ行こ!』が大ヒットした山下敦弘監督の代表作の1本『リンダ リンダ リンダ』が4K版となって公開される。
製作から20年が過ぎた名作は、果たして今も輝いているだろうか。それとも時代の推移と共に経年を感じさせるものになっているのだろうか。つまり、風格か、風化か。
否。どちらも否である。
青春映画として語られがちな本作だが、そもそもキラキラした青春群像などではない。
最後の文化祭。バンドが空中分解し、残された3人の女子高生は、顔見知り程度の韓国人留学生に声をかけ、THE BLUE HEARTSの名曲“リンダ リンダ”のコピー演奏に挑むーー
あらすじを書けば、さぞ熱い物語が繰り広げられると想像するだろう。メンバーたちが激しくぶつかり合い、ライバルとの睨みあいがあり、邪魔が入ったり、苦難があったり、そういう諸々を乗り越えて、感動のクライマックスと涙のラストが待っている……というようなハイテンションの映画ではないのだ。
カタルシスはあるにはあるが、いわゆる能天気な高揚感ではない。エモいと言えばエモいが、独特のエモさであり、ど真ん中ど直球のエモーションではない。かと言って、クールなわけでも、脱力しているわけでもない。あるいは、アメリカ映画によくある、キュートでお気楽な(でもちょっとダウナーな)インディーズバンド映画とも全然違う。もっと、普通なのだ。いや、普通すぎるくらい普通であることが、映画『リンダ リンダ リンダ』最大のオリジナリティであり、最良の美徳なのである。

INDEX
劇的なドラマはあらかじめ終わっている
そもそも、劇性は排されている。というか、「あらかじめ終わっている」のだ。
ことの成り行きは(あえて)明瞭に説明されてはいないが、どうやら5人組であったらしい女子高生バンドは、ギタリストが骨折し弾けなくなり、ボーカルはキレてケンカ別れし、離脱した。このふたりは序盤に登場し、主人公たちと接触もするのだが、そこは全くドラマティックに描かれない。軽くかすった程度。ギターの女の子はすまなそうに退場し、ボーカルの女の子は一触即発のスリルを期待させるものの結局、何事もなかったように物語から退く。
これはどういうことか。すべて「事後」なのである。ボーカルの女の子が抜けるというのは相当なことで、たぶんかなり激しい諍いがあったと想像できる。普通の素人バンドなら、ボーカルが抜けたら解散だろう。しかし残った3人は、オリジナルは無理でも、コピーならやれる、やりたい、やるべきだ、という感じで、予定通り、文化祭への出場から降りない。

このあたり、映画ではっきりは描写されない「エピソード0」がおそらく最も感情の上がり下がりが劇的なはずだが、そういうことは一旦すべて「あらかじめ終わっている」体で『リンダ リンダ リンダ』は始まる。そう、台風一過なのだ。いや、晴れ晴れしているわけではないが、大変な嵐は過ぎ去ってしまった後の「日常」が見つめられている。ここがユニークな点だ。
ギタリスト不在のため、キーボードがギターを弾くことになる。ギター、ベース、ドラムスで3ピース。3人のうちの誰かが歌えばバンドはバンドとして成立するが、誰も歌いたくはない。去ってしまったボーカルの不在が浮き彫りになるから気が進まないのだろう。

INDEX
表情をあえて撮らない演出
仕方なくギターを弾くことになったキーボーディストは、ほとんど思いつきに近いノリで、韓国人留学生に「歌わない?」(というより「歌うよね?」)と呼びかける。おそろしく遠い場所から声をかけるから、韓国人留学生の反応は細かくは見えない。カメラも寄らない。遠くから見ている(この感覚が映画の通奏低音となる)。
韓国人留学生は、日本語が上手く聞き取れなかったのか、それとも楽天的なのか、とにかく安請け合いしてしまう。で、いざ、THE BLUE HEARTSの代表曲“リンダ リンダ”を聴かせると感極まる。しかし、映画はその顔を見せない。このシチュエーションがとんでもなく素晴らしい。
誰もがその顔を見たいと思うだろう。韓国人の女の子がTHE BLUE HEARTSのあの歌を聴いて泣いた。そこから熱い青春ストーリーが始まる。そう信じて疑わないだろう。違うのだ。彼女の泣き顔に『リンダ リンダ リンダ』はカメラを向けない。ヘッドフォンをしている女の子の後ろ頭を映すだけ。そこに心配そうに(でも平常心で)駆け寄る3人の女の子たちの姿を遠くから見ている。盛り上げたりはしない。

このシークエンスは、今見てもハッとさせられる。わたしたち観客は、人物の「顔」を想像することができるという発見がある。というか、映画とは本来そういうものでもあるのだと気づかされる。誰かの泣き顔を見て、もらい泣きする(あるいは微笑む)ばかりが映画ではないのだ。
見せないという省略の美ではなく、見せないという豊穣の海がここにある。その海は凪いでいる。この海は荒れ狂ったりはしない。だから、登場人物の誰も(明確には)泣いたり叫んだりしない。わたしたちの日常は凪いでいる。その様を山下敦弘はすっと見つめる。