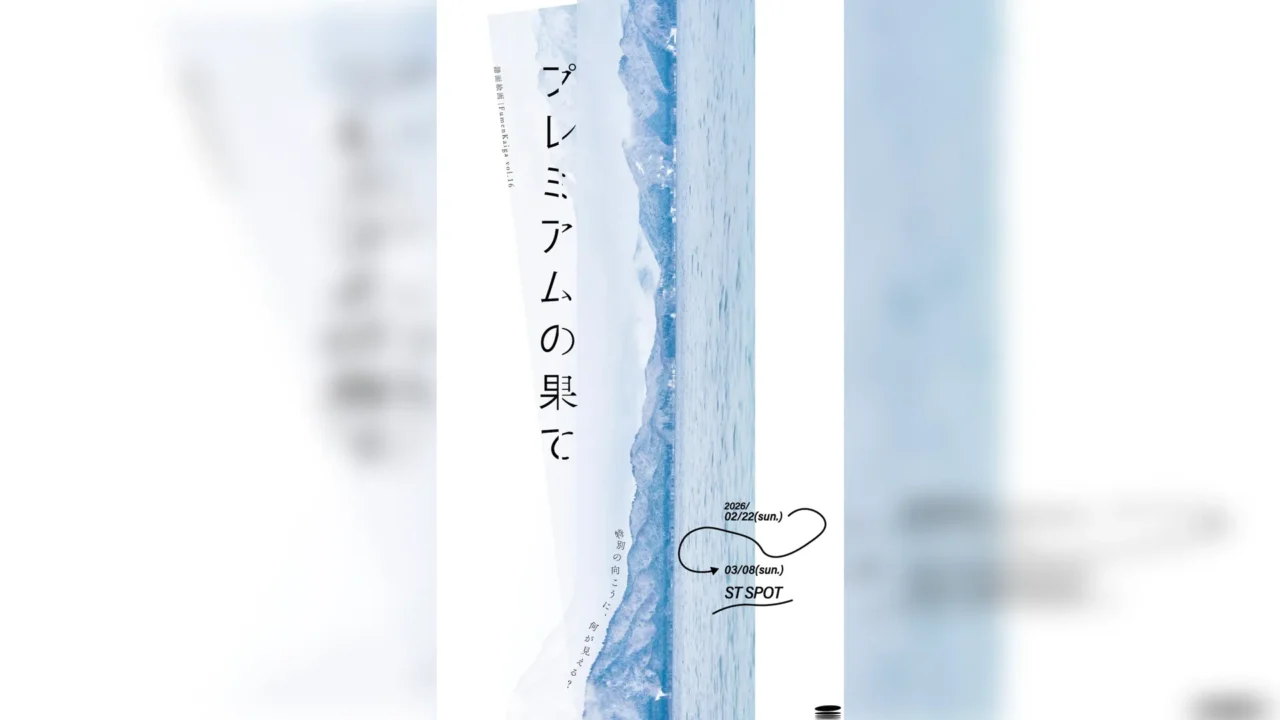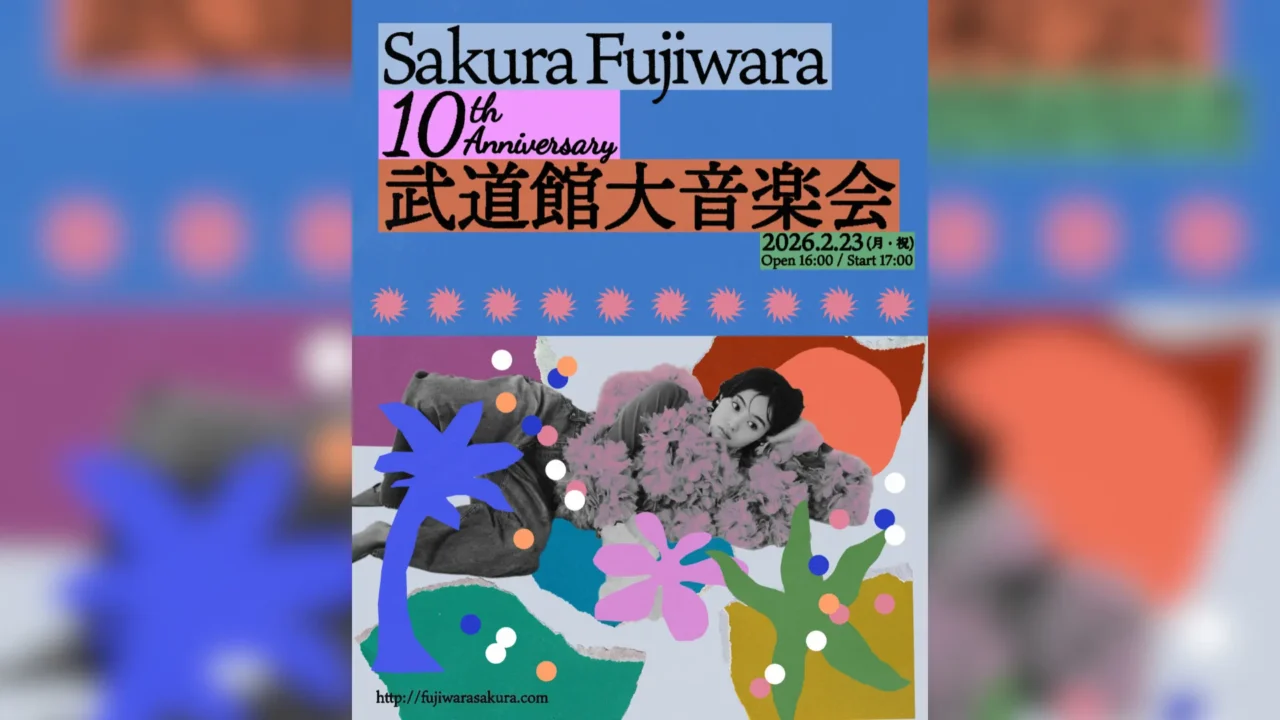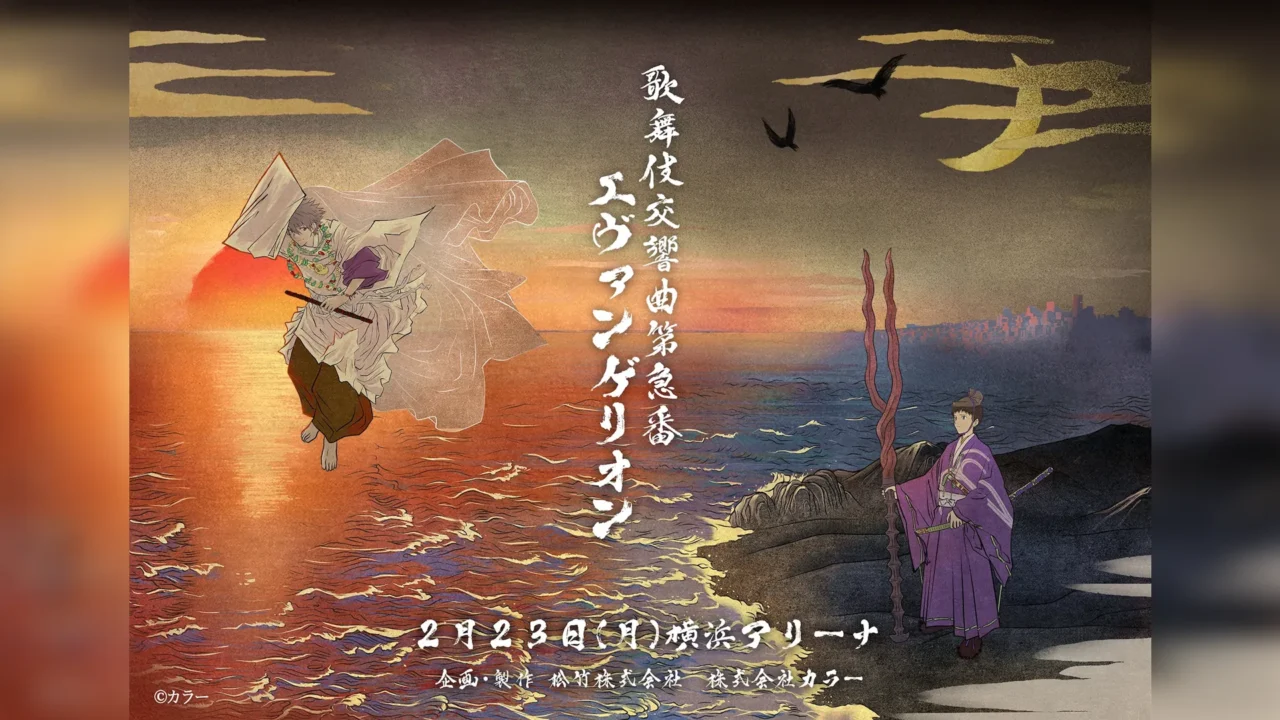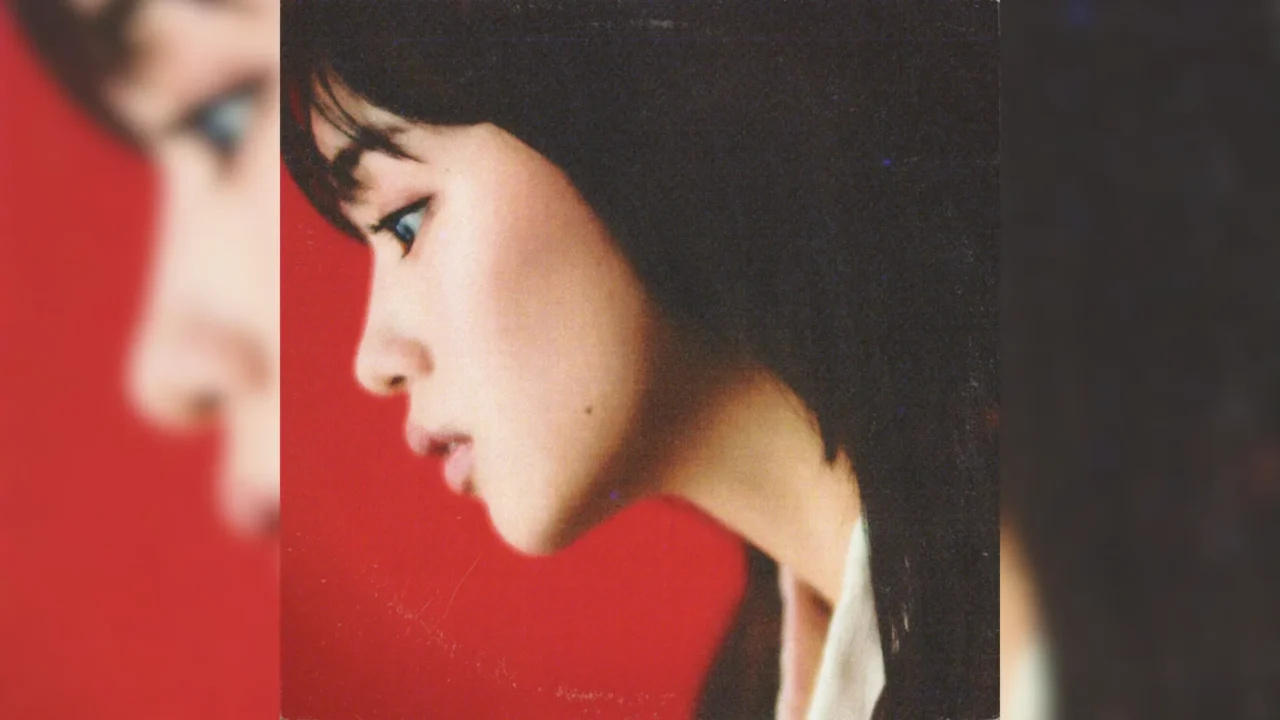グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。
4月10日は、いけばな教室「麗―rei―」主宰の大泉麗仁さんからの紹介で、陶芸家の小野澤弘一さんが登場。作品の技法についてや、小野澤さんが考える陶芸の魅力などについて伺いました。
INDEX
古いものも新しいものも含めて陶芸が好きだから、陶芸家を志した
Celeina(MC):早速ですが、陶芸家を志したきっかけはなんだったんですか?
小野澤:ミュージシャンで、もともと音楽が好きでプロになろうと志す方がいらっしゃるのと同じです。たまたま美術館に行ったりギャラリーに行ったりしていて、古いものも新しいものも含めて陶芸が好きだったので、取り組み始めました。
Celeina:陶芸の勉強はどのようにされていたんですか?
小野澤:最初は学校のサークルで、遊びみたいにやっていました。陶芸を1番本格的に勉強したのは、岐阜県の多治見市陶磁器意匠研究所という専門学校に行っていた時で、2年ほど勉強しましたね。多治見は、美濃焼という焼き物の産地としては日本で1番なんです。
タカノ(MC):そして、今日はスタジオの方に作品をお持ちいただいています。
小野澤:小さい食器ですけれど。
タカノ:これは器ですか?
小野澤:そうですね、鉢と小皿みたいなものです。皆さん聞き馴染みがないと思いますが、技法としては「陶胎漆器」を使っています。漆器のお椀とかは木に漆を施すじゃないですか。陶胎漆器は、焼いた陶器に漆を施すんです。

Celeina:そういった作品は初めて見ました!
小野澤:やっている方はそんなに多くないですね。
タカノ:2つ作品をお持ちいただいたんですけれども、大きい方がちょっと墨っぽい色ですね。
小野澤:細かい話は省くんですけども、色々なものを重ねたり磨いたりして、結構手間がかかっていますね。
Celeina:すごく薄い仕上がりになっていますよね。
小野澤:ろくろで薄く挽くんです。食器なんですけども、自分としてはあまり用途は考えていなくて、造形物として作っています。
Celeina:観賞用に、という感じなんですね。
小野澤:実際に使っていただいても大丈夫なんですけどね。気軽に着れる洋服もあれば、ちょっと緊張して着る服もあるのと一緒で、ちょっと特別感が感じられるお皿として使っていただけると嬉しいです。
タカノ:(メジャーを取り出す)お皿のサイズを測りますね。大きいお皿は、大体直径20cmくらいですかね。
Celeina:小さい方は?
タカノ:小さい方は大体直径16.5cmくらいでしょうか。
Celeina:手のひらサイズよりちょっと大きいかなくらいですね。2つとも色味が違いますけれども。
小野澤:小さい方は金属のスズの粉末を漆で定着させていて、これも漆芸の技法を陶芸に使っています。
Celeina:すごくクリエイティブですね。
タカノ:ちょっと金色っぽくも見えるというか。
小野澤:漆の褐色と、スタジオのライトの影響もあると思います。
Celeina:ライティングによっても違う表情を見せるんですね。