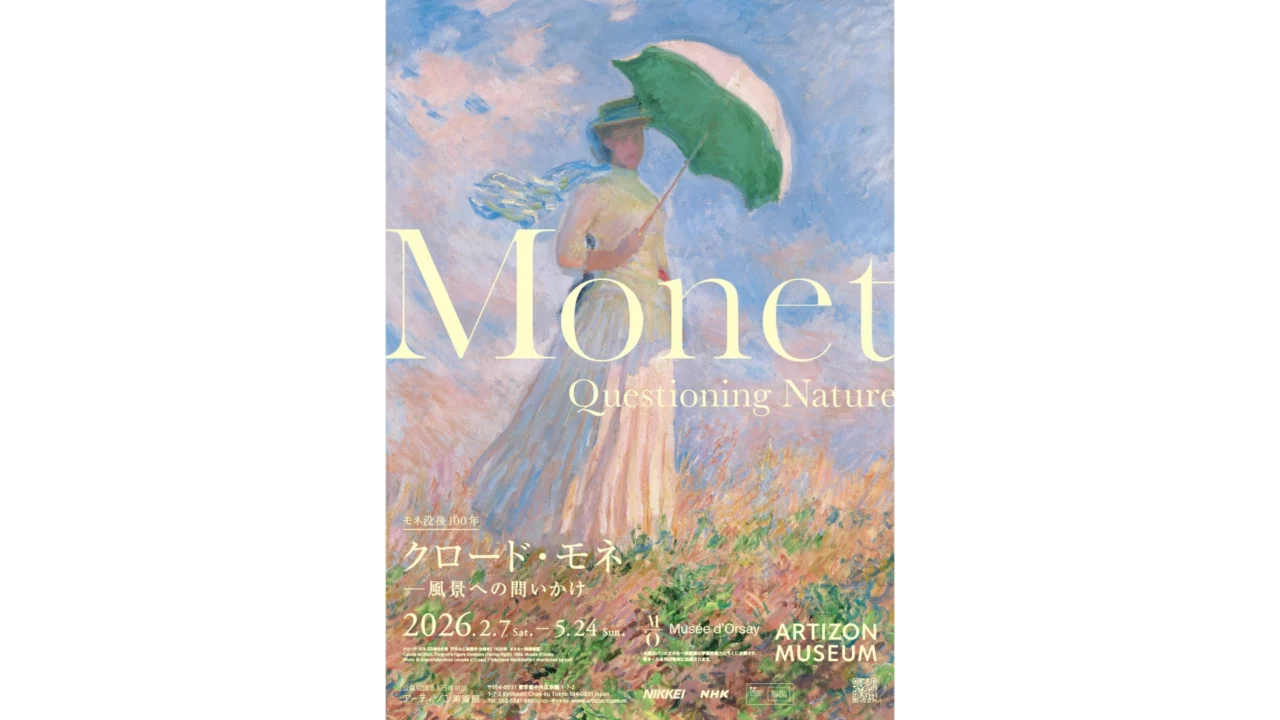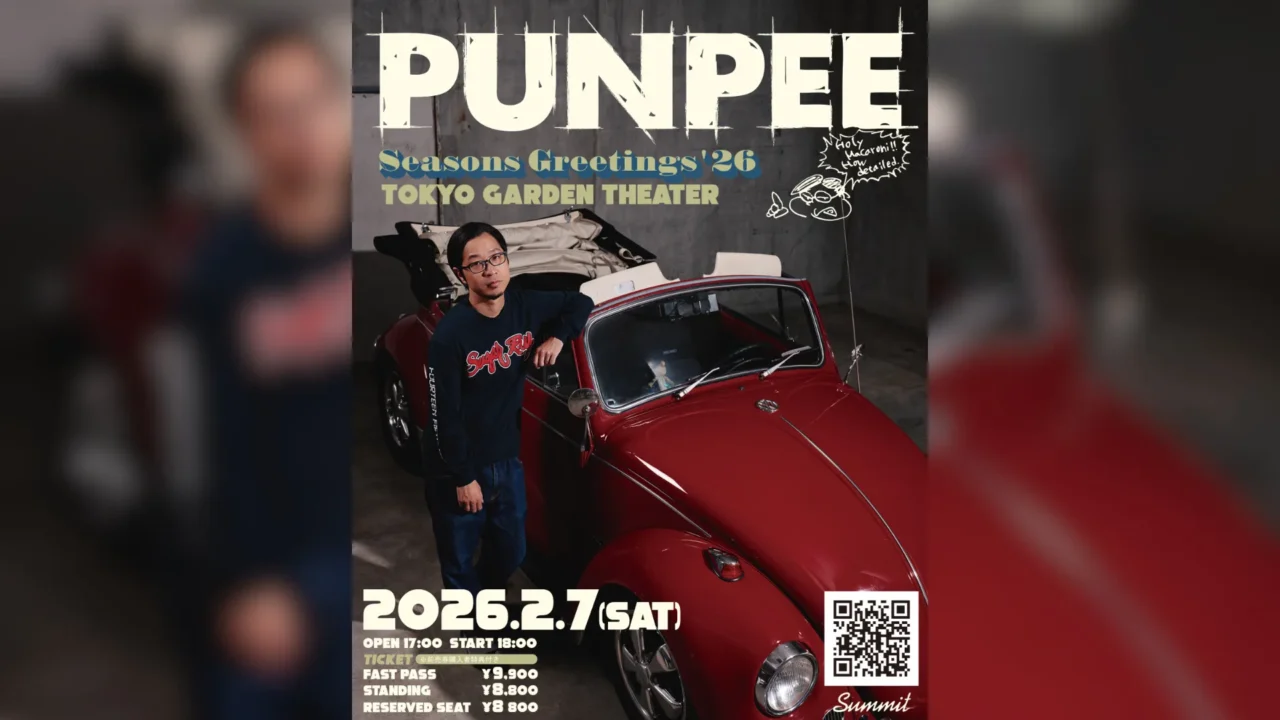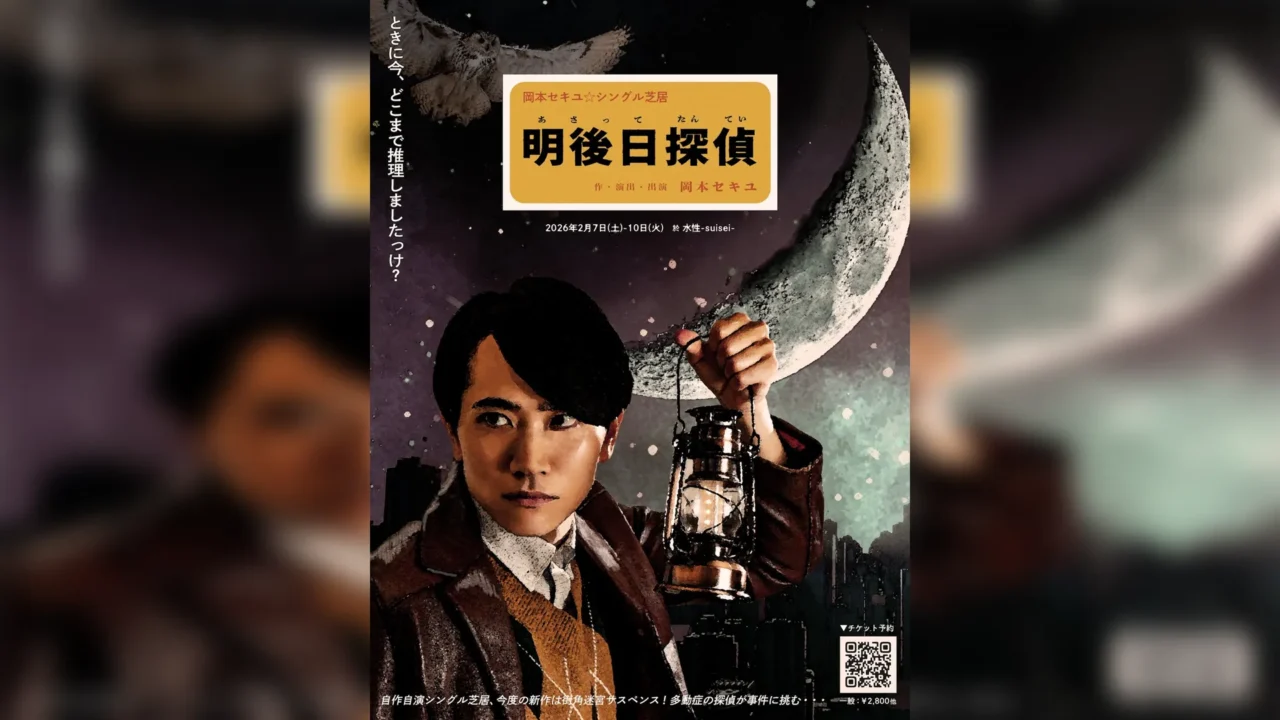グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。
12月26日は、現役大学生の有隅央さんからの紹介で、大学でインド文学を学びながら、様々な言語で詩の創作も行う佐藤雄太さんが登場。インドの古典文学『バガヴァッド・ギーター』の話や、詩を創作する時に大切にしていることなどについて伺いました。
INDEX
ヒンディー語をはじめ、さまざまなインドの言語を教えている
タカノ(MC):佐藤さんは、現在大学院の博士後期課程に在籍しながら、大学の非常勤講師としてインドの言語を教えられています。インドの言語というと、ヒンディー語のイメージが強いですが、具体的にはどのような言語を教えているんですか?
佐藤:まず、ヒンディー語のことを「ヒンドゥー語」と間違って言う方が多い中で、タカノさんが「ヒンディー語」とおっしゃっただけでもすごく詳しいと言えると思います。
Celeina(MC):私は「ヒンドゥー語」だと思っていました……! 「ヒンディー」と「ヒンドゥー」にはどのような違いがあるのでしょうか?
佐藤:ヒンドゥー教という宗教があって、ヒンディー語という言語があるんです。語源は近くて混同されがちなんですが、別物なんです。
タカノ:他にもインド国内に色々な言語があるんですよね?
佐藤:そうですね。ベンガル語やタミル語、マラヤーラム語とか、数えだすとキリがないくらいあります。
タカノ:佐藤さんはどの言語を教えていらっしゃるんですか?
佐藤:私が教えているのはヒンディー語と、あとサンスクリット語と呼ばれる古代の言語です。それらを大学生とか一般の方に向けて教えていますね。
INDEX
インド文学に興味を持つきっかけとなった『バガヴァッド・ギーター』
Celeina:そもそもインド文学やインドの言語に興味を持ったきっかけはなんだったんでしょうか?
佐藤:高校の国語の授業で漢文を読んだ時に、「古代中国って面白いな」と思って、古代中国関連の本をたくさん読むようになりました。そのうちだんだん古代インドにも興味を持ってきて、古代インド関連の本を読んだら楽しかったんです。『バガヴァッド・ギーター』という有名な古典文学があるんですけども、それの岩波文庫の翻訳を読んだら面白くて。「もっと詳しく深掘りしたいな」と思って進路を決めました。
タカノ:『バガヴァッド・ギーター』は僕も最近すごく注目しているんです。
Celeina:昨日も放送以外のところでお話しされていましたよね。
タカノ:「明日のゲストの佐藤さんって『バガヴァッド・ギーター』読んでいるのかな?」と話していました。
Celeina:『バガヴァッド・ギーター』について、ご説明いただいてもよろしいでしょうか?
佐藤:サンスクリット語で書かれた古典です。『マハーバーラタ』と言われるすごく長い叙事詩があって、その中の一部分を切り取って、聖典のような扱いをされている文献です。何が書かれているかというのを一言で言うのは難しいんですが、有名な部分で言うと、ある行為をする時に「結果のことを考えてするんじゃなくて、行為そのものに打ち込むべし」という教えがあります。これはすごく普遍的な教えで、我々にも通ずるんじゃないかなと思います。
タカノ:意外と経営者の方が読んでいたりして、ビジネス界隈でも注目されているみたいですね。
佐藤:ビジネスをやるなら行為の結果を気にした方がいいと思いますが(笑)。
タカノ:言われてみればそうですね(笑)。『バガヴァッド・ギーター』は『マハーバーラタ』の一部分だから、単体で読んでもよくわからないという噂も聞いていて。なので僕は、とりあえず『バガヴァッド・ギーター』をかいつまんで説明している入門書を購入しました。
佐藤:いきなり翻訳を読んでもわかると思いますし、独立して読まれてきたという歴史もありますよ。あとは『マハーバーラタ』全体に関心がある場合でも、最近は入門書がいっぱい出ているので、そういう本を横に置きながら『バガヴァッド・ギーター』を読むと、わかるようになると思います。
タカノ:『マハーバーラタ』ってどれぐらいのボリューム感なんですか?
佐藤:一応全18巻ということになっているんですけど、1巻が辞書くらい分厚いんです。
タカノ:すごいですね。佐藤さんはもう読破されているんですか?
佐藤:いや恥ずかしながら、まだ全部は読めていないんです。一生かけないと読めないかな、と思っています。
タカノ:時間もかかるし大変ですよね。「結果を考えずに行為をすべき」というお話もありましたけど、他にお気に入りの一節だったりとか、人生で参考にされている部分はあったりしますか?
佐藤:『バガヴァッド・ギーター』は、同じ民族だった人たちが内輪で戦争をするというところから始まるんですけど、アルジュナという戦士がいて、戦いを前にしてビビってしまうんですね。それで、隣にいる友達兼神様のクリシュナという人に「もう戦うの嫌になっちゃったからやめようかな」と言うんですよ。 そこでクリシュナは叱咤激励して、「いや、お前は戦うべきだ」と励ますシーンが好きです。
タカノ:いいですね。
佐藤:アルジュナとクリシュナは友達でもあり、人と神でもあるんですよね。11章で、今まで気軽に話しかけていたクリシュナがいきなり神の姿を見せるシーンがあって、「今まで友達と思って気安く喋っていてごめん」とアルジュナがクリシュナに謝るシーンがあるんですけど、そこは面白いなと思います。
タカノ:佐藤さんには『バガヴァッド・ギーター』の解説をYouTubeとかでやってほしいですね。もっと聞きたいです。
佐藤:機会があれば(笑)。
INDEX
色々な言語で韻を踏み、詩の創作に生かす
Celeina:そして佐藤さんは様々な言語で詩の創作も行われているとのことで。
タカノ:すごいですね。日本語以外の言語ということでしょうか。
佐藤:そうですね。メインは日本語なんですけど、それ以外だと、ヒンディー語やウルドゥー語、あとはペルシャ語とか、最近はジョージア語で押韻定型詩という韻を踏んだ詩を書くのも試みました。
Celeina:ちょっと待ってください。色々な言語が出てきましたけど、一体何ヶ国語できるんですか?
佐藤:できるとは言いづらいんですけれども、触ったことがある言語だけだと、50ヶ国語くらいあります。ただ、誰でも図書館に行って本とかを読めば、かじったことにはできるので。
タカノ:いやいや。そこから詩を書くというのが大変ですよね。
佐藤:外国語って勉強していると、「この単語とこの単語が似ていて混同しちゃうな」ということがよくあるじゃないですか。音が似ているなと思ったら、つまりこれとこれで韻を踏めるなと考えるわけですよ。自分になじみがない言語だからこそ、「この単語とこの単語を合わせるとケミストリーが起きそうだな」みたいなアイデアが生まれてくるので、詩の創作に活かしています。
Celeina:なるほど。ゼロベースでその言語に触れているからこそ、母国語と触れ合っている時とは違う感覚が生まれるというか。
タカノ:Celeinaさんも多分そうだと思うけど、英語で喋る時は英語で考えたりするもんね。そうすると日本語の感覚とはまた違う感じでしょ?
Celeina:確かに! そうですね。
佐藤:英語って韻を踏む文化があるじゃないですか。どんなポップソングでもラップでも韻があって、子供でも踏めるという。日本語には韻を踏む文化が英語ほど浸透してないですよね。それがなんか悔しいなと思っていて。 だから自分は日本語で詩を書く時も、「どうやって韻を踏めば美しく響くか」ということを考えます。
Celeina:先ほどのゲストの蔦谷好位置さんとも、ちょうど韻を踏む話をしていましたね。
タカノ:佐藤さんの活動をもっと知るためにはどこにアクセスすればいいですか?
佐藤:一応大学の社会人向け講座で、サンスクリット語を教えているので、そこに来れば、私の語学の授業を受けることができます。
タカノ:オフィシャルホームページとかはありますか?
佐藤:いや、ないですね。友達になってもらえれば、いくらでもこんな話はできます。
タカノ:皆さん、佐藤さんのお友達になるしかないということで(笑)。すごく面白いお話し、ありがとうございました。
Celeina:「FIST BUMP」、本日は大学でインド文学を学びながら、様々な言語で詩の創作も行う、佐藤雄太さんをお迎えしました。ありがとうございました。

GRAND MARQUEE

J-WAVE (81.3FM) Mon-Thu 16:00 – 18:50
ナビゲーター:タカノシンヤ、Celeina Ann