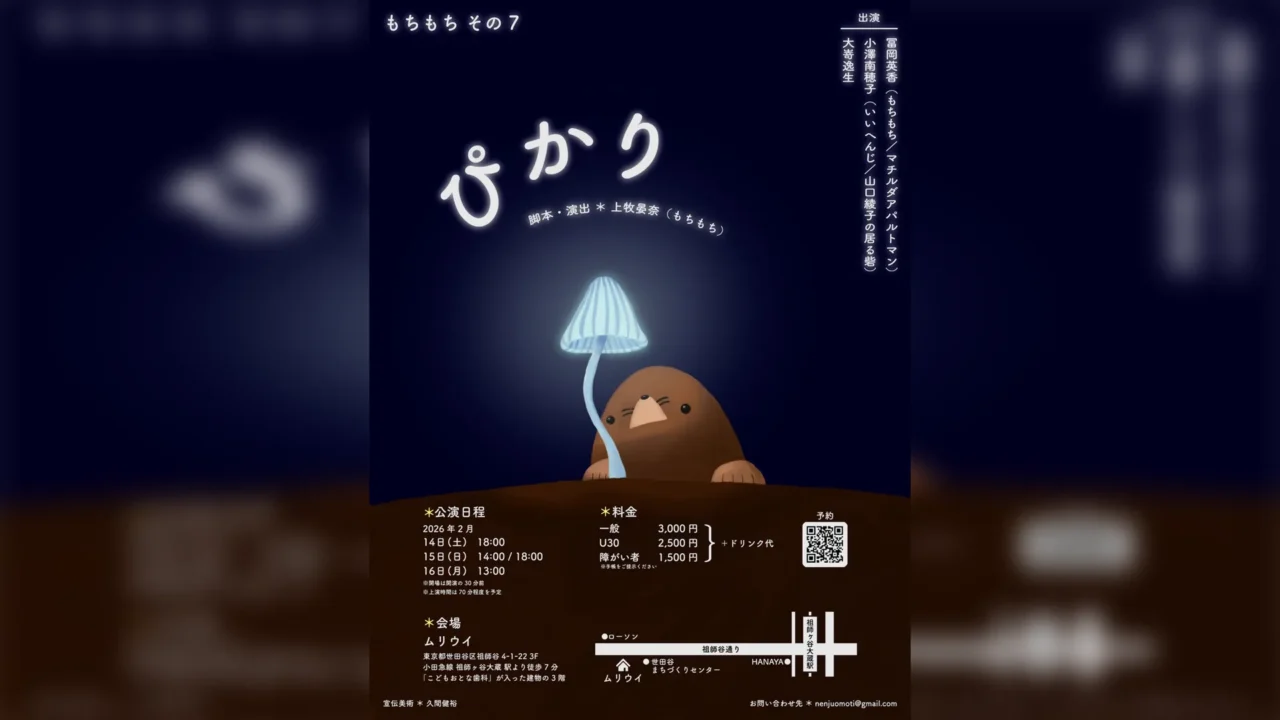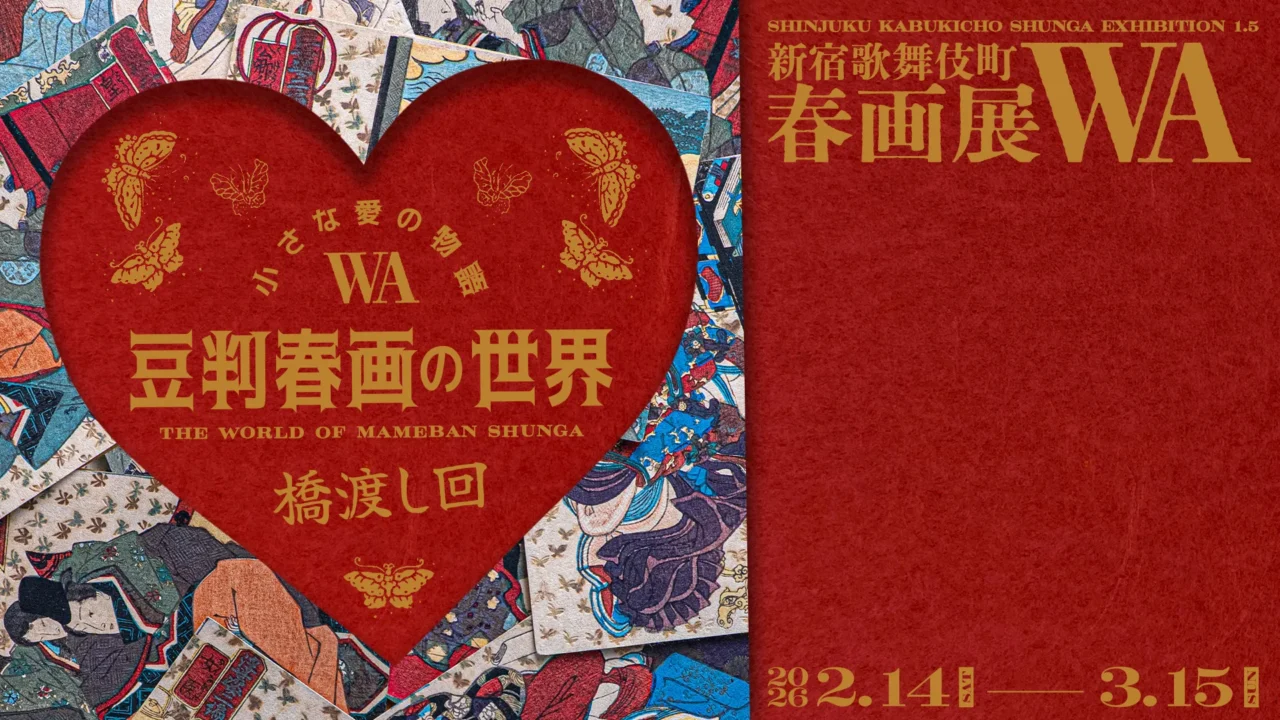INDEX
着物の無駄のない構造に魅力を感じた
タカノ:そもそもテキスタイルとは何か、というところからお伺いしてもいいでしょうか。
高橋:皆さんが着ている服、つまり布もテキスタイルですし、ある意味繊維からできているものはすべてテキスタイルに含まれると言っていいのではないかと思います。不織布のマスクや和紙なども繊維を絡ませて平らな状態にしているという構造は同じで、広義の意味では紙も入ってくるぐらい幅広いジャンルです。
タカノ:デザインが入っているものというイメージですかね?
高橋:繊維が関連するもの全般を指すイメージでしょうか。例えば、土に還る繊維の研究をする学生もいますし、単に白い布に表面的な図柄をデザインしてプリントする学生もいます。さらにそれを服にする人もいれば、伝統的な技法を使って着物にする人もいます。一言では言い表せないですね。
タカノ:なるほど、奥が深いですね。
Celeina:「着物」という言葉が出てきましたが、高橋さんが着物を表現のベースにされるようになったきっかけは何だったんでしょうか?
高橋:もともと小学校2年生の時に、ファッションデザイナーになって世界に出て行くぞというのを心に決めて、それに向かって生きていたんですね。ファッションの高校に進んで服作りを学んで、布から服作りをしたくて大学に進んだんですけれども、私が行った東京藝術大学の工芸科では伝統工芸を中心に学ぶので、常に参考資料が着物だったんです。
日本の伝統染織技法、つまり染めたり織ったりは、基本的に着物を作るために生まれた技法が多いので、昔の着物を参考にしながら技法の習得をしていました。着物という服が日本にはあるんだと知ってはいたものの、実際に手掛け始めたら、生地を全く無駄にせずに、丸ごと身にまとえることに気がつきました。隅々まで染めた生地を仮にシャツにしようとすると、かなりカーブが多くて端切れがたくさん出る。でも着物は、幅約40cm、12mの反物の1反を丸ごと1着にできるんです。捨てるところがないんですよ。
タカノ:なるほど! 考えたことがなかったです。
高橋:だから昨日ご出演された佐藤さんも私も、同じ反物1反から浴衣を仕立てることができるんです。縫い込む量を変えるだけで大きさを変えられるので、切って捨てないんですよね。その合理的で無駄のない構造に魅力を感じて、着物の世界に入っていったので、私としてはファッションの流れの中で、衣服として着物を手がけ始めたというのが最初です。
Celeina:かなり奥が深いですね。