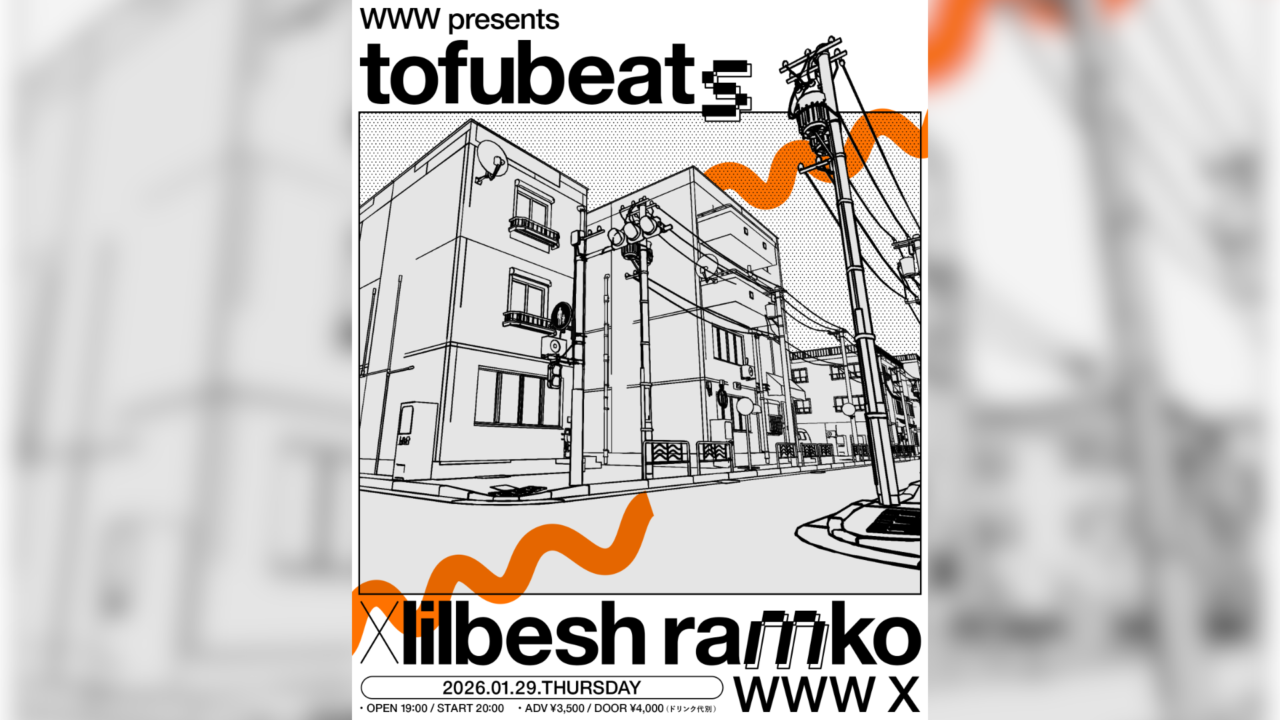映画『映画を愛する君へ』が1月31日(金)から公開中。監督は『そして僕は恋をする』などで知られるフランスの名匠アルノー・デプレシャン。本作は監督自身の自伝的映画だと謳われている通り、デプレシャンが幼少期から見てきた数々の名作や劇場への言及や引用で溢れている。
デプレシャン監督から映画、劇場へのラブレターのような88分の物語をライターの相田冬二がレビューする。
INDEX
映画体験そのものへの情感あふれる文学的オマージュ
男性、女性、恋愛、家族。アルノー・デプレシャンは、孤独と人間関係の機微を真新しい感慨と共に紡いできた監督だ。彼が描けば、ありふれた日常も、喜びも悲しみも、生き生きとした臨場感として、観客の胸に触れてくる。そうか、わたしたちの生命が紡ぐ時間は、こんなにもみずみずしいものだったのか! そう気づかせてくれるのだ。フランス映画の伝統を継承しつつも、常に自由闊達なその筆致は、『そして僕は恋をする』(1996年)でブレイクして以来、不変=普遍の輝きをまとっている。
そんなデプレシャンが、エッセイのような小粋さと、映画史を俯瞰する壮大さを併せ持つ『映画を愛する君へ』を創り上げた。はたして、本作をどのような枠組みに収めればよいのだろうか。映画をめぐるドキュメンタリーとも言えるし、監督個人の幼少期や青年期を踏まえた自伝映画とも言える。作品全体が映画メディアの批評であると同時に、映画体験そのものへの情感あふれる文学的オマージュなのだ。

つまり、主観と客観を行き来する。全11章形式だが、それが章ごとにスイッチされるのではなく、章の内部で、交通する。冷静と情熱のはざまで、そのいずれもを尊重しつづけるデプレシャンの姿勢はまさに自由闊達だ。ミクロとマクロを共に讃える様は、この監督にしかできない離れ業と呼んでいい。
INDEX
「映画監督」デプレシャンが描いた、「映画観客」デプレシャン
エジソンとリュミエール兄弟が登場する幕開けは一見、ものものしい。退屈な「映画の授業」が始まるのでは、という不安が一瞬よぎる。ところが、それが杞憂だったことが直後に明るみになる。「アメリカが映像=フィルムを発見し、フランスが映画=シネマを見出した」と映画黎明期を総括する言葉が作品全体の予告になる。そして、わたしたちは驚きに導かれる。

フランス人であり、フランス映画の伝統をかなりの部分で踏まえているかに思えるデプレシャンは、その後、なんと自国の映画にはほとんど触れず、主にアメリカ映画について言及していく。約50本ほどの作品のシーンが次々に引用されるが、最初に登場するのはなんと『エイジ・オブ・イノセンス/汚れなき情事』(1993年)だ。監督はマーティン・スコセッシ。そうして、フランシス・フォード・コッポラ監督を特権的なポジションに配置しつつ(青年時代のデプレシャンが「尊敬している」と明言する再現ドラマが挿入される)、ジェームズ・キャメロンの2作からの象徴的な引用があり、マイケル・チミノの『ディア・ハンター』(1978年)には最上級の敬意が捧げられている。デプレシャンの自由闊達さの底辺には、アメリカ映画からの影響も深く関与していたことを、わたしたちは知る。映画作家の無邪気で素直な横顔に触れる想い。

とりわけ不意を突かれるのは、『ノッティングヒルの恋人』(1999年)のワンシーンで、ジュリア・ロバーツとヒュー・グラントのやりとりにかなりの時間を割いていることだ。男性性から女性性への限りない憧憬を、ベタつかない情緒で編み上げるモノローグは、『映画を愛する君へ』という映画の本質を体感させる。これは映画作家アルノー・デプレシャンの新作というより、映画観客アルノー・デプレシャンの心情吐露なのだ。
時に懺悔のような記述もあるが、そうしたシリアスな告白も含めて、観客デプレシャンができるだけ正直であるために、監督デプレシャンが力を貸しているかのようにも思える。