INDEX
最晩年、生と死を見つめて
1900年の万博の翌年あたりから、療養を繰り返すようになったというガレ。明かりを落とした最後の展示室では、ガレの最晩年の作品がスポットライトに浮かび上がる。死を前にして(おそらく覚悟して)創造を続けていたガレの心に寄り添うつもりで、作品と静かに対話してみてほしい。

ガレ作品の中でも有名なキノコのランプは、「ヒトヨタケ(一夜茸)」をモチーフにしている。成長した後に、自らの酵素によってカサの縁から溶けて消えてしまうという不思議なキノコだ。液化して消えてゆくのは、胞子を分散させるため、すなわち次世代のためだと考えられている。もしかしたらガレはそこに、自分自身を含めた生命のサイクルを感じていたのかもしれない。

本展で出会える最後の作品は、やっぱりトンボだ。制作年は1903〜1904年、ガレが白血病で世を去ったその年か、前年にあたる。複雑な技法の組み合わせによって、トンボは懸命に羽を震わせているように見える。そこに、死の間際まで創造を続けようともがくガレ自身を重ねて見ることもできるかもしれない。一方で、乳白色の杯は卵の殻のようにも見えて、新しくより大きなものが生まれたような、不思議な明るさをも感じる作品だった。
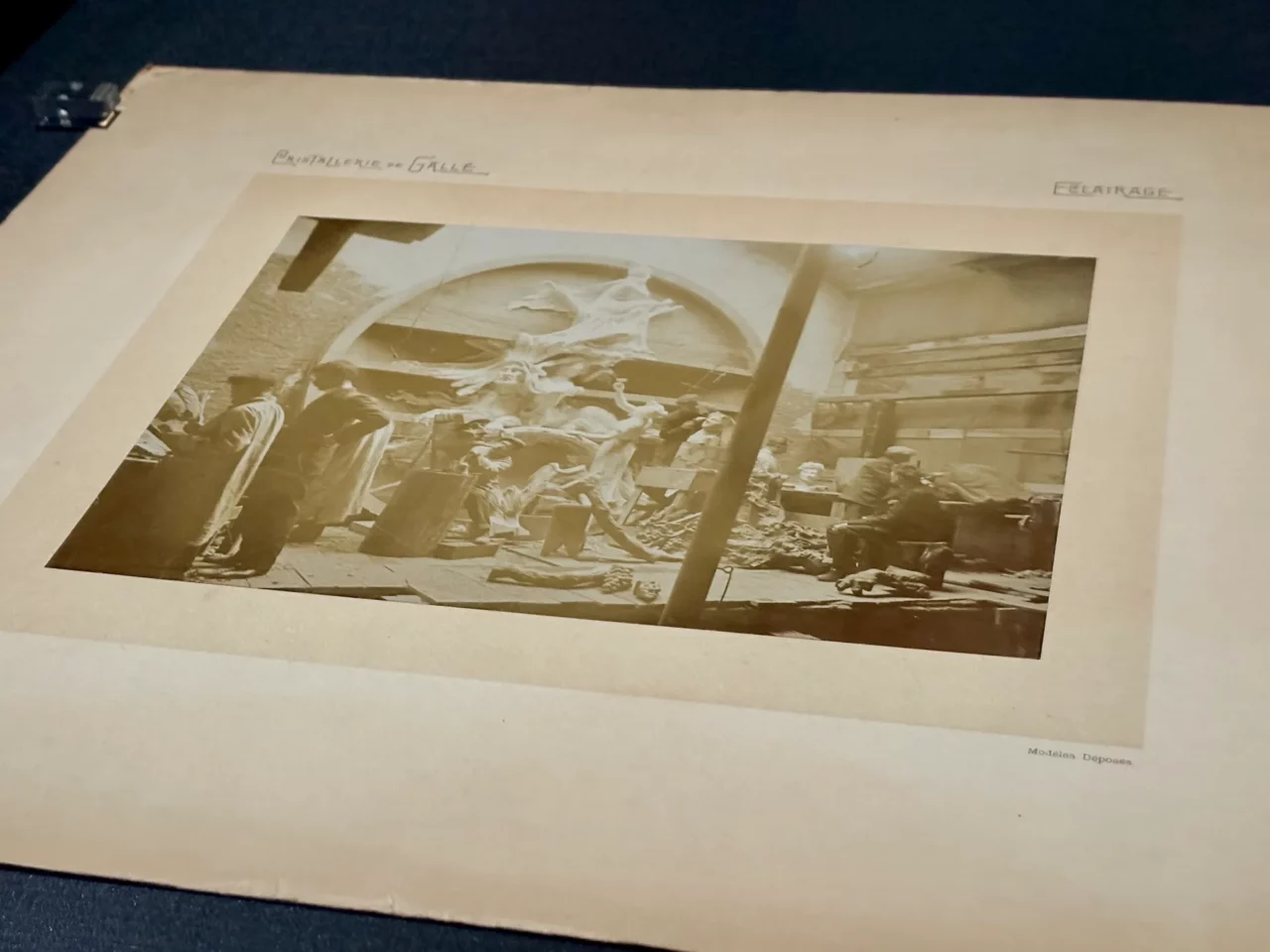
ガレは1904年、58歳の若さで世を去った。最後に尽力していたのは、故郷ナンシーでの産業芸術同盟の結成だったという。本展で見てきた故郷との関係の歴史を踏まえてそれを知ると、切なく感じられる。
























