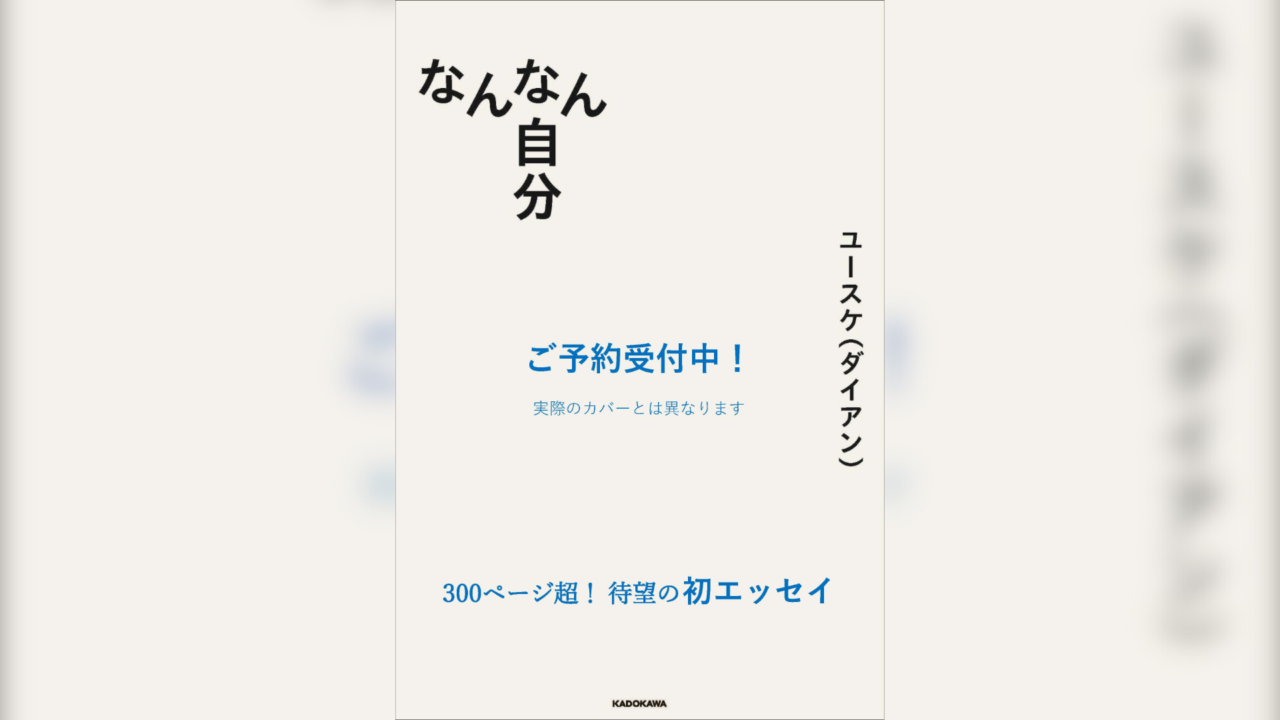サントリー美術館にて開催中の『没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ』は、もうチェックしただろうか。ガラスの分野ではおそらく世界でいちばん有名な作家であり、陶器や家具でもその独自の世界観を展開した芸術家、エミール・ガレ。本展はその作品や資料110件を通じて、時代を駆け抜けた一人のアーティストによる創造の軌跡をたどるものだ。会期は残り半分を切った。鑑賞のポイントを交えてレポートする。
INDEX
故郷ナンシーと大都市パリ
エミール・ガレは、アールヌーヴォーの旗手のひとりとして知られる19世紀フランスの芸術家。特にガラス工芸の分野で国際的な成功を収め、動植物をモチーフにした有機的デザインの作品を多く残している。漠然と「うねうねしたデザインの花瓶の人」というイメージを抱いている人も多いのではないだろうか。
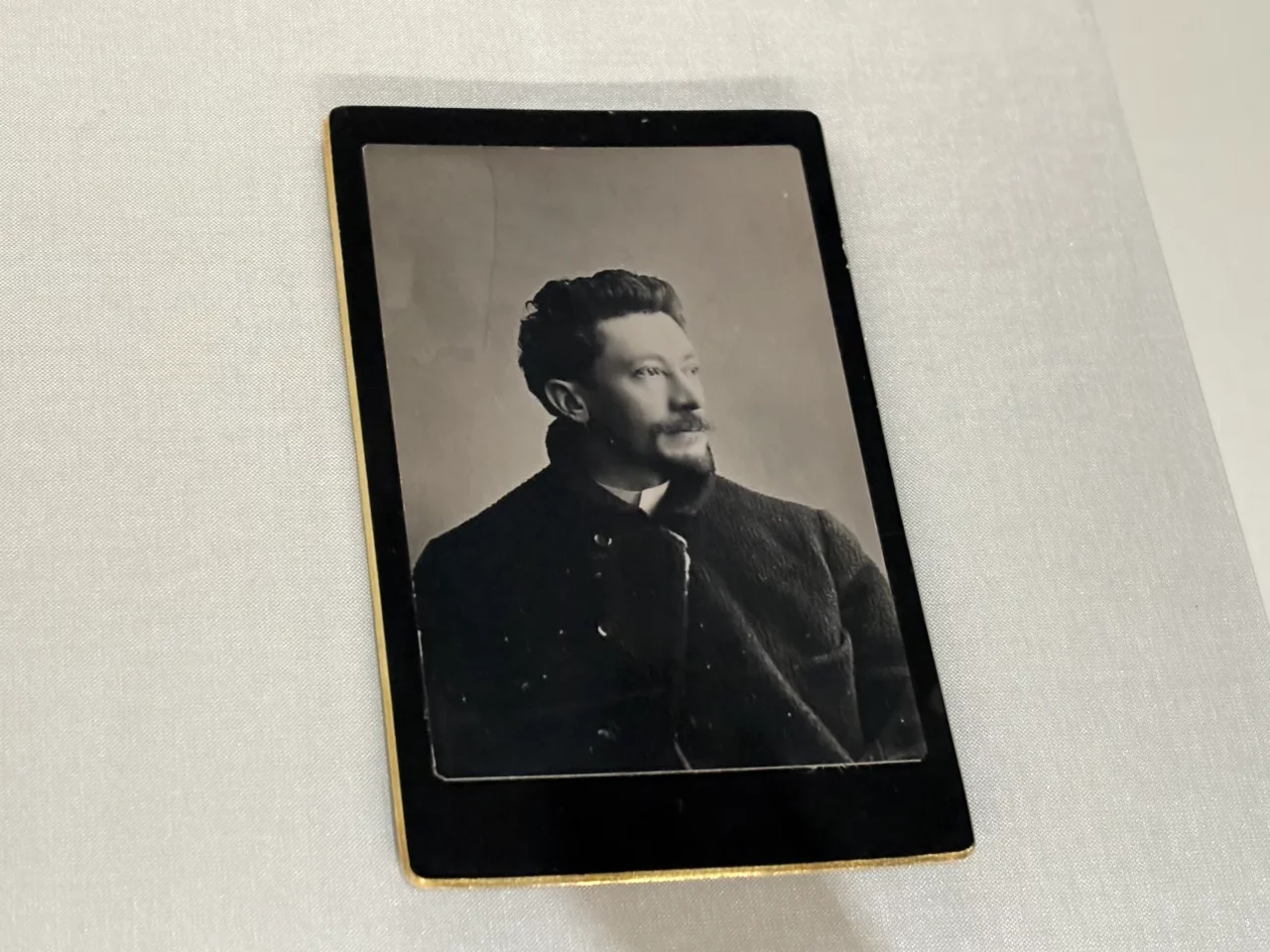
ガレはフランスとドイツの国境近くにある地方都市ナンシーに生まれ、生涯にわたりナンシーに拠点を置いていた。作品の製造ももちろんナンシーで行われた。優れた芸術家として、そして経営者として、名実ともにナンシーの名士だったガレ。けれど、芸術家エミール・ガレの構成要素として首都パリを欠かすことはできない。ガレは「ナンシーの芸術家」というより、「地元ナンシーと首都パリ、ふたつの故郷を持つ芸術家」だったと考えるべきだろう。ちなみにナンシーとパリの距離はおよそ300km。日本で置き換えると、東京と名古屋くらいの感覚だ。

本展は、そんなガレとパリとの関係にフォーカスする展覧会だ。ポイントは2点。1つは、『パリ万博』において、ガレはどのようにステップアップしていったのか。そしてもう1つが、地方都市ナンシーに拠点をおくガレは、売れるためにパリで何をしたのか、だ。展示は、全3章の本編で前者を、章の間に挟まれる「コラム」で後者を明らかにしていく構成となっている。
およそ11年おきに開催されていた『パリ万博』に、ガレは父親のアシスタントとして1回、その後自身が中心となって3回参加している。万博といえば国際的な大舞台。出展されるのはもちろん、各時期におけるガレ渾身の作品たちだ。ではそれぞれの万博で、ガレは一体どんな作品を出品してきたのだろうか。展示品の一部をピックアップしながら見ていこう。
INDEX
ガレ20代、父の背中越しに見た万博(1867年)

父親の手伝いで万博に参加していた頃、ガレ20代の作品、ゴブレット『ジャック・カロの人物画』だ。透明なガラス地に「エングレーヴィング」と呼ばれる当時広く行われていた彫りの技法で装飾を施し、さらに金彩で仕上げている。形状も伝統的なゴブレットの形を踏襲していて、まだまだガレの個性は影を潜めている、と言えるかもしれない。ちなみに中央の楽器を演奏する男はガレと同じナンシーの銅版画家、カロの絵をモチーフにしているという。早くもガレの地元愛を感じるポイントである。なおこの年の万博でガレの父は、クリスタルガラス、高級ガラス、ステンドグラス部門で選外佳作賞を受賞している。
INDEX
ガレ30代、1回目の万博(1878年)

11年後。ガレが家業を引き継いで経営者となった翌年の『パリ万博』では、こんな作品が。脚付杯『四季』は子ども用のお茶碗くらいの小さな作品だが、施された繊細な装飾に目を奪われる。縁の部分に黄道十二宮の名前が記されており、よく見るとその下に星座の姿が彫られている。正面が牡牛座、間に星のマークを挟んで、右隣に双子座……といった具合だ。側面に彫られているのは四季をモチーフにした女性像だという。
本展ではこの作品を含め、ありし日の『パリ万博』で展示されていた実物が数点展示されている。「同一モデル」ではなく、歴史を目撃してきたご本人の登場である。そう知った上で見ると、器の中に当時の観客たちのため息や賞賛をたたえているように思えて感慨深い。
とはいえ、この時点でのガレ作品にはそこまで大きな技法の変化が訪れているわけではない。ガレにとって1878年の万博で最も革新的だったもの、それはガラスの素地なのである。

『北斎漫画』に登場する鯉を絵付けした花器『鯉』(当時はジャポニスム全盛期!)を見てみよう。波打つ花瓶の凹凸が光を屈折させて、まるで鯉が水の中を泳いでいるようだ。なるほどガラスを扱うということは、光の透過・屈折をデザインすることなのかとしみじみ実感する。
ガラス地の部分に注目してみると、かすかに青みがかったガラスが使われているのがわかるだろうか。これはガレが1878年の万博で発表した新素材「月光色ガラス」というもの。月光色ガラスはヨーロッパ各地で模倣されるほどの大人気を博したという。この年の万博でガレは、ガラス部門銅賞を受賞している。
ところで、装飾の技法を分かりやすく紹介するパネル展示にも注目したい。多彩な装飾バリエーションは、作家や職人たちのたゆまぬ研鑽の表れだ。中には「パチネ」「マルケトリ」など、のちにガレが考案した技法もあるので、鑑賞のヒントとして目を通しておこう。