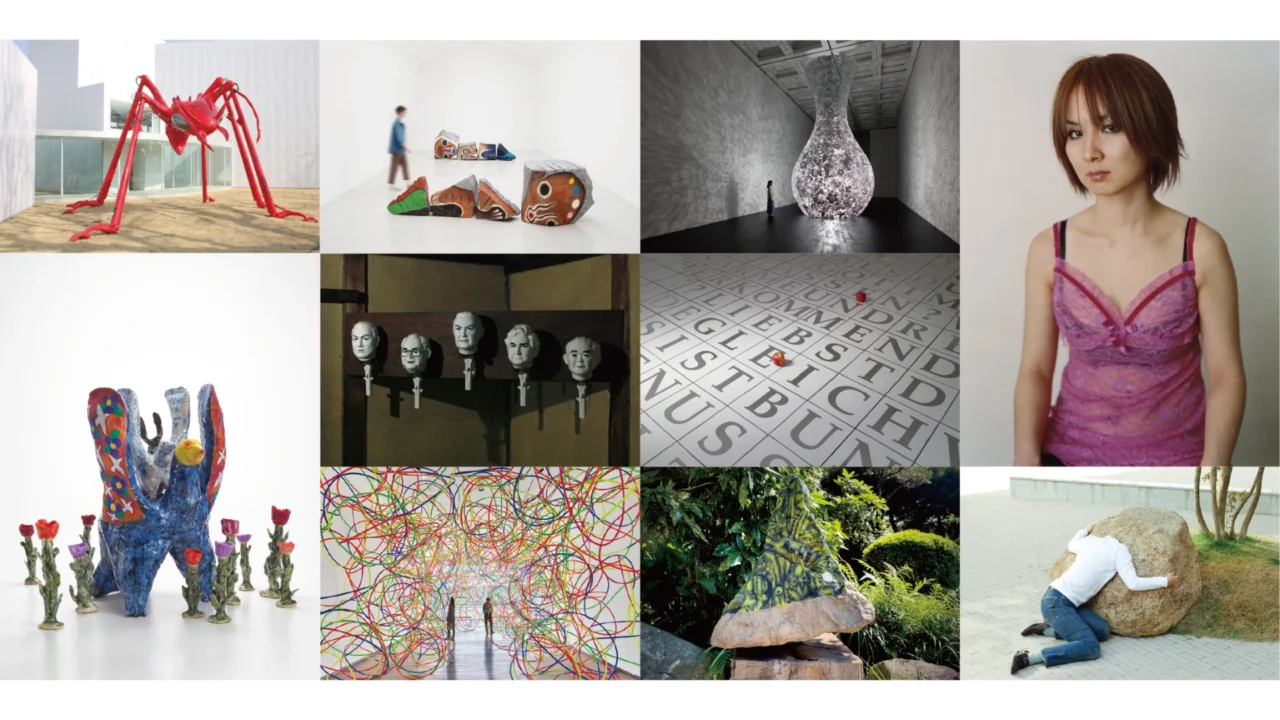INDEX
本作のハイライトを演出した、スカルスガルドとエル・ファニングの交わり
終始そんな調子のグスタヴは父としての信頼を回復できず、結局は別の役者に自身のもっともパーソナルな内容だという作品『帰りたい場所(ホーム)』の主演を依頼することになる。映画祭で出会った国際的に活躍する俳優レイチェル・ケンプ(エル・ファニング)だ。彼女が本作で負っているアイデンティティはまず「スター俳優」ということになるのだが、もう少し細かく見ると、現代の映画産業のなかで苦闘する若手映画人であることがわかってくる。彼女の出演が決まってNetflixの出資を得られることになったグスタヴだが、彼はそのことで劇場公開が不透明になることすら知らない。よくも悪くも20世紀の映画文化を引きずった人間なのだ。一方のレイチェルは、そうしたストリーミング時代の映画業界や、セレブリティとしてソーシャルメディアの好奇の目に晒されることともうまく渡り合わざるをえない。

だからグスタヴとレイチェルの映画製作を通じておこなわれるやり取りはそのまま、異なる世代の映画人たちの交わりになっていく。私が胸を打たれたのは、華やかな業界に身を置くレイチェルもまた映画という芸術に真剣に向き合っている人物であることだ。とりわけ彼女が『帰りたい場所』の台詞を読む場面では、ファニングの真摯な佇まいもさることながら、スカルスガルドの熟練の演技に息を呑まずにはいられない。グスタヴはレイチェルが役に入りこんだ姿を見ることで、自分が書いた脚本の主人公の心情をついに深く理解する。本作ではそのように、グスタヴの個人的な作品として始まった『帰りたい場所』が、製作を通して彼だけのものではなくなっていく過程も描かれる。それが映画なのだと。そしてグスタヴとレイチェルもまた、疑似的だが「家族的」な絆を築いていくことになる。