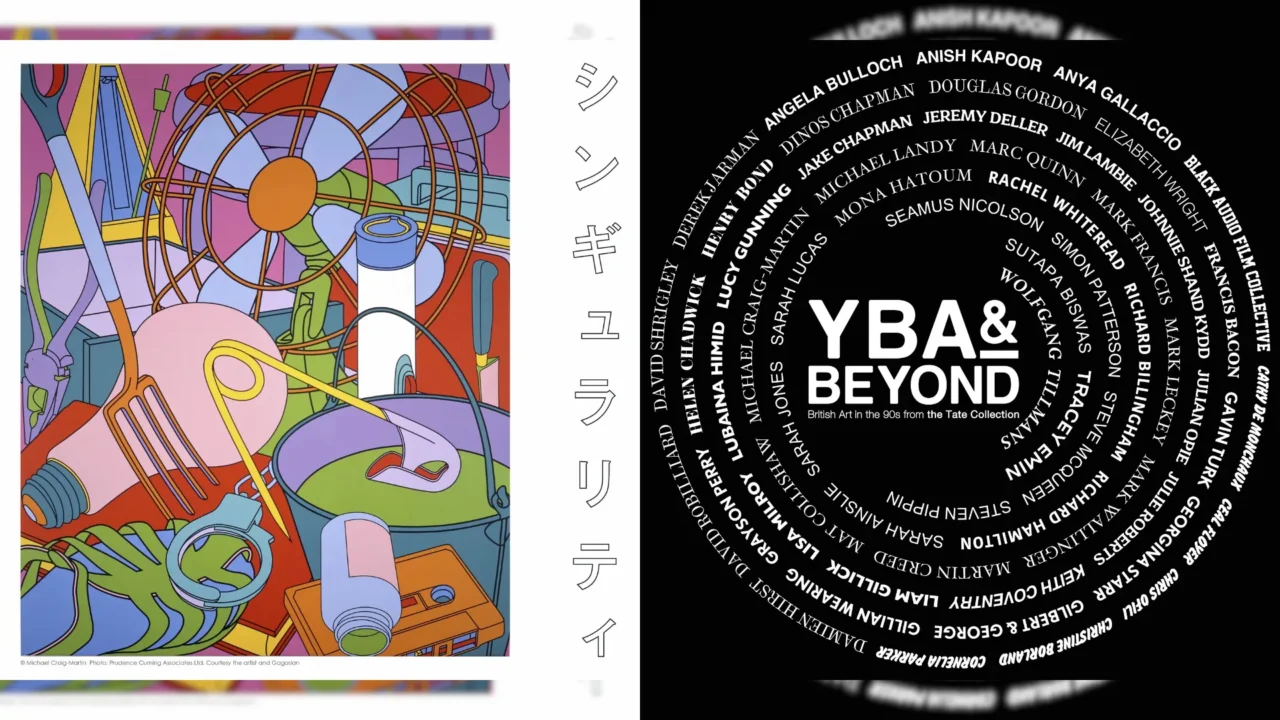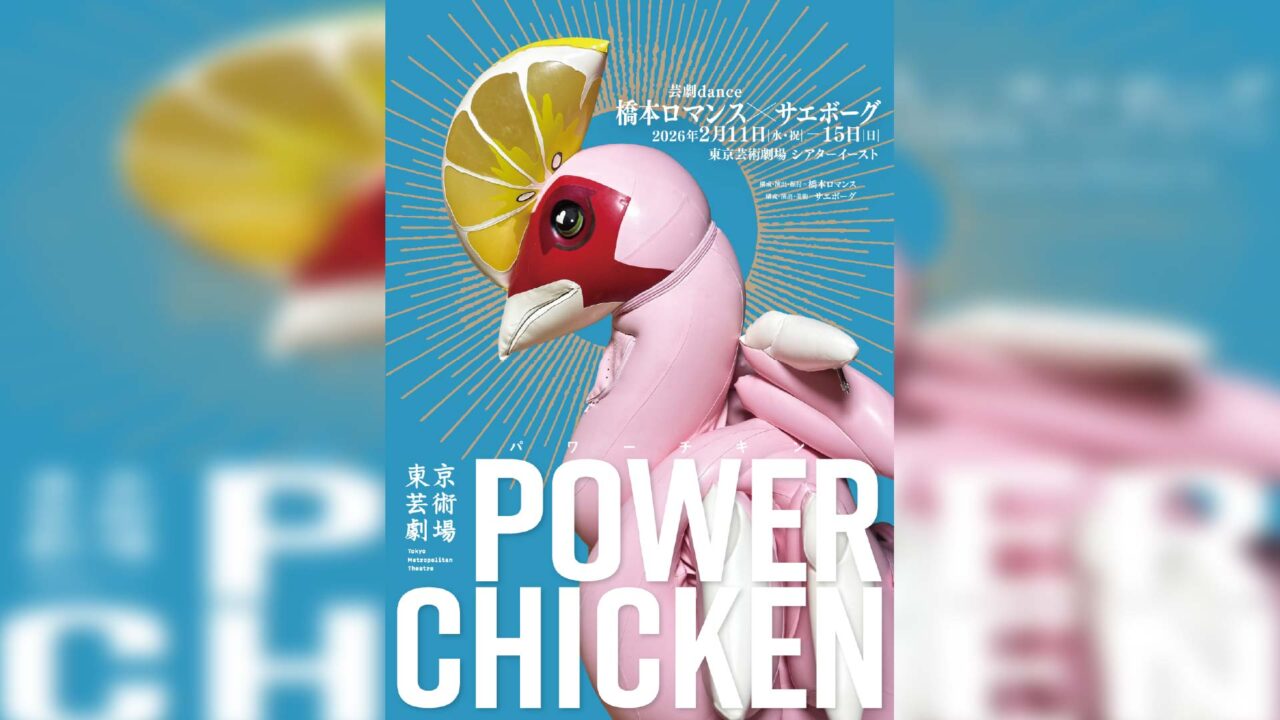ロックバンドにおけるセルフタイトルアルバムとは、絵画における「無題」のような解釈の余地を引き伸ばすための戦略ではなく、自己定義と研鑽の末に到来する最小単位の思念的爆発である。
Gateballersの4作目のアルバム『Gateballers』を再生し、40数分が経過した頃には、その意味がわかるはずだ。
しかしながら、そこにはマッチョイズムの影もなければ、ストイシズムによる肩肘を張った緊張感すらない。バンドのソングライティングを担う濱野夏椰(Vo / Gt)と朴訥としたドラマーの久富奈良(Dr)、2人は様々なメンバーと時間を共有しながら、10年以上も共に航海を続けてきた。その旅程が『Gateballers』では幸福に満ちた表情で刻まれている。
濱野のホームである「伊豆スタジオ」を拠点に、今作はロックのみならずディスコやラテンミュージックも聴こえるバラエティ豊かな1枚に仕上がった。”Tシャツ vs 雨”ではくるりの岸田繁がオーケストラアレンジで参加、その彩りを優美に強調している。
今回はアルバムの骨子を担うバンドとしてのスタンスを紐解きながら、2人に『Gateballers』を解説してもらった。ぜひご一読いただきたい。
INDEX

左から久富奈良(Dr)、濱野夏椰(Vo / Gt)
2013年東京にて結成。サイケデリックかつポップな独自の音楽性で注目を集め、フジロック等の大型フェスにも出演。結成10周年を経て、2026年2月11日にセルフタイトルを冠した渾身の4thアルバム『Gateballers』をリリース。不屈の精神と進化したサウンドを武器に、東名阪ワンマンツアーを皮切りに新たなステージへと突き進む。
10代の頃から変わらない「戦わない」ということ
─去年のインタビューで濱野さんが「次はもう一度、地上に戻ります」とおっしゃっていたんですが、まずはその発言を踏まえた上で、Gateballersにとって今作がどのような位置付けのアルバムになったのかを伺いたいです。
濱野:2020年に事故(※)で手を怪我する前は、「人間より音楽のほうが偉い」って思ってたんです。音楽というアートを歴史の前後や文脈を踏まえた上で、それでも人と同じことをやりたくないというか。メンバーが誰かと同じことをしてたら「ピピピピピピ! (笛を吹くジェスチャー)」みたいな(笑)。自分にも他人にも厳しくバンドをやってたんですよね。
※2020年にバイクによる交通事故により両手首を折る大怪我を負い、その影響で胸郭出口症候群を発症
濱野:だけど怪我をして、自分や他人へのハードルを下げざるをえなくなっちゃって。それ以降のEPでは「みんなが楽しかったら、それでいいよね」っていう一度もやったことがなかったことにトライしたんです。そういう意味で地上に降りたんですよね。

久富:ただ、別に今も丸くなりきってないというか。バンドとして誰でもできることをやってるとは思ってないんです。夏椰さんの内面は変わったかもしれないけど、バンドとしては全然変わってない。
濱野:変は変、だよね?(笑)
久富:うん、変は変。
─どこが変だと思います?
久富:夏椰さんって本当にあらゆることができる⾳楽家なんです。アンビエントとか、実験的なことでも確信を持って良いものを作り上げられる。それができる上でGateballersでは、ポップに落とし込んで開かれていて、かつ誰も聴いたことないものを⽬指してるっていう稀有なミュージシャンだと僕は思っていて。それが変というか、特別なところなんじゃないかと思います。

濱野:Gateballersとは別の場所でプロデュースとかアレンジャーをやってきた経験を踏まえた上で、自分たちの何が変なのかを今考えてみたんだけど……まあ、そもそもこれまで誰かと比較したことがないんですよね。他のバンドと競争も勝負もしてないというか、目指しているゴールがだいぶ違う。
その考えは1stアルバムとか、なんなら10代の頃からあまり変わってなくて。戦わないこと、というか。
INDEX
人類のスピードの更新が、新しいグルーヴとジャンルを生んできたのではないか
─濱野さんは作品を作る上で明確にリファレンスを置き、文脈を踏まえた曲作りをしているじゃないですか。そうした過去の作品を取り込んだ上で、なおも「戦わない」というスタンスを取るために、どのような点を意識しているのでしょうか?
濱野:前提として、日本のバンドをリファレンスに置かないようにはしていますね。その上で、僕がずっと好きだったのは、何から影響を受けたのか全くわからないような音楽だったんです。
それで10代の頃、そういう人になるためにどうするべきか考えてみたんですよね。多分、それは音楽の聴き方を変えることなんです。どの音がどういうトーンで、どういうリズムで、それがどういう旋律で鳴っていて……その中で「なぜ自分はこれが好きなのか?」というのをずっと考えるんです。
そうすると、その曲をその曲たらしめてる要素がわかる。それを抽出して自分の体とか精神に落とし込んで曲を作ると、新しいものができるんですよね。そういうことをずっとやっています。

─そうしたポイントはバンドに落とし込む際にメンバーとどの程度共有するんですか?
濱野:できるだけ伝えますね。
久富:今回のアルバムではタイム感の話をよくしました。曲を印象付けるグルーヴの間があって、それを意識しました。
濱野:1曲ごとに「乗り物」を決めてね。
─乗り物?
濱野:乗り物の更新って人類のスピードの更新じゃないですか。スピードが更新されるたびに新しいグルーヴが生まれて、ジャンルも生まれてきたと思うんです。カントリーもロカビリーも、馬とかハーレーとか移動のスピード、グルーヴと関係があると思ってて。
─アルバムの1曲目“Get Back”は排気音から始まりますね。
濱野:“Get Back”のイメージとしてはバイクのグルーヴなんです。でも、ギターはケルトチューニング(※)で。それって誰もやってないじゃないですか。
※アイルランドの伝統音楽で使用される変則チューニング
─チューニングはケルト風だけど、世界観やグルーヴは映画の『イージー・ライダー』のようなアメリカの景色が元になっているというか。しかも明確なアンセムですよね。
濱野:スタッフの人たちとシングルにする曲を決めた時、「絶対これでしょ」と言ってもらえました。
─<Get back to the morning>と歌われていますが、どういうイメージだったのでしょうか?
濱野:失った経験から<Get back>と歌ってるんです。失ったことによって人生の天井が見えて、それで苦しむかもしれない。けど、また何にも知らないような朝が来る。だからあの頃の朝を迎えていた自分を取り戻そうという、そういうことです。

INDEX
「嫌いなんだよね、日本の“ロック”っていう言葉が持っているマッチョイズムみたいなものが」
─“Get Back”では<泣く子も黙る rock ‘n’ roll music>と歌っているように、古今東西の様々な音楽に触れた上でその救済を成し遂げられるのがロックだと考えた節はありますか?
濱野:えっと、ない。嫌いなんだよね、日本の「ロック」っていう言葉が持っているマッチョイズムみたいなものが。だから、すごく弱そうな名前として「Gateballers」を名乗っているし、『ジョンの魂』(※)についてよく話しているんです。
濱野:今回、生々しく素直になりたかったんです。そもそもグランジってマッチョイズムへのアンチテーゼじゃないですか。ルッキズムに対して全く呼応してないのにPixiesがかっこいいのは「真実」に近いと子供ながらに思っていました。だからマッチョイズムに対してのアンチテーゼは、音楽をやる上でずっと提示してます。
それは子供の頃に引っ越しが多くて、家庭環境、生活環境が周りと違うことで孤立したのが要因の1つだと思う。当時は、カート・コバーンやジョン・レノンのように、バンドという形態であっても独りで戦ってるような人に救済を感じていました。

濱野:当時は「ロックンロール=1950年代の音楽」と明確に思っていたので、「パンク」や「グランジ」みたいなカテゴライズするような言葉を嫌悪してました(笑)。パンクはジョニー・ロットン、グランジはカート・コバーンだけ、みたいな。THE BLUE HEARTSもThe ClashもPearl Jamも「大好きな優しくてカッコいい音楽」でしかなかった。
─それは今作がセルフタイトルであることとも繋がりますか?
濱野:そうですね、「『Gateballers』ってジャンルは何?」って質問されると困ってしまう自分がいるんです。メディアが売るためにつけるラベルの中に自分たちを内包することは自傷っぽくて嫌だった。
そこで「俺たちは俺たち」って言うために、偉大な先人たちがセルフタイトルを掲げるというルールを作ってきたように自分たちもやりたいと思って、ポジティブな理由でセルフタイトルにしました。