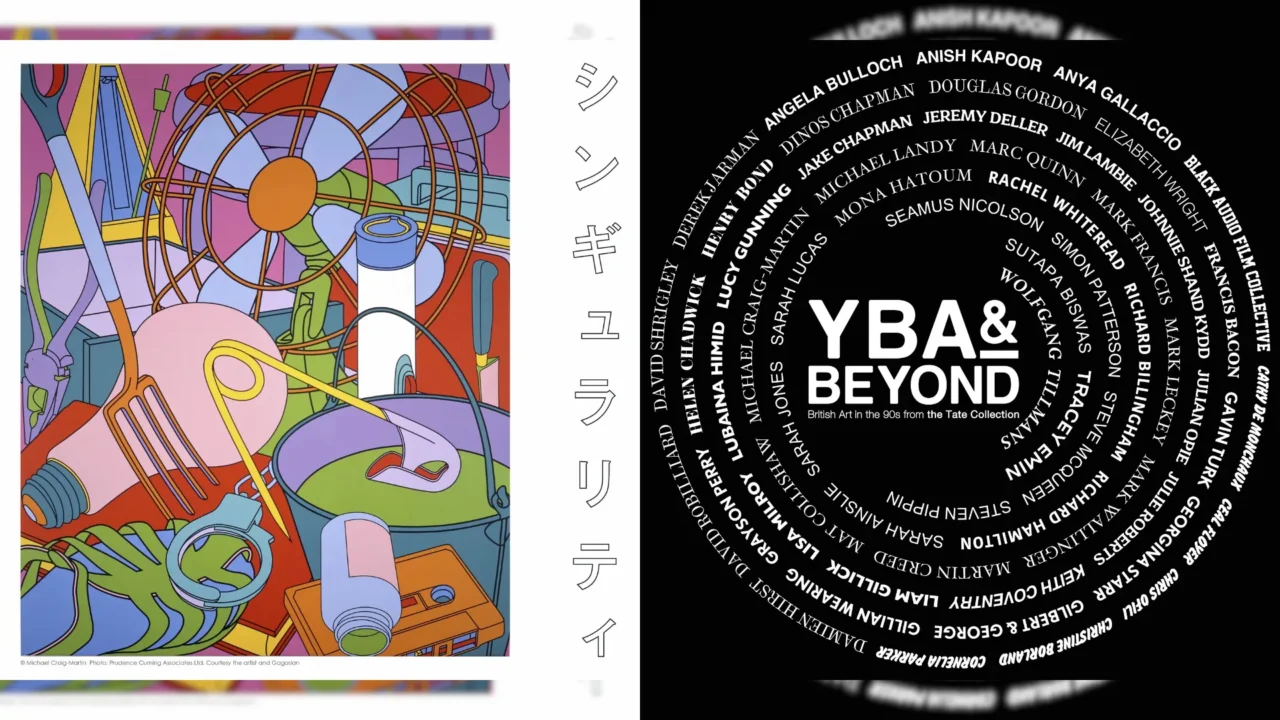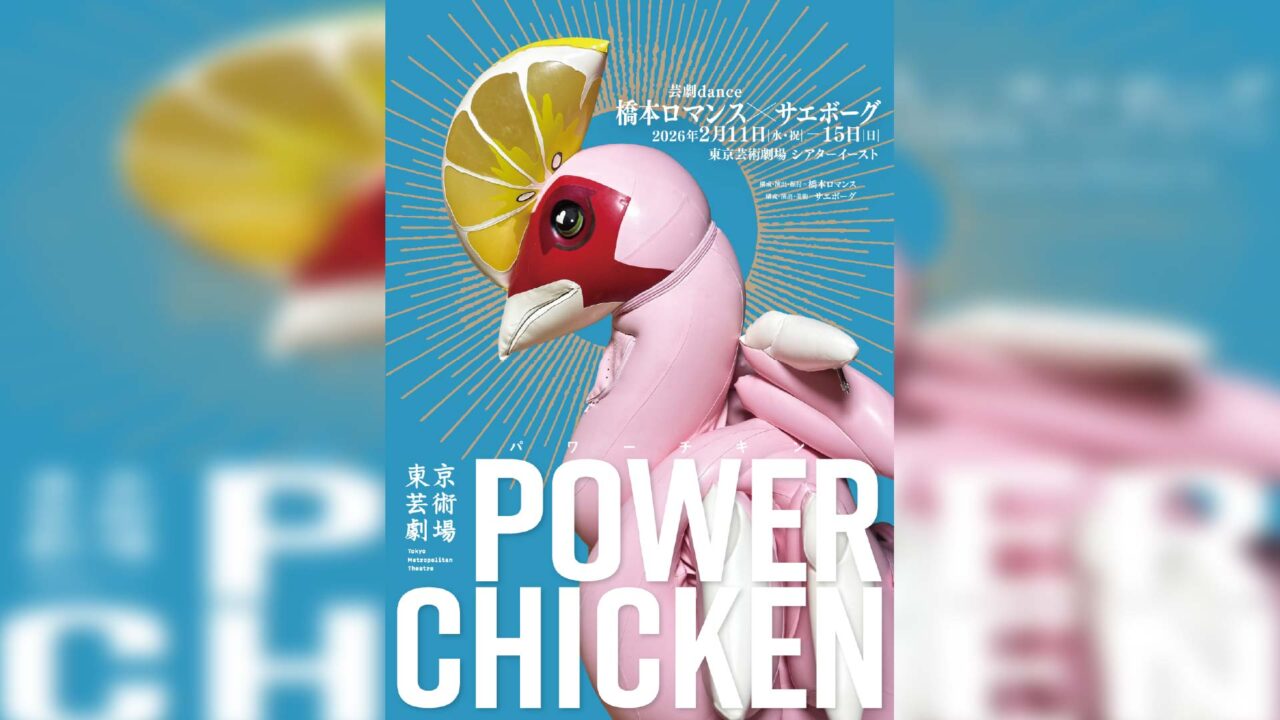渋谷の街を舞台にしたアートとテクノロジーの実験的プロジェクト、『DIG SHIBUYA』。
「渋谷まるごと、ART×TECHの実験中」を掲げ、2月13日(金)から15日(日)の3日間にわたって開催される本プロジェクトは、単なる展示の枠を超え、街の公共空間そのものを「実験場」へと変貌させる。
ハチ公前広場や公園通りをはじめ、渋谷の至る所で同時多発的に展開されるプログラム。大型ビジョンをジャックした映像表現や「街の劇場」など、そのどれもが、そこに訪れる人々の体験や参加が加わって初めて完成を迎える。
行政とクリエイターの間に立ち、現場で実装を担うSHIBUYA CREATIVE TECH実行委員の宮本安芸子。そして、アートの視点から街に新たな問いを投げかける公募プログラム選定委員の久納鏡子。プロジェクトの核心を握るキーパーソン2人が、開催直前の渋谷で、この街の「今」と「未来」を語り合った。
INDEX
通過するだけの街を、探求する街へ。行政と表現者が共に「公共をこじ開ける」挑戦
ーまずは『DIG SHIBUYA』というプロジェクト名について。なぜ「DIG(掘る)」という言葉を選ばれたのでしょうか。
宮本:「DIG」という言葉を採用したのは、DJが名盤を掘り起こす「ディグる」という行為が、渋谷の音楽カルチャーと深く共鳴するからです。今の渋谷、特にスクランブル交差点などは人が滞留してしまい、なかなかスムーズに流れていかないという課題があります。そうした中で、来街者の皆さんがただの通過点としてではなく、好奇心を持って街を「探求」する。そんな能動的なアクションを引き出したいという想いから、「渋谷をディグる(DIG SHIBUYA)」という言葉を掲げました。

渋谷区国際都市戦略特命部長、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員。広告会社にて、外資系クライアントのブランド戦略やコミュニケーション業務に従事。約20年にわたる民間経験を経て、2020年渋谷区役所に入庁。産業振興、文化政策、スタートアップ支援などを担う産業観光文化部の部長として、DIG SHIBUYAにも携わる。2025年8月に渋谷区国際都市戦略特命部長に就任。国際都市・渋谷としての戦略的シティプロモーションをはじめ、スタートアップ支援や都市データ活用などのプロジェクトを牽引。グローバルな視点と高い調整力を活かし、チームを率いて渋谷の都市戦略を前進させる存在。民間・行政双方の経験を融合させ、渋谷の未来像を描いている。
ー『DIG SHIBUYA』において、街への実装を担う宮本さんと、アーティストの視点から実験的なエッセンスを加える久納さん。それぞれの立場から、これまでの歩みに対する感想をお聞かせください。
宮本:私たちは「実証実験を街にインストールする」ということをコンセプトに掲げ、2024年に第1回を主催しました。回を重ねるごとに、その輪が着実に広がっている手応えを感じています。
毎年、一般公募に集まる参加希望団体のプロジェクトも、単に「イベントに参加する」という受動的な意識ではなく、「自分がずっと試したかった実験を、渋谷というフィールドで実現したい」という強い想いを持って、多様なアイデアを持ち込んでくださるんです。
それを私や事務局のメンバーが、実際の街のルールや環境の中でどう展開できるか、一つひとつオーガナイズしていく。主催者、表現者、区民や来街者までもが主体的に関わってようやくひとつの作品となる。それが『DIG SHIBUYA』の個性だと思います。
久納:人が多いからこそ、多様な利害関係が渦巻く渋谷の公共空間を自由に活用できる状態にすることは、極めてハードルが高い。そこを行政がゼロから関わることで、どうやってこじ開け、表現者や市民に提供していくのか。『DIG SHIBUYA』を通して「街がひらかれていく様」を定点観測していくことに、大きな意義と魅力を感じています。

アーティスト、アルスエレクトロニカ・アンバサダー。『DIG SHIBUYA』公募プログラム選定委員。これまでインタラクティブアート分野における作品を手がける一方、公共空間、商業スペースやイベント等での空間演出や展示造形、大学や企業との共同技術開発など幅広く活動している。作品はポンピドゥセンター(フランス)、SIGGRAPH(アメリカ)、文化庁メディア芸術祭など国内外で発表。東京都写真美術館(日本)に所蔵。
INDEX
「個人の実験」を「街の表現」へ。求めるのは、公共空間を実験場にするための覚悟と責任
ー『DIG SHIBUYA』の開催期間中、毎年様々なプログラムが行われていますが、一般公募の中からどういった基準で選考しているんですか?
宮本:『DIG SHIBUYA』は、渋谷区役所だけではなく渋谷区商店会連合会の会長がトップを務める実行委員会を編成しており、まさに街全体が主体となって公募を行います。今年は国内外から約60団体のエントリーがあり、久納さんをはじめとする選考委員の方々によって、最終的に11団体のプログラムが選ばれました。
選考において私たちがまず重視しているのは、「実行能力」があること。どんなに素晴らしいアイデアでも、複雑な都市空間である渋谷で展示まで辿り着けなければ意味がありません。実現性と新規性の両立、そして何より、最後までやり遂げる力は、大きな評価ポイントになっています。
久納:実行委員会の方々にとって、公共空間を実験の場として提供することは、同時に、その「責任」も引き受けることを意味します。ただ「自分が実験をしたいから」という動機だけではなく、それを実行委員会や来街者とどう一緒に作り上げ、共有できるか。そうした「コラボレーション」の視点を持っていることは、とても重要な要素だと思います。
あとは「渋谷らしさ」ですね。ファッションやストリートカルチャーが根差している渋谷で、「ART x TECHの実験中。」というテーマに対して皆さんが興奮してくれるクオリティであるか。そして、その作品を通じて対話を促す要素を持っているか。そういったことを総合的に考慮して選考しています。
宮本:また、海外からの応募も毎年驚くほど多く、今年も半分以上が海外からのエントリーでした。やっぱりスクランブル交差点で自分の作品を出してみたいという思いは、海外のアーティストにとって非常に強いようです。彼らにとっての渋谷は、どこかサイバーパンク的な雰囲気を感じさせる象徴的な場所。あの風景の中に自分の作品を置きたいという、熱意のこもったレターをいただくんです。
ー海外のクリエイターにとっても、渋谷はアート表現の場として魅力的な場所なのですね。
宮本:特に象徴的なのが、スクランブル交差点にある大型ビジョンをジャックするプログラムだと思います。深夜の1時間、すべての広告を止めて、アーティストの作品だけを放映する。普段は商業広告しか流れないビジョンをアートに開放するという具体的なアクションが、強烈なアイコンになっているみたいです。

2/13(金)・14(土)24:00~翌1:00 at 渋谷スクランブル交差点前
INDEX
ただ見るだけでは終わらない。「対話エレクトロニカ」で更新するアートの理解の仕方
ー世界には『アルスエレクトロニカ』(※)のようにアート×テクノロジーの有名な祭典がありますが、日本、あるいは渋谷でこの試みを行うことの独自性はどこにあると思われますか?
久納:アルスエレクトロニカは、アート / テクノロジー / 社会という3つのコンセプトを基軸に未来を考えるフェスティバルですが、日本の場合は、アートという入り口だけではない「クリエイティビティの高さ」や「純粋な技術への追求」が土壌にあると感じます。
また、特定の学問やジャンルに縛られることなく、多様なカルチャーが雑多に混ざり合っていることも日本の、特に渋谷の大きな魅力です。『DIG SHIBUYA』の面白さは、アートやテクノロジーの専門家ではない「たまたまそこに居合わせた人」までもが実験に巻き込まれ、体験を共有できる点にあるのだと思います。
※オーストリアのリンツ市を拠点に45年以上にわたり「先端テクノロジーがもたらす新しい創造性と社会の未来像」を提案し続けている、世界的なクリエイティブ機関。『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』は、1979年に電子音楽の祭典として始まった世界的なメディアアートの祭典。
ー日本では「アートは少し敷居の高いもの」という意識がまだ根強く、自ら美術館に足を運ぶ人は限られているかもしれません。けれど、渋谷の街そのものが会場であれば、日常の中で「たまたま居合わせる」ことが、そのまま参加への入り口になります。アートを特別なものと捉えがちな日本だからこそ、この「偶然の出会い」を設計することに、『DIG SHIBUYA』の大きな意義があるように感じます。
久納:そうですね。海外の、例えば美術館が日常の散歩コースにあるような環境では、確かにアートが生活に溶け込んでいます。ただ、そこで何より大切だなと思うのは、アーティストが提示したステートメントに対して、「自分はどう思うか」を誰かと喋る文化があることです。
アートは決して特殊な分野ではなく、みんなで一緒に考えたり、今までのものの見方を変えたり、新しい物事を体験を通して楽しむことができる「きっかけを生み出す装置」なんですよね。そうした視点が日本にも根付いていけば、もっと多くの人が「自分も表現に関わりたい、やってみたい」と思えるようになるはず。『DIG SHIBUYA』は、まさにそのための実験場でもあるんです。

2/15には、三島賞作家である中原昌也の全小説から学習した「AI作家」と対話しながら共著できる自由参加型ワークショップも。
ー実際に過去2回開催されて、参加者の声や反応はいかがですか?
宮本:神南小学校をはじめ、渋谷周辺の小学校のお子さんや先生方も、イベントを楽しみにしてくださっています。今回は公募団体のプログラムとして「無人オーケストラ」という展示があるのですが、これは部屋に並べられた24台のスピーカーから、オーケストラを構成する各楽器の音がバラバラに流れてくるというプロジェクトです。

宮本:スピーカーの周りをうろうろすると、ある場所ではバイオリンの音が聞こえ、別の場所ではチェロの音が聞こえる。そんな「オーケストラの中を巡る」新しい音楽体験ができるんです。このポスターは、子供たちが実際に楽器に触れながら絵を描くワークショップを通じて一緒に作り上げました。こうした活動を通じて、渋谷周辺にゆかりのある人々の間には、着実に『DIG SHIBUYA』が根付き始めていると感じています。

ーただ参加するだけでなく、より深い「体験」への工夫もされているのでしょうか。
宮本:そういった鑑賞の工夫として、今回は「対話エレクトロニカ」というプログラムを初めて実施します。これは専門のファシリテーターによる「対話型鑑賞」を取り入れたもので、参加者同士で感想を話し合いながらアートを巡る試みです。
ただ、『DIG SHIBUYA』が投げてくるボールって、内容のエッジが効きすぎていて、対話が盛り上がりすぎてしまうんじゃないかと少し心配しているんです(笑)。それくらいダイレクトで刺激的な表現がいっぱい投げ込まれますから。みんながどう捉えるかを私たち自身もすごく楽しみにしています。

2/13 fri~14 sat 10:30〜約3時間 at 渋谷区勤労福祉会館 2F 第2洋室 ※事前予約制。詳細はこちら
久納:最近は日本の美術館でもファシリテーターが介在することが増えましたが、新しいものに対して「自分の疑問に寄り添ってくれる存在」がいる鑑賞体験は、これからどんどん重要になってくると思います。
今の世界は先行きが不透明で、何が正解なのかが分かりにくい。だからこそ、どうやって自分自身で考えられるようにするか。そのヒントとして、対話型のツアーを通じて「新しい体験の仕方 / 理解の仕方」を街の中で提供することには、大きな意味があると考えています。