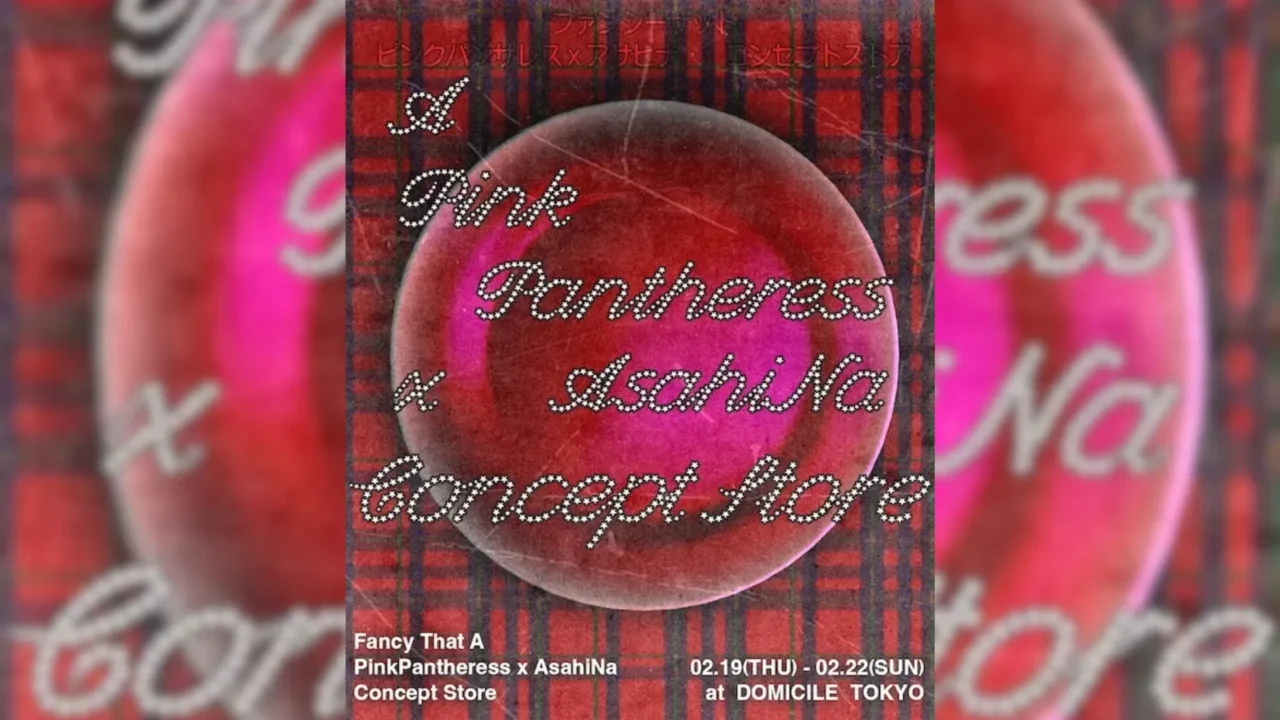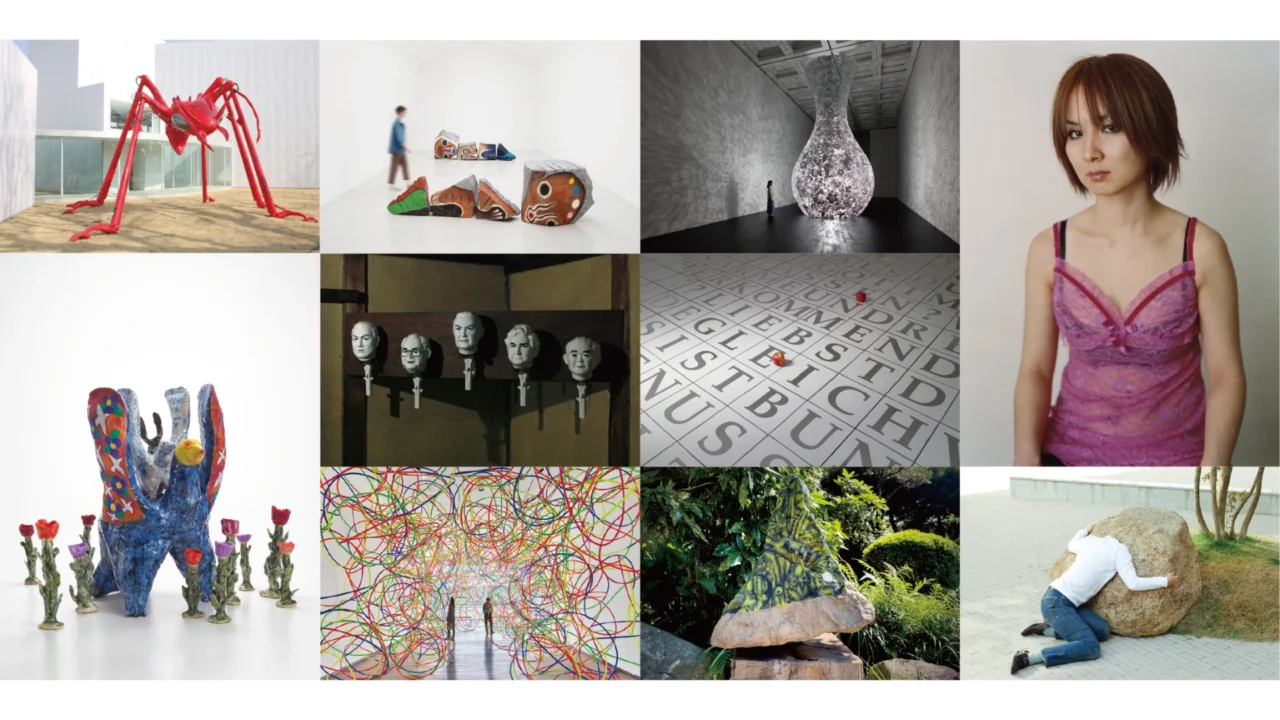2022年の『Betsu No Jikan』以来約3年ぶりとなる岡田拓郎のオリジナル新録アルバム『konoma』が、米ロサンゼルスを拠点とするレーベル・Temporal DriftとISC Hi-Fi Selectsから共同リリースされた。
前作における即興演奏と編集の高度な融合を更に深化させつつも、その聴き心地の面においてより親しみやすい内容となった本作『konoma』。だが、当然ながら単に「ポップ」になったと評してしまえば話が済むようなものとは異なり、きわめて重層的で、聴く者の探究心を焚き付けてやまない奥深さを備えた内容となっている。
アルバムのタイトルが、岡倉天心の代表的な著作である『茶の本』の中に引かれた言葉=「木の間(このま)」から取られている事実が示唆するように、それはまさに、現代を生きる一人の日本人ミュージシャンである岡田拓郎自身が、自らの音楽的 / 文化的アイデンティティの来し方行く末を様々な事象の間から見つめ、そうしたまなざしの元に立ち現れた多様な音のイメージを、ブリコラージュ的に構築してみせた作品といえるだろう。
エチオピア音楽、日本〜ヨーロッパ〜米国のジャズ、ブルース、アンビエント、ビートミュージック……ここに織り込まれた音楽の片鱗は、ただそれが集められ混ぜ合わされるだけには留まらず、お互いの間に「有り得た」接続の回路を、想像的に浮かび上がらせていく。
岡田は、どのような企図の元に本作を作り上げたのか。ブラックミュージックを「借用」することにまつわる自省的意識や、この間の海外滞在体験、更には現代美術家のシアスター・ゲイツによる「アフロ民藝」なる概念から得たもの等について、じっくりと語ってもらった。
INDEX
「“So What”の導入部がずっと続いていたらいいのに」
―今作のアイデアはいつ頃から出て来たんでしょうか?
岡田:いつだったかな……前作の『Betsu No Jikan』を出して以降、プロデュースやらサポートでずっと動いていた感じなんですが、その合間にmaya ongakuに声をかけてもらってWWWでライブをやることになったんです(※)。そこで、漠然としたイメージでしたが、ウィリー・ディクソンのベースラインがミニマルに反復する中で、和声的にも旋律的にも自由な状態で、それがギリギリのところでジャムにならない音楽……みたいなアイデアがあって、その脳内イメージをメンバーと共有するために「アンビエントブルース」という言葉を使っていました。それが最初のきっかけの一つになっていると思います。
※筆者注:2023年8月10日に開催されたmaya ongakuと渋谷WWWの共同企画『rhythm echo noise』
―私もそのライブを観させてもらいました。即興的でありながら、かといって12小節ブルースの定型的なものとも違う、文字通りアンビエント風のアメリカーナ音楽というか……とても興味深い演奏でした。岡田さんにとっては、やはりブルースは大きなルーツの一つなんですよね?
岡田:そうです。中学生の頃は本当にブルース漬けで、レコードを聴くのはもちろん、地元のブルースクラブでセッションに参加したり。

1991年生まれ、東京都福生市育ち。ギタリスト / ソングライター / プロデューサー。2012年からバンド「森は生きている」のメンバーとして活動。解散後、ソロ活動を本格的に開始する。ソロアルバムに『ノスタルジア』(2017年)、『MORNING SUN』(2020年)、サム・ゲンデル、カルロス・ニーニョ、細野晴臣らも参加した『Betsu No Jikan』(2022年)がある。また、ギタリストとして、優河、柴田聡子、ROTH BART BARON、never young beachなどのレコーディングやライブに参加している。
―けれど、プロになってからはそういう「これぞブルース」というような作品は作っていないですよね。
岡田:心の奥底ではいつでもブルースを演奏したい気持があるんですけどね。でも、知れば知るほど、当時のアフロアメリカンの人たちの文化や歴史的な背景と密接に結びついていたことが分かってくるので、そこからは全く隔絶した時代・環境にいる自分が、そういう存在であるブルースを形式的になぞって演奏することにどうしても躊躇してしまうんです。これは、今に至るまでずっとそうなんですけど。そうした時、『Betsu No Jikan』で試みたような、ミニマルで即興的な演奏をモードジャズ〜アンビエント的な発想とともに行うというやり方に、ブルースの中にあるムードやミニマリズムを接続することも可能だろうかと考えたんです。
―たしかに、あの日の演奏もミニマルなフレーズの反復によって展開していくような感じでしたね。
岡田:以前からいろんなところで言っていることなんですが、マイルス・デイヴィスの“So What”の導入部がずーっと続いていたらいいのに、とか、マジック・サムのワンコードのブギが永遠に続いているのを聴きたい……みたいな欲求があって。それを自分なりに具現化してみたらああなったんです。そもそも、昔の自分がブルースのレコードに強烈に惹かれていたのも、そういうムードの部分だったような気がするんです。Chess Recordsのレコードのものすごいリバーブ感とか、カントリーブルースの幽玄な音像だとか。ああいったものは、実際の生演奏とは違う録音物ならではの音響でもあるわけで、そういう部分にもとても惹かれましたね。
―今回のアルバムでも、例えば“November Owens Valley”などには、そういう「アンビエントブルース」的な発想を感じます。
岡田:そうですね。今話していて思い出したんですが、ある集いでやけのはらさんに会う機会があって、そこで色々とお話した経験も大きかったですね。やけのはらさんとしても、ビートを作るときには異文化から借りてきている感覚があるんだけれど、不思議とアンビエントを作っているときはそういう感覚から解放されるんだとおっしゃっていて、すごく共感できる話だなと思ったんです。自分がブルースとアンビエントを結びつけて考えていたのも、もしかしたらそういう開放感を感じていたからかもしれないな、と。
―なぜそういう風に感じたんでしょう? アンビエントというのは、現代音楽のスキームとも縁の深いある種の理知的なコンセプトでもあるわけですけど、ひょっとすると、そういう「非民俗性」みたいなものが関係していたんでしょうか?
岡田:もしかしたらそれもあるかもしれないし、色々要因は考えられるでしょうね。その答えの一つとしては、おそらくその音楽的な柔軟さに起因している気がします。アンビエント一般のシンプルな音階と、反復性、ノンビートなゆらぎ、素朴なメロディーやハーモニー、そういう要素は世界中の土着的な音楽の中に様々な形で見出すことができるものだし、だからこそ世界中の音楽ともコネクトできるんだろうな、と。逆に、アンビエントという概念をブライアン・イーノが提出する前から、アンビエント的なムードを纏った音楽というのは現代音楽の畑に限らず沢山あるし、色々な文化の中に自然に溶け込んでいるものでもあると思うので。

INDEX
Ras G、Madlibからの影響をミニマリズムの発想で
―その一方で、“Galaxy”のように、ビートミュージック的というか、先鋭的なインストゥルメンタルヒップホップのような曲が入っていたり、アンビエント的なものとは異なる色彩もありますよね。このあたりの要素はどこからやってきたものなんでしょう?
岡田:これは単純に、そういう音楽にめちゃめちゃハマったというのが大きかったですね。Ras Gとか、Madlibとか、その辺りを集中的に聴いていて。やけのはらさんに話しかけたのもまさにその辺りの音楽についておしゃべりしたいなと思ったからなんです。けれど、ああいったものも、かなりアフロセントリックな要素のある音楽だと思うので、ブルースの場合と同じで、やっぱり僕がそのまま真似をすることはできないなと感じていて。というか、順番で言うと、Ras G等を沢山聴く中で、ブルースの他者性についてもう一度真剣に考えるようになったという流れでした。なので、自分なりにビートミュージックの影響を消化するにあたっても、表面上はアンビエント的な静謐さとは違うけれど、やっぱりミニマリズムの発想からアプローチしてみたいと思ったんです。
―この10年あまり、J・ディラの再評価が大きく盛り上がったりもしましたけれど、ああいう動きは追っていなかったんですか?
岡田:あの頃はむしろ逆張りしてほとんど聴かなかったんですよ(笑)。Ras Gを聴こうと思ったのも、そういうインストゥルメンタルヒップホップ再評価の流れというよりは、ファラオ・サンダースの曲のイントロだけがずっとループしていたら最高だろうなと考えたことがきっかけでした。「あ、そうか、Ras Gのビートがまさにそれなんじゃない?」と気づいて。あとは、レコード好きの一人として、過去の遺産がこういう形で引き継がれていくという文化的な部分の魅力が、実感として理解できたというのも大きかったですね。
―サンプリング等のマテリアルな操作の蓄積が、アウラのようなものを逆転的に出現させるという……?
岡田:そういう事も起こり得ると言いますか。
―岡田さんはこれまでも『Betsu No Jikan』でマイルス・デイヴィス作品におけるテオ・マセロの手法にインスピレーションを得た編集を行っていたり、そういうエディット的な曲作りも既に実践していたわけですよね。その経験がサンプリングミュージックに対してより強い関心を持たせることに繋がったんでしょうか?
岡田:それは少なからずあると思います。確かに『Betsu No Jikan』でも、ある曲で録音した演奏を切り分けたり変調させて別の曲で使うようなサンプリング的なアプローチをしていましたけど、改めてJ・ディラをじっくりと聴くと、本当に信じられないようなところからサンプリングソースを拾ってきたりしているじゃないですか。しかも、その使い方が全く定型的でなはない。とにかく、音楽が躍動している。サンプルの編集で成り立っているはずなのに、各音の要素が点で存在するんじゃなくて、流れで捉えられている。マテリアルな現象としては点の羅列で成り立っているはずなのに、点と点の間に濃密な空気がある。これまで熱心に聴いていなかったのもあって、それがすごく新鮮に感じました。
―今回のアルバムには、石若駿(ドラムス)、松丸契(サックス)、マーティ・ホロベック(ベース)などジャズの分野で活躍するミュージシャンが参加していますが 、プレイヤーの皆さん誰一人として同時録音をせずに、パートごとバラバラに録音したそうですね。音を聴くだけは到底信じられない気がします。しかしなぜそういう作り方をしようと思ったんでしょうか?
岡田:これまでの自分のキャリアを振り返ってみても、自分の音楽って、どこかの枠組みにはどうしても収まり難くて、常に何かの中間に漂っているものに感じるんです。だから、今回はそれを改めて自覚した上で、手法の面でも、集団即興に全振りするわけでもなく、かといって、すべてコンピューターで完結させるわけでもない、中間的なものをやりたかったんです。そういう中間性への意識というのは、文化的な次元でも同じで、ブラックミュージックに振り切れることがないのはもちろん、かといって日本の伝統文化に振り切れるわけでもないんです。あとは、完成度という意味でも、振り切れた完全・完璧を狙わないというのも心がけました。

INDEX
「“民藝”の思想を知ってしまうと、コピー&ペーストなんてできない(笑)」
―確かに、彫琢を極めたサウンドというよりも、ブリコラージュ的な当意即妙の感覚が強く息づいていると感じます。編集を駆使しているにせよ、コピー&ペースト的手法に基づいた整然とした作りとはかけ離れていますよね。
岡田:ある要素を反復させるにしても、一回テープに入れて、若干リズムがよれるようにして、寸分の狂いのない同じパターンが単に繰り返されるのを避けています。そのあたりはまさに「民藝」の発想と繋がっている部分だと思います。手仕事を尊重する「民藝」の思想を知ってしまうと、手間の省略のためのコピー&ペーストなんてできないので……(笑)。1年半位の期間にわたって、ずーっとコネコネとセッションデータをいじっていたと思います。結果的に最初の形からパッと聴きだと全然変わっていない曲もあったりするんですけど、今回はそうやって手仕事的にいじり続けることも、アルバムを作る目的の一つでもあったような気がします。
―「民藝」というキーワードが出たところで伺いますが、今回のアルバムの重要なモチーフの一つである「アフロ民藝」と出会ったのは、どのくらい時期だったんでしょうか?
岡田:去年(2024年)の夏に六本木をブラブラしていたら、たまたま森美術館で『シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝』という題の展示をやっていて。その時点ではシアスター・ゲイツの名前も全然知らなかったんですが、興味本位で覗いてみたんです。そうしたら、あんなに長い時間美術館の中にいたのはあの日が初めてというくらいに、すごくハマってしまって。
アフロ民藝というのは、その名の通りアフロアメリカンの公民権運動のスローガンでもあった「ブラック・イズ・ビューティフル」美学と、柳宗悦が提唱した日本の民藝の考え方を融合させたものなんですが、まさにその頃に抱いていた関心事――アフロアメリカンと日本人が接続できる可能性――がこういった形でもあるのかと。色々な展示物を順路に沿って鑑賞していく体験ももちろん刺激的だったんですが、その中で突然、酒場というか、クラブみたいな空間が現れる構成になっていて。それが、いい意味で拍子抜けしてしまうというか、コンテクストを厳しく問い詰めるというよりも、もっとフレンドリーな楽しさに包まれた空間に感じられたんです。そして、その親しみやすさこそが、自分の中にある民藝的なものへの関心を促してくれているようにも感じられて。
―そういう体験を経て、今度はアフロアメリカンの音楽文化の中に隠された日本的、東洋的なものに意識が向くようになった、と?
岡田:そうですね。元々、ファラオ・サンダースやビリー・ハーパーのようなスピリチュアルジャズ系の音楽家のアルバムに日本的なモチーフが溶け込んでいることに関心を持っていたんですが、あの展示をきっかけに、よりはっきりと両者の文化の交差可能性について考えるようになりました。展示のミュージアムショップでイターシャ・L・ウォマックの著作『アフロフューチャリズム ブラック・カルチャーと未来の想像力』を買って読んだのですが、アフロアメリカンの人たちが、ブラックカルチャーの有り得た未来を想像する実践を重ねてきたことを知る中で、自分としては、そういう想像力が日本の文化と融合し得た可能性を更に探求してみたいと思うようになったんです。そして、その実践の仕方として、ことさらシリアスかつ自己否定的になりすぎるのではなくて、アフロ民藝展で見たあのクラブ空間のように、あくまで親しみやすい形でできないかなと考えるようになっていったんです。
―その言葉通り、今回の『konoma』は前作と比べてだいぶ親しみやすくなった印象を受けます。
岡田:ガチガチに論理立てて厳密に構築していくと、今話したような「あり得た未来」の想像可能性をむしろ減殺させることにもなってしまうんじゃないかと思っていて。翻って、J・ディラも、あの流れるような親密な音楽によって、ある文化とある文化が接続される可能性を音として具現化していたんじゃないか、と考えるようになりました。そうやって、シアスター・ゲイツ展での経験と「アフロ民藝」という概念を軸に、今まで考えていたこと、やろうとしていたことがどんどん繋がっていったんです。