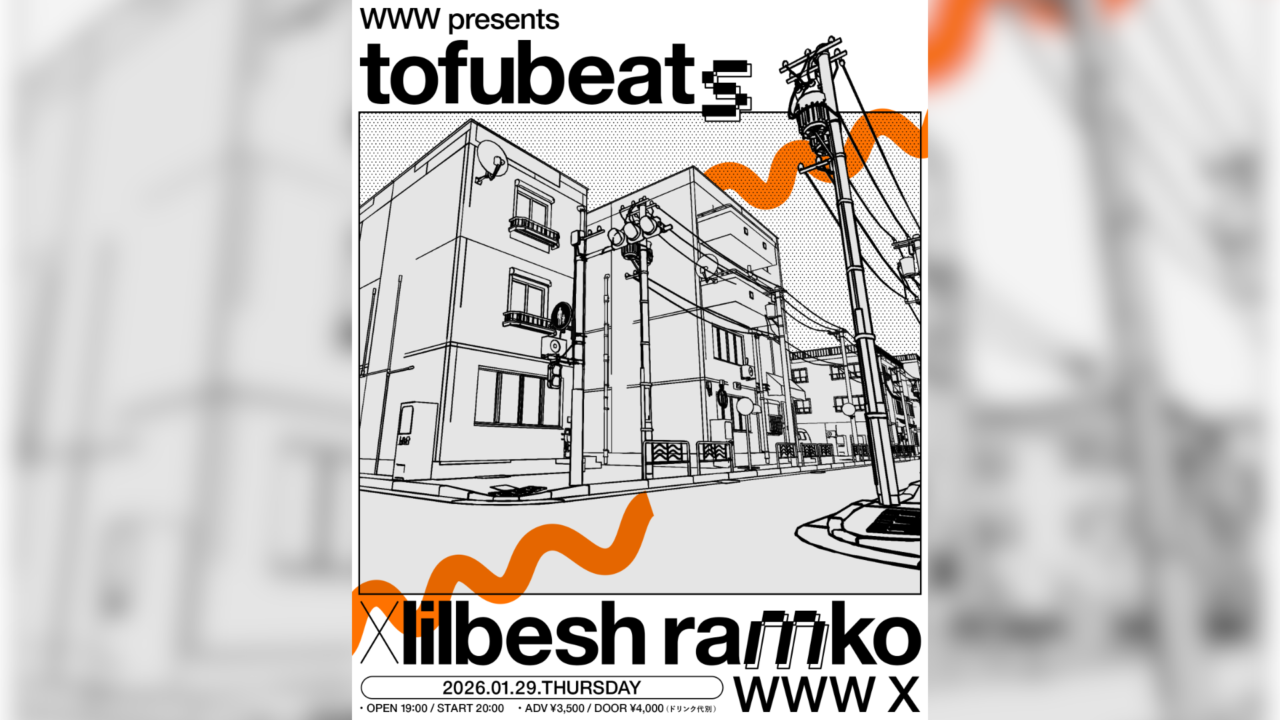記録やデータの長期的保存を意味する「アーカイブ」。舞台芸術においてはコロナ禍以降、舞台映像の配信が増えるなど、記録の活用はますます多様になっている。公演映像や、戯曲、ポスターやフライヤー、チケット、衣装、舞台装置図、舞台写真、劇評……。その舞台がどんなものであったか、記憶や想像を「知」に換える資料は実に多岐に渡る。それらは、まだ観ぬ新たな舞台作品の創作のきっかけになることもあれば、時にはジャンルやメディアを横断し、映画やドラマに活用されることも。かくいう私も戯曲や公演映像など多くのアーカイブに支えられながら、新たな舞台作品にまつわる取材 / 執筆活動を行なっている一人である。
単なる過去の記録 / 保存ではなく、未来の想像 / 創造のタネにもなり得るアーカイブ。その意義や可能性を紐解き、実践と活用に繋げていくための講座『舞台芸術アーカイブ講座 2025』がリアルタイムとオンデマンドで展開されるという。オンデマンド受講募集に際して、「戯曲デジタルアーカイブ」の立ち上げに携わり、劇作家 / 脚本家としても幅広く活躍している長田育恵と、一般社団法人EPAD(舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業)理事で早稲田大学教授の岡室美奈子の対談を実施。アーカイブがなぜ必要なのか、どのように役に立つのか、実践者としての感触も踏まえて話を聞いた。
INDEX
朝ドラ『らんまん』はアーカイブを巡る物語?
―長きにわたって舞台芸術を中心とした作品に携わる中でお2人が「アーカイブ」の重要さを感じるのはどんな時でしょうか?
長田:これまで多くの評伝劇(※)を書いてきたのですが、どの作品も沢山の資料に当たって執筆を進めました。演劇の戯曲でもドラマの脚本でも重要なのは、「その時代を生きている人たちの生活を描く」ということなんですよね。だから、登場人物にまつわる資料だけでなく、当時の作家が残した日記や手記、芝居の台本などにも当たり、やりとりや空気感を通じて時代や生活の様相を見ます。少し極端な例ですが、第1作目の『ゴジラ』(1954年)には電車に乗っている市民がゴジラを噂しながら「(せっかく長崎から逃げてきたのに)やーね。原子マグロだ放射能雨だ。その上今度はゴジラと来たわ」と言うシーンがあって……。私はそこにすごく衝撃を受けたんですよね。
※井上ひさしなどに代表される、歴史上の人物や、実在する人物をモデルとして脚色する演劇のジャンル。

劇作家・脚本家。東京生まれ。早稲田大学第一文学部文芸専修卒。2007年に日本劇作家協会・戯曲セミナーに参加し、翌年より井上ひさし氏に師事。09年、劇団「てがみ座」を旗揚げ。15 年、てがみ座『地を渡る舟』にて文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞。16年に演劇ユニット「る・ばる」の『蜜柑とユウウツ~茨木のり子異聞~』にて鶴屋南北戯曲賞、18年に劇団青年座『砂塵のニケ』、てがみ座『海越えの花たち』、PARCO PRODUCE『豊饒の海』にて紀伊國屋演劇賞個人賞、2020年に世田谷パブリックシアター『現代能楽集X『幸福論』̃能「道成寺」「隅田川」より』にて読売演劇大賞選考委員特別賞を受賞。近年はテレビドラマなど映像作品の脚本も執筆しており、23年には NHK 連続テレビ小説「らんまん」の脚本にて令和5年度文化庁芸術選奨新人賞、第32回橋田賞(作品賞)を受賞。
岡室:最初の『ゴジラ』には戦後当時の記憶や感触が込められていますよね。
長田:1950年代の人々の肉体や言葉の捉え方は今の私たちのそれとは全く違うし、あの台詞は今の時代には絶対書けないものですよね。映画やドラマや舞台芸術の作品にはそんな風に「その時代の人々がどんな皮膚感覚で生きていたか」がアーカイブされていて、私が脚本を担当したNHK朝ドラ『らんまん』(2023年)にも同じことが言えると思っています。
―『らんまん』は神木隆之介さん演じる主人公・槙野万太郎が生きた幕末から昭和初期までを描いたドラマですが、そこには、令和という現代を生きる私たちの皮膚感覚もアーカイブされている、と。
長田:『らんまん』は長引いたコロナ禍が明けた最初の春に放送が開始したんですよ。だから、奇想天外な外連味よりも「足もとの自然や目の前の四季を慈しむ」とか「もう一度誰かとささやかに繋がりあうところからネットワークを広げていこう」というメッセージ性を込めています。穏やかな印象が挙げられる作品ですが、言うなれば、コロナ禍へのカウンターでもあって。作品が生まれるまでには、前段にどんな時代があり、それを受けて何が求められ、作られているか、そういった背景があります。だから、その時代の人々を捉える上でも当時の作品が手がかりになるし、自分の作品もまた後世にそのように残ったらいいなと思います。
岡室:長田さん、早速興味深いお話をありがとうございます。私がかねてより考えてきた「ドーナツとしての舞台芸術アーカイブ」はまさにそういうことなんですよ。
INDEX
生の舞台の素晴らしさが大前提。その周囲を埋めていく「ドーナツ」の考え方
―早稲田大学演劇博物館(通称:エンパク)の館長時代に、「ドーナツ・プロジェクト」という、舞台芸術アーカイブのための人材育成事業を立ち上げられました。この「ドーナツ」という言葉にはどんな思いが込められているのでしょう?
岡室:生の舞台芸術自体は残せないので、舞台芸術アーカイブとは、戯曲や舞台美術や宣材素材や写真・映像等の記録など、その周辺の資料をドーナツ状に集めていくものである、という意味です。後世の人々がその公演を解像度高く想像できるようにするための取り組みですが、ドーナツは資料の集積だけではなく、その背後には、その時代を生きていた人の様々な生活、例えば恋愛観や家族観、社会の在り様までが広がっています。アーカイブは、ただ作品の資料を保存したり、年表的に記録するだけのものではない。その背景にある、大文字の歴史に残りにくい、フィクションでしか残せないような当時の人々の息遣いも含めて残していく、ということなんですよね。

早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系教授。早大演劇博物館前館長。専門はベケット、テレビドラマ、現代演劇など。『テレビドラマは時代を映す』(ハヤカワ新書)発売中。翻訳『新訳ベケット戯曲全集1 ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』(白水社)など。演劇博物館とEPADはEPAD発足初年度から連携し、2021年にはジャパン・デジタル・シアター・アーカイブズ(JDTA)を立ち上げた。

長田:私が執筆の折に活用しているのは、まさにそういった記録たちなんですよ。
岡室:ちなみに、長田さんは『らんまん』執筆時にも数多くの資料に当たられたと思うのですが、それらはどんな風に整理されたのでしょう?
長田:その質問はとても耳が痛いですね。というのも、『らんまん』はあまりに資料が膨大で……。とにかくそれらを次から次へと読み込んで執筆を進めていくわけですけど、スタッフさんたちもあらゆる分野の資料に手分けして当たっているような状態なので、誰とも共有ができていない資料を読んでいる、なんてことも起きるんです。
岡室:なるほど。それこそ、物語のテーマでもある植物や、舞台となる酒蔵にまつわる専門分野の資料探しなどもあるわけですもんね。
長田:モデルとなった牧野富太郎の評伝的資料はもちろん、植物や標本に関する専門文献、当時の酒造やその歴史のわかる資料、酒蔵をモチーフに書かれた小説にも当たりました。あと、東京大学創設時の学校の様子や暮らしを知るために坪内逍遙の『当世書生気質』を読んで、牛鍋屋の描写を入れることにしたり……本当に多岐に渡るアーカイブに当たって執筆しています。2015年に書いた坪内逍遙評伝劇『当世極楽気質』の戯曲を参照して台詞を考えたり、自作品のアーカイブも活用しました(笑)。
岡室:そんな風に思いがけず、自分のアーカイブが必要になる局面もありますね。こうしてお話しながら改めて思うのは、『らんまん』そのものがまさにアーカイブのお話であるということです。万太郎自身が「後世に植物標本を残すこと」に人生を懸けた人ですし、逍遙をモデルとした人物・丈之助も出てきますが、まさにその逍遙が創立したのが演劇博物館ですよね。
長田:丈之助の「演劇博物館を作りたい」「演劇は消えてなくなるものだからできる限りのものを残しておきたい」という台詞にも夢を込めましたが、アーカイブって1人ではできないもの。その点が個人のコレクションとはまた違うところです。世代を越えて多角的にやっていくことなんですよね。アーカイブの「未来に手渡すのだ」という強い意思のようなものに、私は惹かれているのだと思います。
INDEX
アーカイブを未来に残すには、作家の周囲にいる人たちの協力が不可欠
―映画『ゴジラ』に始まり、ドラマ『らんまん』、そして『当世極楽気質』という舞台。それらを横断して資料が活用されているということにアーカイブの豊かさを改めて実感します。
岡室:メディアは違っても、どれもが互いに資料になり得るのがアーカイブなんです。つまり、『らんまん』もまた後世にとって貴重なアーカイブになっていくわけですよね。ちなみに、脚本も初稿からブラッシュアップを重ねて完成されたと思うのですが、その段階の脚本は都度残すようにされているのでしょうか?
長田:改稿したところが分かるような状態で保存するようになっていたので、それは残っています。
岡室:よかった! というのも、長らくエンパクの館長を務めていた身としては、草稿や初稿もアーカイブとして非常に貴重だと思うんですよ。例えば、別役実さんの原稿もエンパクに数多くお寄せいただいているのですが、几帳面な方で、草稿はほとんどなく完成稿だけなんです。だけど、若い頃の創作ノートや名作『象』に至るまでの準備稿のようなものはあって、本当に素晴らしいんですよね。以前は草稿が紙だったのでご遺族から沢山お寄せいただけたのですが、現代はパソコン作業がメインだからなかなか残りにくいというのもありますね。
長田:現場によって独自の保存ルールがあったり、放送局の管理下にあるものとかもありますね。

―近年の小劇場の若手団体で興味深いと感じたのが、まさに草稿や初稿を観客と共有する取り組みでした。例えば、MEMELTという20代の団体は、物販で上演台本とは別にボツシーンを収めた「ゾンビ台本」なるものを販売していたり……。
岡室:へえ! それはとても面白いですね。
長田:性格によると思うのですが、私は台本の執筆中って自己肯定感が地に落ちた状態なんです。だから、正直なところ「私の書いた痕跡など世に残す価値はない」と思ってしまうんですよ。でも、そういう時に「後々役立つかもしれないから取っておこう」と言ってくれる人がいれば未来は大きく変わりますよね。制作さんであったり、劇団員であったり、優秀なアーキビストが作家の周りにいるかどうかでアーカイブの運命は大きく違ってきます。作家本人はつい「作品に全てを込めたのでもはや語るべきことなどありません」と思っちゃうので……(笑)。これも、私が「アーカイブは1人ではできない」と感じる理由の一つです。
岡室:お気持ちはすごくわかるんですけど、アーカイブ推進者としては見逃せないです(笑)。先日ケラリーノ・サンドロヴィッチさんとの対談で伺ったんですけど、KERAさんは原稿の執筆過程が物理的にある程度残っているそうなんですよ。それがもう演劇博物館としては欲しくて仕方がなくて……。長田さんの作品についても同じで、素晴らしい台本を作家がどう書き進めていくのかを知りたいし、その軌跡も後世に残していきたい。常にそういう思いがありますね。もちろん作家だけでなく、俳優が演技のためのメモや息継ぎ箇所を書き込んだ脚本などもとても貴重だと思います。やはり残そうという意志をもった人が周囲にいることが重要ですね。
長田:岡室先生のお話を聞いて、今、少しだけ「自分の書いたものの痕跡にも価値があるんだ」と認識することができました。
岡室:アーキビストたちの思いが通じてよかった!(笑)