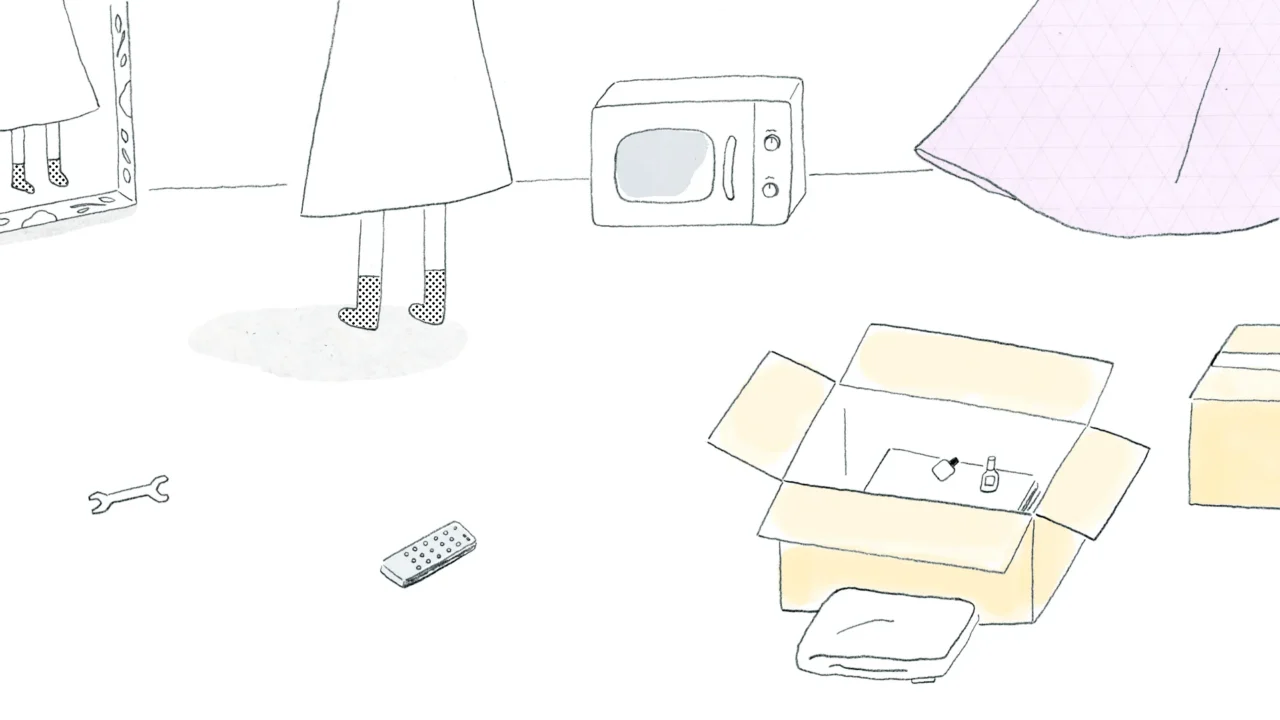絶対に終電を逃さない女の著書『虚弱に生きる』が話題となっている。彼女自身の虚弱体質にフォーカスをあて、これまでどのような症状に見舞われてきたかや、今どのようにして生活を送っているのかなどを赤裸々に書いたエッセイだ。
この記事を書いている私自身、日々の生活の中で、自分の体力のなさに絶望している。午前中2時間パソコンに向かっただけで疲れ果て、1時間半の昼寝をしないと動けず、午後も3、4時間仕事ができればいい方で、そこから体力をつけるための運動をしようと思っても、その体力が残っていない。
本を読んでまず思ったことは、私だけじゃないんだ、ということだ。どうしてこんなに体力がなく、疲れやすく、常に体調が悪いんだろうと悩みながら生きてきたが、そのような悩みを抱えているのが私1人だけではないということが分かっただけでも、少し気持ちが楽になった。そして、疲れやすく体力がない自分を責めずに、こういう体質なのだ、と受け入れられるようになった。今は、少しでもやれることをやろうと思い、朝のルーティンにラジオ体操を取り入れている。
絶対に終電を逃さない女は、この本を、虚弱体質な人だけでなく、健康で体力のある人にも読んでもらいたいと語る。そういう人達にも読んでもらわないと、社会に伝わらない、と。
虚弱体質に向き合い続けてきた絶対に終電を逃さない女には、今の社会がどのように映っているのだろうか。『虚弱に生きる』のこと、虚弱体質だからこそのワークライフバランスや、健康に対するモチベーション、福祉制度の活用法などについて聞いた。
INDEX
1日5食、卓球……虚弱ゆえにアスリート化する生活サイクル
ーまず、終電さんの「虚弱体質」がどんなものなのか、本をまだ読まれていない方に向けて簡単にご紹介いただけますか。
絶対に終電を逃さない女(以下、終電):短く説明するのが難しいんですが、まず睡眠時間は10時間必要です。体力がないからすぐに疲れるし、少しでも無理をすると体調を崩します。なので、それをなるべく防ぐために、食生活の改善や運動を頑張っているんですが、そこにかける時間が長いのもあって、活動量が少ない、みたいな感じですかね。
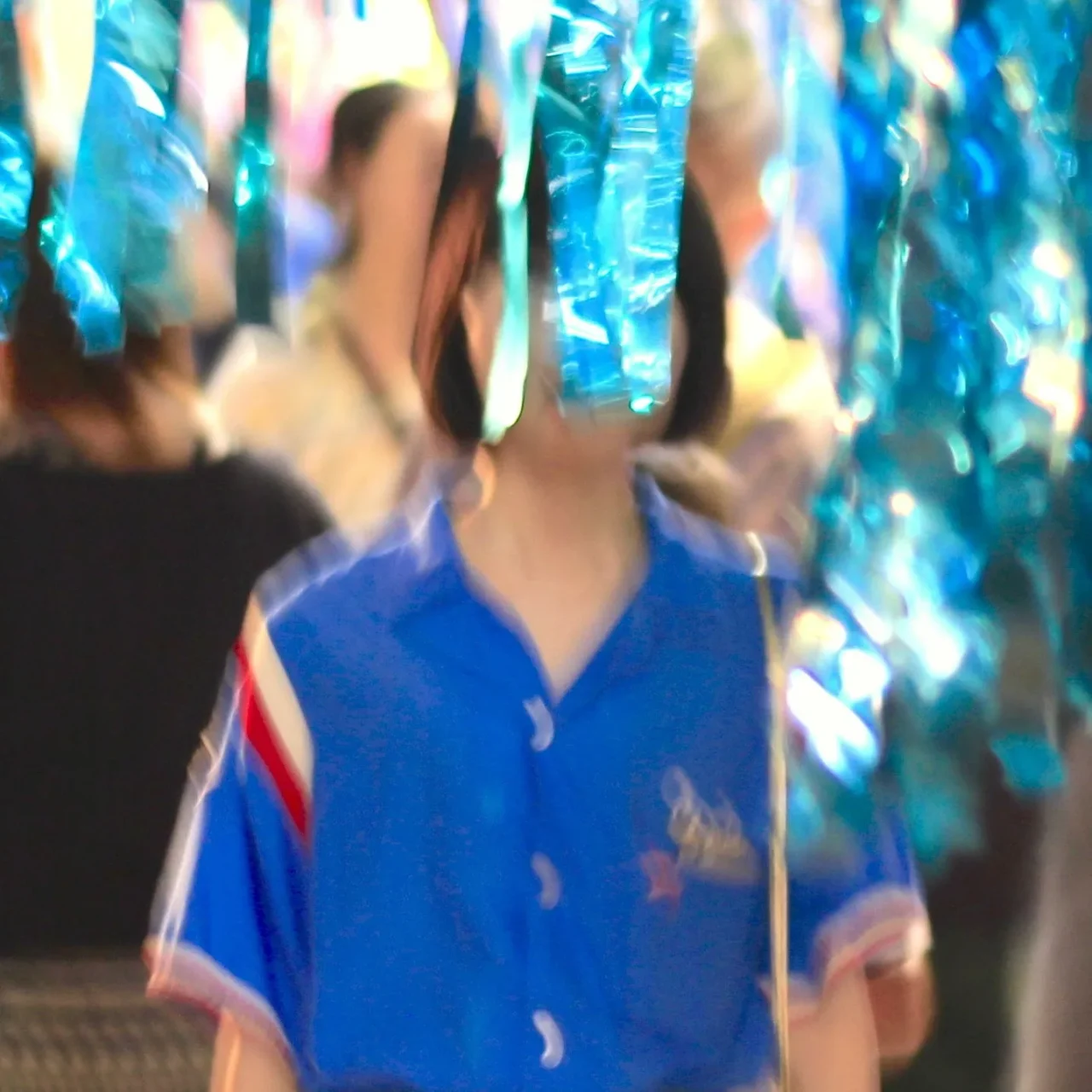
文筆家。1995年生まれ。大学卒業後、体力がないせいで就職できず、専業の文筆家となる。様々なWebメディアや雑誌などで、エッセイ、小説、短歌を執筆。単著に『シティガール未満』(2023年、柏書房)、共著に『つくって食べる日々の話』(2025年、Pヴァイン)がある。
ー今回の本『虚弱に生きる』の中では、今お話しいただいたような暮らしぶりが詳細に書かれていますが、本の執筆を終えたときから今に至るまでの間に、生活リズムに変化はありましたか?
終電:執筆をしている間は忙しかったので、卓球をする時間が取れなくなりました。ジョギングはしていたので、有酸素運動としては十分なんですが、理想としては卓球もしたかったですね。あとは、1日5食になりました。
ー食事の回数を増やした理由は何かあるんですか?
終電:タンパク質を積極的に摂っているんですが、タンパク質って1度に吸収できる量が限られているんですよ。筋トレをしている人ってプロテインを小分けにして飲んだりするので、私も筋肉をつけるために真似してみようかなと思って、2ヶ月ぐらい1日5食にして頑張っています。
ー生活リズムを更新していっているんですね。最近はワークライフバランスが話題になっていますが、終電さんが仕事と生活のバランスを取る上で意識していることはありますか?
終電:多分大体の人はワークを優先していると思うんですよ。決まった時間働いて、その残りの時間でライフをどうにかやりくりするみたいな。でも私はその逆で、生活とか健康の方を優先して、残った時間や体力で仕事をするという感じです。
ー例えば卓球をしているときに、仕事のことを考えて、ちょっと焦ってしまうみたいなことはないですか?
終電:まあ、ありますね。何かに集中するのが苦手なので、仕事とかを忘れる瞬間があまりなくて。卓球は、最初はピンポン玉を追いかけることに集中できていて、他のことを考えずにすんでいたんですが、しばらく続けたら慣れて、卓球をしながら他のことを考えられるようになっちゃったんですよ。それはちょっと残念です。でもそれでも、基本的には運動を優先していますね。
ー仕事よりも運動や生活を優先するのには、けっこう強い意志が必要なのかなと思いました。そのメンタリティはどのように身に着けましたか?
終電:20代前半が一番体調が悪かったんですが、そのときに健康を失ったら仕事もできないんだなというのを身をもって学んでいるんですよね。その記憶があるから、仕事を優先する意味はないなと思っています。
INDEX
休むことを頑張る
ー確かに、結局身体が資本なんだなというのは、疲れたり体調を崩したりすると感じます。終電さんは、仕事中に疲れたときは、どのように対処していますか?
終電:「疲れた」と感じる時点でもうだいぶ限界なので、休まなきゃいけないんです。私の場合、デスクワークで基本的にずっと文字を見ているので、目が疲れるんです。なので、休むと言ってもただ横になるよりは、ストレッチとかラジオ体操とかそういうアプローチをしますね。頭痛や肩こりもストレッチで楽になったりしますし。ただ私の場合は、「疲れた」と感じるところまでやると、やりすぎですね。長いスパンで見て、長時間仕事をするためにも、疲れていない状態で仕事を終わらせています。
ー「疲れそうだな」みたいな予兆はありますか?
終電:短時間だと分からないかもしれないです。日によって、4時間ぐらい仕事をしたら頭痛がするときもあれば、8時間以上やっても大丈夫なときもあるので、そこはまだ読めてないですね。でも基本的には疲れてからじゃ遅いという考え方なので、いいオフィスチェアを使ったりして疲れにくい環境を作ったり、健康ルーティンをすることで、疲れを未然に防いでいます。
ー疲れを感じつつも、「ここは頑張らなきゃ」と無理をしてしまう人もいる気がします。無理をしない工夫は何かありますか?
終電:でも私も、もしこの1.5倍以上とかの仕事をもらえる状況になったとしたら、断りたくない気持ちが勝って、無理をして大変なことになるんじゃないかという気もしているんです。引き受けた仕事の締め切りが迫っているとかだったら、無理せざるをえないところもありますが、絶対にやらなきゃいけない仕事とかがなくて、活動量も多くて、これ以上はやばいなと感じたときは、休むことを頑張ろうと思っています。
ー休むことを頑張るっていいですね。
終電:休むことは義務なので。人生をマラソンだって考えたら、長く走るためには適度に休まなきゃいけないと思うんです。
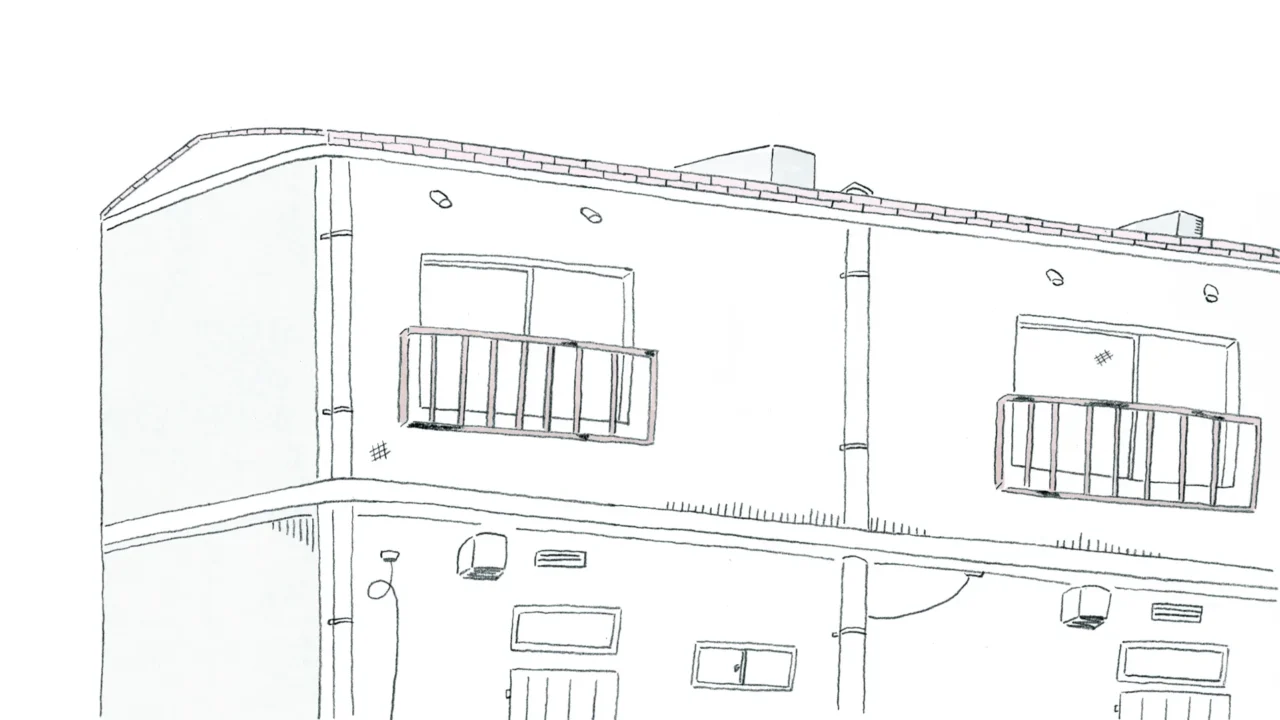
INDEX
虚弱な暮らしと福祉制度
ー本の中でも書かれていましたが、終電さんは色々な福祉制度を活用されて生活されていると思います。そういった情報にたどり着くまでもかなりリサーチが必要だったかと思うのですが、どのように制度を見つけてきましたか?
終電:22歳のときに場面緘黙症で障害者手帳を取って、その後診断名がASDに変わった(※)んですが、役所で初めて手帳を受け取ったときに自立支援医療制度というものがあるというのを説明されて知ったんです。障害者手帳と自立支援医療制度って、診断書1枚で同時に申請できるし、診断書を発行してもらうのもお金がかかるので、本当は同時に申請したほうがいいんですよ。私はそれを知らずに障害者手帳だけ先に申請しちゃったんですが、そういうことを誰も事前に説明してくれなかったんですよね。そのときに、福祉って自分で調べないといけないようになっているんだっていうのを知って、それからは厚生労働省や自治体のサイトの福祉のページを隅々まで見ていますね。
※ASDと虚弱がどのように関係するのかは、『虚弱に生きる』第三章で詳述されている。
ー福祉制度ってけっこうあるのに、能動的に調べないと知らないことばかりだったりしますよね。今は公営住宅に住まれているそうですが、それも福祉について調べていく中で知ったんですか?
終電:そうですね。自治体のサイトに載っていたりしますし、役所にも募集の紙が置いてありました。倍率がすごく高いので、どの地域なら穴場なのか等も色々と調べました。
ーそれを調べるのにもけっこう体力を使いますよね?
終電:時間はめちゃくちゃかかりました。
ー今の一人暮らしが成立するまでに、どれぐらい時間がかかりましたか?
終電:今でも、成立していると言えるのかな……って思うんですよね。本にも書いたんですが、ここ1年近く、居宅介護という福祉制度を使って、軽い掃除をしてもらっているんです。大学生の頃は家事が何もできなくて、当時はそういうことが苦手なんだと思っていたんですが、多分単純にキャパオーバーだったんじゃないかと思うんですよね。今は本当にちょっとずつ自炊を始めたり、片付けもできるようになったりしていますし、より生活を良くするための家具を揃えたりもしています。まだ完成したとは言えないんですが、自分の家以外に泊まるのが嫌だな、と思える程度には自分にとっていい家にはなってきています。
ー自分のキャパを超えているなと感じる部分は、福祉制度を使っていらっしゃるのがすごくいいなと思いましたし、この本を読むまでそういう制度があるのを知らなかったので、困っている人にとって、この本は福祉制度を知る入口にもなるんじゃないかなと思いました。
終電:そうですね。公営住宅とかも知らない人はいると思うので、そうなるといいなと思います。