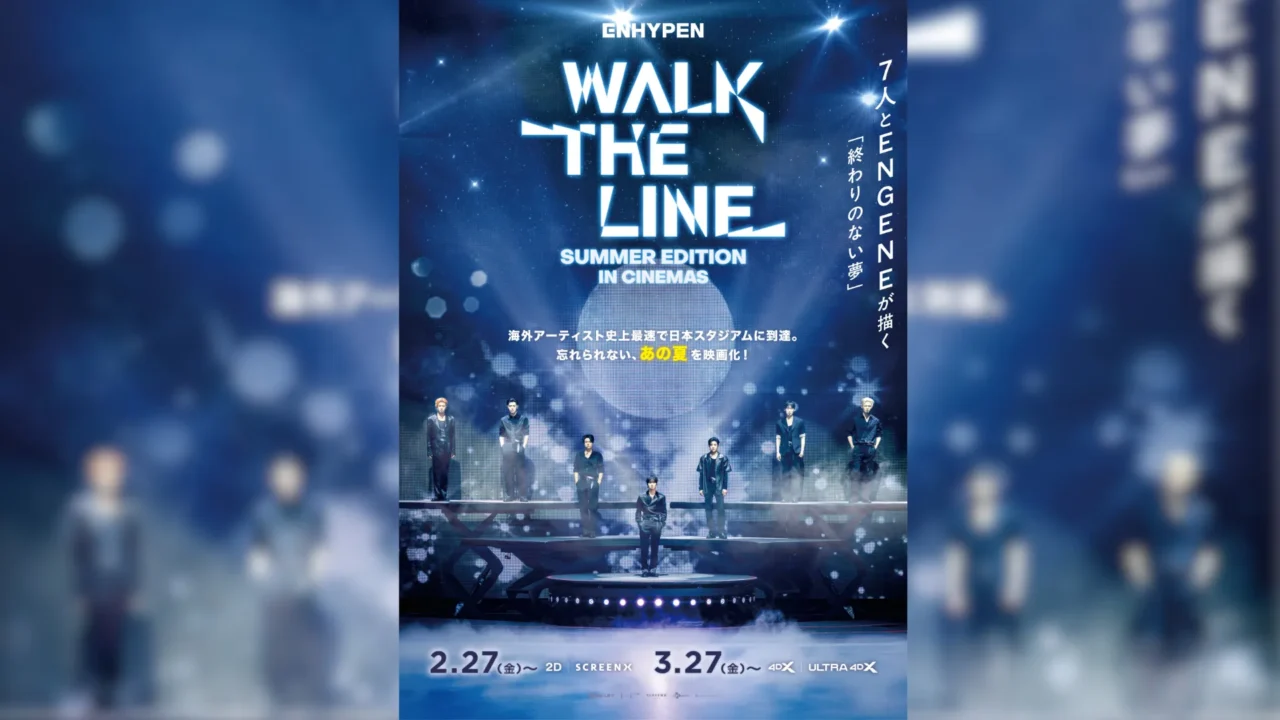音楽を聴いて、心が晴れやかになる。何を歌っているのか、言葉もわからないにも関わらず、悲しい気持ちを、ままならない日常を、退屈な仕事や学校のことを、一時的ではあるにせよ忘れさせてくれる音楽がある。ネクター・ウッドの音楽には、まさにそうした感覚が息づいている。
ネクター・ウッドは、ストリートなソウルの感覚を体現するロンドンのシンガーソングライターだ。グライムの躍進、ジャングル〜ドラムンベースのリバイバル、UKジャズの勃興、サウスロンドンのバンドシーンの加熱などの渦中にある彼女の歌を、「ローリン・ヒルのようだ」と評したのがエルトン・ジョンだった。
ローリン・ヒル、そして先日急逝したディアンジェロらの音楽を研究することで、モダンなソウルミュージックのサウンドプロダクション、アレンジの秘密を理解していったネクター・ウッド。その音楽が宿す感覚について、ライターでトラックメイカーの小鉄昇一郎とともに取材した。
INDEX

1999年生まれ、イングランド・ミルトンキーンズ出身のシンガーソングライター。ガーナ人の父とイギリス人の母を持ち、幼少期から音楽とアートに囲まれた環境で育つ。ロンドンの音楽学校に進学し、在学中からオープンマイクや即興セッション、バンド活動を通じてキャリアをスタートし、現在はロンドンを拠点に活動。ローリン・ヒル、エリカ・バドゥ、ディアンジェロ、エイミー・ワインハウス、Duffyなどから影響を受け、西アフリカ音楽のリズムや感情表現も取り入れた独自のスタイルを確立。2025年7月、EP『It’s Like I Never Left』をリリース。プロダクションにジョーダン・ラカイを迎え、ミックスルーツや家族愛を祝福した作品となっている。
ガーナとUK、2つのルーツと文化に育まれたネクター・ウッドの歌
─昨日のライブ、拝見しました(取材は10月1日に実施)。駅から向かう間に雨が降り出して、慌てて会場に駆け込んだんです。扉を開けてすぐ、あなたの暖かい歌声が聴こえてきて、とても安心した気持ちになりました。
ネクター:そうなんですね、ありがとうございます。嬉しいです。
─ライブでFleetwood Macの“Dreams”をカバーしていましたね。
ネクター:2か月ほど前に「バンドで何かカバーをやろう」という話が出て、たまたまYouTubeでこの曲が目に入ったんです。多くの人が知っていて、誰もが共感できる歌だし、すごく深い意味を持った歌詞だと思います。とにかくあの曲の歌詞が好きで、歌う度に言葉の深みが響いてくる気がします。

─あなたのギターの腕前も非常に巧みで、驚かされました。
ネクター:ギターが一番長く続けている楽器なんです。左手で弦を押さえるコードの感覚、指の使い方が一番しっくりきます。理論的なことはあまり得意じゃないけど、ジャズのハーモニーが大好き。自分でピアノを弾くこともありますけど、鍵盤は今回のライブのように友人のエイミーに任せることが多いです。
─あなたはどんな街で生まれ育ったんですか?
ネクター:父はガーナ出身で、30歳くらいのときにロンドンに移り住んでイギリス人の母と出会い、ミルトン・キーンズに引っ越してきたんです。だから家の中は複数の文化が入り混じっていました。食べもの、そして音楽も。

ネクター:ミルトン・キーンズはロンドンの北方で都市部から引っ越してくる人も多く、いろんなバックグラウンドを持った人が暮らす街です。ガーナのレストランもあるし、学校にもさまざまな文化、家庭の子どもたちが入り混じってる感じ。そういうミックスカルチャーな環境で育ってよかったなと思います。
―ご家族についても教えてください。
ネクター:両親は音楽が好きで、家ではボブ・マーリーが1日中流れているような家庭で育ちました。文化的に豊かな環境だったと思います。両親はボブ・マーリーが大好きで、父は携帯の着信音までボブ・マーリーの曲に設定してました(笑)。
─“Ama Said”では、そのお父さんがサックスで参加していますよね。ご両親の影響で、自然と音楽にのめり込んでいったのでしょうか?
ネクター:はい。でも、反抗期になると親が聴いてる音楽なんて聴かなくなるじゃないですか。私も一時期はそうで(笑)。でも18歳で家を出たとき、「やっぱり、私は家で流れていた音楽が一番好きなんだな」と感じたんです。
INDEX
ディアンジェロらから受け継ぐもの。音楽大学とストリートで磨き、研究したソウルの感覚
─ご両親が聴いていたのはどんな音楽でしたか?
ネクター:ディアンジェロ、エリカ・バドゥ、それからローリン・ヒルとか、たくさんあります。歌はもちろん、アレンジが素晴らしいなと思う。ギターを弾き始めたとき、彼らの音楽のアレンジの不思議さに中毒みたいに惹かれて夢中で聴いてました。
ネクター:彼らは古いソウルミュージックの要素を取り入れながら、アレンジはものすごく現代的で。「どうすればこんなことができるんだろう? 彼らみたいに曲を書く方法を学びたい!」と思って、ディアンジェロのディスコグラフィーを徹底的に聴き込んだりしました。
─ソウルミュージックが自分の原点であると気づいたわけですね。ディアンジェロは日本でも人気ですけど、どこが好きですか?
ネクター:ソウルミュージックはジャズやR&Bとも近い雰囲気があるけど、本質的には「気持ちをよくしてくれるもの」だと思う。1970年代のオールドスクールなソウルは特にそうかな。
でも、ディアンジェロはそれだけではないんですよね。オールドスクールなソウルは、人の喜怒哀楽、ベーシックな感情を表現しているものが多いけど、ディアンジェロはより多面的。ハッピーだとか、悲しいとかだけじゃない、さらに複雑な感情を歌にしているのが好きなんです。『Brown Sugar』(1995年)や『Voodoo』(2000年)を聴いて、アレンジと作曲の研究しました。
─あなたは音楽学校に在学中、オープンマイクやジャムセッションのできる店で腕を磨いていたそうですね。
ネクター:そうです。見知らぬ人の前で歌うことは、いい実験になるんじゃないかと思って。18歳で実家を出て、ギターもソングライティングもまだまだ勉強中のころでした。
ミルトン・キーンズやその周辺にあるお店は、お客さんも温かくて。流行ってる音楽のスタイルとは、別のものをやってもOKって感じ。「流行りじゃないけど、それも面白いね」って、どんな音楽でも寛容に受け入れてくれるんです。
でもロンドンのようにもっと都市部になると、また事情が違っていて。よりプロフェッショナルで真剣なミュージシャンも多いし、お客さんの目も肥えてるから。