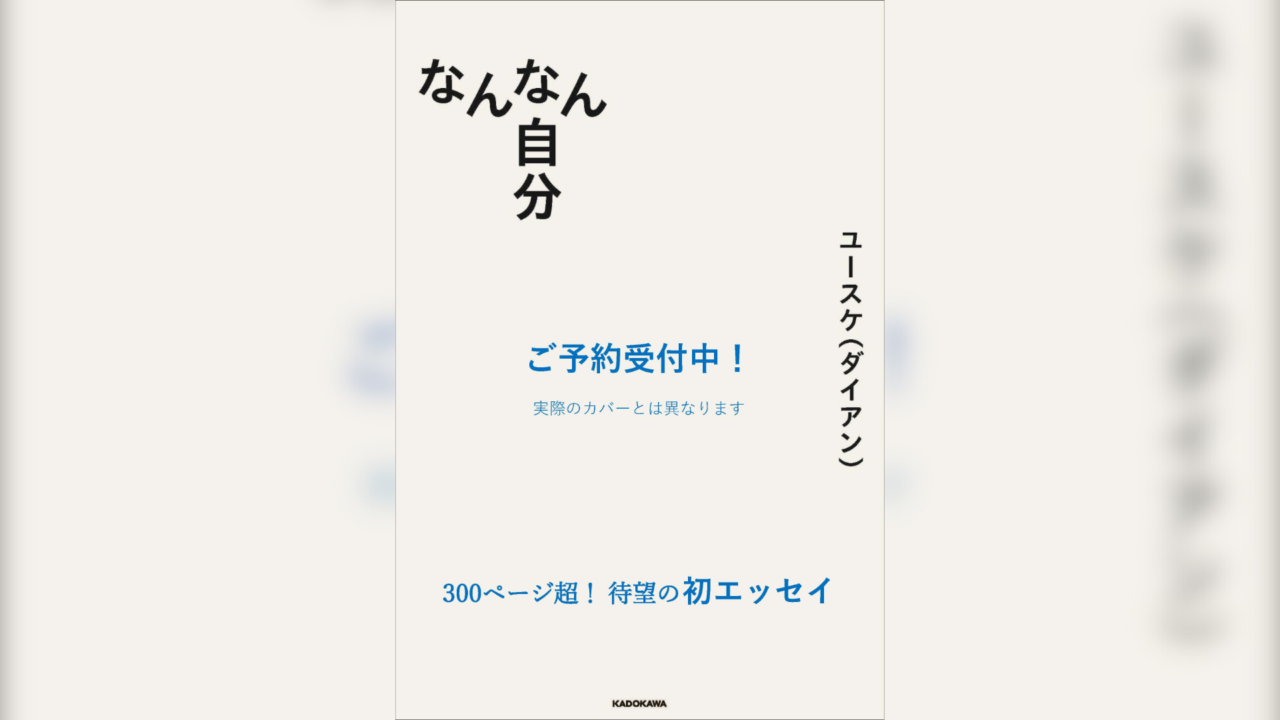9歳の頃にジャズスクールで出会った2人の少年。それぞれの道を進みながら、彼らは日本の新しいジャズシーンになくてはならない存在へと成長した。親友であり良きライバルでもある2人、ドラマーの石若駿、サックス奏者の馬場智章は、昨年、アニメ映画『BLUE GIANT』で演奏担当として共演。そしてこの度、立て続けに新作をリリースした。
石若が率いるAnswer to Remember『Answer to Remember II』、馬場のソロ作『ELECTRIC RIDER』は、どちらも新境地を切り開いた重要作であり、日本のジャズシーンが進化し続けていることが伝わってくる。そこで今回、2人がふと漏らした「酒を酌み交わしながら話をしたい」というリクエストを実現。ビールのロング缶を開け、リラックスした雰囲気のなかで、2人が出会った子供時代や音楽に対する姿勢、新作の話など、彼らのジャズをめぐる友情のヒストリーを訊いた。
INDEX
「僕がミュージシャンをいまだに続けられている理由って駿なんですよ。音楽だけ悔しさを感じた」(馬場)
ー普段、こんな風に2人で飲みながら話すなんてことは良くあるんですか?
馬場:そんなにはないですね。ライブの打ち上げの時とかは他の仲間もいるし。去年の5月くらいに久しぶりにサシで飲みました。急に駿から連絡がきて、「今近くまできてるんだけどいる?」って。それで2時間くらい飲んだよね?
石若:あの時は、ちょっと寂しくて(笑)。
馬場:色々あるよね(笑)。

石若:結構、熱い話をした記憶があります。これから俺たちどうしよう。世代的に大人になったけど、これからのビジョンってある? みたいな。
ー真面目な話ですね。
馬場:2人だけになると、そういう話になってしまうんですよ。というのも、お互い忙しいし、そういうタイミングでしか真面目な話ができないからかもしれません。
石若:お互いに同じ子供の頃からジャズをやってきて、コアなところで繋がりを感じてはいるんですけど、智章は高校卒業してアメリカに行って、僕はずっと日本で活動していた。智章がアメリカから帰って来てから一緒にやったりはしているんですけど、活動しているシチュエーションが違うので、会うと様子を探るみたいなところがあるんです。
ー2人は9歳の頃に北海道のジャズスクールで出会ったそうですね。その頃から相手のことは意識していたのでしょうか。
石若:そうですね。ジャズスクールって大所帯なんですよ。小学生の部で40人くらいいる。智章はソリストだったのでバンドの先頭に立ってマイクの前でサックスを吹くんですけど、キラッと光るソロを吹ける人は数少なくて、その一人が智章だったんです。

打楽器奏者。1992年北海道生まれ。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校打楽器専攻を経て、同大学を卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞。リーダープロジェクトとして、Answer to Remember、SMTK、Songbook Trioを率いる傍ら、くるり、椎名林檎、KID FRESINO、君島大空、CRCK/LCKSなど数多くのライブ、作品に参加。
馬場:ちゃんと吹けてた?
石若:めっちゃ吹けてた。僕はドラムという立場なのでフロントに立つことはなかったですが、アドリブをした人の演奏に反応して、ドラマーの役割でどんな風に空間を蠢かせるのか、というのがジャズの醍醐味だと思っていたんです。そういったところで、智章と一緒にやるのは楽しかったですね。
馬場:そういうことを小学生で感じているのがヤバいでしょ?(笑) 当時、僕はドラマーの役割なんて全然わかってなかったのに。駿の演奏は圧倒的でしたけど知識もすごかった。音楽博士でしたね。「これ聴いたことある? めっちゃいいよ!」っていろんなCDを聴かせてくれるんです。最初にデビューしたてのロバート・グラスパーを教えてくれたのも駿だったし、駿のおかげで音楽の知識が広がりました。

1992年、北海道札幌市生まれ。2011年にバークリー音楽大学入学。卒業後はニューヨークに拠点に活動。2020年に帰国後はリーダープロジェクトに主軸に置き、『ELECTRIC RIDER』(2024年)を含む3枚のリーダーアルバムをリリース。2023年公開のアニメーション映画『BLUE GIANT』にて、主人公・宮本大のサックス演奏を担当。
石若:リアルタイムのジャズを聴いていて、音楽の話ができる仲間が周りに少なかったんですよ。だから知識をシェアして一緒に演奏できる仲間を探していた。その一人が智章でした。
馬場:ジャズスクールでセッションする時には「こんなアレンジどう?」とか、駿はアイデアを先頭切って持ってきました。当時から音楽的な提案をすごくやっていて、それがアンリメ(Answer to Remember)とかに繋がっているんだと思いますね。
ー子供の頃からお互いに影響を与えあっていたんですね。
馬場:僕がミュージシャンをいまだに続けられている理由って駿なんですよ。僕は家族に音楽をやっている人がいたわけでもないし、ミュージシャンになりたいと思っていたわけでもない。音楽以外にも水泳をやったり、医療に興味を持ったりしてました。勉強も嫌いではなかったし、やりたいことはいろいろあった。そんななかで、音楽だけ悔しさを感じたんです。「もっとチャンスがほしい」「もっとできるようになりたい」っていう欲があった。水泳をやってて、そういう悔しさを感じたことはありませんでした。でも、ジャズスクールで駿に出会った時に「こいつに負けたくない!」と初めて思ったんです。もし、駿に出会わなかったら、今頃は医者になっていたかもしれませんね。手術の後に駿の新作を聴いて「最近はなんか難しいことやってるなあ」って思ってたかも(笑)。

INDEX
石若駿が渡米を選択しなかった理由――武満徹や高橋悠治の偉業に触れて考えた「自分たちのアイデンティティ」
ーお互い親友でありライバルだった。
馬場:僕が高校に入った頃、駿は東京に出て日野皓正さんはじめ有名なプレイヤーとガンガンやるようになってました。それを僕は羨望の眼差しで見ていたんです。大切な友達には変わりないのですが、どこか羨ましいさみたいなものも感じていた。でも、大学から渡米したことで、そういう気持ちがなくなってフラットに物事を見られるようになったんです。
石若:そうかあ。僕はアメリカで活動している智章のことを「すごいなあ」と思っていました。自分が好きなプレイヤーと共演したり、同じフェスやイベントに出てる。僕もアメリカで活動したいな、と思っていた時期がありました。
ーなぜ、渡米しなかったのでしょう。
馬場:そうそう。来たらいいのにと思ってた。
石若:大学(東京藝大)で現代音楽と呼ばれるものを演奏したり触れる機会が自分は多かったんです。藝大ではオーケストラ志望のプレイヤーやコンペティションで賞を目指すプレイヤーも多くいましたが、なんというか、自分にとって現代音楽に携わる時の気持ちやワクワク感が心地よくて楽しかった。もっとリアルタイムで、自分のバックグラウンドがダイレクトに反映される音楽だし、引き出される音楽だなと思いました。ここ60年くらいの由緒ある現代音楽の作品を学ぶ上で、リアルな継承を先輩や先生方から耳にしたりすることもワクワクしていましたし。武満徹さんの作品をはじめ、アジアの作曲家の作品を演奏した時の気持ちや、近しいところですと作曲科の方々の新たな響きを模索したり、新曲の世界初演に立ち会って感動する度に、「演奏家として自分はこういうことをやるべきかもしれない」と思ったんですよね。

ークラシックやジャズという海外の音楽をやる時に、日本人としてのアイデンティティや独自性をそこにどうやって落とし込むのか。それは大きな問題ですね。
石若:そんなようなことを考えていたので、その時はアメリカをちょっと疎遠に感じていました。リアルタイムでニューヨークで起こっているジャズシーンには興味を持っていたし、相変わらず好きではあったんですけどね。
馬場:駿が日本にいた理由をいま初めて知りました。僕もアメリカで活動しながら「日本って何なんだろ?」って考えていたんです。というのも、ジャズっていうアフリカやアメリカから生まれた音楽を、いろんな人種の人たちと演奏するなかで、音楽を通して歴史や文化を勉強する機会も多かった。アメリカに渡り彼らと会話をするなかで、自分が日本の文化をあまり知らないことに気づきました。日野皓正さんやタイガー大越さんみたいにアメリカ歴が長い人は、アメリカ文化に通じているのと同じくらい日本文化に通じていて、それぞれを噛み砕いて自分のものにしている。最近、そういったジャズミュージシャンが増えてきたと思うんです。アヴィシャイ・コーエンだったりとかティグラン・ハマシアンだったりとか、地域性のある音楽をジャズとかいろんな音楽のフォーマットにフュージョンしている。黒人文化や白人文化を尊重すると同時に、日本の文化も尊重してジャズをやっていくにはどうしたらいいんだろう、とすごく考えました。

ー2人は別々の場所で同じようなことを考えていたんですね。そして、馬場さんはNY在住の日本人ミュージシャンによるバンドJ-Squadのメンバーとしてデビュー。石若さんはソロ活動に加えて、CRCK/LCKSやものんくるなど様々なバンドで活躍します。
馬場:アメリカにいる時は、駿のFacebookを通じて「いま日本にこんな面白い人が出て来たんだ」って日本のシーンを追いかけていました。江﨑文武(WONK)、額田大志(東京塩麹)、常田大希(King Gnu)とか、新しい才能を持つ人達と駿を通じて知りあって、日本に新しい音楽シーンが生まれていくのを興味深く見ていました(参考記事:藝大出身者が語る、刷新すべき音楽教育 江﨑文武×石若駿×額田大志 / CINRA)。
石若:当時は、日本には面白いミュージシャンがいっぱいいるのに、どうしてそれが世界に広がらないんだろうって思っていたんです。そのためには東京で強力なシーンを作らないとダメなんじゃないかって、先輩や仲間と毎日のように話をしていました。当時はみんな激アツにとんがってたから。
INDEX
ライブができないコロナ禍が、2人にもたらした影響。トッププレイヤー×テクノロジーの化学反応
ーやがて、東京の新世代ジャズシーンが注目を集めるようになるなかで、馬場さんが帰国して日本で活動するようになる。石若さんと馬場さんが演奏で共演したアニメ映画『BLUE GIANT』は、ジャズシーンの盛り上がりを象徴する作品でもありました。そして、今度は2人が同時期に新作をリリースしましたが、どちらも従来のジャズのイメージを打ち破った斬新な作品に仕上がっていますね。石若さんが率いるユニット、Answer to Rememberの『Answer to Remember II』には多彩なメンツに混じって馬場さんも参加しています。
馬場:アンリメの音楽は、まさに駿!っていう感じですね。僕が参加した曲“札幌沖縄”なんて特にそう。コードとかメロディーの作り方が駿っぽいんです。昔と違うのはサウンドの作り方で、以前はジャズのフォーマットに落とし込んでいたけど、今回はどんな音を足して、どんな音を引くのか、曲の長さをどうするのかとか、ジャズの良さを残しながらもプロダクションが細かく作り込まれている。それってトラックメイカーとかポップスの作り方からの影響だと思うし、これまで駿がいろんなジャンルで活躍してきたからこそ身についたことだと思います。
ージャズといえば生演奏や即興のイメージが強いですが、『Answer to Remember II』はセッションをベースにしながら緻密な音作りで現代的なサウンドに落とし込んでいます。
石若:例えばドラムに関して言うと、あまりにも1曲の音数が多いので生のドラムだけだと支えきれないんです。そこで、生で録ったドラムに打ち込みを追従させていく。そんな風にテクノロジーを駆使するというのは前作ではやってなかったことですね。前作を発表して以降、コロナ禍になってライブがストップしてしまって、レコーディングの現場が多くなった。それでテクノロジーに関する知識を身につけて、それを今回のアルバムで試すことができました。

馬場:駿はドラマーなんですけど曲の全体を見ている。プレイヤーとしての視点、作曲家の視点、そして、プロデューサーの視点も持っているんです。そういう人って意外と少なくて。ドラマーがこういうアルバムを出す、というのはすごく意味があると思います。
ー確かにドラマーのアルバムとは思えないですよね。一方、馬場さんの新作『ELECTRIC RIDER』も斬新なサウンドになっていますね。
馬場:今回は「いわゆる“ジャズ”アルバムは作らない」という気持ちで挑みました。僕も駿と同じで、コロナ禍でライブがストップしている間にテクノロジーに向き合っていて、パソコンを新調してAbletonという音楽制作ソフトを買い、独学でコンピュータを使った曲作りを始めました。それで1週間に1曲、できた曲をInstagramにあげてたんです。
馬場:それをBIGYUKIが聴いてくれていて、NYで一緒にバーベキューをした時、「インスタの曲、聴いたで。あれ、ええやん」って言ってくれた。YUKI君とは僕が15歳の頃に知り合って、後にNYで遊んだりしていました。元々YUKI君の音楽のファンで、ずっと一緒にやってみたいと思っていましたが、新作が出せると決まった時に、YUKI君に声をかけてプロデューサーとして入ってもらいました。シンセを使ったり、オーバーダブをしたりするのなら、僕一人の想像力では難しいと思ったし、YUKI君の音楽性と僕の音楽が合わさったら面白いかなと。そして、これまで僕が作ってきたようなアルバムーーアコースティックな演奏でソロを回して、みたいなアルバムではなく、サウンドやプロダクションをしっかり作り込んだ作品にしたい、という話をYUKI君としました。