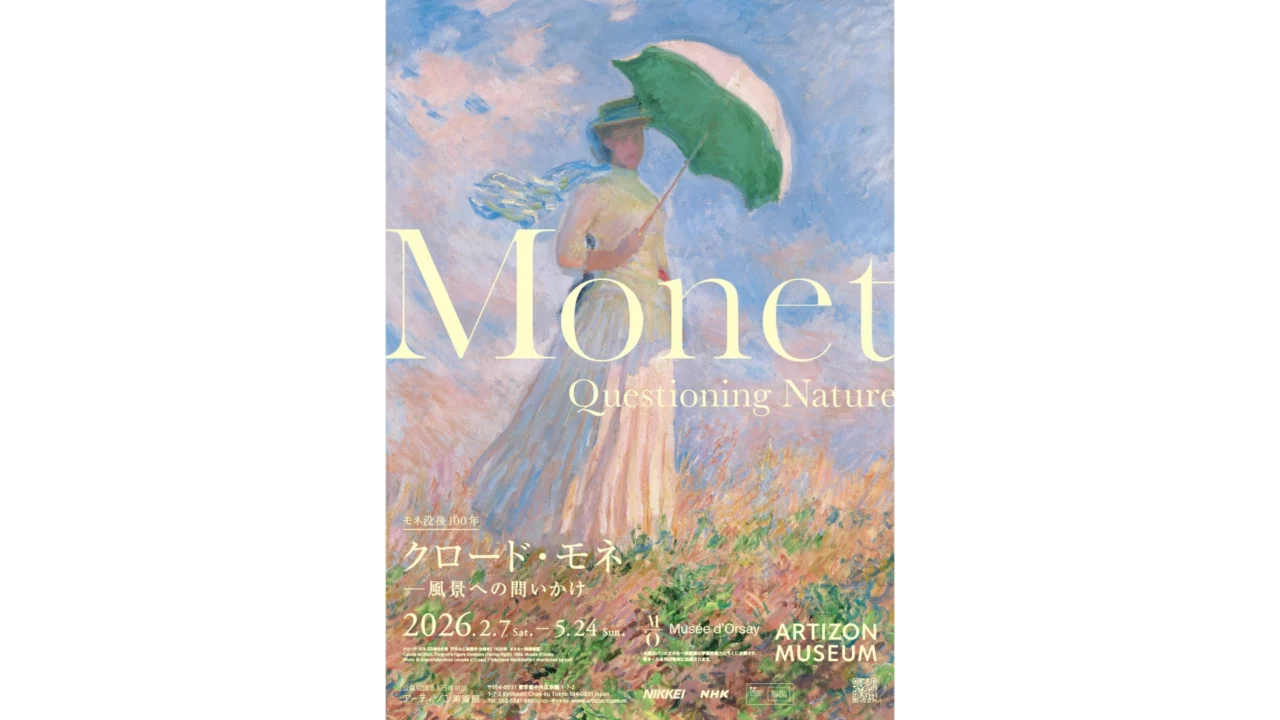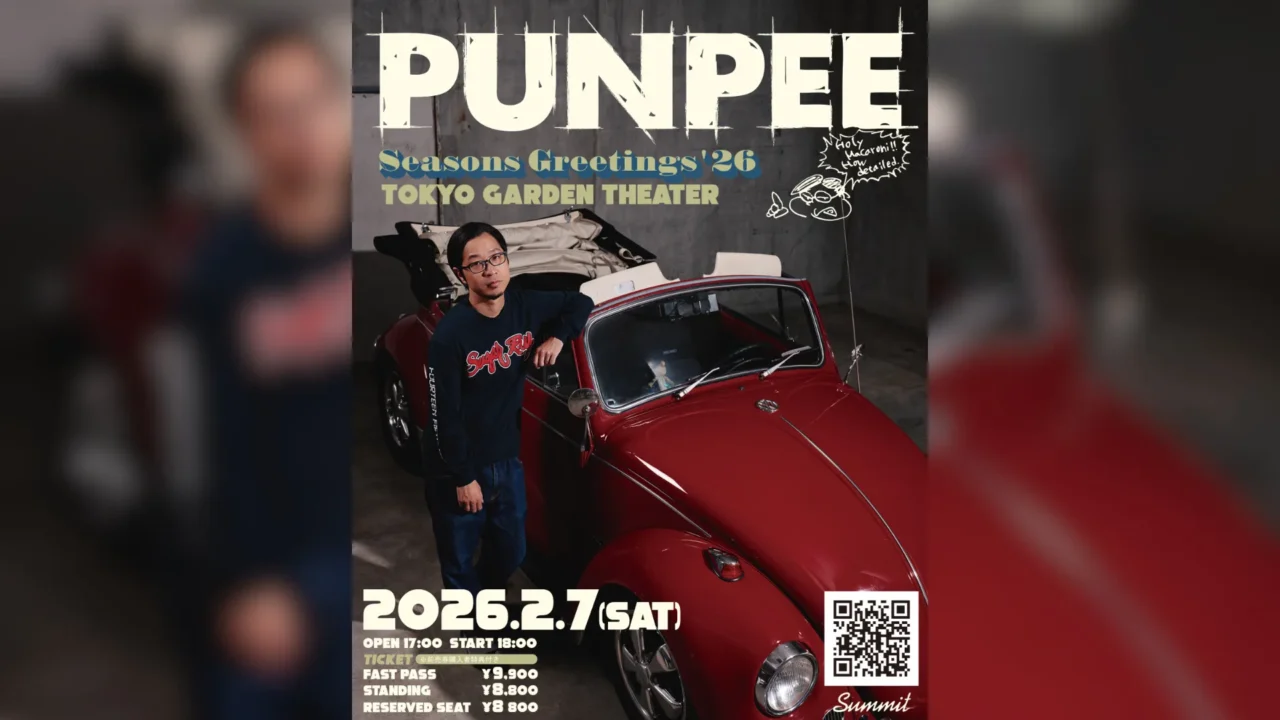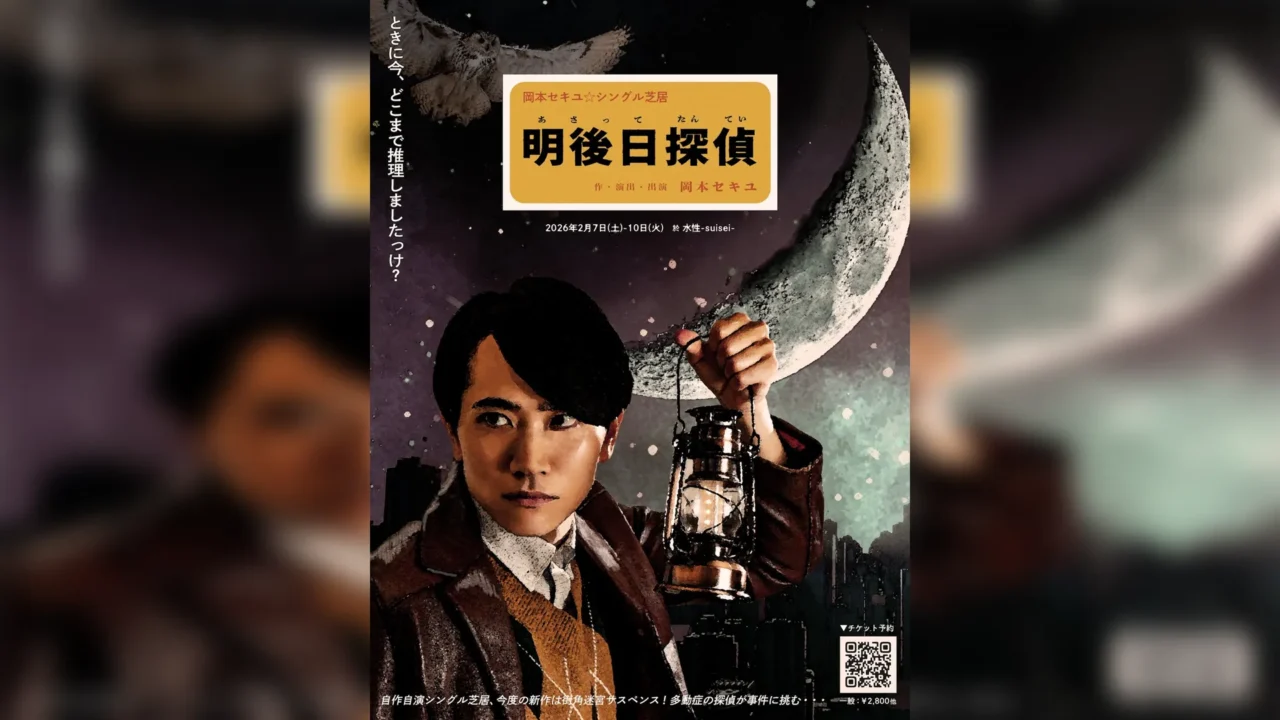INDEX
若者が担うこれからのフェス。多様性と専門性のバランスの中で
―『ロックフェスの社会学――個人化社会における祝祭をめぐって』(2016、ミネルヴァ書房)では、バブル経済の崩壊以後、若者たちが希求するライフスタイルや価値観と共鳴する形でフェスが普及したとして、ミレニアム世代とフェスの結びつきに関して永井さんは論じられていました。今後の担い手となっていくZ世代と、フェスはどのように連動していくと思われますか?
永井:僕は世代とフェスを結び付けて考えているところがあるんですが、内実もそうだと思うんです。ロスジェネ世代が『フジロック』に行って、大規模なものであれ小規模なものであれ、『フジロック』的なものを作っていたのが、最近までの状況かなと。
それでは今後Z世代がどう絡んでいくかというと、送り手の立場になる人が増えてくると思っています。
ー送り手というのはアーティスト側ということですか?
永井:主催者やアーティストです。元来フェス自体がZ世代的な価値観や現代社会的な特徴を多分に含んでいると思うんです。それは例えば、リベラル性やダイバーシティ的なものだったり、あとは流動性。特定の範囲内を移動できてストーリーが決まっていないのは、ゲームのオープンワールドに近いと思っていて。若い人はそれに早くから触れているので、感覚的には馴染めるのではないかな。
あとは、周囲の学生ではイベント業界に就職している人もいますし、フェスの主催者の子どもも大きくなっています。小さい頃からフェスに連れてこられていた子が、大きくなって友達と一緒にボランティアをしたり、独り立ちした後もフェスを手伝うような形で、帰る場所としてのフェスがあったら面白いなと。

ーフェスの主催者に留まらず、参加者の方でも家族で来られている人も多いと思います。親に連れられて来た子どもが担い手になる未来はありそうです。
永井:若者が担い手になっていくことが、ジャンルやメッセージ性とも連動していて。SNSなどを通じ大量の情報にいち早く触れることで、アジアのアーティストや他ジャンルの音楽に詳しくなり、多様性のあるフェスになっていくのではないかなと思います。
とはいえ他方で、色々なものへのアクセスができるけれども、国内に視点が集中して、蛸壺化しているという懸念もあります。映画のランキングを見ても邦画が大半だし、音楽も邦楽だけでOKという雰囲気もあるのが、気になります。
ーZ世代が送り手となっていくこれからのフェスに関してお話しいただきましたが、多世代化が進行し成熟する現存フェスにおいて、新規の若年層を増やしていくためにはどうしていくのが良いのでしょうか。
永井:先にも述べたように、ジャンルを混ぜて新規の顧客を獲得する手法もあると思います。ただ、出演者を変えることが一概に良いとは言い切れないので、そこのバランス感覚が難しいですね。
ー難しい問題です。出演者が固定化してしまうと、同じ趣向のお客さんしか来なくなってしまうので、内輪になってしまうということですよね。
永井:もちろんそういったフェスもあって然るべきだと思いますし、そうではないフェスもあっていいと思います。現在は、1人がたくさんのフェスに行く状態だと思うんです。
ジャンル特化型のものにも行けば、ミックス型のものにも行く、大規模なものにも行けば、ローカルなのにも行くという風に楽しんでいるのが現状でしょう。
フェス自体が多様化しているから、下手に中身を多様化させる必要はないのかもしれない。それでも、多様化する流れと専門性を確保する流れの2つがありそうです。