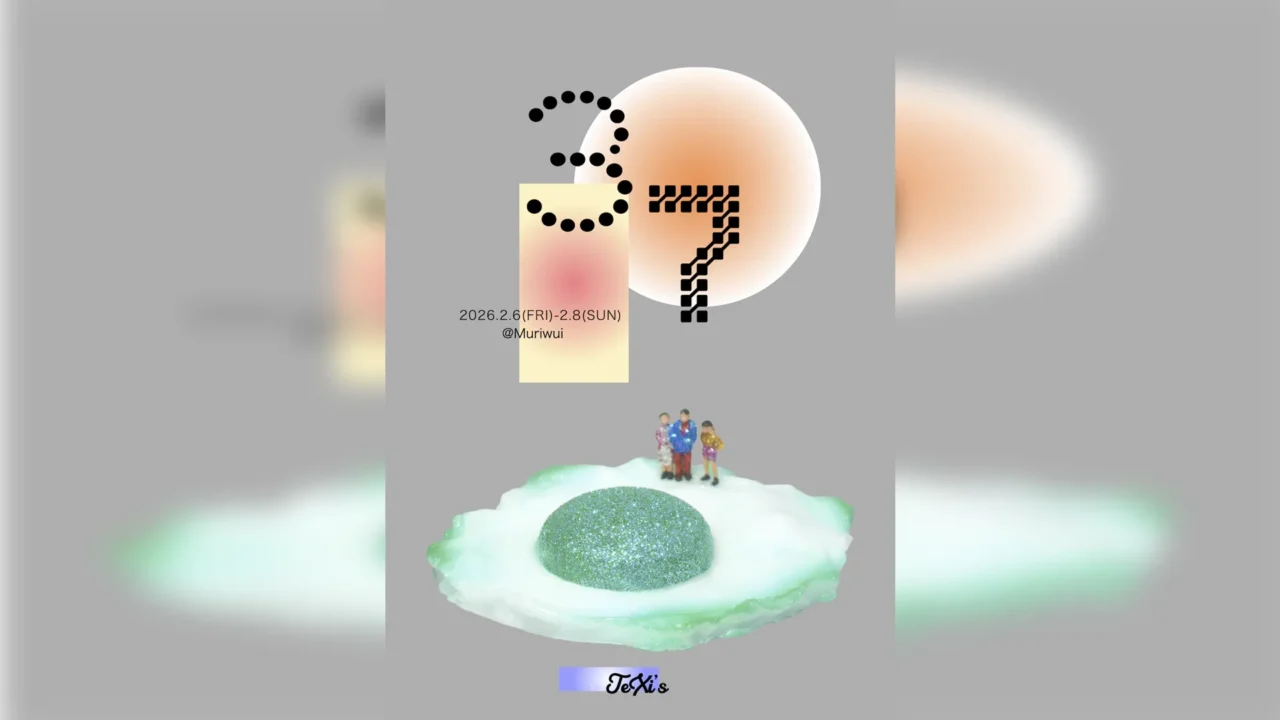INDEX
ショッピングモール型のフェスと商店街型のフェス。それぞれのメッセージ性
―『コーチェラ2023』のヘッドライナーをバッド・バニーやBLACKPINK、フランク・オーシャンと非白人アーティストが務めたように、人種やジェンダーなどの社会的ムーブメントに連動した形でブッキングが行われているように思います。こういったフェスのメッセージ性は、今後どのように組み込まれていくのでしょう。
永井:『コーチェラ』のブッキングは、トレンドや価値観、エンタメ業界のビジョンを反映した批評性のあるラインナップだと思うんです。そこまでやれているのは海外でも多くないでしょうし、日本では『サマソニ(SUMMER SONIC)』と『フジロック』になるのかな。
ただ、どのフェスも「これは〇○のためのフェスです」という打ち出し方ではないですよね。目的を明示するのではなく、環境問題や人種、ジェンダーに関するメッセージをメタ的に提示している。
多様性を反映することがマストになってきている中で、日本でもアジアのアーティストを呼んで交流したほうが面白いと思いますし、ジェンダーのことも一層向き合っていくようになると思います。

また、世界のフェスや音楽市場を見ていると、日本はドメスティックの割合が高くて。もちろん国内アーティストだけでフェスができるのは良いことですが、どうしても似通った内容のイベントが増えてしまうので、フェスとして何を打ち出したいのか、見えづらい気もします。
大規模フェスを、僕はショッピングモールのようだと思っています。イオンに行けばある程度は色々と見れるし、体験としては十分良いですよね。ただ、それでは物足りないという人が増えてきた時に、地域色をだして商店街的な役割を担うローカルフェスのほうが、大規模フェスよりユニークで面白いかもしれないなと。
ー大規模フェスがショッピングモールのような役割を担う一方で、ローカルフェスが強く好みや特性を打ち出し、メッセージ性が強まっていくという考え方になるのでしょうか。
永井:そうですね。ローカルフェスの方が成り立ちからしても興味深いかなと思います。例えばこの前記事も書いたのですが、福島の『LIVE AZUMA』というフェスは今話した形式の両者が融合しているんです。
ー『LIVE AZUMA』は2022年にスタートした、福島テレビや(『サマソニ』を企画・制作している)クリエイティブマンプロダクションが主催するフェスですが、イオン的でもありながら商店街的でもあるということですか?
永井:イオンの店舗に商店街的な尖がった店が出るような作りになっていて、最初の話とも繋がるんですが、マネタイズを考えたことでもあると思うんです。「自分たちで面白いことをやろう」というだけではなく、「継続していくために儲かる仕組みが必要だよね」とか、「地域の会社やお店に頑張ってほしいよね」ということが始点になっている。システマティックで綺麗だけれども、提供しているものは手作りでファストフード的ではないという面白さがあります。
ーファストフード的でないというのは、アーティストのブッキングに特徴があるということでしょうか。それとも、地域のお店が出ることのローカリティといった面になりますか。
永井:それもさすがだなと思ったのは、スタジアムでやっている方はスケールの大きいライブ(電気グルーヴや[Alexandros]、STUTSらが出演)、駐車場でやっている小さいほうのステージはローカルフェスくらいの規模(C.O.S.A.やALI、どんぐりずらが出演)になっていて。大きいフェスと小さいフェスを同時に開催している感覚です。
―なぜ、そのような大規模フェスと中小規模のフェスが複合した形式のフェスが登場してきているのでしょう。
永井:ネガティブな話ですが、個人や実行委員会がフェスを立ち上げて開催することが、物価上昇に伴う制作費などの高騰で難しくなってきているのかなと。そうした時に、コンテンツはこっちで作るけれど、お金はこっちが出すなど、複数の企業・団体による実行委員会が組織されて、各社の思惑がフェスに反映されることになるのだと思います。