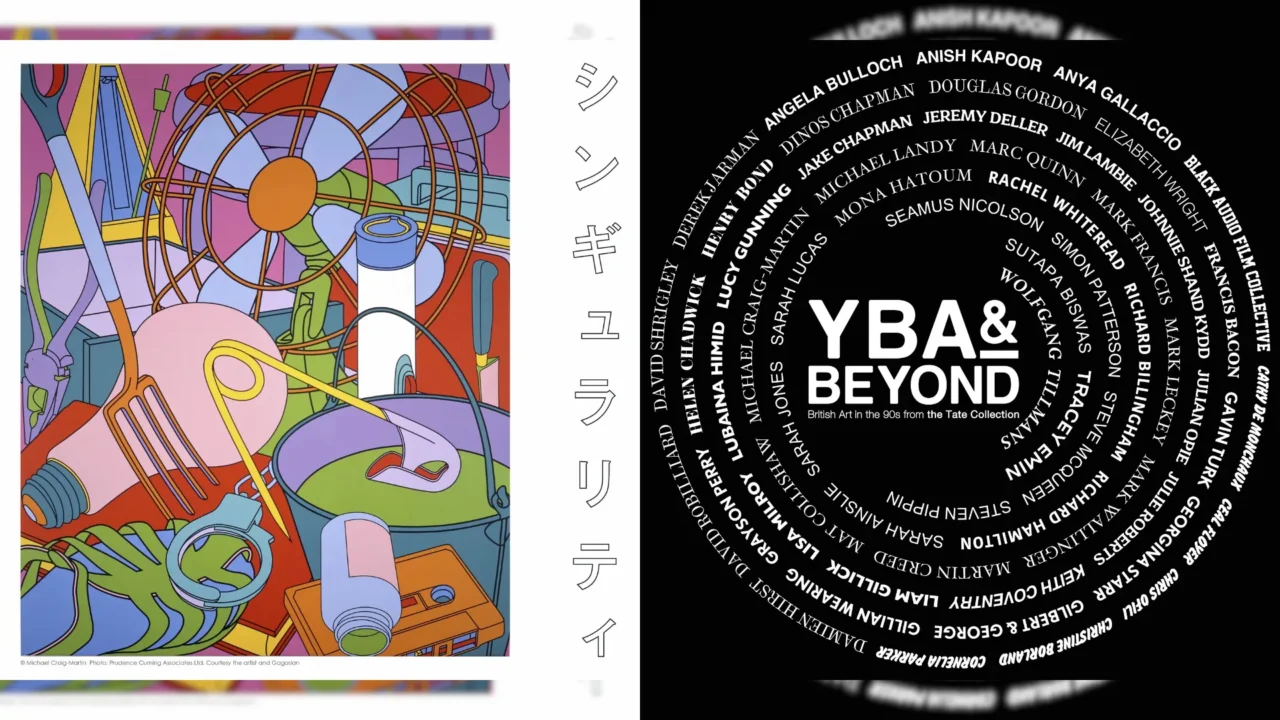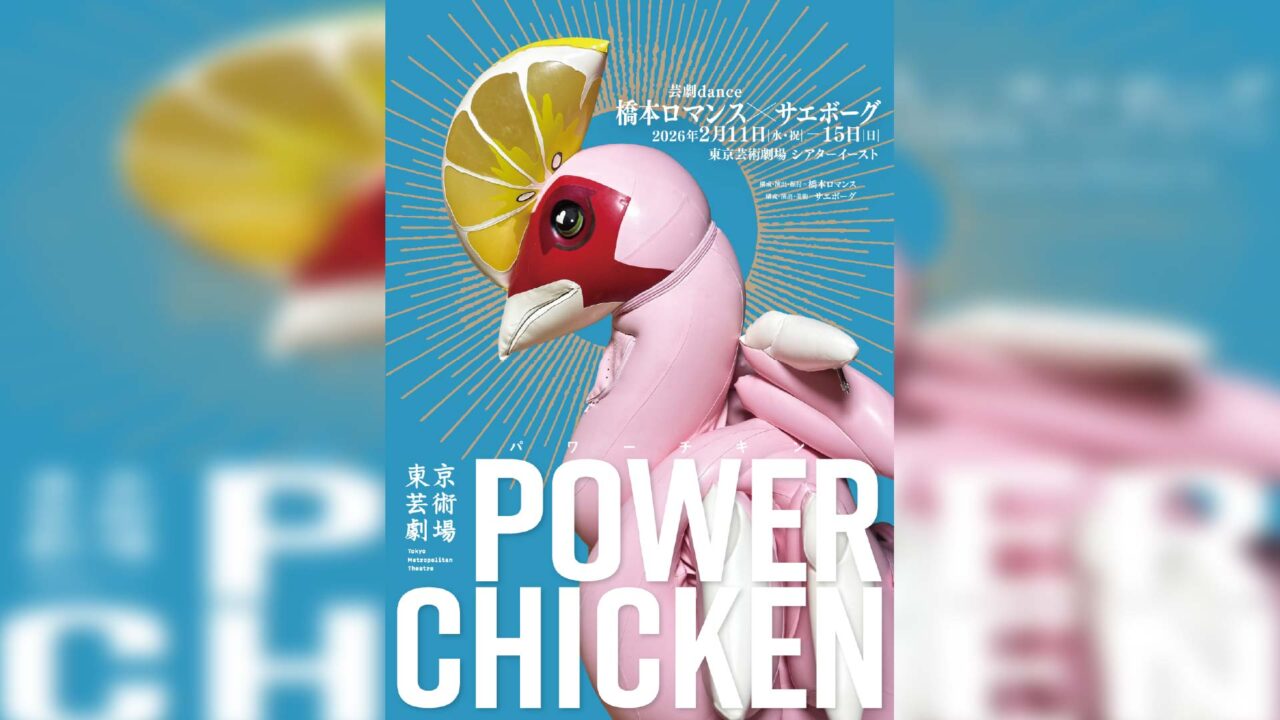現在破竹の勢いで観客動員を増やしている映画『8番出口』。音楽家の千葉広樹の連載「デイドリーム・サウンドトラックス」第1回は、そんな話題沸騰の本作をピックアップ。
映画『8番出口』は、なぜ『第78回カンヌ国際映画祭』を沸かせることができたのか。そのユニークな映画体験を、中田ヤスタカと網守将平が手がけたサウンドトラック、作中で印象的に使用された“ボレロ”と“主よ、人の望みの喜びよ”を入り口に考える。
INDEX
映画『8番出口』では、なぜ“ボレロ”が使われたのか
公開4週間足らずで興行収入37億円、観客動員260万人を突破した映画『8番出口』は、同名の大ヒットゲーム作品を原作に、主演は二宮和也、監督は川村元気という話題作。
舞台は、地下鉄の駅構内。「出口8」を目指して歩く主人公(二宮和也)が、いつまでも出口に辿り着けず、やがて自身が同じ通路をループしていることに気づく。
壁に掲示された案内板はある、「異変を見逃さないこと」「異変を見つけたら、すぐに引き返すこと」「異変が見つからなかったら、引き返さないこと」「8番出口から外に出ること」という注意書きを見つけ、さまざまな「異変」に感覚を研ぎ澄ませ、何度も地下通をループしながら出口を目指すというストーリーです。

この映画でメインテーマのように使用されているのが、モーリス・ラヴェルの“ボレロ(Boléro, M. 81)”。川村元気監督は「世界で最も有名なループミュージックだから」と起用した理由を本作のパンフレットで語っていますが、まずこの“ボレロ”が映画のなかでどのように機能していたか、という点から考えていきます。
“ボレロ”はもともとイダ・ルビンシュタインというバレエダンサーのために書かれた作品で、スペインで18世紀末に民俗音楽として存在していた舞曲、現代的な言い換えをするとダンスミュージックがもとになっています。
3拍子を基本に、延々と同じスネアのリズムが繰り返されるこの曲は、今でこそ多くの人が聴き覚えのあるものですが、調性の不明瞭化、不協和音、印象主義、新古典主義、ポリリズムなど、世界情勢とともにさまざまな様式に変化していく近代音楽史のなかでも、ストラヴンスキーの『春の祭典』に匹敵する、センセーショナルな作品のひとつです。
“ボレロ”の最大の特徴は、スネアドラムのループするビートと2つの旋律のみという極端にミニマルな構成、ピアニッシモからフォルティッシモまで約15分かけて演奏するという巨大なクレッシェンドのような構造です。
本作で“ボレロ”が使われた理由は、この特徴にあるかもしれません。地下通路という限りなくミニマルな状況で、少しずつ要素が増えていき、最後に大団円を迎えるという『8番出口』という作品の構造は、“ボレロ”と大きく重なります。“ボレロ”と『8番出口』には、ループ構造を採用したカタルシスの極みという作品体験、という共通点を見出せるというわけです。
あるいは、地下通路という見慣れた風景を舞台としたシリアスなサスペンスに、非常にポジティブな響きを持つ“ボレロ”を当てることで異化効果を増幅させるという狙いもあったのかもしれません。そうした機能面だけでなく、“ボレロ”という超有名なクラシック曲を起用するにあたっては、ヒットメーカーである川村監督の大衆的な感覚も作用しているのは言うまでもないでしょう。
INDEX
繰り返し登場する不穏なフィードバック音の役割
中田ヤスタカさん、網守将平さんのサウンドトラックも非常に素晴らしかったです。
まず印象的だったのは、シーンの変わり目で流れるギターフィードバックのようなサウンド。サンドトラック1曲目の“Growl”の冒頭に現れるこのフィードバックのようなサウンドは、全体を通してひとつの主題(テーマ)として機能しているように思いました。“Yellow”“Sprout”“Darkness”(ともに中田ヤスタカ作曲)にもにパラフレーズ的に引用されています。
所々で繰り返し出現するこの音は、ループ感、あるいは何か異質な物を暗示させるようなサブリミナル的な効果、あるいは「次に何かが起きるのでは?」という予感を醸成するトリガーのような役割を果たしているように感じます。付け加えると、観客をより映画世界に引き込む効果も見出せます。何気ないサウンドひとつとっても意味や役割を持っているというのが、映画音楽の興味深いところです。
このフィードバック音は、和声的にはF#→Dの長3度の関係性にあります。長三度は世のなかの大抵の音楽に存在するありふれた音程関係で、現代の観客にとって耳馴染みのあるもの。だからこそ映画を観る人の意識が向きやすく、印象に残るように作用したところもあったはずです。
INDEX
地を這うような電子音は、地下通路という巨大な化け物の息遣い
サウンドトラック全体に耳を向けてみます。本作では、なぜ地を這うような電子音のドローン(持続音)が使用されたのか、ということが気になりました。
この映画における地下通路は、もしかすると巨大な化け物のような存在として描き出されているのではないか——そんなことを感じさせるように、サウンドトラックが作品世界のなかに存在しています。
このことは、サウンドトラックに“Growl”(唸る)、“Pulse”(脈打つ)、”Howl”(遠吠えする)と名付けられた楽曲が収録されていること(いずれの楽曲も中田ヤスタカさん作曲)、本作の美術を担当した杉本亮さんが、地下通路自体を「ひとつの役」と捉えて制作が進んだとパンフレットのなかで語っていたこととも符合します。
本作におけるサウンドトラックは、地下通路という巨大な化け物の息遣いや実態のメタファーだったのかもしれない。そのように思われました。
作中の物語が進行するにつれて、調性の判別しにくいドローン、電子音を主体にしたサウンドトラックは、徐々に楽音的な調性を獲得していきます。
序盤では重く冷やかな電子音によるテクスチャー、重く脈打つビート、不安定なストリングス、唐突に時を分断するようなプリペアードピアノのサウンドが主軸ですが、中盤になると“Encounter”“Envounters”(ともに網守将平さん作曲)では、D♭→B♭のコード進行上に冒頭のテーマ(主題)が再び現れ、終盤の“Sea”の壮大なクリシェのなかに現れるコーラスの旋律は、冒頭の主題のリプライズとも感じ取れます。
その調性感の推移もサウンドトラックではとても巧みに、そして有機的に展開されていて素晴らしかったのですが、映画音楽の観点から見て作品全体の分岐点のように機能していたのが、ヨハン・セバスティアン・バッハの“主よ、人の望みの喜びよ”でした。
ダンテの『神曲』における煉獄を彷彿とさせる作品世界において、この曲は天上の世界を想起させるだけでなく、ある種の「スイッチ」として映画全体に作用を及ぼしています。
つまり、0番出口から8番出口へというカタルシスに向かっていく過程、作品構造のなかで、主人公の心情が絶望から希望に転換する、あるいは生命感を取り戻すにつれて、劇伴も楽音的な調性を獲得していく——そうした展開点でこの楽曲を用いることによって、いくつもの効果がもたらされている、というのが私の解釈です。