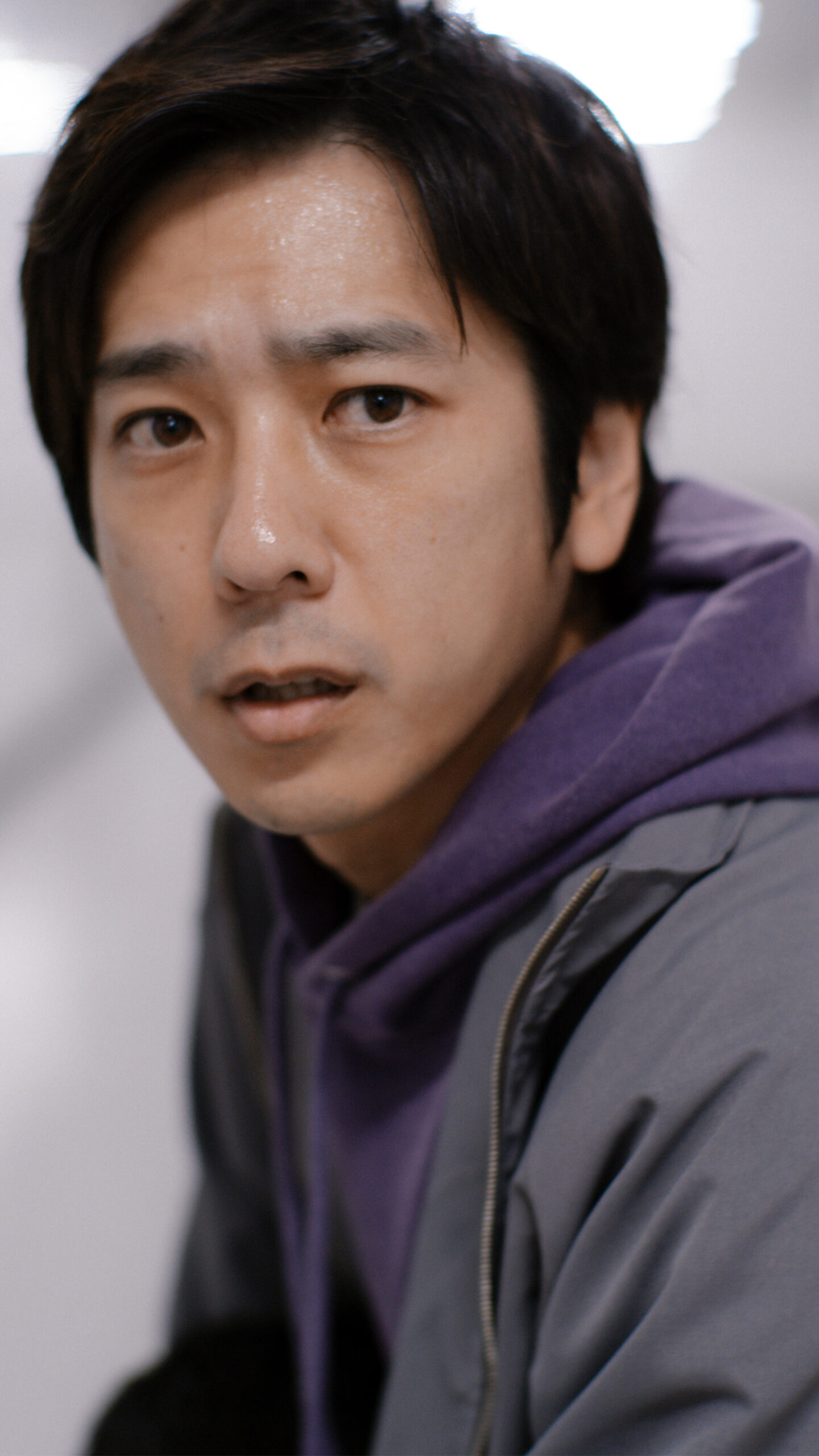INDEX
地を這うような電子音は、地下通路という巨大な化け物の息遣い
サウンドトラック全体に耳を向けてみます。本作では、なぜ地を這うような電子音のドローン(持続音)が使用されたのか、ということが気になりました。
この映画における地下通路は、もしかすると巨大な化け物のような存在として描き出されているのではないか——そんなことを感じさせるように、サウンドトラックが作品世界のなかに存在しています。
このことは、サウンドトラックに“Growl”(唸る)、“Pulse”(脈打つ)、”Howl”(遠吠えする)と名付けられた楽曲が収録されていること(いずれの楽曲も中田ヤスタカさん作曲)、本作の美術を担当した杉本亮さんが、地下通路自体を「ひとつの役」と捉えて制作が進んだとパンフレットのなかで語っていたこととも符合します。
本作におけるサウンドトラックは、地下通路という巨大な化け物の息遣いや実態のメタファーだったのかもしれない。そのように思われました。
作中の物語が進行するにつれて、調性の判別しにくいドローン、電子音を主体にしたサウンドトラックは、徐々に楽音的な調性を獲得していきます。
序盤では重く冷やかな電子音によるテクスチャー、重く脈打つビート、不安定なストリングス、唐突に時を分断するようなプリペアードピアノのサウンドが主軸ですが、中盤になると“Encounter”“Envounters”(ともに網守将平さん作曲)では、D♭→B♭のコード進行上に冒頭のテーマ(主題)が再び現れ、終盤の“Sea”の壮大なクリシェのなかに現れるコーラスの旋律は、冒頭の主題のリプライズとも感じ取れます。
その調性感の推移もサウンドトラックではとても巧みに、そして有機的に展開されていて素晴らしかったのですが、映画音楽の観点から見て作品全体の分岐点のように機能していたのが、ヨハン・セバスティアン・バッハの“主よ、人の望みの喜びよ”でした。
ダンテの『神曲』における煉獄を彷彿とさせる作品世界において、この曲は天上の世界を想起させるだけでなく、ある種の「スイッチ」として映画全体に作用を及ぼしています。
つまり、0番出口から8番出口へというカタルシスに向かっていく過程、作品構造のなかで、主人公の心情が絶望から希望に転換する、あるいは生命感を取り戻すにつれて、劇伴も楽音的な調性を獲得していく——そうした展開点でこの楽曲を用いることによって、いくつもの効果がもたらされている、というのが私の解釈です。