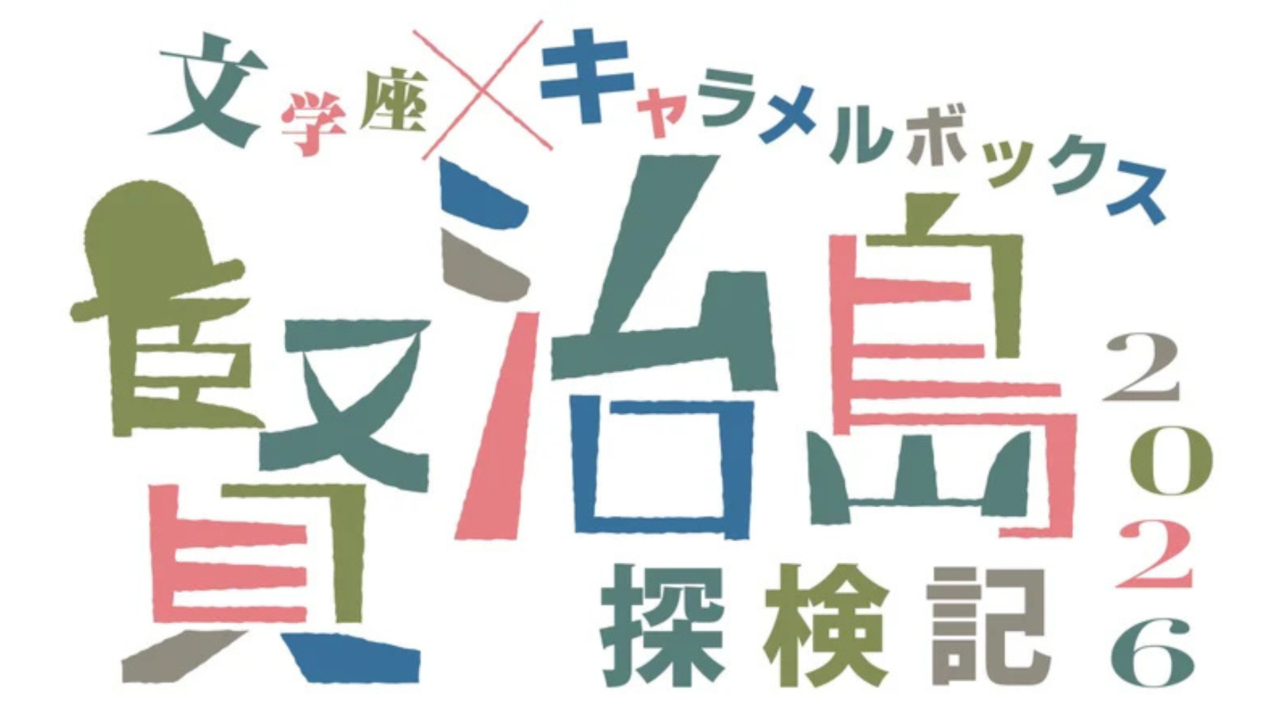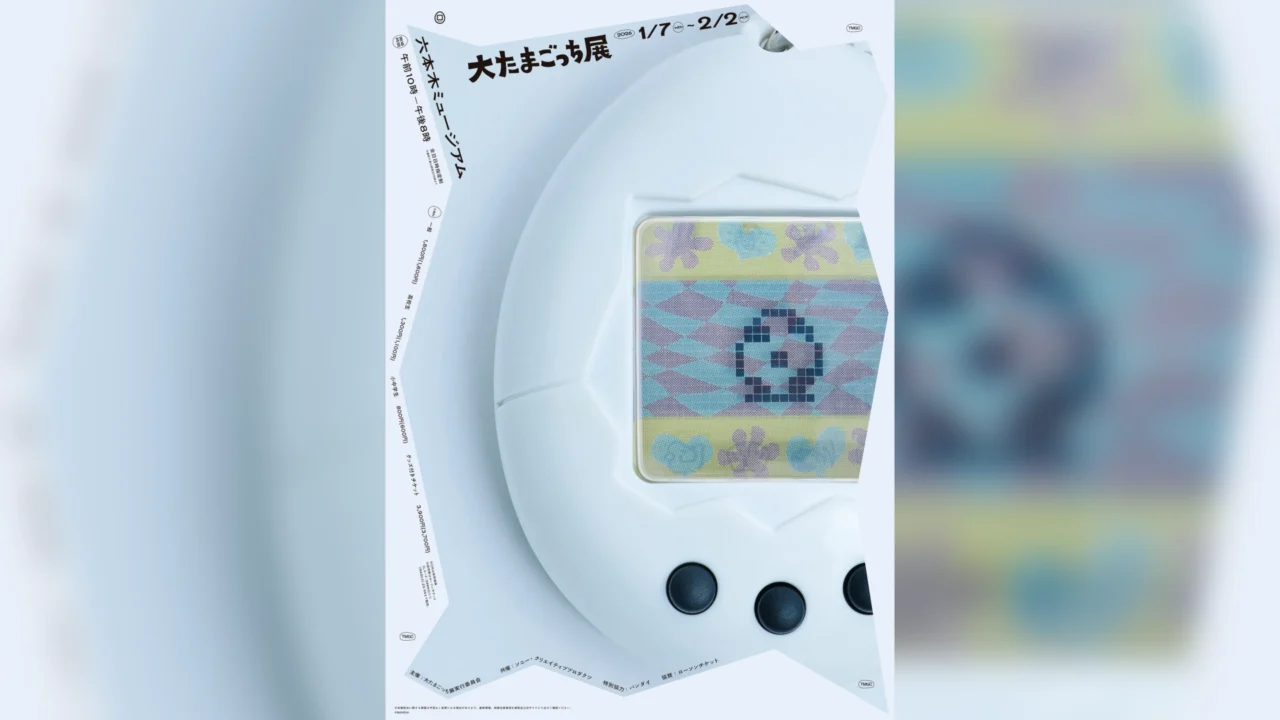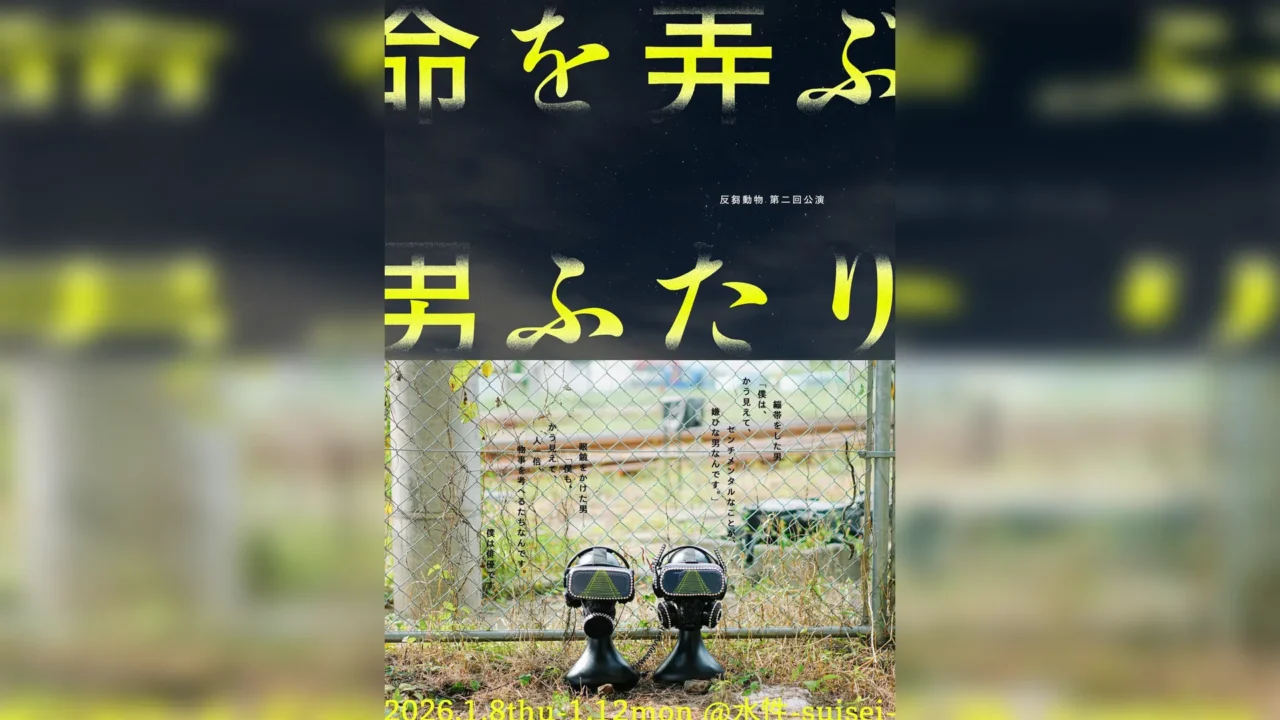ジョニー・グリーンウッドという名前を聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか? Radioheadの音楽的支柱、あるいは鬼才的ギタリストというイメージがより一般的ですが、グリーンウッドにおいては現代の大監督ポール・トーマス・アンダーソンと長年にわたってコラボする映画音楽家という側面も見逃せません。
音楽家の千葉広樹の連載「デイドリーム・サウンドトラックス」第2回は、ポール・トーマス・アンダーソン監督による最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』から、ジョニー・グリーンウッドのキャリアとその音楽的到達点について紐解いていきます。
INDEX
「良質であるが聴かれてはならない」——『ワン・バトル・アフター・アナザー』がかくもスリリングなわけ
かつて革命組織で爆弾工作員だったパット / ボブ(レオナルド・ディカプリオ)が、子育て期間を経て娘(ウィラ)を奪還するために駆けずり回るサスペンス・アクション映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』。
あらすじ:かつて革命運動に携わっていたボブ(レオナルド・ディカプリオ)が、16年ぶりに姿を表した敵と対峙し、誘拐された娘を救い出そうと奮闘するサスペンス・アクション。ボブは反乱組織「フレンチ75」に所属し、アメリカ・メキシコ国境付近の収容施設を襲撃するなど、軍と対立していた。その後、16年を経てボブは娘ウィラと共に隠遁生活を送っていたが、過去の敵ロックジョー(ショーン・ペン)が再び動き出し、ウィラが誘拐されてしまう。ボブは、娘を取り戻すため孤立無援の戦いに身を投じる。
ポール・トーマス・アンダーソンが監督・脚本を手がけ、『アカデミー賞』最有力候補と囁かれる大傑作の映画音楽を担当したのが、Radioheadの音楽的頭脳として知られるジョニー・グリーンウッドです。
2007年公開のポール・トーマス・アンダーソン監督映画『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』で、グリーンウッド自身としては初の映画音楽を手がけて以降、音楽家としての類稀なるキャリアを切り拓いています。以降、現代を代表する名監督のひとりであるポール・トーマス・アンダーソンが、自らのすべての映画作品でグリーンウッドに音楽を依頼。そのことから、両者、および映画と音楽の間には緊密かつ創造的な関係性があること想像されます。
映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』同様、映画音楽におけるグリーンウッドの到達も非常に高い次元にあることは間違いありません。それはスリリングでドラマチックな映像にぴったりな音楽を作り上げた、という意味ではありません。「ぴったり」という以上に、本作では音楽そのものが「空気」のように存在し、観客に意識させないレベルで映像と緊密な関係を築いています。
それはつまり、『映画にとって音とはなにか』(1993年、勁草書房刊)の中でミシェル・シオンが定義した「良質であるが聴かれてはならない」という第一原則を達成している、ということに他なりません。それも、既存曲も含めて劇中でほぼずっと、そしてときには爆音で、音楽が鳴り続けているにも関わらず、です。
そしてもう一歩踏み込むと、本作のサウンドトラックには21世紀以降の「現代音楽」の領域において、ジョニー・グリーンウッドを重要な作家として認識して然るべき達成も刻まれていると言うことができます。
INDEX
Radioheadの音楽的頭脳としてではない形で、グリーンウッドが才能を爆発させた原点
ジョニー・グリーンウッドは1971年生まれ、オックスフォード出身の英国人音楽家。Radioheadのメンバーとしてもっともよく知られていますが、幼少期にピアノやビオラなどの楽器を習得するなどクラシック音楽を学び、ロック、電子音楽、民族音楽、クラシックなどをミックスした独自のスタイルを築く音楽家です。
そのギター演奏、モジュラーシンセサイザーやオンド・マルトノといった電子楽器を巧みに操る姿はまさに、鬼才 / 奇才と呼ぶに相応しく、Radioheadの“How to Disappear Completely”などからもその特異な才能の片鱗が垣間見えます。
しかし、音楽家としてのジョニー・グリーンウッドの才能は一言では言い表せないほど複雑かつ壮大で、計り知れないものです。もしかするとグリーンウッドはRadioheadの中心的メンバーとしてではなく、むしろ映画音楽家、現代音楽家として、歴史に名を残す可能性すらある、と言っても過言ではないと思います。
そう感じさせるのは、何より『ワン・バトル・アフター・アナザー』のサウンドトラックが「映画音楽」として、音楽として、出色の出来であるからです。
なぜそこまでのことが言えるのか。本作での達成について考える前に、その映画音楽家として原点を振り返る必要があります。
Radioheadの6作目『Hail to the Thief』が発表された2003年、ジョニー・グリーンウッドは『Bodysong』でソロデビューを果たします。同作は、イギリスのドキュメンタリーフィルムのために録り下ろされたサウンドトラックです。
『Bodysong』はジョニー・グリーンウッドという才能が、真の意味で、遺憾なく発揮された最初の例と言っていいでしょう。
『Bodysong』と題された映画は、音と映像だけで人間の存在を描いており、音楽がストーリーテラーのように機能した作品です。サウンドトラック自体はロック、クラシック、コラージュ、フリージャズなどの要素がミックスされた音楽ですが、弦楽器のグリッサンドや、スル・ポンティチェロ(※)などの特殊奏法が使われているなど、特に“Iron Swallow”や“Tehellet”など、この時点で後の『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』へと繋がるような独自のスタイルが確立されています。この点において、『Bodysong』はグリーンウッドのソロキャリアにおける、後の映画音楽、現代音楽作品の源流とみなすことができます。
※筆者註:弦楽器の特殊奏法のひとつで、弓で弦を擦る際、極端にブリッジ寄りで弾くこと
INDEX
ジョニー・グリーンウッドの特異な音楽を紐解く「トーンクラスター」という技法
ジョニー・グリーンウッドのキャリアを紐解く最大の鍵となるのは、クシシュトフ・ペンデレツキという音楽家です。そして、今回のサウンドトラックのキーワードとなる「音の密度」、およびそれを用いた作曲スタイルとも深い関わりがあります。
ペンデレツキはポーランドの作曲家。グリーンウッドとは2012年にコラボレーションアルバムを発表しています。ペンデレツキは個々の音や和声ではなく、音の「質感」や「群れ」そのものを構築要素にし、弦楽器のトーンクラスター(密集した音の塊)、ノイズ的サウンドなどを精密に譜面化した現代音楽のパイオニアのひとりです。
グリーンウッドの音楽の根幹、そして本作の映画音楽を理解する上で、「トーンクラスター」は重要な手法です。『ワン・バトル・アフター・アナザー』の冒頭、移民収容センターのシーンで使われるM3“Baktan Cross”には、グリーンウッドのペンデレツキからの影響が顕著に表れています。
ここで、ムクドリの群れを想像してください。無数の個体が群れをなし、1匹1匹が集合・離散しながら塊となって空を飛び回る……そうした様子さながらに、オーケストラの一つひとつの音を粒子のように捉え、メロディーやハーモニーといった形式的なものとしてではなく、「物理的な要素」、あるいは「点と線」として音を「彫刻」のように扱い、音響空間をデザインするのがトーンクラスターという技法です。
トーンクラスターを用いたペンデレツキの楽曲の多くは、調性も旋律もほぼなく、純粋なテクスチャーの流動で構成されています。まさに、ペンデレツキは音を空間的存在として扱っているわけです。
しかし、グリーンウッドはこの技法をそのまま本作の映画音楽に導入したわけではありません。グリーンウッドは音響空間に、映画の登場人物の心理的要素を加えることでトーンクラスターを援用した、というのが私の解釈です。