海の向こうでその名を轟かせ続けている日本人大型野球選手の大活躍。子どもの頃の夢を叶えた上に、前人未到の記録を成し遂げた人が受けるべき賞賛が連日、パソコンの入ったバッグを背負って夕飯どきをすぎた電車に揺られる自分の目に飛び込んでくる。自分の現在地が、幼い頃の夢とはかけ離れた場所であったとしても、「こんなはずじゃなかった」と自分の夢を他人の活躍に託すわけには、まだいかない。
She Her Her Hersがリリースした最新アルバム『Pathway』は、前に進もうとしているあらゆる人の挑戦に寄り添う作品だ。長年の夢を追っている人でも、置かれた状況で「より良い」方向へともがく人でもその内容は問わない。なぜなら、バンド自身も自らと向き合い、「本当にやりたいことはなんなのか」を問い続けてきた結果、現在のメンバーでのスタイルを確立し、突然舞い込んできた中国からのオファーをきっかけに、中国での人気を自分たちのものにしたからだ。
幾度の中国ツアーを経験したShe Her Her Hersは今、バージョンアップを続け、最高のコンディションにあるという。そして2月に、最新アルバム『Pathway』のリリースツアーファイナルとしてバンド史上初であり、目標の1つであったLIQUIDROOMでの単独公演に挑戦する。新たな挑戦に臨むメンバーに、中国での取り組みや歩みを止めない理由について伺った。
INDEX
立ち止まることだって時には「前進」。『Pathway』が聴いてくれる人の「お守り」になってくれたら。(松浦)
―She Her Her Hers(以下、シーハーズ)の最新アルバム『Pathway』は、ライナーノーツによると「世を前へ後ろへ横へ進みだす8つの物語を覗きながら、それぞれの道に重なったり、ヒントが見つかったりしたら、という想い」とのことですが、テーマについて改めて教えてください。
松浦(Dr):直訳で「道筋」という意味ですが、ビジネス分野では、プロジェクトやキャリアの進行経路を指すみたいで。日々の生活でも、何かに向かって進んでいる過程はいつだって、判断して選択したのであれば道筋だと思うんです。立ち止まっている状況さえも。時には、みんなが左に進むなかで自分だけ右を選択することもあるかもしれない。その選択を笑う人はいるかもしれないけど、選択した勇気は消えて欲しくない。「どこへ行っても正解」だし、「どこへ行っても前進だよ」ということを伝えたかったんです。
模範解答のような明確な「答え」を示す作品ではないけれど、聴く人の道筋を照らす作品になり、「これは自分のための曲だな」と思える曲を見つけてくれたら嬉しいです。内容ははっきり覚えてないけど、数行のセリフが残る本や映画ってあるじゃないですか。今回のアルバムの曲に僕たちが散りばめたパンチラインが、聴いてくれる人の「お守り」のような存在になれたら最高ですね。

(写真左から)高橋啓泰、松浦大樹、とまそんによる3人組オルタナティブバンド。
2019年12月に3rd album『location』をリリース。同年、中国レーベル「Weary Bird Records(Taihei Music Group)」との契約を交わし、全7都市を廻る中国ツアーを大盛況に終え、アジア進出を成功させる。2022年3月にアルバム『Afterglow』、2023年11月にはアルバム『Diffusion of Responsibility』をリリースし、自身最大規模となる初のアジアツアー『”Diffusion of Responsibility” Asia Tour 2023-2024』を開催し、16都市17公演のワンマンを行う。2024年10月にはアルバム『Pathway』をリリースし、ツアーファイナルとなる東京Ebisu LIQUIDROOMでのワンマンライブを行う。
―なるほど。実体験が無ければ「立ち止まることも前進」だとはなかなか言えないのではと思います。これまでバンドとして足踏みした状況に陥ったことがあったんでしょうか?
とまそん(Key):2016年頃に、ギターを弾いていたメンバーの脱退などがあったタイミングで、「本当にやりたいことはなにか」をバンドで真剣に考えたタイミングがあったんです。バンド名が変わってもおかしくないくらいの転換点だった。そして、自分たちにちゃんと向き合って、前のレーベルを離れて再出発することに決めました。レーベルという後ろ盾を失うことは大きな決断だったけど、振り返ると今日のシーハーズの根幹になっている。プロフィール上は2011年結成のバンドですが、正直そのタイミングでバンドは生まれ変わったなと思うくらいの出来事でした。
ー企業で働いている人の場合、会社という後ろ盾を離れて1人で新しいことに挑戦するようなことだと思うのですが、当時の選択に後悔はありますか?
とまそん:ないですね。その後に『SPIRAL』をリリースして最初に声をかけてくれたのが中国のレーベルで。そこから今に繋がっているので、本当にやってよかったです。

ー個人で何かに挑んでいる場合、足踏みしてしまう状況からなかなか抜け出せずに、1人でもがくことも時にはあると思いますが、そういう状況を打開するにはどんなことができると思いますか?
松浦:自分がドラムとして参加する仲間のアーティスト達を間近で見てると、回転し続けることが大事だなと思うんですよね。完全にストップしてしまうことが逆にストレスになりやすい。無理に動かすのも疲れてしまう。いつも劇的な速さじゃなくていいから、緩やかでも常に「動き続けている」感覚を持つことが大事。やらなきゃいけないことがあるのに気分が乗らない時、手を動かせば終わる作業から始めてみると意外と集中できることってあると思う。
今のシーハーズは、ツアーでオーディエンスからもらったエネルギーを制作に反映するコンスタントで良いサイクルができている。回転率が高いのが、コンディションが良い証なのかもしれない。
ーバンドとしてやりたいことに向き合い続け、苦しい時も歩みを止めないことがシーハーズの哲学なんですね。その姿勢を貫いてきたこれまでのキャリアのなかでターニングポイントがあるとしたらどこだと思いますか?
高橋(Vo, Gt):やっぱり2019年の中国ツアーですね。当時は中国にオーディエンスがいることも信じられなかったし、いきなりワンマンを主体とした7カ所のツアーが実現するなんて想像もしてなかった。でも、そのツアーがあったからこそ、以降にリリースした楽曲が聴かれるようになったのは間違いなくて。
松浦:たまたまいち早く声をかけてくれたのが中国だったというだけで、もしかしたらアメリカや他の地域の国だったかもしれない。僕らには、作った音楽を楽しんでくれる土地に行きたいという純粋な気持ちしかなかった。だから聴かれていた中国で、より聴いてもらうための取り組みを続けてきた。ある意味、偶然を必然にする作業だったと思います。
ーここまでの話で、バンドとしての意思決定がスムーズな印象を受けましたが、メンバー同士で意見が食い違うことはあるのでしょうか?
とまそん:もちろん、ありますよ。でも、その都度、些細な違和感もそのままにしないで、話をする。お互いに食い違ってることを理解したら、それはそれでやりようがあるし、そうやって進めてきたDIYなバンド。一つ一つ選択しながら進めている中で、2023年にバンドを法人化したんですよ。法人として、お金のことも考えながら前に進めていくためにも、メンバーそれぞれがいろんな見方をするようになったし、同じ方向を向いているので、3人の結束力も深まったなと思います。

INDEX
エンジニアにミックスを依頼した理由。「自分もレベルアップして、もっと対等に会話できるようになりたいと思った」。(高橋)
ー作曲は(高橋)啓泰さんが手がけていますが、サウンド面としてはいかがでしょう?
高橋:そうですね、前作のアルバムはほとんどパソコンで楽曲を作り上げたんですが、今回はアナログシンセのような生の楽器を弾くことにこだわりました。2023年のツアーで味わった達成感やチームの熱量、お客さんの雰囲気をもう1回味わいたいという気持ちが強かったので、そのためには実際に楽器を弾くことが大切だったんです。パソコンで制作する方が編集しやすいんですが、生の楽器だからこそのズレや感じられる体温や人間らしさを大切にしたかった。結果として今まで以上にバリエーションが豊かな作品になったと思います。
そして、前回のツアーより規模が大きくなったので、大きい会場でお客さんをいかに巻き込むかを考えた時に、サウンドをブラッシュアップしたいと思いました。そこで、新しい風を取り込むために、The fin.のYuto(Yuto Uchino)、宇多田ヒカルなどもやってる小森雅仁さん、Tempalayなどを手がけている奥田泰次さん、3人のエンジニアにミックスを依頼しました。自分が作る延長線で人の力を借りて広げていこうと思ったんです。
松浦:啓泰がそこに寛容になったのが大きいと思っていて。前は、自分でやりたい人だったから。おかげでいい味が出ているアルバムになってるよね。
高橋:前までは、人に任せると自分の思考が止まっちゃうような気がしていたんです。でも、自分もレベルアップして、専門の人ともっと対等に会話できるようになりたいと思うようになりました。次作はまた自分でやってみたいですが(笑)。

ークールだけど静かな熱量を感じさせるシーハーズのスタイルは独自のものだと思うのですが、どのように確立されたんでしょうか?
高橋:自分の曲ばっかり聴いてます。できたデモをずっと聴いているんです。他の音楽にも触れた方がいいのかもしれませんが……(笑)。
松浦:坂本慎太郎さんが言ってた「自分が買いたいと思うようなレコードと同じようなものを作りたい」をなんだかふと思い出したわ。原動力。模倣のなかにオリジナルが見つかる時もあるよね。
INDEX
酸いも甘いも経験することが、人としての豊かさだからこそ「選択」を続ける。(とまそん)
ー歌詞についても伺わせてください。”Strawberry Picking”の<成果だけ得られるはずない / 大抵の人生は / いちご狩りではないさ>は、努力の先に進歩があることの見事なメタファーだなと思いました。
松浦:幼い頃、おかんにいちご狩りに連れてってもらった時に見た、農家のおじさんが手塩にかけて育てたいちごの説明を聞かず、我先にいちごを食べようとしてた参加者の姿が脳裏に焼き付いてて。子どもながらに「(説明を聞くことを)早送りしてあのいちごはほんとに美味しいのかな」みたいな感覚になったんです。味はまあまあ同じかもしれないけど記憶にはあまり残らない気がしていて。工程に夢中になれたら完成形は自然と愛せるはずだなと。はい。
ー曲のタイトルでさえも、実体験に基づくものだったんですね。とまそんさんが作詞した”moreish”の<酸いも甘いも しゃぶり尽くせよ everybody / 粋も曖昧も 味わえよ 全部>は、効率主義の社会で上手に「こなして」生きようと思ったら出てこない言葉だと思いました。
とまそん:本当に僕たちは酸いを味わったからこそ甘さがあったし、その喜びも実感できたんです。そのダイナミクスがあることが人として豊かだと思うし、そうありたいからこそ選択するんだと思います。
選択したものがどう転ぶかは自分次第だけど、そもそも選択しないと始まらないじゃないですか。誰かにおすすめされて選んだものに自分の意思があるとは言い切れないと思うんです。意思を持って選択したことが自分の身になっていく経験を積み重ねていきたいし、そういう人がもっと増えてほしい。そしたら世界はもっとおもしろく見えるはずだから。
松浦:今のとまそんは開眼しているというか、出てくる言葉が面白いフェーズに入ってるよね。
とまそん:2024年の8月からフィリピンのセブ島に移住したんですよ。今はセブと日本と中国の3カ所を行き来してて。「いつかタイミングがあったら海外に住みたいな」って前から思っていたんですけど、タイミングは待ってても一生来ない。自分で作るもの。自分が動くと、自然と状況もついてくる。やってみないとわかんないっていうか、山に登ってみないと見えない景色もあるので。そういう、最近感じた「やってみることの重要性」が自然と歌詞に表れているのかもしれないです。海外移住を考えてることを2人に話した時は「おもしろそう」って前向きなリアクションが返ってきたのもありがたかったですね。
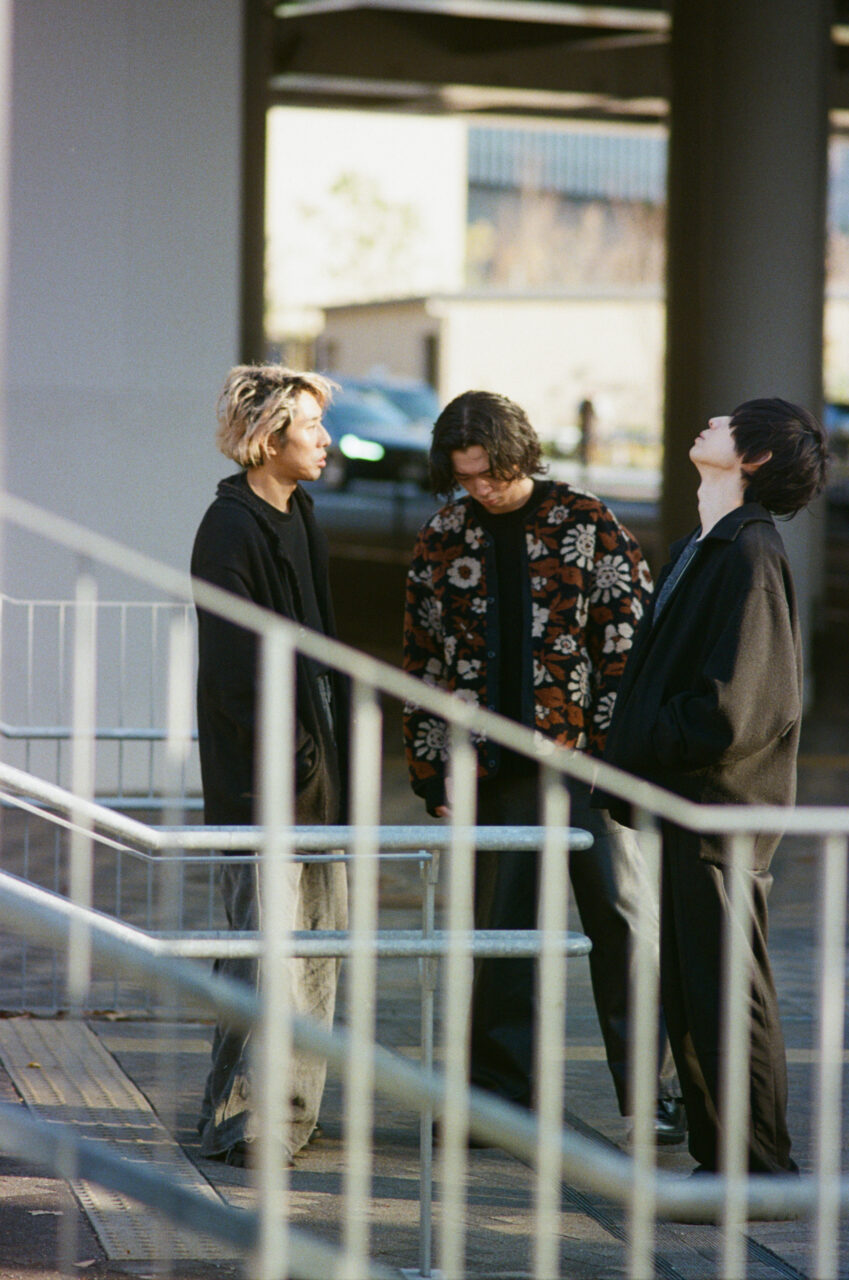
ー日々の生活の忙しさに身を委ねてしまうとつい、自分が「本当にやりたかったこと」を見失ってしまうこともあると思います。「やりたいことをやる」とは、子どもの頃の夢を貫くことなのか、置かれた状況で自分が心踊る方向に向かうこと、どちらだと思いますか?
とまそん:「やりたいこと」はどんどん変わっていくけど、情熱がある事の方がよっぽど大事。子どもの頃からやりたかったことが今も変わらないのであれば、それはそれですごく素敵なこと。大人になったって、やりたいことを見つけちゃったならやってみればいい。でも、多くの場合僕達は「やらない理由」を無意識に探してしまう。子どもの時のように気軽に一歩目を踏み出せる心持ちが大事。違うなと思ったらそれはそれでいい経験になるはずで。結局、何歳から始めるのも全然遅くないんです。僕も中国語の学校に通っていて、「40代で今さら新しい言語を学ぶなんて」という気持ちもありましたが、やったらやった分だけ伸びるんですよね。




























