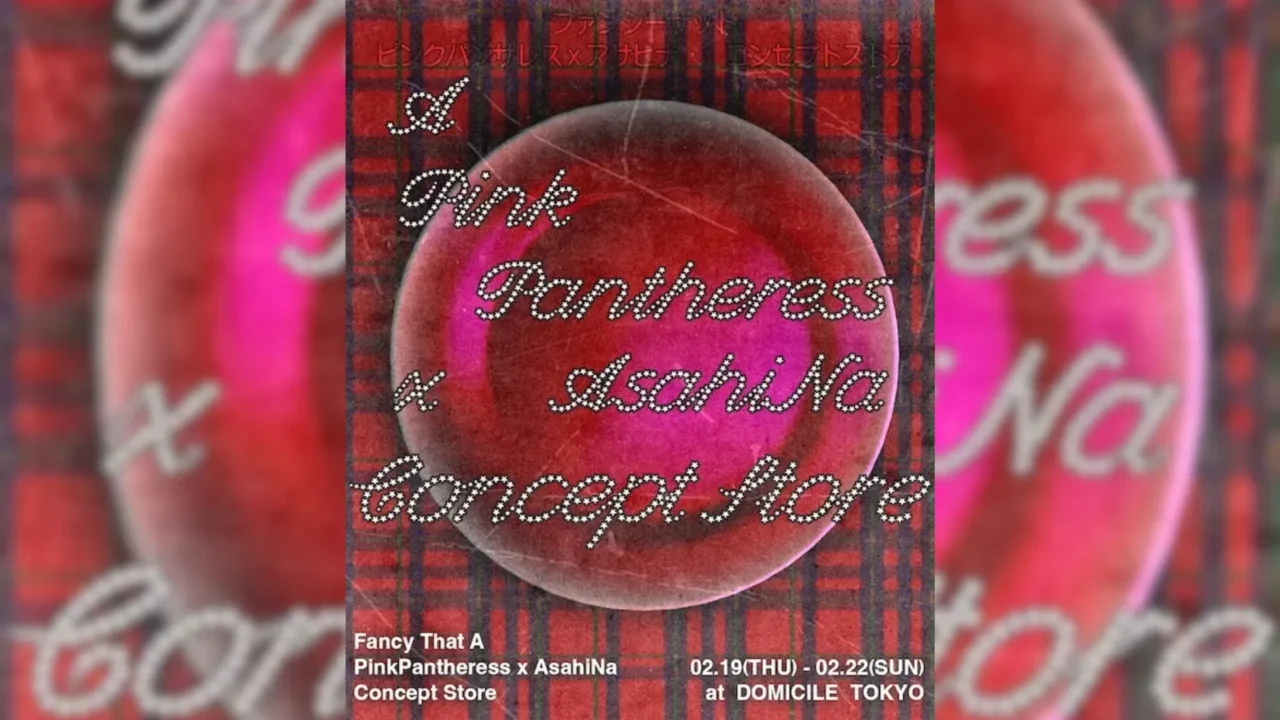INDEX
受け継がれてきた音にそっと違和感を忍ばせることで生まれた、無国籍なサウンド
─また、今作ではフィールドレコーディングを行なっていますね?
小瀬村:今回は、ミャンマーのナガ族の音源を使わせていただいています。井口寛さんという、もう10年以上付き合いのあるレコーディングエンジニアの方がいるのですが、彼は年に何度かミャンマーに滞在し、現地の伝承音楽を記録する活動を続けているんです。あるとき井口さんから、「面白い音があるから良かったら聴いてみてください」「もしなにか使えそうなら自由に使ってくださいね」と、いくつかの素材が送られてきました。その中には、村で歌われている歌を収録したアルバムや、多くのフィールドレコーディングが含まれていて、非常に興味深いものでした。
そうした素材と、今回コラボレーションしたジャティンダー・シン・デュルハイレイによるディルルバ(インドの伝統楽器)を組み合わせていくうちに新しい音楽が立ち上がるような感覚も得て、1曲目の”SECAI”と4曲目の”Lore”が生まれました。この2曲はプロジェクトの初期に完成した楽曲で、その方向性を示してくれた、アルバムの中でも重要な位置付けです。
─1曲目“SECAI”に収録されているナガ族の言葉は、英訳すると<Let’s stop fighting. Let’s also stop lying, stealing, and speaking ill of others, because it is not good>という詩の朗読でしたが、先ほどお話されていた「分断」に対するメッセージにも取れますよね。
小瀬村:そうなんです。井口さんから送られてきた音源の一つだったんですけど、英訳と解説を読んだときに、心から感動しました。歌そのものも、村の長老がアカペラで静かに語りかけるように歌っていて、言葉の重みと響きが本当に唯一無二なんですよね。
僕がそこに音楽をつけることで、あの言葉をもう一度、別の文脈で紹介できる。そこに意味があると感じました。アレンジは控えめに、音数も少なくコードをそっと添える程度にとどめています。それでも、どこか不思議な響きがありますよね。不協和音のようでありつつ、風通しの良い音像というか。

─一方、畠山美由紀さんが歌う“Autumn Moon”は、「百人一首」の79番、左京大夫顕輔(藤原顕輔)の和歌がそのまま歌詞になっています。
小瀬村:僕自身はそこまで詳しいわけではないのですが、百人一首は日本に古くからある「詩の形式」として象徴的な存在ですよね。それを現代の音楽に取り入れて、「新しい日本の音楽」として提示できたら面白いと思ったんです。
前作『SEASONS』でもそうでしたが、もともと僕は季節や風景にインスピレーションを受けて曲を作ることが多く、「景色を音で描く」ことに強い関心を持っています。今回の楽曲も、笙の音から始まり、シンセサイザー、尺八、二胡、ストリングス、そしてジャズギターまで加わるという、あまり例のない編成にしました。いろんな音楽的要素が混ざり合っていて、どこかに「違和感」があるようなサウンドになったと思います。
まずは僕がトラックやメロディーをすべて考えてから、畠山さんに声をかけました。もともと畠山さんの音楽がとても好きで、日本語の響きや言葉を大切にしているところにも共感していたんです。実は畠山さんも百人一首にとても親しみを持っていらして、それを聞いたときは本当にうれしかったですね。
─和楽器をフィーチャーしつつも、いわゆる「オリエンタルな響き」ではなく無国籍なサウンドになっているのが、アルバム全体を通して感じる魅力だと思いました。
小瀬村:ありがとうございます。和楽器は音にすごく存在感があるので、全体が引っ張られすぎないように注意しながら構成しましたね。むしろ、和楽器の響きに少しだけ異物感や違和感を加えることで、耳なじみがありながらも新鮮に聴こえるような、そんな音像やアレンジを目指しました。