「本日は僕のひとつの区切りになる公演になります」。
少し前のことになるが、2025年1月、LINE CUBEで行われたワンマン公演『笑う亀裂』の前夜、君島大空はこんな言葉をXに投稿していた。このインタビューは最新EP『音のする部屋』のためのものであったが、まず本作にも深く関わっているであろう君島大空が「区切り」と表現した言葉の意図について話を聞いている。
「区切り」とは、君島大空が音楽を作り続けてきた「動機」と密接に関係しているようだが、ここではその「動機」に具体的に立ち入ることは避けている。なぜならそれは、この音楽の可能性、聴き手の関係性を閉ざしてしまうことになりかねないからだ。その代わりにデビューEP『午後の反射光』(2019年)からの6年間、君島大空という音楽家がどのような音楽を、いかなる意図から生み出してきたのかを振り返った。
鍵となったのは“午後の反射光”と“Lover”という2つの楽曲。君島大空はその音楽を通じて、一体何を表現してきたのだろうか。
※NiEWでは後日、君島大空『音のする部屋』の全曲解説を公開予定
INDEX
君島大空が迎えた「ひとつの区切り」とは何だったのか
―LINE CUBEのワンマンは君島さんにとって「ひとつの区切り」という位置づけだったとのことですが、この言葉を使ってどんなことを伝えたかったのでしょうか。
君島:……難しいですね。今の活動の仕方って、『午後の反射光』(2019年)を出した頃に思い描いたものとは全く違っていて、LINE CUBEでバンドでワンマンやって、しかもソールドアウトするとは全然想像してなかった。伝えたいことも最近変わってきていると思うし、そういう節目でもあったと思います。
―あの日のライブは、小曲的なイントロダクションを経て“午後の反射光”で始まり、“Lover”で本編が締め括られました。ライブの内容から、君島さんのデビューEPの表題曲“午後の反射光”から、あの当時の最新曲“Lover”に至るまで期間を「ひとつの区切り」としているのかなとも思ったんです。
君島:そうですね。
―そうやってひとつの節目を迎えた今、君島大空のデビューからの6年間を改めて共有しておいたほうがいい気がします。
君島:僕も最近、めっちゃそのことを考えます。

1995年、東京都青梅市生まれ。ソングライター/ギタリスト。ギタリスト/サウンドプロデュースとして、吉澤嘉代子、アイナ・ジ・エンド、ゆっきゅん、細井徳太郎、坂口喜咲、RYUTist、adieu(上白石萌歌) 、高井息吹、など様々な音楽家の制作、録音、ライブに参加。2019年 EP『午後の反射光』を発表後から本格的にソロ活動を開始。2025年3月、4th EP『音のする部屋』をリリースした。
―まず前提の確認をすると、『午後の反射光』から1stアルバム『映帶する煙』(2023年)までは、おそらく君島さんの中に明確にある「音楽を作る『動機』」が純度を保ったまま楽曲となってこぼれ落ちてくる、というような作り方をしていましたよね?
君島:『映帶する煙』まではかなり地続きに続いてます。自分の遍歴の振り返りというか総括で、アルバムの半分ぐらい占めている昔の曲も出すならこのタイミングってことがあったので。
―その9か月後に出した2ndアルバム『no public sounds』(2023年)で、そことは違う可能性が見えてきますね。
君島:『no public sounds』は、作る理由を自分のことにしなかったんです。それまでは作る理由が全部自分の過去や自分の周りのことや気持ちに紐づいていたけど、この作品は友人の作った映画が制作のきっかけ、ブースターになっていて、その中で友達の音楽に刺激を受けてできた曲があったり、Skrillexみたいな曲を作ろうと思って四つ打ちの曲(“˖嵐₊˚ˑ༄”)を作ってみたり。
君島:それ以前は、そういう気楽さで制作に取り組むことに対してすごく嫌悪感があったんです。僕はかなりこねくり回すタイプで、特に『午後の反射光』のときは「パッと作る曲に価値があるのか」って思っていたから、1曲に何年もかけるのが当たり前だった。
―君島さんがそういうスタイルだったのは、音楽を作る「動機」自体が、君島大空というひとりの人間、その生きてきた時間そのものに密接に関係しているからでは、と思うんです。
君島:そうだと思います。自分が音楽を作る「動機」そのものにタッチして、人には見せられないものをポップスとして出すことにすごく抵抗があって。そこまで自分の心を削いで音楽を作ることは果たしていいことなのかってことも思っていたし、同時に低カロリーで「いい歌っぽいもの」を作って生きていくのは嫌だってこともずっとありました。
―そういう葛藤の中で、「動機」そのものを明かすことはなく、それでも君島さんはその音楽を聴き手が自分のものにしながら受け取れるようにも作ってきましたよね。
君島:うん。僕はそういう秘匿の仕方をずっとしていると思います。
INDEX
君島大空のサウンドの秘密が刻まれた『午後の反射光』

―君島さんが6年間、何を表現し続けてきたのか掘り下げるべく、『午後の反射光』からの作品を振り返っていきたいのですが、このEPの表題曲には君島大空のサウンドシグネチャーが全部入っていると感じます。
君島:やりきりにいってますからね、これ。
―しかもそのサウンドは歌詞の世界と呼応するように機能している。
君島:うん、歌詞に合わせて変えたりしましたから。
―逆再生された音、軋むような電子音、躁的な音の連なり、フィードバックノイズやドローン、具体音のコラージュ……ギターと歌の表現にこうしたサウンドを織り交ぜるのは、すごく記名性の高い表現のあり方だと思うのですが、そこにはどういう意図があったのでしょうか?
君島:理由はいっぱいあって、まず歌詞もその一要素であるし、歌詞にリンクした映像の演出装置としてその音が必要だからっていうのがあります。あとは、逆再生のアコースティックギターって何か始まるような気がして昔からすごい好き、みたいな単純な理由もあるし。
僕がやりたかったのは、日本語で、歌があって、その周りで鳴っている関係なさそうな音も全部が関係しあっていて、それが僕の支配下で有機的に機能している音楽だったんだと思います。そうやって自分の音楽を作る中で、それまで好きで聴いていたミュージックコンクレート(※)のような音楽も仲間外れにしたくないって気持ちもありました。
―さっきフィードバックノイズと僕が言い表した音も、おそらく君島さんの中で「ノイズ」という認識ではないですよね?
君島:そうですね。ノイズだと思って出してないと思う。このEPは強烈に映像ベースかもしれないです。夕方で、風が吹いていて、木が揺れてて、っていう映像、景色をどう表現していくか、って話で。例えば、“夜を抜けて”は実家の坂の上のイメージで作っていて、バイオリンの弓で12弦ギターを弾いて風の音を表現してみた、みたいな工夫をしています。
※人の声、動物の声の音のような自然界の音、鉄道の音のような都市の環境音などの具体音を録音、編集、音響処理して制作された音楽のこと
―つまり映像や景色を、音楽に置き換えるように作っていると。映像の話が出ましたけど、最初の取材ではアンドレイ・タルコフスキーの名前を挙げていました。タルコフスキーの映像的な美観が、君島さんの表現したい映像と重なる部分があったんでしょうか?
君島:そうですね。単純に映像のテイストが僕が見たい世界に近かったのと、物語を見せるという映画ではないところがすごくしっくりきて。(松永)つぐみさん(※)に教えてもらったのかな。
※君島大空のデビュー前から親交のある映像作家・写真家で、“遠視のコントラルト”や“19℃”“向こう髪”などのミュージックビデオなどを手がける
―もうひとつキーワードとしてあったシュルレアリスムは、どういうところに共感したんでしょう?
君島:シュルレアリスムも、つぐみさんと話していく中で知って。ただ、シュルレアリスム全般にめっちゃ共感するかと言われたら、別になくて。当時、何に共感したかっていえば、関係ないものがひしめている感じで。ひとつの額の中に一見関係なさそうなものがあって、作り手によって支配されていて、表現としてちゃんと貫かれていることに安心したんです。
―先ほど話してくれた君島さんのやりたかった音楽像と重なりますね。
君島:僕はエレクトロニカとか音響派と呼ばれる音楽も好きだし、いわゆる弾き語りの音楽もメタルも好きだけど、それを1曲の中で全部やるのは変だと思っていて。でも何か方法論があるんじゃないかと模索していたときにそういう芸術に出会って、「できるじゃん!」ってなったんだと思う。何かひとつにジャンルを縛らず、自分の好きな音楽を全部1曲ないし、作品1枚の中でやろうとしたのが『午後の反射光』です。
―“午後の反射光”にある組曲的な構成、テンポチェンジによる時間が伸縮する感覚は、君島さんの音楽に頻出する要素ですが、これはどういう意図があるのでしょうか。
君島:戻したくて、時間を。すごく大切な曲だったり、好きな曲を聴いているときにしかならない気持ちってあるじゃないですか。そういう曲を聴いているときって時間がちょっと止まるし、戻る感じが僕にはあって。自分の音楽を聴いた人の体感時間も延びてほしくて、そういう仕掛け、という意図があります。
それに時間の伸縮は、ずっとあるテーマで。音自体でもそうだし、1曲の中でいろんな場所に連れていけるもの、同じ場所にいながら景色が変わっていくようなものが作りたいんです。部屋から一歩も出なくても、めまぐるしく見えているものは変わっていって、1日の中で思ってること、気持ちは変わっていくよね、っていう自分の情緒に正直に曲を作った結果こうなっていると思います。
―どうして君島さんはそういう音楽を作っているんでしょうね。
君島:自分の記憶のどこかに急にどんって戻りたい欲求が常にあるし、会えなくなっている人に会えるような音楽を作りたいってことが動機としてずっとあるんです。
そういう音楽って歌詞にフォーカスしていくパターンが多い気がするんですけど、自分は違う何かをやりたかった。言葉だけで満足しちゃいけないと思っているから、「戻ってる」って言ったとき、音でも同じように表現されていてほしい欲求がすごく強くあります。
あなたが笑う度に その潤んだ右の眼から
溢れ出す光の中でいつか会えるなら
すぐに教えなくちゃ ずっとここにいたんだよって!
きっと伸ばした指先が 空をまためくるよ
君島大空“午後の反射光”より

―実際に時間が伸縮するようなサウンドと呼応して、“午後の反射光”では<溢れ出す光の中でいつか会えるなら>と歌っています。
君島:“午後の反射光”は全く違う時間の流れにあるものを1曲の中で表現したかったんです。組曲っぽくしたくなかったんですけど、結果そうなったのは、「ここでこの場面」「ここでこの時間」っていう映像ベースのディレクションだからだと思います。
―“遠視のコントラルト”の歌詞にも、<焼きついたまま化石した景色を ただ見ている まだ見ている>とあります。一瞬の情景を引き伸ばして、音と言葉で形にする、ってことは、おそらく君島さんの音楽を作る「動機」にすごく密接に関わっていますよね。
君島:そうですね。でもこのEPって聴き手に開いてはいるけど、「わかる人だけわかれ」って思って作りすぎているから、今より全然閉鎖的だなって思います。でもそれが素直でいいなと思いますけどね。
容易く色は変わって 遠視のレンズ越しに消えた
どこまでゆくの? もう止んだ雨の中に
抑え込んだ笑みの影だけ残して
焼きついたままの化石した景色を
ただ見ている まだ見ている
反射した光の果てを掴めて消えてゆく
君島大空“遠視のコントラルト”より
INDEX
デビュー作の反響に戸惑いながら、新たな可能性を形にした『縫層』
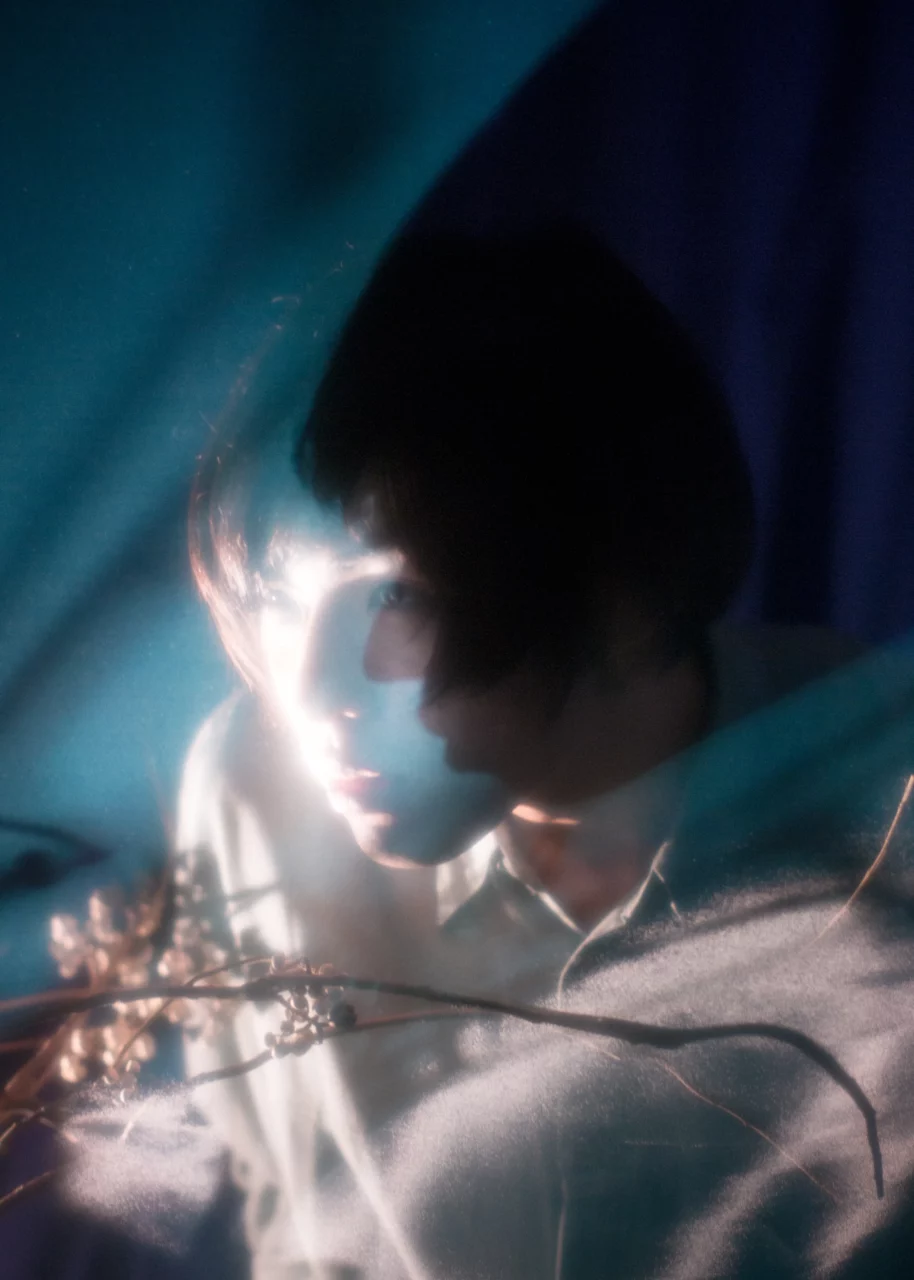
―デビューEPから4か月後、シングル『散瞳 / 花曇』を発表します。
君島:“散瞳”は『午後の反射光』が出てすぐ、ただ音楽が楽しいってテンションで作って、“花曇”はこねくり回したと思います。『午後の反射光』はあの時期にああなるべくしてなったもので、「自分の名刺になるようなものを」と思って作った作品だったんです。
それが思ったより聴いてもらえたショックで、「聴いてくれた人たちに向けて、何か新しいもの」って視点が出てきて、自分の中の空気がガラッと変わって。それでもともとの感覚を取りこぼしそうになって、次の『縫層』(2021年)も外圧というか、作ろうとして作ることのストレスとかジレンマが正直めっちゃありました。
―『縫層』は新しい可能性がいくつも出てきた作品で、1曲目の“旅”では初めてエレピを弾いています。
君島:そうですね、ギターは弾いてない。これは『午後の反射光』より前のめっちゃ昔の曲で。自分のマインドセットを初心に戻したくて、1曲目に配置した感じです。後半に入れたノイズは声ですね。声を歪ませて加工したやつ。
―このEPの表題曲は『午後の反射光』と共通のサウンドシグネチャーがありながら、複雑な拍子感覚や複雑なキメのような要素も表出してきています。
君島:僕、あまり変拍子が気にならないんですよね。7拍子が普通にインストールされている感覚があって、キメのセクションとかもギターを弾いてたら勝手にこうなった感じです。このときは、『午後の反射光』で思ったより自分のやりたいことができてしまったことのプレッシャーがあって、前作を超えなきゃって気持ちで作っていました。
―“笑止”みたいなエアー感がほとんどない曲は今でこそいくつかありますけど、その起点はここだったのかなと思います。
君島:そうですね。“笑止”は本当に人と初めて作った曲だったんで、当時は正直、抵抗がありました。背伸びをしていろんなことをしてみようってEPだなと思います。自分の体に合ってない動きを、(西田)修大とか、(石若)駿さんの力を借りて、やろうって感じでした。
―“傘の中の手”はLINE CUBEでもやっていましたが、どんな位置づけの曲なんですか? リズムも不思議な弾む感じがあります。
君島:それはドラムを叩いて録ってみたら、自然にできました。8分の6拍子だけど、歌は付点で伸ばしているから歌だけ聴くと4拍子的で。この曲はサビで直接的に言いたいこと言えたし、「こういう歌詞、書けるんだ」って思いました。サウンドは開けていて明るい曲なんだけど、ハーモニー感があまりポップスっぽくないもの、ちょっとブラジリアンなものを作ろうって気持ちもありました。
痩せた魔法と笑いたがるあなたと手
三つ編んでご覧、扉棚引く
ね!眠りの中で歌ってたあの日
「寸でのところで飲めば嘘だよ」
君をずっと待っていたようだ
君島大空“傘の中の手”より
―“笑止”でメタル的なもの、“傘の中の手”でブラジリアン的なものという『午後の反射光』には表出してないサウンドスタイルが出てきています。
君島:きっかけの1枚って感じですね。多分、自家発電のやり方に迷っていて、今までのやり方で続けると、新しいサウンドスタイルは取り入れづらくなるかもしれないって悩んでたと思います。もっと気を抜いて作りたかったけど、過去の自分の影みたいなものに邪魔されながら、友達の手を借りて作れたものです。
INDEX
危うげだが、素直な言葉が紡がれ始めた『袖の汀』

―次の『袖の汀』は過去2作と比べて音数が絞られているのも印象的ですが、彼岸の音楽というか、「君島さん、生きてる……?」って聴き返しながら思いました。
君島:生きてなさそう(笑)。
―ちょっと不安になりました(笑)。まず聞きたいのは“向こう髪”はガットギターの超絶技巧と歌が印象的ですが、冒頭やサビ前にドローンの音が入っています。
君島:ぐわーんってやつ。あれは声です。
―どういう意図だったんですか?
君島:“旅”にも共通する話ですけど、明確に対比ができる要素があるほうが綺麗だと思います。よく思い返す映像があって、浅めの川で、水面がキラキラしていて、川底を踏むと土煙がぶわーって立って、っていう。土煙と光みたいな対比がすごく好きで。ただ綺麗な音が鳴っているだけでもいいんだけど、周りが濁ってると、より透けて飛んで聞こえてくる気がするんです。『午後の反射光』からそういうアプローチをしています。
―このEPが彼岸の音楽なのではと思ったのは、“白い花”に<幽霊みたいになって>という歌詞があること、あとこの曲の導入の拍子とテンポが曖昧で、ここではないどこかから歌っている感覚があったのも理由で。
君島:ああ。本当にざわざわしてるだけというか。こういう帰り道ってありませんでしたか? 暗くて、家に向かって歩いているんだけど、「今どこ? 暗っ」みたいな(笑)。
―そういうことを音楽にしたいと思う理由は?
君島:そういった明言されていない自分の中の景色を作りたいと思うんです。あと、聴いた人が「こういう気持ちのときあるわ」って思えるものって、共感性があるもの、ないものありますけど、その虚を突きたいというか。自分の中にある映像のストックを音に置換していくことにはすごく興味があるし、ずっとやってきていることですけど、ただ単純にそれだけってことが僕の場合、すごく多いかもしれないです。
―あと“銃口”は冒頭、<あなたのことを誰にも言えずにいる>という告白の前に、<(ねえ、まだ黙って、待ってる?)>って歌詞があって、これも君島さんがここにいない感じがありました。
君島:“銃口”は多分、作ろうと思って作ってないんですよね。
―この曲の後半、音像が崩れていきます。
君島:これは本当にめちゃくちゃで。2mix(ステレオで書き出した音源データ)をモノラルにしてコンプに過入力したら、位相がぐちゃぐちゃになるんです。その処理はマスタリングの段階でやりました。
―それはどういう意図で?
君島:このEPを作り終えたときの気持ちはあまり覚えてないんだけど、彼岸って言葉はかなり近いかもしれないと今思いました。僕の音源って最後の曲が1曲目に帰ってくるんですけど、このEPはしてない気がするんだよな。出したときは「戻ってる」って言っているんですけど、行きっぱなしな感じがする。
―『袖の汀』で重要なのは1曲目の“光暈(halo)”だと思うんですが、彼岸に渡ろうとしている君島さんをこの曲が繋ぎとめている感覚があります。
君島:“光暈(halo)”ができて作ったEPではあるし、戻って来れる場所ではありますね。それに比べると“銃口”は破滅的に終わっていく。だから“光暈(halo)”は今聴いてもいいなって思うし、“銃口”は逆に考えすぎちゃっているのかな。崖から飛び降りるように直接的に言おうとするんだけど、ずっとたじろいで全部は言わずにいる。苦しい曲だなと思いますね。
それこそ自分が音楽をやる「動機」をメンバー以外の人にずっとシェアできずにいたんですけど、この時期、七尾旅人さんとか寺尾紗穂さん、butajiさんをはじめ、僕が好きだった音楽家に出会って話すことができたんですよね。だからこのEPでは選び取る言葉がより自分の気持ちに素直になり始めていると思います。
いつか会えたら
忘れてしまっても
知っていたよと言って
白い波が全て攫っても
同じだけ打ち寄せる光量
君島大空“光暈(halo)”より
INDEX
徹底的にサウンドプロデュースを追求した『映帶する煙』

―キャリアを俯瞰してみると『袖の汀』はどこか危うさがあって、でも次の『映帶する煙』はその道を行き切る方向にはいかなかったですね。
君島:そうですね。『袖の汀』はちょっと違う場所かもしれない。
―『映帶する煙』の表題曲も“銃口”と同じような処理がされているかもと思いました。
君島:結果的に似てるんですけど、これは少しプロセスが違っていて。『映帶する煙』を作ったときにサウンドデザインのリファレンスがあって、ブレイク・ミルズとか、フィービー・ブリジャーズのプロデューサーのイーサン・グルスカが左右のチャンネルの限界より後ろで音を鳴らしていたんですね。
ギターをそこに飛ばして音場を広く確保できれば、ドラムも過剰なEQ処理せず、ナチュラルなサウンドが作れるんじゃないかって。1曲目はその結果から生まれた実験場のような音です。2021年から2022年は定位の研究をずっとしていました。ずっとミックスを自分でやってきたし、『映帶する煙』には自分の成長が見える処理が随所にあると思います。
―音場に対する関心、研究の背景にはどんな意図があったんですか?
君島:作品に収録される音の限界値を考えていて。自分の中にある手法のストック、サウンド処理の工程がプリセットに固まってきたのが嫌で、新しい方法論を作りたかったのと、「音をもっとよくしたい」っていうエンジニア、プロデューサー的な脳みそでこの作品は考えていました。
でも、クソつらかったですね……。制作中、何にもうまくいかない時間が来ちゃって、ミックスが全部よくなくて本当に落ちきって、酒を飲んで、気絶してみたいな2週間ぐらいがあって。廃人みたいになってました(笑)。
―それだけ曲作りよりもミキシング、エンジニアリング的なもの比重が高かった?
君島:そうですね。理由としては、デビューからのまとめを1stアルバムとして出す、って意味合いがあったからで。自分ができることを全部やりきらないと気が済まなかったし、半分以上昔の曲だったのも大きくて、ソングライティングではそんなに悩まなかったかな。
君島:それまでは、ガンガン音を重ねてからどう処理するかを考えていたけど、『映帶する煙』は最終的にこうしたいって処理が見えているから、サウンドのイメージに対してどう音を録っていくのかが難しかった。「1人でやることじゃねえ!」って思いながら、なんとか狙った形になったんですけど、マスタリングアップを確認して3か月ぐらいは聴き返さなかったですね。「もういい」ってなって(笑)。
―制作の過程で聴きすぎたのもあるでしょうし。
君島:やっぱ念が強すぎて。それに『映帶する煙』は「1曲1曲を聴いてください」って作り方だったから、僕の中で作品として貫いている流れはないんですよね。重いなって思います。
―本人的にはそうなんですね。“ぬい”の冒頭にギターのノイズが入っていますけど、これは?
君島:あれはギターを録ろうとしたら、勝手に入ってて「ええやん」って(笑)。
―意図していない音なのか。不思議と気持ちがほぐれるというか、よい作用があります。
君島:この音のエアー感のおかげで、曲との距離感が掴めるというか。このアルバムは今までに比べるとコントロールしようとしすぎているかもしれないです。よりサウンドプロデュースに頭を振り切ってたから、勝手に鳴っちゃった音に対して「これいいじゃん、採用」みたいことを徹底的にしてない。でもそうした結果、あり得ないぐらい病んだっていう。出したことで、すごくせいせいしましたね。
―“光暈”は合奏形態で再録されています。この曲はそのままつるっと出てきたと『袖の汀』の取材で話してくれましたけど、君島さんの意図が感じられないというか、不思議な曲で。
君島:そうそうそう。
―この曲は、海に行って作った曲という話もありました。海は命が生まれる場所であり、帰って行く場所とよく言われますが、その相反するものが一緒にある感覚、生と死の両方があって落ち着くような感覚は君島さんの音楽の故郷、原点なのかなと改めて思ったりしました。
君島:明るくも暗くもありますよね。希望があるのか、絶望があるのか。“光暈”はすごいところから歌ってくれてる感じがします。自分が作った歌なのに、歌われてる感じがする曲ですね。歌うと元気になります。
INDEX
「自分の外側」、他者との繋がりをエネルギーにした『no public sounds』

―次は『no public sounds』です。
君島:奇跡のアルバムだ。
―『午後の反射光』や『映帶する煙』は、ある意味、遺書みたいな念がこもった作品のような気がしますが、『no public sounds』はこれからも続いていくことが念頭にある作品のようにも感じます。
君島:言ってしまえば、『映帶する煙』ができたときにそう思えなかったんですよね。悔しさのほうが全然勝ってて。サウンドプロデュース的な面での達成はあったけど、圧倒的に見えてないもの、できなかったことが多すぎて全然ダメだった。
―総括をしにかかったがゆえに、自分への要求も相当高かったってことだと思いますけど。
君島:『午後の反射光』でやった方法、サウンドテクスチャーって未だにすごく好きで、何歳になってもできるし、それを『映帶する煙』で一度やりきったつもりだったんですけど、「やりきったって思ってんじゃねえ!」って自分にムカついてました(笑)。
―自分に厳しい(笑)。世の中的には『no public sounds』で君島さんの活動規模がもう一段変わった認識かと思いますが、本人的にどんな位置づけですか?
君島:ここからモードが変わっていて、「その場のノリで行ったれ!」っていうかなりチャラい気持ちで作ったアルバムですね。それはすごく大事なことですけど、楽な感じで作りました。単純にミックスが速くなったとか、自分の技術の向上を感じたし、楽しいまま制作は終わりました。
―この作品は、君島さん自身と作品の距離感や動機との関係性が以前のものとは違うような感触があります。
君島:そうですね。『no public sounds』は今まで歌ってきたことはあんまり言ってないんじゃないかな。わからないようにしているというより、単純に動機自体が違う曲が多い。あとこの辺りで「こういう曲できたんだけど」って共有できる友達に出会っているから陽の気がある作品だと思います。
ゆっきゅんとか、映画『暁闇』(2019年)の監督の阿部はりかさんとか、あとはトリオの2人(ベースの藤本ひかり、ドラムスの角崎夏彦)とか、参加してくれた友達のおかげスペシャル(笑)。合奏で録った曲は1曲もないし、ドラムも石若さんが2曲、トリオで2曲かな。
―リリース時、音楽の取り巻く状況を踏まえて、「なくなってしまった場所に克明な居場所を見つけようとする実験です」とコンセプトノートで発表していましたが、ストリーミングで音楽を聴くことが当たり前になった時代に、誰にも聴かれることのない歌への眼差し、「音楽の居場所」に対する君島さんの視点を感じて。君島さん自身に基づいていた音楽を作る「動機」が、そうやって自分の外側にあるものも増えていった。
君島:うん。
―これまでで一番、他者を受け入れているというか、聴き手が暮らしている現実や社会と繋がっている感覚があります。
君島:オープンだし、単純にポップだなって思います。でもあまり振り切った感じもしてなくて、自分の中では、このとき出会った友達と一緒にやったって意味で実験性が高いかもしれないです。
























