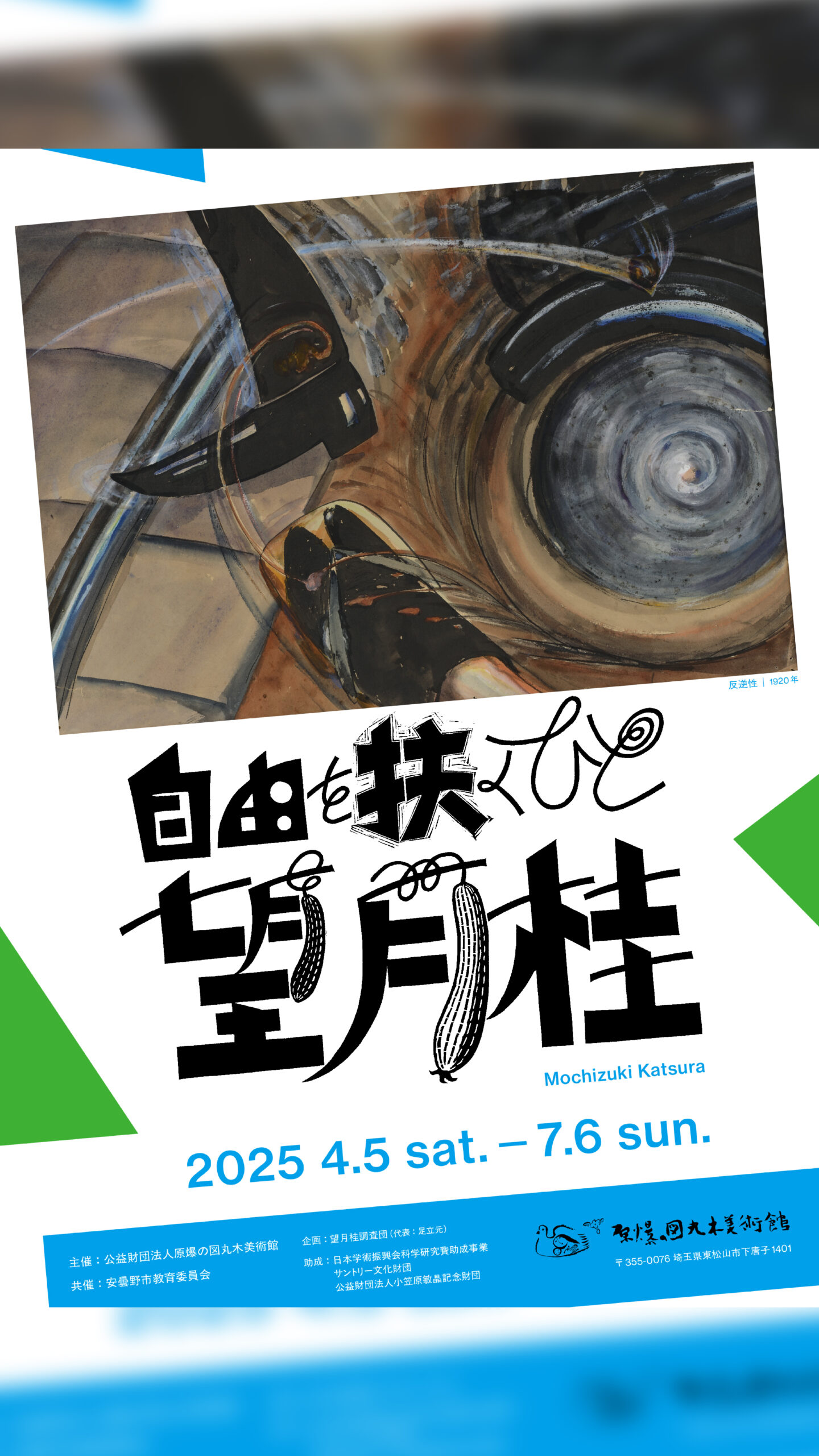INDEX
「ニューイヤー」である2026年に、美術界が向き合うべき大衆とは
南島:2025年は『万博』の影響で、文字通り建築界は大衆に向き合った1年だったはずです。そのサバイブ術から学ぶべきことはたくさんあると思います。特にSNSでの発信に関しては、『あいちトリエンナーレ2019』「表現の不自由展」のネット炎上のようなトラウマもあり、美術界はかなりセンシティブになっていた気がします。それをもう少し開いていく方法を探っていきたいところです。美術館での経験も踏まえて個人的に思うのは、ネットならではの多様性もあれば、現場ならではの多様性もあるということです。自分ならこの2つをどう繋ぎ合わせることができるかな、と最近は考えています。
杉原:ある種、若い人たちにアクチュアルに届く言葉や場みたいなものを自分たちはセッティングできてないという危機感は、美術メディアの内部の人間たちには結構ある気がします。少なくとも、僕はこの数年、それをひしひし感じています。大衆というか、すごくコアなファン以外に届く場をいかに作れるかみたいなことは考えますね。
中島:2025年を1つの区切りとして捉えたときに、2010年代から続いていた、政治哲学者であるリチャード・ローティの言う「文化左翼」みたいな今までのモードが明らかに大衆に通用しなくなっている、ズレてしまっているということを美術界は自覚すべきだと思っていて。この分断と紛争の時代に、2010年代までの左翼活動やリベラリズムはいわばオールドリベラルになってしまった。2026年以降はそれを乗り越えるモデルをみんな本気で模索すべき段階に入っていると思っています。
南島:一応、2025年は昭和100年でした。2026年は、昭和の日本を象徴する1964年『東京オリンピック・1970年の大阪万博』の反復として行われた『東京オリンピック』や『万博』が終わった次の年でもあるので、その蓄積を踏まえて、ある意味では新しく何かを始められるニューイヤーだと言えるかもしれません。
ー「文化左翼」という言葉について、もう少し詳しくお聞きしてもよいでしょうか。
中島:「文化左翼」はリチャード・ローティの言葉で、社会を実際に改良していく左翼ではなく、文化的なポストモダニズムをベースに、記号操作をしている左翼のことを指します。ここ5、6年、2010年代後半からずっとポリティカルコレクトネスやDEI推進が続いてきている。題目としては立派なことなんだけど、少なくともこれまでのやり方はあまりにも独善的だったり、すごく恣意的だったりする部分が強くて、ダブルスタンダードを隠せなくなってきていて。もう大衆レベルでは通用しなくなっているという感覚があるんですね。
杉原:政治に引き付けて言うと、高市政権やトランプ政権の支持率が結構高いのをどう捉えるか、ということかもしれません。表現の世界にいる人たちは、これらの政権に批判的な人が多いと感じますが、そこで共有し合っている空気と、世間が持っている空気がどうやら違うらしいぞというのが数字的にも表れてきている。この状況をどう見ていくか。そういう意味でも2026年は注目の年かもしれないですね、アメリカの中間選挙もあるし。2025年はアートというより政治の状況自体が想像の斜め上を行っていて、良くも悪くも目を離せない感じはありました。
中島:池田さんは海外での活動も多いかと思いますが、2025年を踏まえて今後の動きはどのようになっていくと考えていますか?
池田:2025年に私が注目していたのは、アーティストが主導するプロジェクトや作品ではなく、例えば「集団」そのもの、いわゆるアーティストコレクティブだけではなく市民活動を含めた実践が芸術祭や展覧会に登場し始めたという点ですね。『ドクメンタ15』などで紹介されてきた出店形式が国内で増えてきた印象があります。例えば、『六本木クロッシング2025展』にも参加している山形のコレクティブ「アメフラシ」は、自分たちの活動を「市民アトリエ」と位置付け、長年にわたって取り組みを続けています。もしかすると、こうした市民活動を含む実績の紹介が美術館で今後増えていくのかもしれないというのは、2026年に期待するところです。