INDEX
偏りや限定性こそが、作品と鑑賞者に親密な関係を生む
──「私はこの作品に24年間取り憑かれていた」。
ターセム監督は、本作の実現を夢見続けた自身の半生をこう語る。しかし意外にも、公開当時の興行はそれほど振るわず、大成功とは言い難いものであった。つまり、多くの人がこのおとぎ話の始まりを見逃してしまったのである。だが、そのことこそがこの映画をより特別なものにしたのかもしれない。
商業的に苦戦した公開から20年近くが経とうとする今、この作品は忘れ去られるどころか、むしろ時の経過とともに、劇場の暗がりを愛する人々のあいだで幻の映画として語り継がれてきた。二度と忘れられない白昼夢として、まるでとっておきの秘密を打ち明けるように、お互いの鑑賞体験を囁き合いながら、人々は本作の伝説を大切に育ててきたのである。
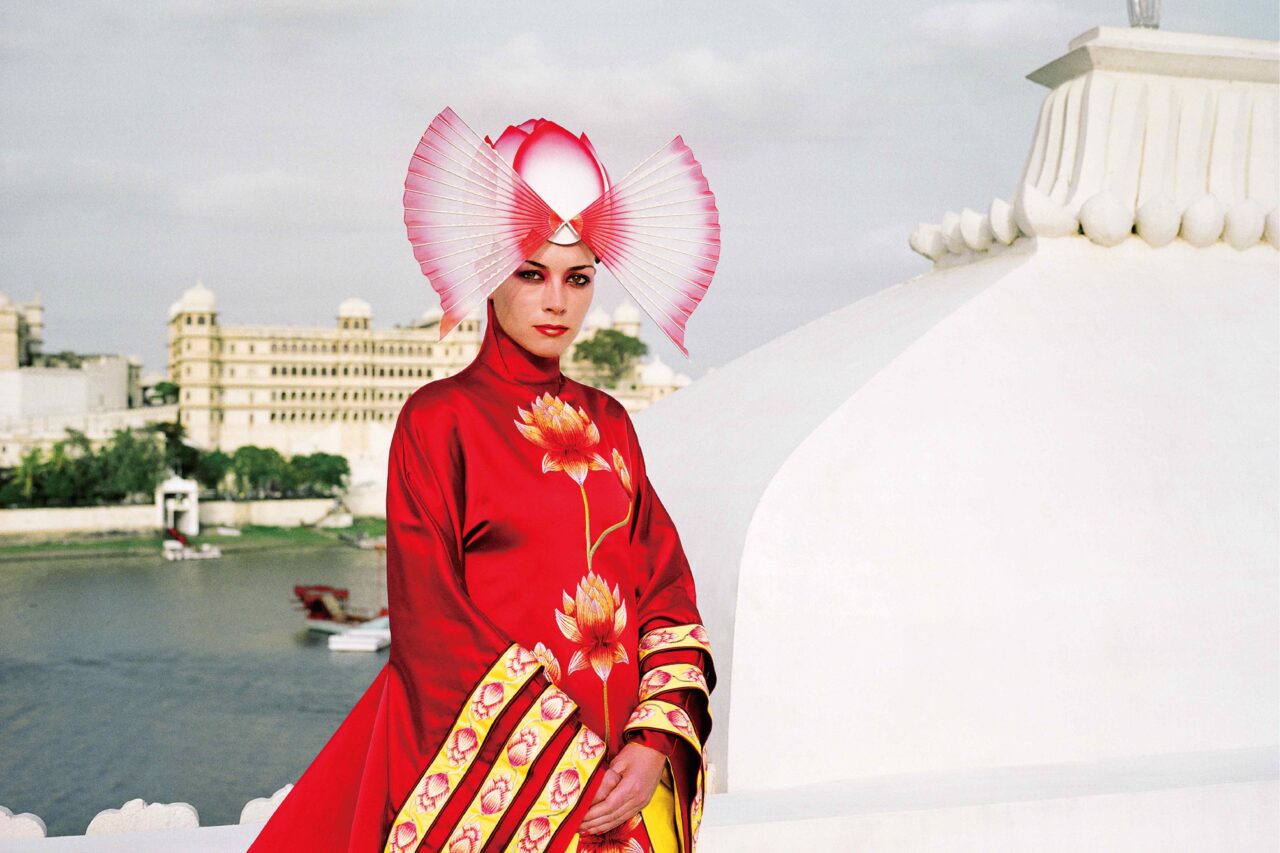
この点にこそ、21世紀の映画史における本作の重要性があるといえるだろう。作品としての普遍的価値よりもむしろ、その偏りや限定性こそが、作品と「私」、そして「私たち」との関係において特別に親密な意味をもつ映画であること──これが本作が「カルト的」と呼ばれる所以である。
本作の原点には、監督がヒマラヤの学校で過ごした幼少期に、先生が語ってくれた物語の思い出がある。先生は子どもたち一人ひとりの顔を見ながら、その感想やアイデアを取り入れ、山賊や海賊が活躍するわくわくするような即興の冒険譚を語ってくれたという。その物語は先生だけのものではない。語り手である先生と聞き手である子どもたちが一緒に紡いだ物語であった。
本作のメッセージの核心も、まさにその物語を介した語り手と聞き手の心の交流にある。
























