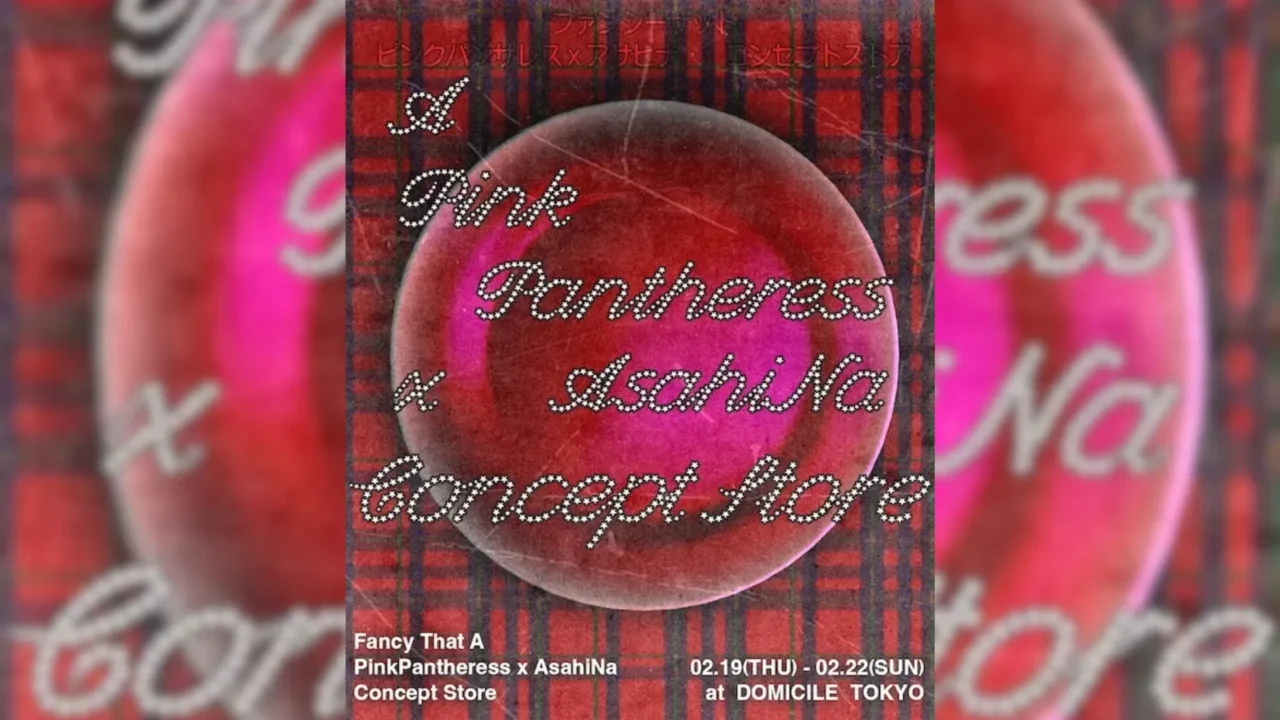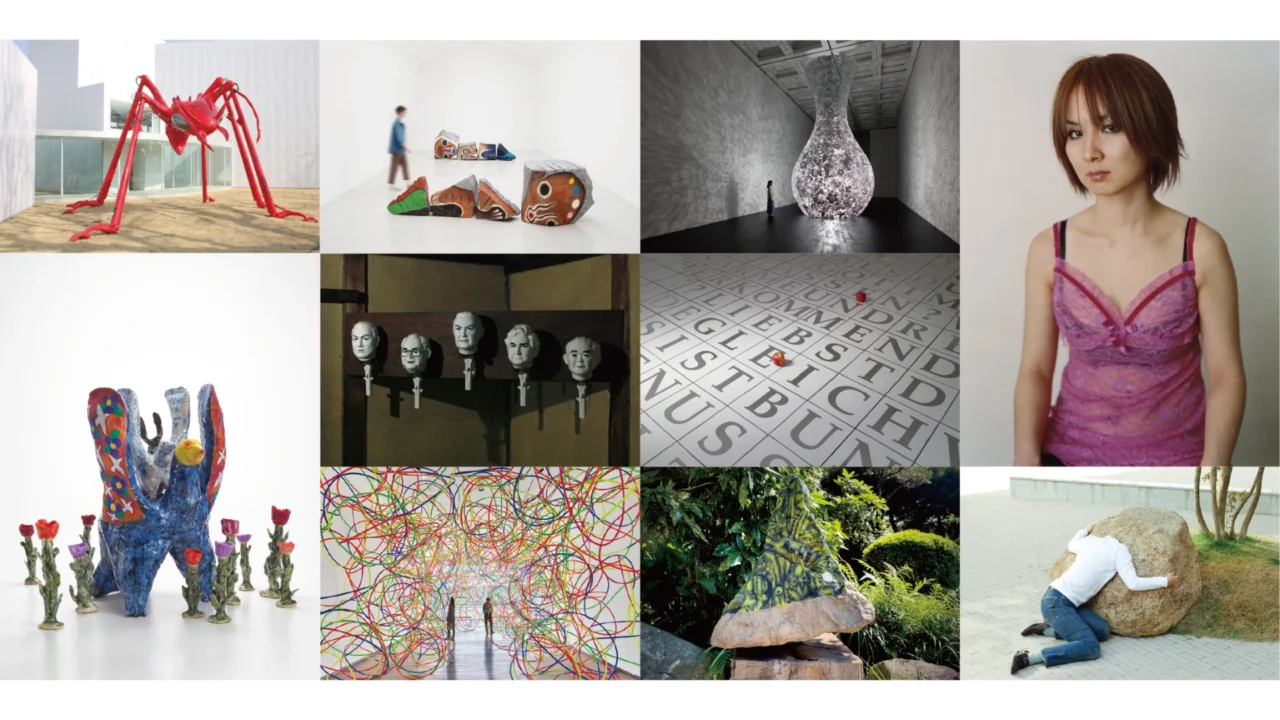ヨアキム・トリアー監督最新作『センチメンタル・バリュー』が、2026年2月20日(金)より公開となる。第78回カンヌ国際映画祭ではグランプリを受賞、3月に発表される第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞を含む主要8部門で9ノミネートされており、最有力候補の呼び声も高い。テリー・キャリアーの“Dancing Girl”(1972年)をはじめ、劇中を流れるポップソングも印象な同作について、評論家 / 音楽ディレクターの柴崎祐二がレビューする。連載「その選曲が、映画をつくる」第35回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
姉妹と、長年会っていなかった父の「家」をめぐる物語
この不信と喧騒に満ちた世界の中で、私達は誰もが心安く自由になれる場所を必要としている。それは、ある人にとっては、独り気ままに振る舞える場所かもしれないし、またある人は、世界から自分を守ってくれる繭のような場所を夢想するかもしれない。居場所。そこに私が居るところ。居るべきところ。そういう場所への憧憬を私達は心の奥底に抱えながら、この世界を生きている。
「家」は、多くの人に、そういう居場所を提供してくれる存在だ。すくなくとも、多くの人にはそう信じられている。しかし、家の中には、しばしばすれ違いや心を乱す喧騒が、反対に、寂寥と孤独が漂ってもいる。家は、居場所であると同時に、ときにそこから逃れたいと願わずにはいられないような場所となる――。
ヨアキム・トリアー監督の最新作『センチメンタル・バリュー』は、そうしたアンビバレントな「居場所」としての「家」をめぐる物語である。
舞台は、ノルウェーの首都オスロ。主人公のノーラ(レナーテ・レインスヴェ)は、舞台俳優として大きな成功を収めているが、心の奥底に深い不安を抱えている。かたや、彼女の妹アグネス(インガ・イブスドッテル・リレオース)は、家庭を築き、夫と息子とともに穏やかな日々を送っている。母の逝去に際して、古くから家族が住んでいた家でささやかなお別れの会を営んでいると、かつて彼女たちを捨てて家を出た映画監督の父グスタヴ(ステラン・スカルスガルド)が突然姿を表す。彼は、長年のブランクを経て取り組んでいる新作映画をその家で撮りたいと考えていること、更には、娘のノーラに主演を演じてほしいと思っていることを告げる。だが、身勝手な父への怒りを抱えつづけてきたノーラは、その依頼を断る。それでも映画作りを諦めきれないグスタヴは、偶然知り合った米国の人気俳優レイチェル(エル・ファニング)に出演をオファーし、撮影の準備を進めるのだが――。

INDEX
同じ家に流れる、それぞれの時代を映す音楽
ヨアキム・トリアー監督は、ここ日本でも大きな話題となった前作『わたしは最悪。』でアート・ガーファンクルが歌う“3月の水(Águas De Março)”のカバーを効果的に使用していたことからも分かるように、映画を構成する重要な要素として音楽を巧みに用いてきた作家だ。今作においても数々の楽曲が散りばめられており、個々のシーンの演出を補うにとどまらず、主要なテーマの提示という面においても、欠かせない存在として効果を発揮している。
まず、本作の特徴の一つとして、回想を織り交ぜながら過去と現在を行き来するその構成の妙が挙げられるが、そこで重要な役割を果たしているのが、やはり音楽の存在だ。ナチスドイツ侵攻前の宅内の風景にアーティ・ショウのスウィングジャズ曲“Rose Room”(1939年)が、カウンターカルチャーの時代のダンスパーティーでジョニー・サンダーのファンキーなソウル曲“I’m Alive”(1969年)が、更に時代を下って、グスタヴが家庭を設ける1980年代後半に、ジュディ・ツークの“Shoot From the Heart”(1983年)が流れる様子は、一軒の家が数世代にわたる時間の厚みを経てきたことを表現するにあたって、そこに写る優秀な美術とともに実に雄弁な働きを果たしている。同じ家を被写体としながらも、そこに流れている音楽(のテクスチャー)が時代とともに明確に移り変わっていくことで、巧みに物語が駆動していく様を味わうことができるのだ。
加えて、グスタヴが古馴染みの撮影監督ペーターを尋ねる際にRoxy Musicの“Same Old Scene”(1980年)が流れるシーンをはじめとして、楽曲の歌詞と物語の内容が微妙に呼応している様も、それがあからさまではない分、かえって含蓄深い効果を生んでいるのが見て取れるだろう。更には、エンディングに使用されているラビ・シフレの“Cannock Chase”(1972年)も、この映画のテーマを優しく包み込むような効果を発揮しており、じんわりとした感動をもたらしてくれる。