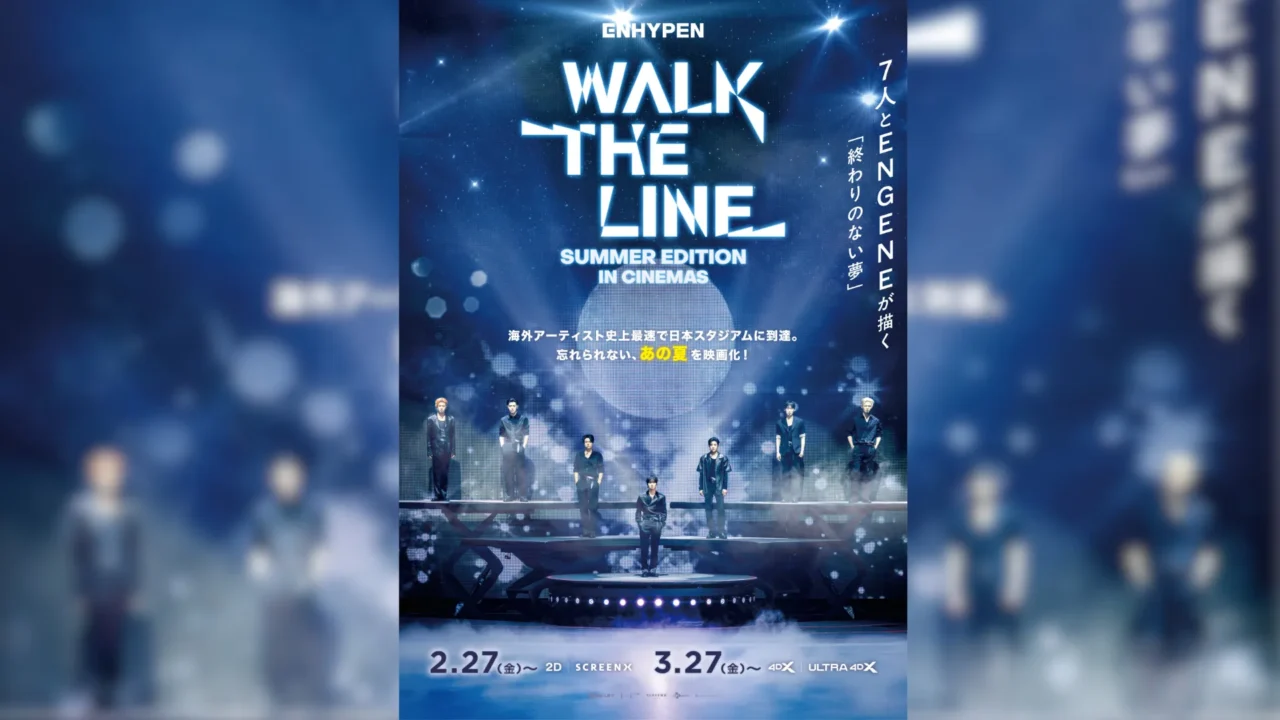INDEX
目の前に(物理的に)転がる、巨大な「問い」

会場内にはQ(問い)が文字通り「転がっている」。チケット売り場のあるホールには『Can you be lonely and happy(孤独なまま、幸せでいられるの)?』『Do shadows have sounds(影に音はあるの)?』と名付けられた作品たちが。巨大な黒いバルーンに記された問いは斜めになったりひっくり返ったりしており、読もうとすると自然と首が「はてな?」の角度になってしまう。

作品の周囲に柵などが立てられていないこともあり、会場ではバルーンに吸い寄せられるように近寄り、ムニムニと触れてみる人の姿もちらほら。スタッフさんに触ってもいいかと尋ねると、そこは美術館としては何とも言えないようだ。